不動産テックが地域コミュニティの希薄化を救う?テクノロジーを活用した最新の試み

- Civic Techは市民が社会について自ら考え、より良い社会づくりに能動的に関わることが本質であり、そのためには市民同士のコミュニティが重要。
- 現在の日本社会ではライフスタイルの変化に伴い、地域コミュニティが希薄になっている。
- 不動産業界において、地域コミュニティを深めるための最新サービスが登場している。
- 地域コミュニティの再構築は不動産業界の成長にもつながる。
はじめに
市民が抱える小さな悩みから社会問題まで、行政サービスが対応しきれない部分について、市民自らがテクノロジーを活用して解決を図るCivic Tech(関連記事はこちら)が広がりつつあります。Civic Techは、単に市民が自らサービスやアプリを作るというだけでなく、それらを通して市民がより良い社会について考えることがその本質です。そこで重要となってくるのが、市民がその考えや意見を交換し合えるコミュニティの存在です。
課題を共有し、解決に向けて一緒に動く市民同士のコミュニティ。このコミュニティづくりこそ、不動産業界がCivic Techの一役を担える可能性を秘めた領域です。
今回は希薄になりつつある地域コミュニティの現状について考察し、人々のつながりを深めるための不動産業界の取り組みの最新事例をご紹介します。
減少しつつある地域コミュニティ
少子高齢化、都市への人口集中と地方の過疎化……これらの社会問題を抱える日本において、都市部での人間関係の希薄化、過疎化による地方のコミュニティの崩壊など、地域のつながりについての課題が顕在化しています。
「再配達から置き配へ? 物流テック最新事情」でも取り上げたように、ECサイトの利用者は増加の一途を辿り、人と直接関わらずに買い物をするケースが増えたことや、SNSの普及によるネット上のコミュニティ重視の傾向、共働き世帯の増加に伴う地域活動への参加時間の減少など、ライフスタイルの変化も、地域コミュニティに関わる機会の減少に拍車をかけています。都市部では、隣に住んでいる人がどんな人かわからない、といったことも珍しくありません。
少し古いデータですが、国土交通省の「平成17年度 国土交通白書」では、当時すでに地域の人々との付き合いの希薄化が問題視されており、「地域の人々との付き合いが疎遠な理由」の質問に対して、「昼間に地域にいないことによるかかわりの希薄化」や「コミュニティ活動のきっかけとなる子供の減少」など、ライフスタイルの変化が地域の人々との付き合い方に影響を及ぼしていることがわかります。
【地域の人々との付き合いが疎遠な理由】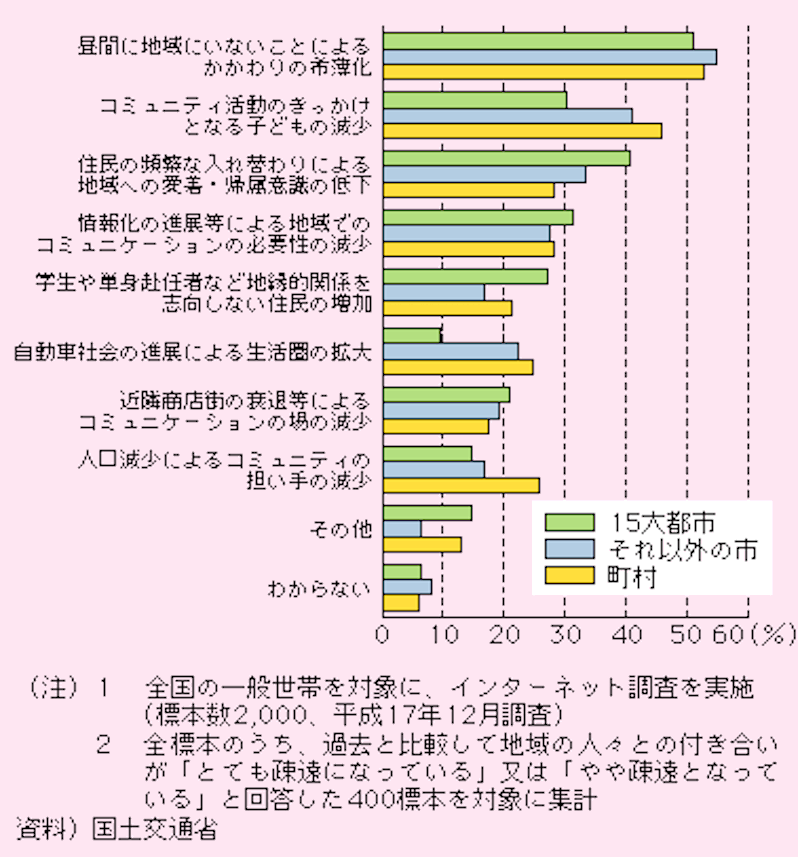 【出典】国土交通省「平成17年度国土交通白書」より【URL】http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h17/index.html
【出典】国土交通省「平成17年度国土交通白書」より【URL】http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h17/index.html
地域コミュニティのつながりを深めるためのテクノロジー
このようにライフスタイルの変化により従来の地縁的な人間関係が希薄化する一方で、不動産業界においてテクノロジーを活用して地域コミュニティを深める試みが始まっています。
KOU
中古リノベーション売買サイト「cowcamo」を運営する株式会社ツクルバは、物件購入後のユーザーの暮らしにも寄り添うため、ホームパーティや街歩きを開催するなど、ユーザー同士のコミュニティづくりを大切にし、つながりを促進する様々なサービスを展開しています。
その一つ、コミュニティコインアプリ「KOU」は、特定のコミュニティのメンバー間で、感謝の気持ちをコミュニティコインのプレゼントという形で表すことができるアプリです。コミュニティの中で何かの善意を受けた時、実際のお金を渡すことが必ずしも適当ではないようなシーンにおいて、コミュニティのメンバー間でのみやりとりが可能なコミュニティコインを送ることで感謝の気持ちを伝えることができます。
KOUに登録すると、ユーザーに一律でオリジナルのコミュニティコインが配布され、コミュニティの仲間同士でコメントとともにやりとりすることができるようになります。
例えば街の一角のマルシェの出店者を応援したり、出店者がお客様にお礼を伝えたりと、コインが循環することで地域コミュニティを盛り上げることができます。
そんなKOUでは貯めているコイン数よりもコインを送りあった延べ数を重視しています。コミュニティ内でどれだけ感謝のやりとりが行われたかがランキングで見られるようになっており、たくさんの「ありがとう」のやりとりが行われているコミュニティは上位に表示されることにより自然と新規の人もアクセスするようになるなど、感謝のやりとりを中心にコミュニティが広がる仕組みになっているのです。
 KOUサイト【出典】KOUサイトより【URL】https://kou.by/
KOUサイト【出典】KOUサイトより【URL】https://kou.by/
PIAZZA × Flatto
Civic Techの5分野の1つに「Social NetWorks」、専門家や地域とのネットワークがありますが、コミュニティづくりをネットワークと情報発信によって支援している地域SNSアプリの一つに「PIAZZA」があります。PIAZZAは、地域の様々な情報を発信、交換することのできるアプリです。その地域に住んでいる人だけではなく、そこで働いている人や行政など、その地域に関わりのある人々が主体となって情報発信を行うと同時に、受け手としても有益な地域の情報を得ることができます。
 PIAZZAサイト【出典】PIAZZAサイトより【URL】https://www.lp.piazza-life.com/
PIAZZAサイト【出典】PIAZZAサイトより【URL】https://www.lp.piazza-life.com/
さらにPIAZZAは三井不動産と連携し、アプリ上のコミュニティづくりに留まらず、アプリで繋がった人々が、ビジネスサークルや朝活、運動イベントなど、直接、リアルでもコミュニケーションが取れるよう、コミュニティ活動を行う場所の一つとして使用できる多目的スペース「Flatto」を東京都中央区日本橋にオープンしました。
 【出典】Flattoサイトより【URL】https://www.flatto-nihonbashi.jp/
【出典】Flattoサイトより【URL】https://www.flatto-nihonbashi.jp/
ハード面を三井不動産、ソフト面をPIAZZAと、それぞれの得意分野を活かして協働することで、各社単独で行うよりも、より質の高いサービスが実現できるようになったといえます。このようなコミュニティづくりのためのインフラサービスもまた、新たなCivic Techを生み出すきっかけとなるかもしれません。
まとめ
Civic Techにおいては、その土台となる地域コミュニティづくりも重要です。単に目先の課題解決だけではなく、解決した後も、また別の課題への取り組みを行なったり、成果や反省を共有できる人と人とのつながりを深め、さらに持続し、より良い社会を目指していく。そんな持続可能なコミュニティづくりはSDGsにも通じるところがあります。
テクノロジーの発達が人々のライフスタイルに変化をもたらしたことで、地域のつながりが希薄になった部分もありますが、一方でそのつながりを再度構築することにも、テクノロジーが活用されています。
不動産テックは、地域コミュニティを物理的な面からのみならず、サービスや情報という面からも支えていくことができる可能性を秘めており、その発展が不動産業界全体の成長にもつながるといえるでしょう。






