爆増する民泊需要は、空き室・空き家問題の解決糸口になるのか?
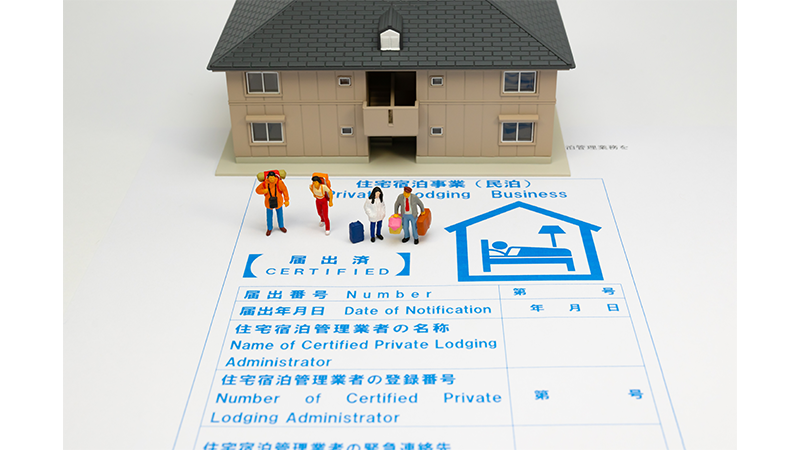
- 民泊需要が再び高まってきており、あらためて民泊のトレンドを知る
- 民泊は賃貸と異なる需要があるため、空き家などの活用に向いている
- 空き家の運用を活性化させる空き家税の認知度は低く、今後の課題もある
アフターコロナで再び注目を集める民泊
それぞれが持っている時間や技術、モノなどを共有・交換して需要と供給を補う「シェアリングエコノミー」。Uber Eatsに代表されるビジネスモデルは、今やすっかり一般的になりました。その中でも、再び注目を集めているのが民泊です。
民泊は一般的に本来住居である建物(アパートやマンションなどの賃貸物件を含む)を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指します。日本には古くから、住まいの一部あるいは全部を宿泊施設として提供する「民宿」がありますが、民宿の多くが食事なども含めた総合的なサービスなのに対して、民泊は主に空間の提供に特化しています。
民泊仲介大手の米エアビーアンドビー(Airbnb)が5月9日に発表した2023年1〜3月期決算は、売上高が前年同期比20%増の18億1800万ドル(約2460億円)、最終損益が1億1700万ドルの黒字でした。日本でも海外からの旅行客を多く見かけるようになりました。
宿泊先を選ぶための検索、予約申込も宿泊先に直接行うのではなく、Airbnbに代表されるインターネット上の仲介システムを利用することにも特徴があります。この仕組みのおかげで、普段は自分が暮らす住居、あるいは別荘として建物を利用しながら、使わない期間だけ、または空室となっている部屋だけを民泊として開放し、収益を得ることが可能になりました。民泊専用として住戸全体を貸し出している戸建て物件も存在します。
新しいビジネス、副業としての民泊
民泊は一般の人だけでなく、不動産投資家からも投資対象として注目されています。従来、実物不動産投資における投資対象はアパートやマンションなどの賃貸物件のみ、定期的な収入源は入居者からの家賃収入でした。
一方、民泊では、宿泊費が収入源となります。賃貸物件では空室となった場合の収入はゼロですが、民泊なら小回りを効かせた運用が可能。一般的には賃貸需要が少ない地域にある物件でも、「観光地やイベント会場に近い」といった条件が揃っていれば、宿泊需要が見込めます。つまり、賃貸ニーズが少ない物件であっても、観光需要がある地域なら民泊として活用できる可能性があるのです。また伝統的な和風の建物は現代の賃貸ニーズに合わないかもしれませんが、外国人旅行者には好まれる可能性があります。
こうしたニーズを満たすために古民家をリノベーションし、民泊にしてサービスを提供する人たちも増えてきています。空き家を見つけてオーナーと交渉し、リノベーション。オーナーに賃料を支払いながら、民泊を運営し、利益を得ていくといったパターンです。
実際に3軒の古民家をリノベーションし、運用をしているオーナーに話を聞くと「利益は出ており、4軒目を準備中」と話します。同オーナーは副業としてやっているため、稼働率は抑え目にしていると話しますが、それでも利益がでている状態。民泊の運営は宿泊客をネットで集めてチェックイン処理(鍵を渡すなど)、利用者がチェックアウト後に清掃するというフローなので時間の制約があまりなく副業としてもいいのだとか。
日本で民泊をはじめる上でのルール
民泊需要は2010年頃、日本でのAirbnbサービス開始とともに急拡大しましたが、当時は民泊に関する法令がなかったために旅館業との区別が曖昧であること、周辺住民とのトラブルが多い、といった混乱も生じました。そのため2018年に「住宅宿泊事業法」、通称「民泊新法」が施行されます。
民泊新法におけるポイントは、以下の3つです。
1)民泊を営むには「住宅宿泊事業者」として都道府県知事等への届出が必要であること。
2)宿泊施設としての営業日数が年間180日までに制限されること(自治体によってさらに営業日数が制限される場合もあります)。
3)宿泊者一人あたりのスペースが3.3㎡以上であること。
宿泊させる日数が年間180日を超える場合、民泊(住宅宿泊事業者)ではなく旅館業として届出を出し、許可されなければなりません。旅館業を営むには消防設備や衛生管理等の規定があり、住居と併用はほぼ不可能です。詳しく知りたい方は以下のサイトを参考にしてください。先ほどの古民家をリノベーションし、民泊を行っている場合は一戸建てのため、旅館業への申請も可能となります。

民泊ポータルサイト minpaku 【URL】https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html
日本の課題である「空き家」を再生する機会、しかしオーナーの認知度は低い
高齢化が進んだ日本では2030年には空き家が430万戸になると言われており、京都市では対策として「空き家税」の導入が決定しています。SUMAVEでも「日本だけでない、世界の「空き家問題」はマッチングとリノベーションで救う」で空き家税などについてご説明しましたが、民泊はこの空き家問題を解決できる一つの手立てになるかもしれません。
空き家税によって放置している不動産を手放したり、運用しようしたりする動きがオーナーに出てくれば、変化が起きるかもしれないのです。しかし、まだ「空き家税」の認知度は低いようで、知らない人は66.2%でした(株式会社AZWAY調査)。認知度がより高まれば空き家のオーナーも放っておくことが損になるのでなんらかの対策を行うようになるかもしれません。その対策の一つが民泊である可能性は高いでしょう。2025年の大阪万博など大きなイベントも控え、インバウンド需要の拡大、民泊の活用が期待されています。






