2020年以降の物件活用-スタートアップの新サービス事例

- 東京オリンピック以降の物件活用に関心が高まっている。
- テック系スタートアップによる新たな不動産活用事例の紹介。
- 消費者ニーズの変化を掴むことで、ビジネスチャンスの拡大が見込める。
はじめに
ここ数年、日本では何かというと東京オリンピックが開催される「2020年」が持ち出され、ベンチマークに据えられる傾向にありました。不動産業界においても重要な年として注目されてきたかと思います。
しかし、国外の企業は既に2025年、2030年を見据えて事業計画を刷新していっているといいます。
人口の減少は止まらず、オリンピックが終わった後の日本。不動産業界にとって逆風が強くなると目されていますが、打開策はあるのでしょうか。人々の消費行動の変化から生まれた新たな物件活用法など、先進事例を見ていきましょう。
人口減少、東京オリンピック後に不動産業界が迎える試練の時代
厚生労働省の政策研究機関である国立社会保障・人口問題研究所が2017年4月10日に発表した「日本の将来推計人口(平成29年推計)」によると、2015年時点で1億2,709万人の日本の総人口は減少傾向が続いており、2040年には1億1,092万人、2053年には9,924万人と1億人を割ると推計されています。日本の少子高齢化の流れは避けられない流れですが、加えて不動産業界では冒頭で触れた「2020年問題」に注目が集まっています。
簡単にいうと、東京オリンピック終了後、都心部の不動産価格が大暴落してしまうのではないかという懸念です。しかし、実際の不動産価格は様々な要素で決まるため、この予想は確実なものでありません。
例えば、2012年に開催されたロンドンオリンピック。ニッセイ基礎研究所が2015年2月3日付けで発表した基礎研レポート「変貌するロンドンの不動産投資・開発状況」によれば、ロンドンの不動産価格は「開催翌年となった2013年も取引量は前年比+39%で過去3年より高い増加率となった」とのことで、必ずしもオリンピック後に不動産価格が下落するわけではないことが分かります。

不動産業界においては、必要以上に「2020年」を警戒するよりも、現在進行形で深刻化が進む空き家問題への対策を考える方が建設的かもしれません。また、人々の消費意識が「所有する」ことから「共有する」ことへと移行しつつあることから、人々と不動産との関わり方にも変化が生じてきています。
こうした流れを受けて、最近ではスタートアップを中心に5年後、10年後も不動産としての価値を維持し続けるための新たな物件活用法に注目が集まっています。
テック系スタートアップが提供する新たな物件活用
人々の行動や価値観の変化を受け、個人間で物や場所、サービス等を共有する「シェアリングエコノミー(共有型経済)」の普及が始まっています。象徴的なものに、フリマアプリや民泊の流行があります。
シェアリングエコノミー協会の定義では、シェアリングエコノミーのサービスは主に「場所・乗り物・モノ・人・スキル・お金」の6つに分類されています。直接不動産に関係があるのはもちろん「場所」。既存の土地や空間に新しい価値を見出し、活用するサービスを提供するスタートアップが増えてきています。民泊プラットフォームを展開する「Airbnb」や、空きスペースを貸したい人と借りたい人とを結ぶ「スペースマーケット」はその代表例ですが、他にもユニークなアイデアが次々に生まれています。早速、注目企業を見ていきましょう。
モノオク
荷物の置き場所に困っている人と、自宅の余ったスペースを活用したい人をつなぐ物置きシェアサービス「モノオク」を展開。引っ越しやリフォーム、出張・転勤・留学等で一時的に荷物を預けたい際、トランクルームを使うよりも手軽かつ安価に利用できるとあって注目を集めています。
また、同社は荷物の配送や引っ越しに関する企業との提携・協業を進めており、ユーザーの利便性向上を図っています。2019年3月11日には、トラックとドライバーをセットでレンタルできる「レントラ便」を手掛けるハーツとの業務提携を発表。運転はもちろん、荷物の移動も手伝ってくれるレントラ便とモノオクを連携利用することで、大きな荷物も預けやすくなります。
「空き部屋を活用したいけれど、宿泊施設として貸し出すには抵抗がある」という人たちからのニーズも見込まれるモノオク。空き家問題に対する解決策の一つとしても期待が集まるサービスです。

【出典】ホームページより:https://monooq.com/
ecbo
荷物預かりプラットフォーム「ecbo cloak」を展開。駅付近のカフェや店舗等の空きスペースを利用して、スーツケースやバッグ、ベビーカー等の荷物を預けられるサービスプラットフォームを提供しています。上で紹介した「モノオク」がトランクルームの代わりなら、こちらはコインロッカーの代わり。貸し出す側も大型の空間を確保する必要はないため、東京・品川・池袋・上野駅構内といった山手線エリアや、飲食店・小売店に留まらず、郵便局や美容院、不動産会社の店舗等、様々な場所で導入が進んでいます。
2019年3月11日からはそごう・西武との提携により、西武渋谷店での実証実験を開始。初の大手百貨店への導入となりました。国内・国外問わず観光の際にありがちな「コインロッカーが見つからない」問題を解決できるサービスとして、都心部を中心に借り手・貸し手共に拡大していきそうです。
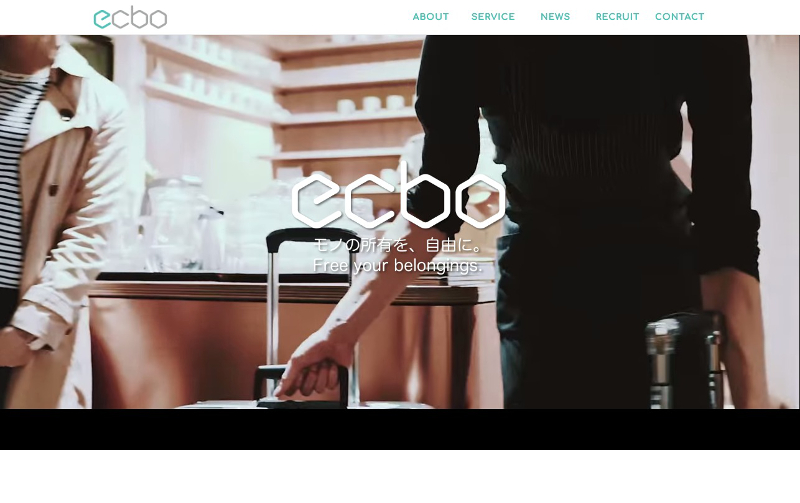
【出典】ホームページより:https://ecbo.io/
Mellow
ビルの空きスペースと個性豊かなフードトラック(キッチンカー)をマッチングさせるプラットフォーム「TLUNCH」を展開。約500店舗のフードトラックと提携し、曜日ごとに別々のフードトラックを配車することで、毎日職場周辺の店舗という限られた選択肢の中から昼食を選ぶオフィスワーカーに向けて、飽きずに昼食を楽しめる仕組みを提供しています。独自システムによる配車や仕入・仕込みを最適化するためのフィードバックを行い、ビルオーナーやシェフ、利用者全てのメリット向上を図っています。
2018年11月6日の発表によると、サービス開始から2年9カ月で「TLUNCH」の運営スペース数は118箇所を突破。この急成長の理由について、同社はビッグデータやスマートフォンアプリの活用、空間デザインや行政との連携等を挙げています。今後TLUNCHではキャッシュレス環境の整備を進めると同時に、フードトラックのシェフに提供するデータの拡充を図っていくと発表されています。
一方で同社は、ネイルサロントラックや靴磨きスマホ修理トラックなど、食以外にもユニークなモビリティサービスを展開していく準備も併せて進めているそうです。同じ場所でも時間によって集まる人やニーズは違いますから、ラインナップを拡充していけば、店舗ごと移動できるというメリットを存分に活かせそうですね。

【出典】ホームページより:https://www.mellow.jp/
Akippa
空いている個人宅の車庫や月極の駐車場の一時利用予約ができる駐車場予約アプリ「akippa」を運営しています。契約されずに空いている月極駐車場や個人宅の車庫だけでなく、空き地や商業施設等の空きスペースを駐車場として利用することも可能です。スマートフォンアプリで事前予約・決済を行なうため、目的地に近い駐車場へ格安かつ確実に停められる点が人気のサービスです。15分からの利用が可能なため、オーナー側も都合に応じて柔軟な貸し出し方を選択することができます。
2014年4月25日のリリースから約4年半で会員数は100万人を突破(2018年11月7日時点)。利用できる駐車場は47都道府県累計で24,000拠点以上に上ります(同上)。デベロッパー等との提携を進めるほか、国土交通省やタクシー協会、トヨタ自動車と西日本鉄道による実証実験に参画していることからも分かる通り、多くの注目を集めるスタートアップです。

【出典】ホームページより:https://akippa.co.jp/
軒先
空きスペースとそれを利用したい人を結びつけるプラットフォームを運営。低コストで自分の店舗を持ちたい、教室を開きたい、イベントを開催したい人向けの「軒先ビジネス」、駐車場としての利用に特化した「軒先パーキング」、吉野家ホールディングスの共同事業で、飲食店向けに特化した「軒先レストラン」を展開しています。
特に注目されているのが、バーや居酒屋など、夜だけ営業している店を間借りして営業する「間借り」スタイルでの飲食店経営をサポートする「軒先レストラン」。貸し手側は営業時間外も店舗から収益を得られるようになり、借り手側は初期費用やリスクを最小限に抑えたまま自分の店を持つことができます。テストマーケティングの方法としても有効ですし、昨今、米国では「ゴーストレストラン」と呼ばれる無店舗型の飲食店が人気を集めています。
こうした営業形態なら、商品を作るためのキッチンさえあれば凝った内装の店舗は不要。間借りする店舗の内装や雰囲気を気にする必要もないでしょう。「Uber Eats」や「LINEデリマ」といった、今活況のフードデリバリーサービスに配達網を任せてしまうことも可能です。日本でも、限られた空間を活用した飲食店が増えていくのかもしれません。
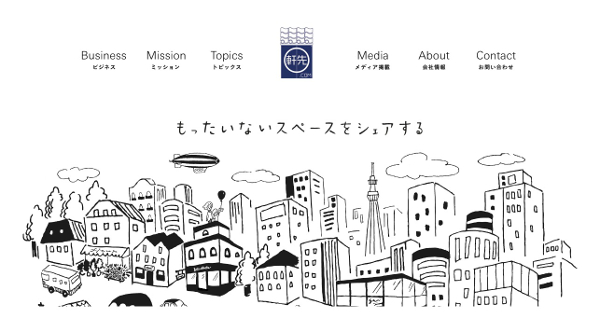
【出典】ホームーページより:https://www.nokisaki.com/
消費者ニーズの変化を捕まえる
遊ばせている空間を効果的に運用していくには、消費者のニーズの変化を知る必要があります。前項で例に挙げた企業の取り組みからも分かるように、消費者が空間に求めるものは「住宅」や「オフィス」だけではありません。「広さ」や「築浅」か、「駅近」かどうかといった一般的に物件の価値として挙げられる条件は、必ずしも全ての空間に当てはまるものではありません。
例えば一時的な荷物置き場として利用して欲しいのであれば、むしろコインロッカーが存在する駅から遠い方が、利用者にとってありがたい場合もあるでしょう。建物自体が古く、住居やオフィスとして利用するには不便な場所であっても、展示会やイベントを行ないたい人にとっては「景観や雰囲気がぴったりなのでぜひ利用したい」ということもあるかもしれません。
宿泊先やイベントスペース、駐車場や物置、飲食店以外にもまだまだ空間の活用法は眠っているはず。固定観念に囚われず、物件を「部屋」や「ビル」ではなく「空間」として捉え、そこで何かできないか、切り取って一部のみを利用することはできないのかといったことを考えていくことが、「体験」や「共有」に価値を置く、いまどきの消費者のニーズを満たす鍵なのかもしれません。
まとめ
人口が減少していく中、多くの企業が飽和した空間へいかに人を集めるかに腐心しています。しかし人々の価値観が変化しつつある今だからこそ、これまでは見向きもされなかった物件や土地に価値を見出すチャンスでもあるのです。
サブスクリプションサービスの流行などからも、何事も「使いたいときに、使いたいだけ」利用するという消費の仕方が広がっていることが分かります。こうしたサービスは「買って終わり」ではない以上、「契約してもらう」ことではなく、多くの人に「利用し続けてもらう」にはどうしたら良いかに重きが置かれ、運用されています。
「売ったら終わり」ではなく、多くの人に何度も利用し続けてもらうにはどうしたら良いか。かつて圧倒的に主流だった「持ち家志向」が陰りを見せる今、不動産の運用もこうした潮流の変化を意識した上で行なっていく必要があるのかもしれません。






