【3Dビジュアライゼーション】不動産業界における活用状況と展望

- 立体的かつ視覚的にバーチャル空間で表現する3Dビジュアライゼーション技術は、不動産業界でも活用され始めている
- 新築物件では「VR内見」や「3Dウォークスルー」などの3Dビジュアライゼーションが取り入れられているが、中古物件や賃貸物件に普及していくためにはコストが最大の課題
- 今後、3Dビジュアライゼーションの活用により、顧客に合わせた物件の提案の幅が広がる可能性も
3Dビジュアライゼーションとは?
3Ⅾビジュアライゼーションとは、現実に存在するものやまだ存在しないものを、立体的かつ視覚的にバーチャル空間で表現することです。
3Dビジュアルといえば、ひと昔前までは映画やゲームなどの目で楽しむエンターテインメントが連想されていたと思います。
しかし、今では機械やプロダクトデザイン、建築のシミュレーション・設計、さらには実用的な営業・販売・広報手段のためのビジュアル作成など、様々な業種で使われるようになっています。
こうした、直接見ることのできない事柄や現象、関係性などをイメージできるように、画像や図表、データなどを3Dで視覚的に確認できるようにすることを、3Dビジュアライゼーションと言います。
3Dビジュアルを活用することのメリット
3Dビジュアライゼーションのメリットの1つとしては、実物や模型を作る前でも、コンピューター上で具体的な検討を重ねられることが挙げられます。これにより、シミュレーションや設計の効率が格段に上がりました。

さらに、実際に建築が出来上がる前に、3Dビジュアルを用い、まるで本物のような完成予想図を示すことは、そのプロジェクトを説得力のあるものへと変えていきます。
ビジュアルの質感や光の当たり具合といった質の向上は、視覚的にわかりやすく、印象に残る建物の3Dビジュアルを作り出すことに寄与しています。
3Dビジュアルを共有することにより、顧客や社内外の関係者のイメージが一致しやすいというメリットもあります。例えば、広告や販促の分野では、3Dビジュアルで作成したデータを使用することで、顧客がまるで本物と思い込んでしまうようなビジュアルで広告を展開することが可能だったり、顧客に購入後のストーリーを想像してもらえるような、本物以上のビジュアル表現を実現できたりするなど、効果は多岐にわたります。
3Dビジュアライゼーションの広がり
これまでの3Dビジュアライゼーションは、一部の専門家のみが扱える高度な技術でした。しかし、近年、操作が比較的簡単なソフトが登場したことで、多くのビジネスマンが利用できる便利な手法に変わり、その用途も圧倒的に広がっています。
その上、現在ではクラウド型の3Dビジュアライゼーションツール「VividPlatform」など、直観的に操作し、3Dビジュアルを生成できるツールも出ています。こういったサービスを利用すれば、複雑なソフトの知識すら不要になります。
不動産業界における3Dビジュアライゼーションの活用例
前述の通り、様々な分野で3Dビジュアライゼーションが普及していく中、不動産業界ではどのように取り入れられているのでしょうか?
今回は、不動産業界における3Dビジュアライゼーションの活用例と、今後どのように使われていく可能性があるのかを、検討していきたいと思います。
大規模な不動産での3Dビジュアルの活用例
不動産業界における3Dビジュアライゼーションの活用と聞いて、一番初めに思いつくのはデベロッパーの分野でしょう。
街の再開発、大規模な住宅街造成、マンション開発事業において、地形の工学的な検討や設計段階での検討、施工、販促に至るまでの全ての領域において、3Dビジュアライゼーションは欠かせない存在となっています。
デベロッパーは不動産を開発し、作り出す事業を行う分野です。まだどこにも存在しない建物等を構想し、プロジェクトを進めるためには説得力のあるビジュアルが必要となってきます。そのためには、3Dビジュアライゼーションは最も有効に作用すると言えます。
よって、開発段階で作成していた3Dビジュアルを、販促でも大々的に使うことが可能です。
販促での活用においては、大規模な集合住宅が、竣工前から間取りと3Dビジュアルによる竣工予想図等の情報のみで多くの買い手がつき、抽選でなければ購入できないほど人気となる場合もあります。
VR(バーチャルリアリティ)の活用例
VR(バーチャルリアリティ)技術は、建物内部を立体的に把握できるように視覚化したという意味では3Dビジュアライゼーションと言えます。
そのVRを活用している例としては、新築の不動産販売が挙げられます。
この1・2年で、物件を撮影した画像を構造的に組み立て、実際とほとんど変わらない視界を実現する「VR内見」や、コンピューター上のモデルハウスのように、3Dビジュアル化された物件をWebサイト上でバーチャルに体験する「3Dウォークスルー」等、ウェブサイト上で建物内部を立体的に把握できるシステムが活用され始めています。

しかし、「VR内見」や「3Dウォークスルー」はまだまだ特別な物件だけの活用にとどまっているのが現状です。
中古の不動産販売においては、購入者にとって高額な買い物であるにもかかわらず、限られた写真で検討した上で、目ぼしい物件だけを内見し、購入するケースがほとんどでしょう。
しかし、中古物件を購入する場合、複数の物件を比較しながら、建物内部の状態の確認や間取りの把握など、新築物件以上に確認項目が多く、1回の内見のみで決断するのは難しい場合もあります。
一方で、購入者が内見を重ねれば重ねるほど、同行する担当者に対する人件費はかさむことになります。その点、「VR内見」や「3Dウォークスルー」の導入が進めば、不動産会社に対する費用対効果の面での貢献など、そのメリットは計り知れないでしょう。
VR普及の最大の課題はコスト
このように便利である一方で、不動産業界におけるVRの普及にあたって、何が障壁となっているのでしょうか?
普及が進まない理由として考えられるのが、第一に導入コストといえます。
費用はVR作成サービスによっても異なりますが、1物件あたりで月々に一定の費用がかかるものもありますし、初期費用のみのもあります。
新築物件の場合、一般的にディベロッパーやハウスメーカー自身が販売を行っています。この場合、販売件数が利益と直結しているため、VR技術の導入などにコストをかけてでも、他社との差別化を図ることが重要です。
設計段階で3Dビジュアル化された建物のデータがあれば、それらを活用した販促資料を作れます。これにより、顧客により多くの情報を与えられるため、高い訴求効果、他物件や他社との差別化、そして顧客へのサービス向上へとつながっていくでしょう。
一方、中古物件販売の場合、案内を行うのは一般的に不動産仲介業者です。また、売却時の契約形態によっては、1物件に対して、複数の不動産会社が販売・契約を請け負う形となります。この場合、自社で契約を獲得できるとは限りません。
その上、仲介によって得られる利益は、新築物件と比較すると少額であり、これらを考慮に入れると、確実に費用がかかってしまうVR技術を自社だけで導入するのは、難しい判断と言えます。
現在、不動産会社向けのVRサービスとしては、スマートフォンで撮影し、WEBサイトに簡単に埋め込みが可能なものや、ウォークスルーの設定が不要で、間取り図と3Dモデルも自動作成してくれるものなどが出てきています。
今後、VR技術がさらに普及し、これらのサービスが無料、もしくは安価で提供されるシステムが構築されるなど、各社が取り入れやすい環境が整わない限り、中古物件販売への普及は難しいでしょう。
設計段階のCADデータの活用にみる可能性と課題
現在、小規模な住宅を含めて、住居設計のほとんどがCADで設計されています。そうすることで図面の修正も容易におこなえ、電気や水道の設備関連を交えた施工図も効率的に作成することが可能となります。
現状、CADデータは設計段階のみの活用にとどまっていますが、高さ情報さえ与えればCAD上で簡単に3D空間を作ることが可能です。そうすれば、正確な寸法情報のもとに、今持っている家具、もしくは新たに買おうと思っている家具がうまく配置できるか等の検討が可能になります。
しかし、課題もあります。例えば、設計したCADデータだけでは、床や壁の素材感を出すことができません。また、オープンハウスのように家具をレイアウトするためには、また別のデータと紐づける必要があるなど、CADデータを加工していく必要があります。
そのため、不動産業界でさらにCADデータを活用していくためには、設計、施工、そして販売に至るまでのCADデータの受け渡しや連携が容易にできるシステムの構築が求められるのではないでしょうか。
3D住宅設計アプリにみる活用例
建築業界では、設計士でなくても誰でも簡単に利用できる3D住宅設計アプリが登場しています。
「HouseMaker」は、iPad上で動作する住宅設計のエンドユーザー向けのアプリです。アプリをダウンロードさえすれば、誰でも簡単な操作で設計から住宅の発注までを行えます。
簡易な構造計算と積算を逐次行うことで、外壁や開口部の位置やサイズを自由に変更し、ユニット家具のパーツを選ぶように自分に合った家をつくれます。
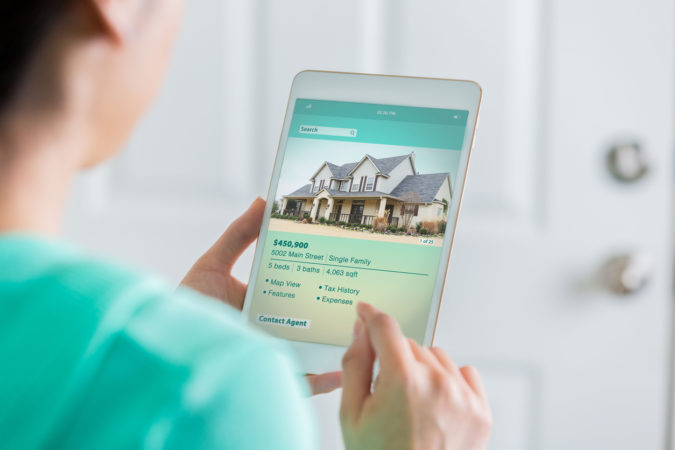
開発した吉村靖孝氏は、エンドユーザーがアプリで自分の家の設計や見積りができて、発注ボタンを押すと何週間後かに加工された材料が職人と一緒に届くような仕組みを作り出しました。
現状はすべてを自分で作るしかありませんが、いずれは他の人がつくったデータをもとに、途中から自分好みにカスタマイズしていくことも可能にしたいという構想もあるようです。
「窓の大きい家に住みたい」、「大きなオープンキッチンが良い」、「寝室も南向きにしたい」等、細かい好みやこだわりを持っている場合、「HouseMaker」のアプリのように、Webサイト上で自分好みの間取りやこだわりを表現した「理想の住まいの3Dデータ」を作ることができれば、不動産会社の仲介担当者にも、容易にイメージを伝えることができるようになるでしょう。
さらに、AIの技術を取り入れれば、「理想の住まいの3Dデータ」と既存の物件との条件マッチ率から、候補となる物件をピックアップすることも可能になるのではないでしょうか。
様々な技術の掛け合わせにより、今後の3Dビジュアライゼーションの活用可能性は広がっていくはずです。
3Dコンテンツを販売データと連携できるツールの登場
Webサイト上の3Dコンテンツを販売データと連携させる機能を持つツールも存在します。
VividWorksが提供するクラウド型3Dビジュアライゼーションサービス「VividPlatform」はその1つです。
自動車販売を例にとってみると、顧客はWebサイト上に埋め込まれた「VividPlatform」のデータで、自動車内部のカスタマイズやパーツ等のオプションの選択をリアルタイムにシミュレーションすることができます。過去の販売データと連携させ、好みの傾向をカスタマイズ提案することも可能です。
これらで検討を重ねた顧客に対して、販売店から最適なキャンペーンの発信を行えば、確度の高い潜在顧客へのアプローチできるほか、カスタマイズ部分については、データとして管理できるため、納期の変更などに対しても、容易に対応できます。
このサービスを不動産販売に当てはめてみましょう。
Webサイト上で物件の室内をシミュレーションし、家具の配置や壁紙、床の素材などをリアルタイムに再現できれば、購入検討者の興味を喚起できます。また、実際にシミュレーションを利用した検討者の情報を、確度の高い潜在顧客として、販売店に共有することも可能です。
さらに、「VividPlatform」の過去の検討状況や他に見ているWebサイト上の行動履歴、エリア情報などのデータと連動させることで、顧客に見合った物件を自動的に提案することもできるでしょう。
一方的に発信していく広告に頼らず、顧客一人ひとりに合った販売を行っていくためには、3Dコンテンツが重要な鍵を握りそうです。
まとめ
ここまで3Dビジュアライゼーションの活用例と今後の展望を見てきました。
新築物件の販売において、3Dビジュアライゼーションは設計段階、また、販促資料での活用において欠かせない存在となっています。また、「VR内見」や「3Dウォークスルー」などを用い、Webサイト上で建物内部を立体的に把握できるシステムが活用され始めています。

一方で、中古物件の販売や賃貸物件での一般化には、収益構造の違いから、コスト面の課題が残っています。
顧客ニーズに鑑みて3Dビジュアルを活用すべき
不動産の購入、契約を検討しているときに、「価格や面積、築年数だけでなく、間取りに対する好みも条件に入れたい」、「今持っている家具、新たに買おうと思っている家具がうまく配置できるか事前に知りたい」なども顧客にとっては重要な検討材料のはずです。
これらの検討材料は、現状の不動産の検索機能では条件に入れることは難しく、検索によって絞り込まれた物件情報の間取りひとつひとつを確認したり、実際その物件を内見に行ったりする必要があります。
また、1回の内見だけでは部屋の正確な寸法までは計測することは難しく、家具の配置を考えるためには購入もしくは賃貸契約を結んだ後に再度訪れることになるのが現状です。
もし、Webサイト上で3Dビジュアライゼーションの技術を用い、顧客好みの間取りや建物の質感を再現でき、そのビジュアルに近い物件を検索・提案できる機能があれば、今後の物件販売の方法は大きく変わっていくことでしょう。
また、顧客自身も、事前に部屋が3Dビジュアル化されていて、自分が持っている家具をコンピューター上でレイアウトできれば、こんなに便利で楽しいことはないのではないでしょうか。
こんなことが、世の中に出回っている全ての不動産物件で実現できる日が、いつか来るかもしれません。
3Dビジュアライゼーションの今後の可能性は、まだまだ広がりそうです。






