ハウスコム×トライエル誕生秘話。オンライン内見で成約率を高めるまで
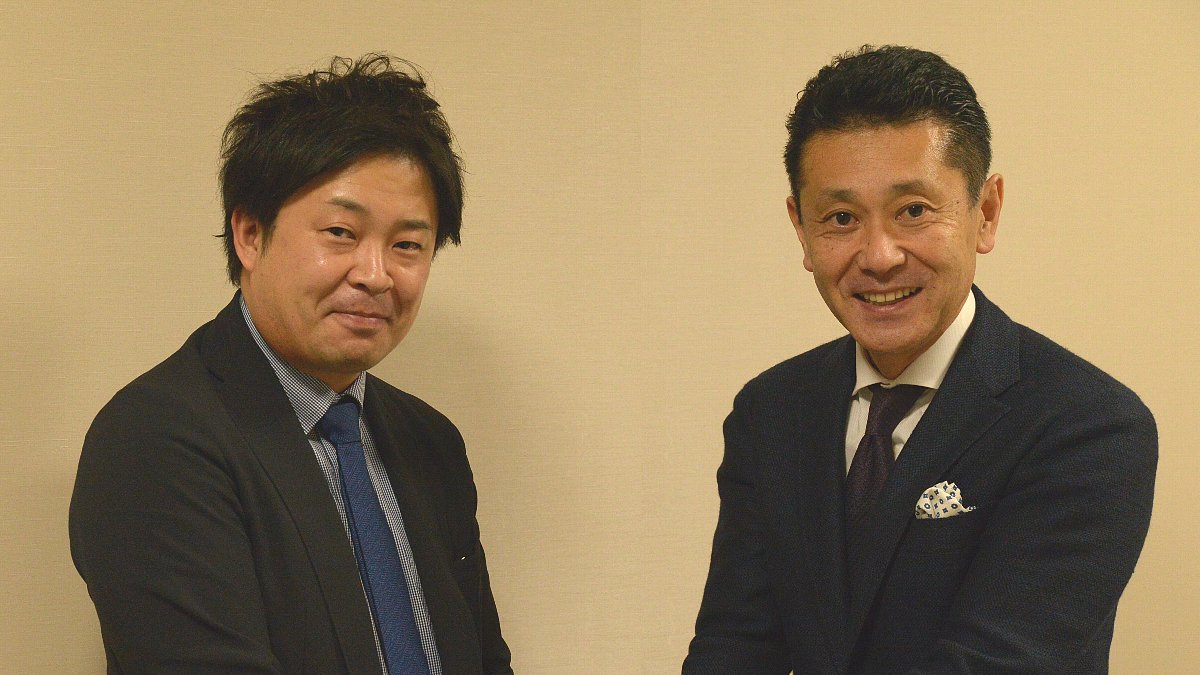
- 『オンライン内見』は、成約率を高める不動産テックサービスである
- その成功事例を築くまでの物語を紹介
- 試行錯誤の末につかんだ、ハウスコムの成功体験を共有する目的の記事
はじめに
不動産テックサービス『オンライン内見』を使って、成約率や来店率を高めているハウスコム株式会社の成功事例を以前、SUMAVEは紹介しました。そのアナザーストーリーとなるのが、今回の記事です。
前回同様に、ハウスコムのサービス・イノベーション室室長、安達文昭氏(画像下)に話を聞きました。ハウスコムは、いかに『オンライン内見』で成功事例を築いたか。その物語をご覧ください。
LIFULL、SUUMO、at-homeの3社が登壇。きっかけは勉強会
Q:株式会社Tryell(トライエル)が提供する『オンライン内見』を御社が導入することになった経緯から、教えてください。いつ頃から、ハウスコム×トライエルの取り組みがはじまったのでしょうか?
「取り組みをはじめたのは、2015年ごろです。当時は、いまのように、インターネットを使った内見のサービスを聞きませんでしたし、”オンライン内見”という言葉も世間にありませんでした」
Q:IT重説の社会実験が(賃貸契約に限り)実施されたのが2017年ですから、業界の関心は、いまよりも低いときでは? どんなきっかけがあったのでしょうか。
「そうですね。きっかけは、勉強会でした」
Q:社内で新規ビジネスを検討するような勉強会ですか?
「いえ、社外の勉強会です」
Q:どんな人たちの集まりですか?
「基本的には同業他社の集まりです。以前の不動産業界は、とても閉じていて、同業他社を単純な”敵”とみなすようなところがありました。しかし、時代は変わりつつあります」
Q:どのように?
「インターネットの登場以来、産業全体に共通していえることは、ユーザーの動向が変化しているという点です。この変化をほかの産業は、うまく活用していますよね。「ほかの産業にならい、学べる部分を真摯な姿勢で取り入れ、私たちも発展しよう」そうした重要性が、不動産業界のなかで次第に叫ばれるようになりました」
Q:志を同じくする、不動産業界の関係者が集まった会、ということでしょうか?
「そうです。業界全体の発展を真剣に考える個社が集まり、無理のない範囲で成功事例を共有し、互いに一皮むけて進化しようとするものです」
Q:安達さんは、いまも参加されているのですか?
「いえ。久しく顔を出していませんが、その集まりを私は、新不動産革新連盟と呼んでいました。略して新革連です。楽天株式会社の三木谷社長が代表理事を務める、新経連にインスパイアされて名付けました(笑)。新不動産革新連盟は名前を変え、いまは、リーシングマネージメント(Leasing Management)の頭文字から”LM研究会”という名称で、存続していたはずです。当社の代表である田村も、顔を出したことがある集まりです」
Q:安達さんが勉強会に参加していた当時で、印象に残っているテーマやイベントは?
「私が企画した回で、LIFULL、SUUMO、at-homeの3社から担当者を招き、パネルディスカッションをやったことが印象深いです」
Q:3大ポータルが一同に会したのですか。それは話を聞いてみたい。3社を集めたのは、無理のない範囲で成功事例を共有し、業界全体の発展につなげようという思いから?
「その通りです」
Q:そうした集まりの1つで、トライエルの社長である野田伸一郎さんと知り合ったのでしょうか?
「正確には、その集まりで知り合った、ダイヤモンドメディア株式会社の武井社長から紹介されました」
Q:不動産テック協会の共同代表理事も務める、武井浩三さん(画像下)ですか?
「はい。いまでも覚えています」
安達さんに紹介したい社長がいるんです。御社は、不動産業界のなかで、ITを活用し、先進的な取り組みをされている不動産会社ですから、ひょっとしたら、お役に立てるかもしれません。話だけでも、聞いてみてもらえませんか(武井氏)
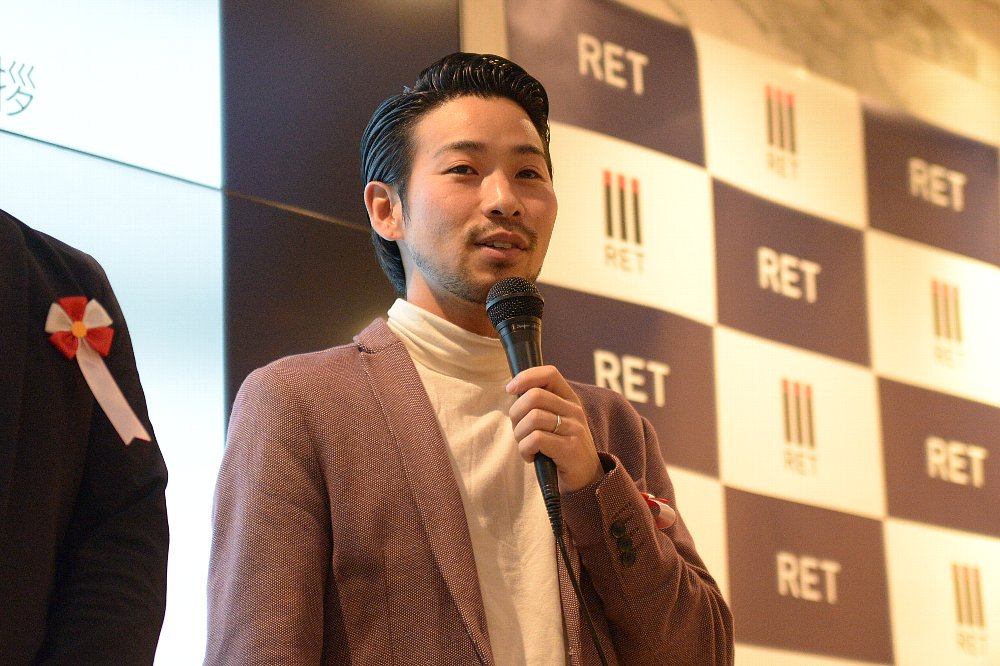 「Facebookを通じて、当時の武井社長から、そんな連絡をもらいました」
「Facebookを通じて、当時の武井社長から、そんな連絡をもらいました」
Q:武井さんのいう、「安達さんに紹介したい社長がいるんです」が、トライエルの野田社長だった?
「ええ。最初は武井社長と野田社長が2人で当社にお越しくださいました。2人の話を私と(ハウスコムの代表取締役社長を務める)田村で話を聞き、以後、ハウスコム×トライエルという二人三脚がはじまるわけです」
店長から「役に立つのか」「面倒だ」の声。進まないテスト運用
「田村の信条の1つに、”体験していないコトの良し悪しを判断してはいけない。まずは体験しよう”があります。『オンライン内見』のときも同じで、「まずは20店舗くらいでやってみよう」ということで決まりです。ハウスコムにとっては、『オンライン内見』のテスト運用、という位置づけになります」
Q:いきなり20店舗ですか。2、3店舗ではなく?
「これには田村の特技が、深く関係しています」
Q:田村社長の特技と、20という店舗数の関連を教えてください。
「田村は、社員の顔・名前・特徴を覚えるのが得意で、2019年4月現在、パートや派遣スタッフを含めた1,200名ほどいるハウスコムの全社員を記憶しています。「来年になって、もうあと、100名ほど増えたら、さすがにキツイな」と本人は話していますが、記憶力は健在です。この特技は、「オンライン内見をハウスコムで試験運用するにあたり、適任者は誰か」を考えたとき、瞬時に、顔や名前を田村に連想させました。頭に浮かんだ店長の顔が40名ほどだったため、そこから、営業部の意見を取り入れて厳選し、ふるいにかけることを逆算しての”20店舗”です」
Q:営業部の意見を取り入れて厳選するとは、具体的に、どういうことでしょうか?
「どの店舗の店長が適任者かを聞き取る作業です。当社では、毎月2回、エリアマネージャーを本社に集め、営業会議をしています。全店舗の最新事情となると、さすがに、田村よりもエリアマネージャーのほうが詳しいですから、「どこどこ店の誰々はネットに詳しいからオススメです」そうした意見徴収です。営業会議には田村も同席して、結果的に20店舗に絞られました」
Q:テスト運用の狙いは?
「まずは、やってみること。そのフィードバックには問題点があるでしょうから、ハウスコムの本社で集約して、トライエルさんとの共通課題として認識し、一つひとつ解決していくことが狙いでした」
Q:首都圏や関西圏など、テスト運用する店舗は、エリアを限定しましたか?
「いえ。全店舗のなかから、関東圏の店舗もあれば、静岡県の店舗もあれば、愛知県の店舗もあるような状況でした。その20店舗で、用意ドンで、一斉にテスト運用をはじめました」
Q:20店舗からあがってきたフィードバックは、どんな内容でしたか?
「内容どころか……。お恥ずかしいもので、実は、誰も『オンライン内見』を使いませんでした」
Q:誰も? なぜです?
「いろいな理由があってですね、「忙しい」「必要と感じない」「面倒だ」などが大半です」
Q:「必要と感じない」という声は、誰からの声?
「20店舗の店長たちです。店舗での作業が新たに増えるとなれば、鍵を握るのは店長です。まずは、店長が使ってみてどうか、という反応を知る必要がありますが、それ以前の問題でした。営業会議での報告内容も判然とせずで、思い通りには、いきませんね(笑)」
Q:その状況をどうされたのですか?
「手始めに、エリアマネージャーへの聞き取りを細かくやり直しました。すると、忙しいや必要と感じないという言葉が”建前”で、20名の店長たちは、本音を抱えていることがわかってきたんです。ここへの対応に乗り出しました」
Q:本音とは?
「大別して2つありました。1つ目は、「マニュアルを読んで説明も聞いたけど、手間がかかりそうだ」などの、『オンライン内見』へのネガティブな先入観です。テスト運用を任せた20店舗は、当社のなかでも、スマホを使いこなしたり、ネットに詳しかったりするような、ITリテラシーの高い店長が仕切る店舗です。その店長たちからしてみれば、当時はまだ、”オンライン内見”という言葉を耳にしたことがありません。聞いたことがない、とは、”ほかの不動産会社が使っていない”ということになります。ほかの不動産会社が使っていないサービス、とは、”売上につながったという実績がない作業”です。「売上につながるか、わからない作業を命じられ、「はい、そうですか」と、前向きに取り組めないよね」という気持ちが2つ目の本音です」
Q:売上につながらないことを店長たちは、やりたくない?
「ほかの不動産会社も同じなのかもしれませんが、当社の店長は、売上へのこだわりを強く持っています。そのためのアイデアや施策にアンテナを張り、情報収集に余念がありません。そんな店長たちからすると『オンライン内見』は、成功事例を聞かない取り組みです。すると、”『オンライン内見』は、いますぐに、自分たちが取り組むべき施策ではない”という考えに、店長たちは陥ります。課題として認識すべきは、その思考回路です。重要なテーマとして繰り返し、田村が日頃から発信しているメッセージでもあり、「それが実践されていない」ことで、このときは田村の雷が落ちました」
田村社長の大号令「体験していないのに良し悪しを語るな」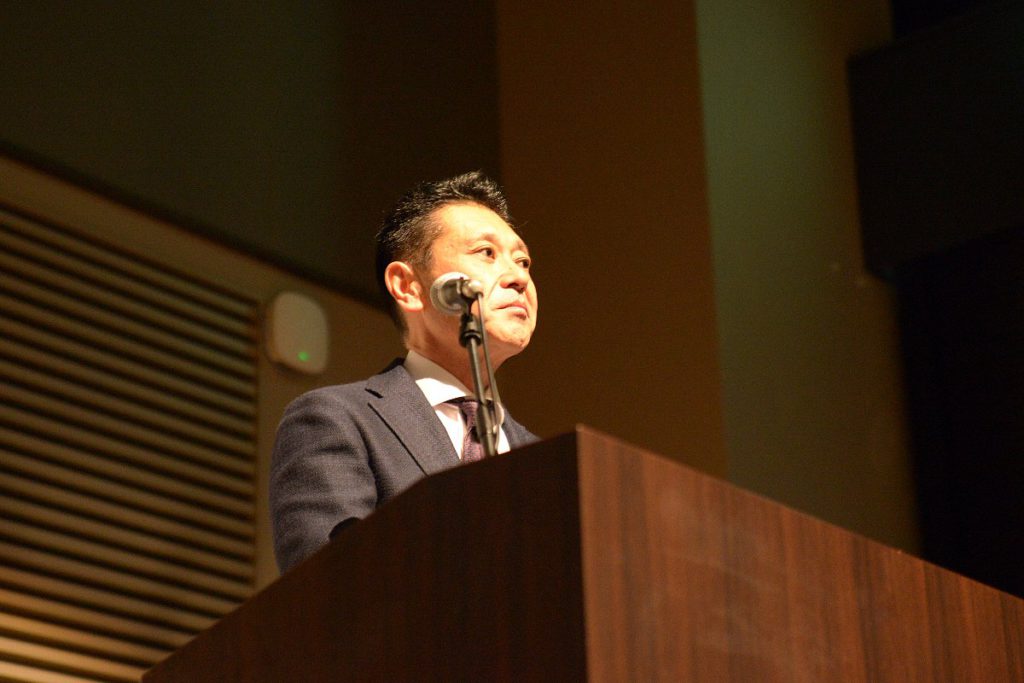
「先ほどもいったように、「体験していないコトの良し悪しを判断してはいけない。まずは体験しよう」という哲学を田村は非常に大切にしています。ところが、『オンライン内見』のテスト運用に踏み出したときは、その哲学が実践されなかったのです。店長たちは先入観を持って判断し、体験することを避けました。田村(=ハウスコム)の信条を軽んじるものです。これには、田村も黙っていません。大号令です」
Q:田村社長(画像上)の大号令とは?
「「良いも悪いも、やってからいえ! 体験していないのに良し悪しを語るな! 」です。この価値観を浸透させるには時間を要します」
Q:追加の指示を出したのでしょうか?
「ええ。リスト化し、細かく指示を出しました。たとえば、次のような感じです」
- スタッフ同士で、”店舗スタッフ役”と”お客様役”にわかれ、ロープレをする
- ”店舗スタッフ役”のスマホから撮影しているカメラ映像が、”お客様役”のスマホにちゃんと映るか
- 音声は問題なく聞こえるか
「そうしたチェック、使用感のフィードバックを回収するような指示です」
Q:期限は?
「設けました。「本日中に必ず試すように」というオーダーです」
Q:その日のうちに実行された?
「されました。朝一番に通達し、夕方には、テスト運用に取り組む、全20店舗で完了です」
Q:店舗スタッフへのフォローは、どうされたんでしょうか?
「そこは、トライエルさんの功績が大きいですね。「店長やスタッフが失敗しないように」と、野田社長が当社のヘルプデスクのような立ち位置でかかわってくれました」
Q:ハウスコム専用の問い合わせ窓口ですか?
「そうです。わからないことがあったら電話で相談できるようにと、1名、新たにスタッフを野田社長が手配してくれて」
Q:20店舗からの問い合わせ対応を2名で? 大変そうに感じますが、野田さん(画像下)がパンクすることはなかったのでしょうか?
「踏ん張ってくれましたよ。フリーダイヤルでつながる番号も用意してくれて、さらに、野田社長とトライエルの営業のかたの計2名で、テスト運用をしている全20店舗を訪ねてくれました。一店舗ずつ、野田社長が電話し、店長にアポをとって、です」
挨拶を兼ねて伺います。そのときでも後日でも大丈夫ですから、もし、使いかたがわからなければ連絡ください!(野田氏)
 「野田社長は、そういって、一人ひとりの店長に直接、会いに行ってくれました」
「野田社長は、そういって、一人ひとりの店長に直接、会いに行ってくれました」
Q:電話でのフォローと、店舗を訪ねての対面フォローですか?
「はい。それはもう、ハウスコムにとっては、社員教育ですね。よく、協力してくれました」
Q:このあとのテスト運用は、順調に進みましたか?
「ええ。田村の大号令や、野田社長のフォローのかいがあって、20店舗ではいったん、全員が『オンライン内見』を試すところまで、こぎつけました。ここからは、テスト運用の狙いである、「まずは、やってみること。そのフィードバックにある、問題点をハウスコムの本社で集約して、トライエルさんとの共通課題として認識し、一つひとつ解決していくこと」の繰り返しです。いわゆる、PDCAサイクルを回す、というやつですね」
Q:”追客の連絡をするタイミングでオンライン内見の提案をすると来店率が上がる”という成功事例が生まれたのは、PDCAを回しているときですか?
「そうですね。改善を繰り返すうちに、「こう使えばもっと効果的では」「こんな使いかたもできるんじゃ」というアイデアを自分の店舗で試すスタッフが増えていきます。アイデアが何がしかの成果に結び付いたとき、店長たちの間で噂になるんです。たとえば、こんなように」
〇〇店の店長が『オンライン内見』を使って、来店率を効果的に上げているらしい
「こうなると全国の店長たちから、「うちでもやりたい」「全店舗展開はいつか」といった問い合わせがエリアマネージャーを通り越して、直接、私のところに集まるような状況です。ここで、『オンライン内見』の全店舗展開を視野にいれます。最終確認ということで、テスト運用の店舗数をそれまでの倍の数である”40”に増やしました」
Q:20から40店舗に増やした感想は?
「トライエルで取締役を務める、大住憲司さんの功績が大きいです。これは、店舗スタッフから聞いた後日談なんですが、40店舗になってからのサポートは、彼が中心となって進めてくれたと聞いています。店舗訪問、全店への電話サポートなどです。当時は、「使いかたマニュアルを見ても操作がわからない」という店舗スタッフが、まだまだ多かったころでした。こうしたことは、いまでこそ、もう、ほとんど起こりません。なぜなら、大住さんが地道に対応してくれたからです。彼の功績にも触れておきたいと思います。「大住さんに、使いかた相談の電話をかけると、すぐに、店舗へ向かってくれた」当社のスタッフから、そう聞いています。そのことを野田社長に話すと、こんな話をしてくれました。
店舗のサポートに出かけた大住さんが、サポートを終え、トライエルさんの事務所に戻ってきたときの会話だそうです。このとき、大住さんは野田社長に、よく、こんな話をしたんだとか」
やっぱり、顔を見ながら話すのと、そうしないのとでは、相手の納得感がまったく違いますよね。顔を見ながら話すと、相手の理解度をこちらが把握できますから、しっかりと伝えられたときは、相手の表情を見て、「納得していただけた」という実感がわきます。新しい作業だし、店長やスタッフのかたは、気乗りがしないでしょうから、できる限り納得して使っていただきたいですよね(大住氏)
「野田社長や大住さんのサポートのかいあって、店長だけでなく、店舗スタッフも次第に『オンライン内見』を使いはじめます。しばらくすると、営業会議でエリアマネージャーから、”あの報告”が上がってきたんです」
面白い使いかたをしている店舗がありました。来店してくださったお客様に『オンライン内見』を使って、成約率を上げるものなんですが――
「この報告には驚きました。当初、私たちがまったく想定していなかった使いかたです」
Q:この成功事例が、全店舗展開の足がかりになった?
「はい。店長たちの目の色も変わりました」
Q:『オンライン内見』が売上アップにつながる施策であると、わかったからですね?
「その通りです。来店してくださったお客様に『オンライン内見』を使うという成功事例を真似る店舗が続出します。実施件数は増え、つまずきやすいポイントや、その改善策も集まりはじめます。全店舗展開の手応えを確かなものとして感じたのは、このあたりですね。スキームも次から次へと整いました。
いまでは、店舗スタッフの利便性を考慮し、当社の顧客管理システムの一部として『オンライン内見』が使えるような仕組みに改善し、運用を続けています」
Q:現在、トライエルさんとのつながりは?
「野田社長に、利用状況のフィードバックをお願いしているので、いまも、関係は続いています。フィードバックの頻度は、3か月に一度くらいのペースです。
今後も、こうした協業やアライアンスには、積極的に取り組みたいと思っています。これは、田村の意向です。当社は、今年(2019年)の2月より、『るーむはっく』という取り組みもはじめました。ライターの高橋将人さんに、YouTuberになってもらい、賃貸生活のお役立ち情報を発信するものです。
当社の店舗数は、今年に入り180を超えようとしています。数字の推移は順調です。このまま、田村を先頭に、本業である”賃貸サービス業”を進めながら、その付加価値として、あるいは、お客様のニーズにあったサービスとしてのIT活用を目指していきます」






