クラス久保裕丈氏インタビュー! 初代バチェラー・ジャパンの不動産テックサービスとは

- 初代バチェラー・ジャパンの不動産テックサービス『CLAS(クラス)』が好調。
- C向けにローンチした家具シェアリングサービスで、2018年の後半からB向け事業もスタート。
- これに問い合わせが増加中、今春にも導入1,000社の予定。
- そんな久保氏直筆サイン入り著書を抽選で1名さまにプレゼント!
はじめに
不動産テック領域で、いま、注目を浴びている人物の1人に、久保裕丈氏がいます。久保氏は、Amazonプライム・ビデオで配信された、恋愛リアリティ番組にメインキャストとして出演。以来、連日のように、SNSやネットニュースで取り上げられています。
久保氏が人気を集める理由はいくつもありますが、代表的なキーワードを列挙すると以下です。
- イケメン
- 東大卒
- ベンチャー企業の経営者
- リッチな独身男性
- 初代バチェラー・ジャパン
- 女性への接し方が紳士的
 そんな久保氏をなぜ、SUMAVEも取り上げるのか。それは、彼が経営する株式会社クラスというベンチャー企業が、家具シェアの不動産テックサービス『CLAS』を展開しているからです。
そんな久保氏をなぜ、SUMAVEも取り上げるのか。それは、彼が経営する株式会社クラスというベンチャー企業が、家具シェアの不動産テックサービス『CLAS』を展開しているからです。
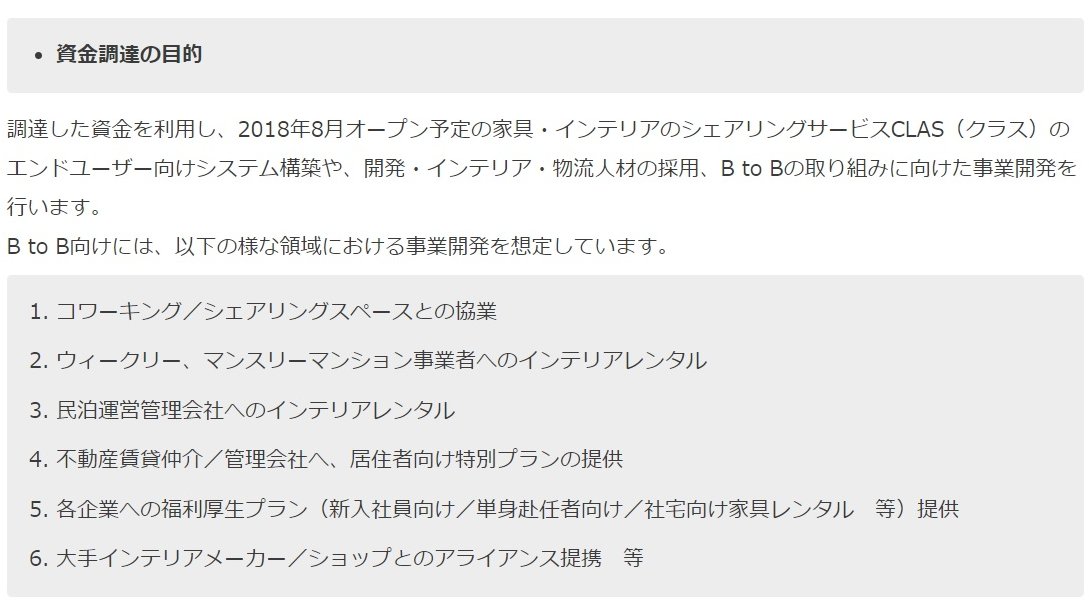
画像出典元:PRTIMES
もともと、C向けにローンチさせたサービスですが、2018年8月より正式にB向け事業もスタート。2018年11月8日にはスペースマーケットと、11月20日には、店舗・オフィスの空間創造事業やオンラインプラットフォーム事業を展開するユニオンテックとの提携も発表しました。
話題の人物によるB向け不動産テックサービスの詳細を探るべく、同社で代表取締役社長を務める、久保氏裕丈氏に話を聞きました。
『CLAS』誕生の背景
 Q:まずは、御社のサービスについて教えてください。『バチェラー・ジャパン』に出演していたときからの事業なのですか。
Q:まずは、御社のサービスについて教えてください。『バチェラー・ジャパン』に出演していたときからの事業なのですか。
「いえ、違います。株式会社クラスは、番組終了後に起業した会社です。きっかけは私の引っ越しでした。1年前くらい前にさかのぼります。当時、私は引っ越をしたばかりでした。住まいを定期的に変える習慣がある私は、そのたびに家具を買い替えます。新居の広さや部屋のテイストに、それまで使っていた家具があわなくなるためです」
Q:使っていた家具はどうするのでしょう。
「友人に譲るなど、処分の方法は引っ越し時の状況によって違います。ただ、毎回同じなのが、家具を新しく買い替えること。1年くらい前も、新居用の家具をそろえるため、付き合いの古い家具屋を訪ねました。そのとき、家具屋の代表と、「使える家具を引っ越しのたびに処分するのは、なんだかもったいないよね」という話に」
 「その人物とは昔からの知り合いで、気心の知れた間柄です。家具を見立ててもらいながらの、何気ない会話でしたが、「家具を借りる文化にしちゃえばいいよね」と、どちらからともなく。
「その人物とは昔からの知り合いで、気心の知れた間柄です。家具を見立ててもらいながらの、何気ない会話でしたが、「家具を借りる文化にしちゃえばいいよね」と、どちらからともなく。
それがきっかけで、『CLAS』というシェアリングサービスを立ち上げることになりました。家具屋の代表には、COOとして当社に参画してもらい、家具シェアの事業をスタートさせたという背景です」
Q:事業の着想から起業までが、非常にスピーディであるように感じます。ビジネスのスピード感は意識されていますか。
「そうですね。私は、新しいことをはじめるとき、「これはやりたい」「いける」という手ごたえを得られたら、ほぼ、ノータイムではじめます」
 「以前に経営していた『ミューズコー(MUSE & Co.)』をミクシィに売却したときもそうでした。今回も事業計画は、それなりにちゃんと作りましたが、くまなく市場をリサーチすることなどはしません。
「以前に経営していた『ミューズコー(MUSE & Co.)』をミクシィに売却したときもそうでした。今回も事業計画は、それなりにちゃんと作りましたが、くまなく市場をリサーチすることなどはしません。
知人の経営者をはじめ、大勢に事業のアイデアを“壁打ち”して、会う人会う人に、しつこく聞きます。でも、それくらいですね。「ポジティブな声が3割くらい集まれば事業をはじめよう」そう考えていたところ、ほぼ、全員からポジティブな意見を聞けたので、「いける」と確信しました」
Q:ポジティブな声とは、どんな意見でしょうか。
「「家具を気軽にレンタルできる(CLASみたいなサービス)なら使ってみたい」などですね。さらに、今回のように、これまでとは違った文化のサービスでマーケットインを狙う場合は、熱烈なファンを作ることが重要になってきます。総花的にターゲットを設定すると、ビジネスは早いフェーズで息詰まるものですから。
そうならないためには、“利用者となるユーザーに深く刺さるサービスコンセプトがあるかどうか”がもっとも重要です」
商品選びでユーザーを迷わせたくない
 Q:サービスのコンセプトをユーザーに深く刺すためのポイントを教えてください。
Q:サービスのコンセプトをユーザーに深く刺すためのポイントを教えてください。
「1つは、コンセプト設計にこだわることです。たとえば、トマトに包丁を刺すとき、刃の先端が尖っていると、少ない力で深い切り込みを入れられます。先端を鋭くすることに、こだわればこだわるほど、わずかな力で刃を深く刺せます。新規事業の考え方も同じです。
ユーザーにサービスを刺すとき、コンセプトが尖っていると、少ない施策で深く刺すことができます。深く刺さるとは、深く愛されるサービスである、ということです。コンセプトを鋭くすることに、こだわればこだわるほど、わずかな施策でコンセプトを深く愛してもらえます」
 Q:『CLAS』でいうところの、コンセプトにこだわるとは、たとえば、どのような点ですか。
Q:『CLAS』でいうところの、コンセプトにこだわるとは、たとえば、どのような点ですか。
「商品のデザイン数を絞っているのが一例です。私たちの家具は、デザインのかたでいうと10型くらいで、サイズと色の展開が片手で数えられるくらいと、商品のデザイン数を意図的に少なくしています。少なくすることで、ユーザーは迷いにくくなるのです。
迷いにくいので、物事が前へ進みやすい
↓
進みやすい、は、はじめやすい
↓
はじめやすい、は、サービスが刺さりやすい
デザイン数を減らし、「どの商品にしようかな」とユーザーを迷わせない工夫です。こうしたコンセプト設計に、私たちはこだわっています」
Q:『CLAS』のユーザーには、どのようなペルソナを想定していますか。
「現時点では、ライフステージが変化するスピードが速く、人生で2回目の引っ越しをする人がメインのペルソナです。
“更新料を払わず、2年くらい住んでは引っ越す“を繰り返し、キャリアアップとなる転職のタイミングがキャリアの初期から訪れ、昇進スピードも速い。彼ら彼女らのような、ライフステージの変化が速い人たちは、IT企業の社員である場合が多い、と想定しています」
重なるエンドユーザー。B向け事業の狙い
 Q:B向け事業についてお聞きします。具体的にどういったサービスなのでしょうか。
Q:B向け事業についてお聞きします。具体的にどういったサービスなのでしょうか。
「2019年1月現在は、以下のような内容のサービスを検討しています。
- ホテルやホステルへの家具・家電レンタル
- マンスリーマンションや家具付き賃貸マンションへの家具・家電レンタル
- 民泊事業運営者への家具レンタル
- 賃貸や分譲マンションへのステージング
- オフィスへのオフィス家具レンタル
- スペースマーケット等、スペースシェア事業者との提携
- 不動産仲介業者との提携
B向け事業を展開する理由の1つに、導入までのスピードの速さがあると考えています。C向け(個人)の文化形成には時間がかかりますが、B向け(法人)には”リース”という文化がすでにありますよね。これは、レンタルに近い利用方法です。つまり、リースの定着しているB向けのサービスなら、導入までが早いであろうと考えての施策です。
『CLAS』ならサービス利用にあたり、手間やコストがほとんどかかりません。デザイン、利用期間、納期の柔軟性が高く、手前みそですが、こうしたメリットからコンペなどになっても競り勝ってきました」
Q:『CLAS』を通じて届けたい価値、または、思いなどを教えてください。
「シェアリングサービスなどのプラットフォームを利用するオーナーが、スペースシェアリングをはじめやすくすること。または、初期投資のリスクを軽減すること、などですね」
 「オーナーや物件ホストがシェアスペースを作るとき、家具をそろえるための初期費用は、思いのほか負担になります。投資物件としてスペースを見たときのキャッシュポジションも悪くなりがちです。家具を購入してシェアスペースを続けていけば、オーナーは在庫問題で困るリスクもあり、そうした視点から、スペースマーケットさんと『CLAS』の親和性は高いと考えています。
「オーナーや物件ホストがシェアスペースを作るとき、家具をそろえるための初期費用は、思いのほか負担になります。投資物件としてスペースを見たときのキャッシュポジションも悪くなりがちです。家具を購入してシェアスペースを続けていけば、オーナーは在庫問題で困るリスクもあり、そうした視点から、スペースマーケットさんと『CLAS』の親和性は高いと考えています。
それとは別で、ベンチャー企業向けにオフィスチェアを貸し出す事業例が、ユニオンテックさんとのアライアンスです」
 Q:不動産仲介業者との提携とは、どのような内容ですか。
Q:不動産仲介業者との提携とは、どのような内容ですか。
「ユーザーが私たちのサービスを利用するタイミングの1つに、引っ越しがあります。そこで、不動産会社さんへ向け、特別価格で家具を貸し出すという内容です。当社にとってはレベニューシェアをさせていただく取り組みです」
Q:B向け事業ははじまったばかりのサービスですが、導入実績はどのくらいですか。
「今春以降では、ホテルやマンスリーマンションなど含め、1,000部屋以上の導入が決まっています。たとえば、Airbnbなどでゲストルームを作ろうとすると、かかる費用がインテリアだけで4,50万円くらいになることも。そのあと、思い描いていたような運用に至らなかった場合、ホストはどうしたらいいか。という話があります。
そうしたリスクを回避するのに、家具シェアやレンタルサービスはうってつけ。私は、投資物件にこそ、CLASのようなサービスがフィットするのではとも考えます」
Q:C向けとB向け事業のバランスについては、どのように考えていますか。
「決まると大きいB向け事業ですがが、どうしても人の手を介する必要があることから、最終的に自律的なスケールを狙っていくのはC向けです。しかし、C向けの需要が大きく花開くのは1.5~2年後くらいだと私は考えています。それまではB向け事業を中心に成長していくことになるでしょう」
 「B向けサービスのユーザーであっても、必ず、どこかでC向けユーザーと一致してくるはずです。たまたま泊まったホテルの家具が『CALS』のものだったり、ユーザーが勤める会社で利用されている家具が『CLAS』のものだったりすることで、最終的にはC向けサービスの認知を獲得することにつながります。それは、私たちがB向け事業に積極的に取り組む理由でもありますね」
「B向けサービスのユーザーであっても、必ず、どこかでC向けユーザーと一致してくるはずです。たまたま泊まったホテルの家具が『CALS』のものだったり、ユーザーが勤める会社で利用されている家具が『CLAS』のものだったりすることで、最終的にはC向けサービスの認知を獲得することにつながります。それは、私たちがB向け事業に積極的に取り組む理由でもありますね」
Q:最後に、今後の展望を教えてください。
「ユーザー本位ではないサービスの行き先は明るくないと、私は思っています。家具の領域もその1つなのではないか、というのが私の考えです。不動産の領域にも、近しい課題はあるように感じていて、ずいぶん先の話になりますが、ゆくゆくは不動産事業もてがけたいと思っています。
たとえば、数か月単位で、イケてる物件に気軽に移り住めるとか。マンスリーマンションがすでにありますが、それとはまた、違ったコンセプトのサービスです」
 「いまの私は、家具というキーワードを入り口に“人を軽やかに”、“ライフスタイルを自由に”することに関心が向いています。しかし、ビジネスを進めるうえで産業や領域への執着はありません。不動産テックの領域は、人の暮らしを包括しますから、さまざまな業界とのかかわりは欠かせないという認識です。タイミングやめぐりあわせ次第で、今後もCLASを介して、よりよく暮らしたいと願う人たちの伴走者でありたい。それが私の思いであり、展望です」
「いまの私は、家具というキーワードを入り口に“人を軽やかに”、“ライフスタイルを自由に”することに関心が向いています。しかし、ビジネスを進めるうえで産業や領域への執着はありません。不動産テックの領域は、人の暮らしを包括しますから、さまざまな業界とのかかわりは欠かせないという認識です。タイミングやめぐりあわせ次第で、今後もCLASを介して、よりよく暮らしたいと願う人たちの伴走者でありたい。それが私の思いであり、展望です」
■スチール撮影/芹澤裕介






