1000店舗が導入。VR内見のトップランナーに聞く!VRが部屋探しに与える影響とは
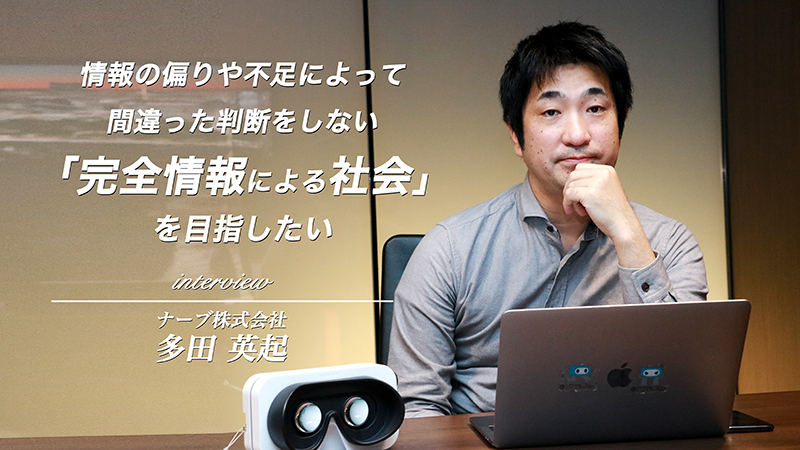
- ナーブの提供する「VR内見」は、導入に伴うスタッフの学習コストをほとんど要しない
- VRが部屋探しに与える影響は3つ考えられ、そのどれもが不動産業界の活性化につながる
- ナーブが目指すのは、情報の偏りや不足によって間違った判断をしない「完全情報による社会」である
以前に、「360度カメラ「THETA」で見える世界。今求められる不動産情報の質の高さとは?」でVRコンテンツを利用した内見をご紹介しましたが、次々にVRを使った内見の導入が報告されています。
2017年9月に、近鉄不動産はマンションのモデルルームにHTC Corporationの「VIVE™」を利用した「VR体験ルーム」を設置。同サービスでは、部屋、共有部分、そして室内からの眺望までをVRで体験することができます。
大東建託は、2017年末より国内10店舗でナーブ株式会社のサービスである「VR 内見™ plus Movie」の試験導入を開始しました。このサービスは、従来の静止画をつなぎ合わせたものと異なり、360度カメラを使って撮影した動画を静止画情報とつなぎ合わせ、より「ここにいる」という臨場感を味わえるようにしたもの。さらに、Googleストリートビューと連携することで、室内のみならず、物件の周辺環境などのVR体験も提供しています。
このように、VR最新技術の導入は、大手不動産会社を筆頭に目まぐるしい速さで進められています。そこで今回は、VRでの家・部屋探しに関連する企業のトップランナーとして注目されているナーブ株式会社(以下ナーブ)の多田英起社長に、VRを使った内見の現状とVRがこれからの家・部屋探しに与える影響を聞きました。
ナーブの「VR内見™」とは、VR技術を使って不動産物件を疑似内見できるシステムのことです。「VR内見™」の操作方法はスマホとほぼ同じで、導入に伴うスタッフの学習コストがほぼないそう。管理会社が撮影済みの物件であれば、システム上にデータが存在しているので、物件の撮影に行く手間も省けます。
実際の不動産仲介会社での接客の際に、ナーブの「VR内見™」がどのように使われているのかを知りたい方は、以下の動画をご覧ください。
累計150回を超えるバージョンアップをし続けた先にある今
Q:現在、御社の「VR内見™*」はどのくらい利用されているのでしょうか?
多田: 2015年10月に本格的なサービスを開始した当初は利用店舗数が伸び悩んでいました。しかし、昨年5月頃より急速に増えてきて、現在は1000店舗で導入されています。
*ナーブの提供しているVRを使った内見システムの名称。以下、「VR内見™」はナーブのサービス名を指します。
Q:利用店舗が増えてきている要因はどこにあると思いますか?
多田:サービス提供を始めて以来、小さなものも含めてこれまでに150回以上のバージョンアップや機能追加を繰り返しています。ちょうど100回目のバージョンアップあたりから、急速に利用店舗が増えたのですが…。
率直に言って、どの機能がきっかけなのかはわかりません。小さな修正を根気よくやってきたことが、利用店舗の増加につながったと認識しています。
VRと内見という言葉をセットで目にしたり耳にしたりする機会が増えたので、不動産会社の方の中で「うちもそろそろVRを使った内見を考えないとな」という人が増えたのかもしれませんね(笑)。
Q:次々に機能を追加されていますが、最新のサービスを教えてください。
多田:VR全般に言えますが、Googleストリートビューなどのように画面がワープしてしまい中間の情報がわからないという問題が当社のサービスにもありました。そこで、それを解決するサービス「VR 内見™ plus Movie」を2017年の11月にリリースしました。かなりユーザー体験の質が良くなったと思います。
VRで解消したいのは、業界に現存する「ゆがみ」だった

Q:なぜ部屋探しにVRが有効なのでしょうか。
多田:接客する不動産会社の社員とお部屋探しをする来店客では、知識や情報に対する理解力に差があります。例えば「○駅徒歩5分、RC造マンション3階の2LDKの部屋」という情報を聞けば、不動産会社ならすぐに部屋のイメージができると思います。一方で、来店客はイメージできない場合がほとんどです。
文字情報だけでは、一般の人たちには不十分な場合もあるのです。でも知識が豊富な不動産会社側は、イメージができてしまいます。このお客様との経験や知識の差による空間の把握能力の違いに気がつけていないケースが発生しているのだと思います。
これが、不動産会社側と顧客の間に生まれるある種の「ゆがみ」であると考えたのです。
これは他のネットサービスの世界でも起きています。今なら、動画を使ったレシピサイトが伸びていますよね。写真と文字情報だけだったサイトより、動画があったほうがわかりやすい。ユーザーにそう認識されているから、利用が増えているんだと思います。
不動産仲介では、「VR内見™」を使って来店客にヴァーチャル体験をしてもらうことによって経験による空間把握能力の差を埋めることを目指しています。
Q:ユーザー側の経験不足を補うことができるというわけですね。では、不動産会社にとってはどのようなメリットがありますか?
多田:実は私は家探しをする客側だけでなく、不動産会社側も困っていると思っています。例えば「通勤時間40分以内」という条件で部屋探しする場合、会社のある場所から同心円上に探せばかなりの選択肢があります。だけど会社から東側と西側で良い部屋があっても、どちらも内見に行くのは時間がかかりすぎる。だから、不動産仲介の担当者は「この辺で探しましょう」と、まずはエリアを絞ってしまいます。
客の立場で考えると、「他にもあったはずの選択肢を奪われた」と思うかもしれません。ですが、これは悪い接客とも言い切れません。土日に来店客が集中するなかで、効率よくやろうと思えばどうしてもそうなってしまう。丸一日使って、候補となる全ての部屋を内見して契約まで行っても、賃貸仲介手数料一月分では経費倒れになる。不動産会社からするとやりたくても、できないわけですね。そこに多少の「ゆがみ」があると思います。
それを「VR内見™」で解消すれば、双方にとってメリットがあると思うのです。
導入後は成約率が1.5倍 — 実証されるVRの効果

Q:店舗で利用されている方の反応はいかがでしょうか。
多田:新築物件やまだ居住中の中古物件、入居中の賃貸物件はもともと内見が難しかった。そういった物件を紹介する場合、「VR内見™」があることが来店客の満足度につながっているのはありますね。
そのほかに、複数の物件をVRで内見をして絞り込むことで時間が削減できる点はとても評価されています。
Q:実際に「VR内見™」で成約率が向上した店舗もありますか。
多田:不動産仲介のニチワ様では、退去予定の物件で「VR内見™」の貢献度が高いようで、導入後は成約率が1.5倍になったそうです。利用された来店客向けのアンケートでも、退去予定の部屋を内見できる点は好評でした。
Q:では逆に、VRを使った内見での来店客から言われたトラブルやクレームなどもあるのではないでしょうか?
多田:隠す訳ではないのですが、あまりないんです(笑)。逆に、VR用に使う360度カメラの画像をクレーム対応で役立っているという側面もあります。賃貸の場合、退去時に部屋の傷について問題になることがありますよね。その際、VR用の画像で元の状態を確認して、瑕疵(かし)がどちらにあったのかを確認するという使い方です。サービス提供側としては、全く想定していなかったものですが、VRを使った内見の画像の蓄積や利用が進めばこうしたことが今後もたくさん出てくると思います。
Q:今後、改善したいことはありますか?
多田:利用される方の中には、「VRの部屋情報は嘘なんじゃないか」と思われる方もいるようです。「都合の悪い部分は見せていないはずだ」というわけですね、もちろんそんなことはないのですが、こういう不信感は払拭しなければいけないと思っています。
もう一つは、VRだけでは部屋以外の周辺環境までわかる訳ではないということです。音、匂いなども含めて、マンションであれば隣室や上下階の住人や様子も部屋探しの重要な要素なので、そこの情報差をどうやって埋めるかは今後の課題ですね。
成功の鍵は、どこまで利益を度外視して死ぬ気でやれるかどうか

Q:開発する中で最も苦労した部分はどこでしょうか?
多田:先ほども言いましたが、リリースしてから毎週のようにサービスを改善しています。それも、こちらの都合で改善するのではなく、やはり現場の実務に即して良くなっていないとリピートして使ってもらえないと思っています。だから実務を知るために不動産店舗に通いつめて、細かな実務については調べてきました。本当に入り浸っていたので、接客の邪魔だと怒られたこともありました(笑)。
実務を知って、「VR内見™」だけでなく不動産会社の手間を削減できるサービスを追加することに気が付いたのも良かったです。例えば、「VR内見™」用に撮影した360度カメラの映像から、ポータルサイト用の画像が切り取れるサービスもその一つです。切り取った画像は歪みを自動で補正するので「社員がデジカメで撮影した画像より良い」と言われたこともあります。
その他にも、部屋の画像に家具写真を合成して、ホームステージング画像を作れるサービスも好評です。そこからさらに実際にホームステージングを発注できるサービス「VRホームステージング」も始まりました。これからも、仲介がしやすくなるサービスを追求したいと思います。
Q:現存する「どこでもストア™*」のようなVRを活用した接客サービスは、不動産業以外にも応用が可能だと思います。まだ先の話にはなると思いますが、どういった将来があると考えていますか?
多田:旅行業にはすでに実績が出ています。今まで、なんとなくでハワイを選んでいた人が、VR体験することで旅行先が広がる、ホテルのアップグレードにつながったなどと多くの人にいい効果をもたらしています。
当社が目指しているのは「完全情報による社会」というものです。「完全情報による社会」というのは、情報の偏りや不足によって間違った判断をしないようになる社会。それを、まず不動産の分野で実現したいと思います。
*ナーブの提供している遠隔通話とVRを使った無人店舗サービスの名称
Q:今後の目標を教えてください。
多田:「100回の改修は、100回の失敗をしたということだ。」ある先輩の経営者に言われた言葉です。
これまでに投じた開発資金は合計で数億円を超えます。これからVRを使った内見を一から始めようと思うと、100回以上の失敗をしてきて、それ以上の投資をして僕たちと勝負しなければいけないということになります。
実際に不動産会社の方に、VRを使った内見で当社以外と組むのはちょっとリスクです、と言われたことがあります。つまり、シェアが圧倒的に強い僕たちみたいな会社がいるのに、わざわざ他のサービスを選ぶ理由が見つからないということのようです。
それでも、 VRを使った内見が根付き、部屋探しのやり方が変わるかどうかは、これからが重要です。どこまで利益を度外視して、死ぬ気でやれるかだと思って、追求していきたいと思います。
目標は、全国5万店舗で導入してもらうことです。現在150万戸がプラットフォームに載っています。これが500万戸くらいになると、部屋探しはほとんどがVRで内見ができるという印象になる。そこを目指したいですね。
まとめ
VRを使った内見の先駆者であり、業界トップを走り続けるナーブの代表に話を聞いて浮かび上がった「VRが部屋探しに与える影響」とは、以下のようにまとめられます。
今後、VR内見が普及するにつれて、
- 経験による空間把握能力の差を埋めることができ、顧客と同じ目線での会話を可能にする
- 時間的制約のせいで顧客の選択肢を狭めざるを得なかった『不動産会社』。それによって選択肢を奪われていた『顧客』。双方のニーズを満たすことができる
- 退去予定の部屋や未完成の物件の内見の疑似体験が可能になったことで物件が空室である期間が減る。
という3点が予想されます。
リクルート住まいカンパニーが2015年度に行った調査によると、現状10人に一人は実際の内見をせずに成約をしているそう。彼らのすべてがVRを使って内見しているかどうかは不明ですが、実際の物件を内見することにこだわらずに成約をする人の数が増えているのは、数字でも現れている事実です。
さらに、VRでの内見によって、実際の物件を内見するのと同程度の物件に関する情報提供が可能になっています。これは、ナーブの目指す、情報の偏りや不足によって間違った判断をしない「完全情報による社会」を実現するという、一つのモデルではないかと思います。






