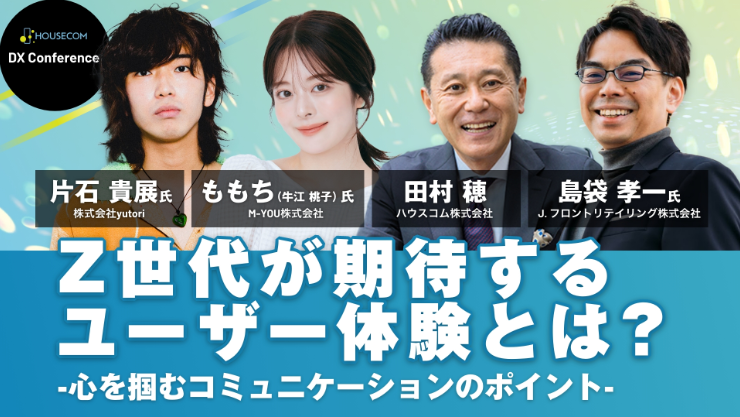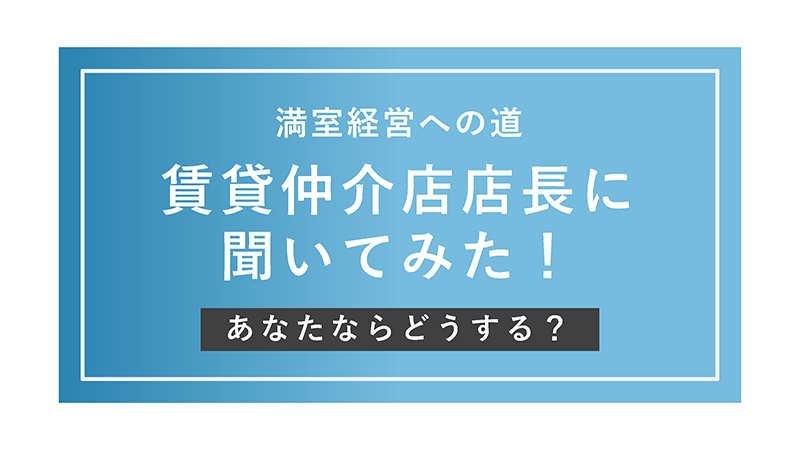【2022】スマートホーム普及のヒントは「代替性」と「子育て」? ニューノーマルの時代に求められる住環境も【住宅DXウェビナー】

- ニューノーマルの住環境では通信環境・通風・換気・遮音性・省エネ仕様が重要に
- スマートホーム普及のヒントは代替性、子育てのスマート化、機器の初期設定
- 人々の幸せに寄与するスマートホームを
2022年2月25日一般社団法人リビングテック協会は第4回目となる「LIVING TECHカンファレンス2021-2022 2025年の社会課題を解決する住宅DX」を日経BP総研との共催で開催しました。
今回は株式会社リクルート・池本氏の講演「見えてきたニューノーマルとテクノロジーで進化する暮らし」をレポートします。
業界横断型・3つの社会課題に関する講演と6つのセッション
「LIVING TECHカンファレンス2021-2022」は、大阪万博が開催される2025年に向けて社会課題を解決する住宅DXのウェビナーです。
業界を横断し、日本の住まい・暮らし方について3つの基調講演と6つのテーマについて多くのパネリストの講演・セッションが行われました。
今回は株式会社リクルートの不動産ポータルサイト「SUUMO」編集長兼SUUMOリサーチセンター長の池本洋一氏が語る「見えてきたニューノーマルとテクノロジーで進化する暮らし」の講演のポイントをまとめていきます。
ニューノーマルの暮らしで重要視されるものとは
コロナ禍ではテレワークが普及し在宅時間が増加しましたが、新しい住環境に求められるものは何でしょうか? 池本氏はユーザー視点でニューノーマルの暮らしで重要視されているものを語ります。
「新築マンション検討者に「住宅・住宅設備必要度×必要度の変化」についての調査を行ったところ、必要度が高いものは基本的な通信環境・通風・換気・遮音性・省エネ仕様の4つです」
池本氏は1位がワークスペースになると予想していましたが、検討者には快適性が重視されているそうです。
「家に「快適性」を求める人が増え、利便性の高い宅配ボックスや通信環境といった新しい部分を求めていくという話になっています。共用部では通信速度の速い環境が求められるのが当たり前。また、アンケートの結果では収納は重要と書かれています。あと景色に関する価値が上がってきたと思います。
今後定着しそうなものは、優れた通信環境と通風・省エネ・遮音性といった快適性を司るようなものに加えて、可能であればワークスペースと宅配ボックス。宅配ボックスも冷蔵品・冷凍品も対応できる物が増えています」
池本氏が「真鶴の家プロジェクト」で実感したスマートホーム普及のヒントとは?
カンファレンスを開催する日本リビングテック協会では、神奈川・真鶴町にある「真鶴の家」 で、スマート照明、お掃除ロボット、スマートスピーカーなどを設置したスマートホームを体験する「真鶴の家プロジェクト」を実施しています。
「スマートホームによるWell-being(幸福・満足な生活)の実現」を提案し、2組の家族にIoT機器について勉強会を開きスマートホームの生活を体験してもらいました。
イベントに参加した池本氏が実感した、スマートホーム普及のための仮説は以下の3つとなっています。
- 何かの代替になっているか?
- 子育てのスマート化
- 機器の初期設定の簡素化
1.何かの代替になっているか?
スマートホーム普及のためには、スマート化が「何かの代替になっているか、代替に対して優位性があることを明確にすることです」と池本氏は提案します。

スマートホーム導入にはコストがかかりますので、「代わりになる」だけではなく「優位となる(メリットが大きい)」ことを強調することが重要という話です。
「例えばお掃除ロボットは割と普及していますよね。これは通常のお掃除機の代替になり時間効率が優れているから(ではないでしょうか)。吸引力を求めているお客さんの代替にはなってないかもしれませんが、そこそこ掃除できればいいという方の代替になっている」
「スマートスピーカーが何の代替になっているのかは色々あると思うのですが、一つは田舎にいるおばあちゃんとかとのコミュニケーションツールの代替品になるということを真鶴のイベントですごく感じました。会えなくても近くにいるような感覚がいいなと。まるで隣にいるような、ちょっと窓を通した向こうにおばあちゃんがいるように感じることができる。その再現性が磨きどころです」
「親が仕事をしている間、子どもが動画サイトで同じ動画ばかり見ていると、子どもに “ちょっと好奇心を伸ばしてほしいな”、 “図鑑を見たりしてほしいな”と思うことがあるのでは。そういう時に Alexa (スマートスピーカー)が親の代わりになって興味の幅を広げてくれる装置になったら、結構嬉しいですよね。リビングにそっと置いてある図鑑とかの代替になるという事です」
ロボット掃除機は掃除の代替、スマートスピーカーは遠方に住む家族や大事な人とのコミュニケーション・子どもの好奇心を伸ばすツールの代替となっていることから、普及が進んだと分析します。
2.子育てのスマート化
2点目はファミリー世帯にとって重要な「子育て」のスマート化です。

池本氏は近年共働きの家庭が多い事から「育児と仕事の両立ってみんな一生懸命行っています。誰も別にサボっているわけじゃないけどそれでも大変」と語ります。
「何か少しでもミスがあるとミスした人が怒られストレスになる、という家庭が結構多いのではないでしょうか。
このストレスをいかに軽減させるかが、スマートホームの一つの目的です。
例えば朝の1時間の行動のどこにストレスがあるのか。
カーテンを開けて(子どもに)朝のご飯を用意して食べさせてそして歯磨きさせて、自分も食べて服を着替えて、と結構大変ですね。もう本当に綺麗にタスク管理できないと終わりません。ここをスマートホームの活用によってどれだけ時間の削減ができ、どこまで快適に合理化できるのか(が普及のためのポイントでは)。
たとえば、親がつい『歯磨きしなさいと言ったのになんでやってないの』とガミガミ言う代わりに、Alexa がそっと『次歯磨きだよ』『できた、すごいね! 昨日できなかったのに』と言ってくれたら、子どもはみんなほくほく喜んでくれる。そういう子どもの習慣づけなんかをAlexaがやってくれるという話になると、結構流行るのではと思います」
子育て世帯にとって、IoT・ICT機器を利用することで子育てのストレス軽減・朝の時間の合理化、子どもに必要な習慣を身に付けさせることができたら、スマートホームに代替性と優位性が生まれ、普及に繋がる可能性があります。
教育とICT機器に関しては文部科学省が公表する「2018年度 文部科学白書」の「ICT(情報通信技術)の活用の推進」の章で以下のように記されています。
日常生活の様々な場面でICT(情報通信技術)を用いることが当たり前となっている子供たちは,情報や情報手段を主体的に選択し活用していくための基礎的な資質としての「情報活用能力」を身に付け,情報社会に対応していく力を備えることがますます重要となっています
小学校でもタブレット端末やPCを導入することが当たり前となっている昨今、スマートホームは将来子ども達の教育の要となるかもしれません。
3.機器の初期設定の簡素化
3つめのスマートホーム普及のヒントは機器の初期設定です。
真鶴の家プロジェクトに参加した池本氏は「初期設定が大変そうでした」と語ります。
「とにかく初期設定を楽にしてあげる方法は必要かと思います。機器の使い方に慣れているかどうかは、人によって差があるので。例えば家電量販店の保証サービスと紐付けるなどして、オプションみたいな形にして1~2%程度追加のお金を払ってもらえれば機器の保証も付くし最初の初期設定をやりますよ、というようなサービスなど。初期設定をフォローアップするっていうのをちゃんと仕組みで作った方がいい」と提案します。
「スマートホームは人々の幸せに寄与する、ストレスを軽減させて時間の効率性を上げて今時の生活を支援してくれて、しかも子どもの教育にもいいとなれば(さらに普及していくだろう)」
2021年に創設されたデジタル庁のホームページには「デジタル庁は、我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現を目的とするデジタル社会の形成の司令塔となります」との記載があります。
スマートホーム、IoT機器・ICT機器などの普及によって実現させたいものは「人々の幸せに寄与する」という提言もDX化、スマートホーム普及への重要なキーワードとなる可能性があります。
まとめ
池本氏の講演ではスマートホーム普及のためには、①代替性がある、②子育てのスマート化、③機器の初期設定の3つが重要という仮説が語られました。
今回お届けしてきました「LIVING TECHカンファレンス2021-2022」の内容はごく一部です。筆者もすべてを閲覧しましたが、3つの講演と6つのセッションがあり有益な提言と活発な議論が交わされていました。
2022年で4回目となっており、リビングテック協会のホームページでは3月1日から3月12日まで、そして4月12日から5月16日までアーカイブが配信されています。
次回の開催は未定ですが、他にもイベントが開催される可能性がありますので気になる方はリビングテック協会のホームページ、公式FacebookやYouTubeをチェックしてみましょう。