今、賃貸の不動産営業の現場で利用されているツールとは アンティホーム店長インタビュー
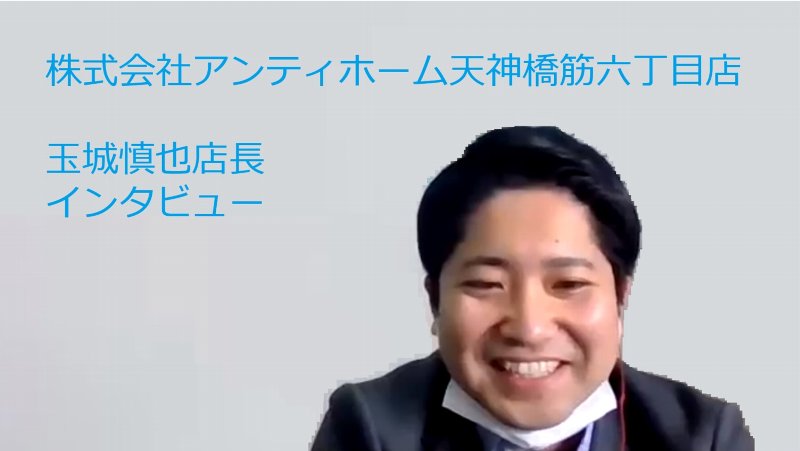
はじめに
今回の記事では、大阪府大阪市北区で賃貸仲介業を営んでいる、株式会社アンティホームの玉城さん慎也店長をオンラインでインタビューしました。玉城さんは元・システムエンジニア。6年前にアンティホームに転職しました。天神橋筋六丁目店の店長になったのは3年前でした。
アンティホームは6年前に創業し、現在は大阪に3店舗を構えています。大阪市北区天神橋7丁目にある天神橋筋六丁目店(本店)、大阪市淀川区西中島5丁目にある新大阪店、吹田市江坂町1丁目にある江坂店の三店舗です。そんなアンティホームで店長を務める玉城さんに、「大阪での賃貸仲介業にコロナがどう影響しているか」「業務のIT化事情」などをお聞きしました。
アンティホーム・天神橋筋六丁目店の店長に聞く
画像出典元:https://www.antynet.co.jp/company/
Q:土地勘がないのでお聞きしたいんですが、天神橋筋六丁目店がある地域は、どんなエリアですか?
玉城さん:栄えていますが、住宅街も広がっていて、梅田駅まで歩いて20分くらい。商業施設もあって、いろんなものが混在しているエリアです。それでいて家賃が安いエリアもあり、単身者や学生でも住めるのが特徴です。
Q:コロナの影響をお聞きしたいんですが、反響にはどんな影響がありましたか?
玉城さん:去年、最初に緊急事態宣言が発出された4月は、だいぶ落ち込みました。法人さんのキャンセルとか。しかし、それ以降5月、6月、閑散期である7月には、落ち込みを一気に巻き返す反響で。今年の1月は例年通りです。2月、3月もフタをあけてみるとそんなに影響はありません。少しだけ落ちましたが、大幅に落ちるって感じではなかったですね。
Q:コロナの影響で反響がならなかったのは去年の4月ぐらい? それ以外は通常に戻ってきている?
玉城さん:そうですね。去年の7月は、これまでの7月のなかで、もっとも売り上げました。
Q:来店率はどうですか?
玉城さん:法人さんで多い契約に、実際のお部屋を内見せず、まったく見ることなく契約を済ませる”見ず決め”があります。それは例年、あることなんですが、オンライン内見ができるということで、来店&内見をせずにオンライン内見を希望されるお客様は増えました。
Q:写真だけを見て入居を決めていたお客様が、オンライン内見を希望するようになった?
玉城さん:そうです。当社では、ほとんどのお部屋を動画撮影しているので、日中に連絡が取れるお客様にはオンライン内見、それが難しいかたに動画をお渡しする。そんな対応も増えました。当社では実際のお部屋を結構、細かく撮影するんですよ。それをYouTubeチャンネルにあげることもしています。
コロナ前から取り組んでいた動画コンテンツ。注力度を高めニーズに合わせて提供
Q:動画コンテンツに取り組み始めたのは、コロナ禍になってから?
玉城さん:それ以前から取り組んではいたんですが、本格的にやりはじめたのは去年からです。
Q:動画撮影を始めた目的は?
玉城さん:内見できないお客様のためというよりは、集客施策の1つとして取り組んでいます。YouTubeのチャンネルに動画を蓄積しているフェーズですが、それがいつか”花開く”ことを期待して。「お部屋の動画がありますか」と言われればお渡しすることもしています。
Q:YouTubeのチャンネルに投稿している動画と、お客様にお渡しする動画は違う?
玉城さん:ほとんど同じです。動画は丁寧に撮影しているので、編集せずに公開しようと思えばできる、という感じです。
Q:「動画を渡している」とは、YouTubeで公開している動画のURLを送る、ということですか?
玉城さん:基本的にはそうなりますが、新着物件へのお問い合わせで、お急ぎのお客様には、未編集の撮影したままの動画を”お客様限り”という限定で送る場合もあります。それ以外の場合は一般的に公開しているYouTubeのURLを送っています。コロナの影響については、売上への大きな影響がありませんでした。それは業界全体でも同じだったんじゃないでしょうか。当社でも落ち込むことはありましたが、本当にマズいかと聞かれるとそうじゃない。「不要不急の外出を避けて」と言われても、引っ越すお客様は明確な理由があって、ほとんどが必要で急なお引っ越しです。動かなきゃいけない人も多い。そういうお客様にオンライン内見が認知されていないこともあって、「内見したい」というご要望は以前と変わらず多いです。実際のお部屋を見ないと決めることができないというお客様の気持ちがあるのも事実です。だから、ご来店されるお客様は、いまでも多いですよ。
Q:同じ市内の引っ越しで、「忙しくて見ている時間ない」「めんどくさい」などを理由にリアルな内見をしないお客様はいますか? オンライン内見だけで済ませるお客様です。
玉城さん:ほとんどいません。市内なら絶対に来ますし、どんなにお忙しいお客様でも、土日のどっちかは休みですから、その日に合わせてご案内しています。
Q:お聞きしていると、コロナの影響はほとんどなさそうですが、成約率への影響もない?
玉城さん:ありません。コロナの影響があったとすると、アポのキャンセルや、引っ越しのキャンセルが数件あったくらいです。「親に相談したら、このタイミングで引っ越すべきじゃないんじゃないかと言われた」「コロナがひどくなってきたので、時期を変えます。引っ越しを急いでないので」「来店がちょっと厳しいので、いまの時期を外します」などなど。引っ越しを急いでないお客様の引っ越しは確実に減りました。明確な理由がないお客様がご来店されなくなったというのもあります。
お客様との連絡手段はLINEが9割。オンライン内見もLINEビデオ通話
Q:次は御社の業務フローをお聞きしたいと思います。集客手段から契約までの一連の流れを教えてもらえますか。
玉城さん:ポータルサイトからの反響があって、そこから電話やメールでお客様とコンタクトします。来店日を決めて、来店してもらい、お部屋にご案内。そのあとはLINEでやり取りを続けます。「お客様がよく使うツールでご連絡したいんですが、電話、メール、LINEだとどれが良いですか」と。当社の場合、基本的にはLINEが9割です。LINEでやり取りをして審査を通過したら、契約日の日程調整もLINEでやります。遠方のお客様など、場合によってはIT重説をして、すべての書類を送ってもらい、契約の不備がなければ鍵渡しでご来店いただくという流れが多いです。
Q:お部屋にご案内したあと、LINEを交換するんですか?
玉城さん:はい。基本的にはそこでLINEの友達登録をしてもらうことが多いです。スムーズに来店までのコミュニケーションがとれるお客様の場合は、もっと早い段階で。反対に、来店へのハードルが高いお客様には様子を見つつメールや電話を使い、当社のHPをご案内してLINEの友達登録をうながします。メールを見るお客様は少ないので、メールを返信しても通知に気づきにくいものです。でもLINEは違います。お客様が頻繁に使うアプリなので、通知にも気づきやすい。私たちとしても、物件や動画のURLを張り付けやすかったり、極端な敬語がなくてもコミュニケーションをとりやすかったり、来店アポにつなげやすかったりします。
Q:内見を終えるまでは、基本的にLINEの友達登録をうながさない?
玉城さん:そうですね。ただ、最初にいただいた反響に返信するタイミングで、LINEの友達登録のURLをメールに貼り付けていますし、追客メールを送るときも毎回つけています。
Q:電話でお客さんとやり取りをしている場合は?
玉城さん:電話がつながるお客様の場合は、「来店どうしようかな」と迷われているタイミングにご案内しています。「LINEで物件のURLを送ることもできますが、いかがですか」など。それをきっかけに、来店へ誘導していきますね。
Q:電話でお客さんとやり取りをしていて、LINEの友達登録を提案するときに気をつけていることは?
玉城さん:「えっ」と思われないようにすること。物件や希望条件などの話を最初にします。「当社で物件をたくさん探せるので、条件とかをお伺いできないですか」「今後、物件の情報を送るので、LINEとかだったら見やすいですか」など。連絡手段は、何が使いやすいかをお聞きします。お客様が、「LINEで」と言えば友達登録をご案内しますし、「メールで」となればメールで。メールが好きな人もいますし、年配のかただと、「電話がよい」となることも。むりにルートを決めないことを大切にしています。
Q:オンライン内見についてはどうでしょう。Zoom、Skypeなどありますが、どのツールがよいですかとお客さんに聞いていますか?
玉城さん:いえ。
Q:御社から指定している?
玉城さん:そうですね。
Q:お客様から指定されたことは? 「Zoomでできますか」などです。
玉城さん:ないですね。一度だけ、「SkypeでIT重説をしてほしい」と言われたくらいです。私たちは店舗をまたいだ会議などでZoomを使うこともありますが、基本的に一般のお客様にはほとんど普及していない印象です。
Q:使い慣れているという点でLINEが好まれる?
玉城さん:その通りです。Zoomのアプリをダウンロードするのはお客様にとって面倒です。何かの操作をお願いするということを極端に減らして、「面倒だなあ」とお客様に思われないことが重要です。
Q:お客さんに「面倒だなあ」と思われると、どうなりますか?
玉城さん:すぐに連絡が取れなくなります。
Q:LINEだと?
玉城さん:チャットのやり取り、ビデオ通話もアプリ内で全部できるので、とてもスムーズですね。いつも使っているアプリなので、お客様にとって取り組むハードルが低い。
IT重説の取り組み事例
Q:IT重説はどうでしょう。 御社では実施していますか?
玉城さん:やっています。契約が10件あったとして、そのうち3件くらいです。
Q:3件は、お客様からのご要望?
玉城さん:はい。でも、新規のお客様をご案内することを考えると、土日に重要事項説明をするのはできるだけ避けたいのが本音です。土日の予定が契約業務で埋まってしまうと、新しいお客様をご案内することができなくなってしまうので。だから、私たちのほうからIT重説をお願いたいという気持ちもあります。お忙しいお客様にとっても、平日の隙間時間とか、遅い時間とかで、ご自宅にいながら済ませることができると便利だと思います。
Q:IT重説を実施するときの担当者は、その契約物件を案内した人?
玉城さん:そうとは限りません。宅地建物取引士(宅建士)であれば重要事項説明をすることはできるので、物件を案内したスタッフではないこともあります。
Q:IT重説だけを担当する専任スタッフがいるとか?
玉城さん:いません。お客様とスケジュールのあう宅建士を当社の三店舗のなかから調整して、アサインしています。
Q:IT重説をするとき、スタッフはどこにいますか?
玉城さん:店舗です。
Q:玉城さんがいる天神橋筋六丁目店のお客様のIT重説を御社・江坂店の宅建士が実施することもある?
玉城さん:あります。新大阪店の宅建士からお客様のスマホにつないでもらうIT重説などもあります。
Q:お客さんから、「物件のことで質問があるんだけど」と言われたら、物件のことを知らない他店のスタッフはどう対応していますか?
玉城さん:事前に物件資料を共有しているのでそれを見て案内してもらっています。オーナーに聞かいないとわからないことはオーナーへ。
Q:資料を見てわからないことはどうしていますか。たとえば、自転車置き場はどこか、ゴミ置き場やゴミの回収日など。
玉城さん:重要事項説明の内容以外のことで、物件資料を見てもわからないことがあれば、「のちほど物件担当者よりご連絡させます」と回答しています。IT重説のポイントは、重要事項説明の内容をしっかりと説明、納得、署名捺印してもらうことなので、そこにご理解いただきクローズさせています。
Q:店舗のスタッフに、「当社でもこれから、IT重説をはじめます」と説明したときのファーストリアクションは?
玉城さん:とくに何も。当社では、スタッフ同士でLINEのビデオ通話をしていましたし、それを使うということなら問題ありません。
Q:ネガティブな反応はない?
玉城さん:ないです、LINEなので。
IT化やオンライン施策に取り組みやすい環境
Q:店舗スタッフの人数を教えてください。
玉城さん:私がいる天神橋筋六丁目店が4名、新大阪店が3名、江坂店が2名です。あと、物件写真を撮影する専門のアルバイトが6名います。
Q:写真撮影専用のアルバイトを雇われているんですか。ということは、動画撮影をする人とは違う人?
玉城さん:そうですね、違う人です。動画を撮影しているのは当社のスタッフです。GoProで撮影しています。
Q:GoProですか。本格的ですね。それは社長の意向ですか?
玉城さん:そうです。けっこう力を入れているんです。社長もそこにはお金かけて真剣に取り組もうとしています。だから、私たちとしてもIT化やオンライン施策に取り組みやすいという環境ですね。
Q:スタッフの年齢層は?
玉城さん:30代前半が一番多いですね。社長が40代の中盤くらい。一番上の人で34歳、一番下が21歳です。
Q:若いですね。玉城さんの話からITルーツへの抵抗感の話がほとんど出てきません。背景には、社長の理解もありそうですが、スタッフがデジタルネイティブであることも関係しているように感じました。いかがでしょうか?
玉城さん:あるかもしれません。当社は6年目の会社で、若いだけじゃなく、社長もデジタルツールやオンライン施策に積極的です。さきほどYouTubeの話をしましたが、当社ではInstagramもTikTokもやっています。TikTokは同業他社もけっこうやっていまして。当社でもTikTokには力を入れています。よかったら見てみてください。
電子契約の普及はオーナーのご協力が不可欠
Q:積極的な姿勢でオンライン施策に取り組んでいるんですね。ほかはどうでしょう、電子契約は使われていますか?
玉城さん:電子契約は6年間の業務のなかで一度だけ。これについては、仲介会社にできることが少なくて、管理会社さんやオーナーさんのご協力が不可欠かと。当社から電子契約にしてほしいと、アプローチすることはできないんです。
Q:不動産業界に電子契約が普及してほしい?
玉城さん:めちゃくちゃ普及してほしいです。やっぱり、楽ですよね。メールを飛ばすだけだし、保証会社にも自動的に連絡が行きますから。そうはいっても、個人オーナーがいらっしゃるので100%電子契約化は難しいでしょうし、高齢オーナーができるかというと簡単じゃないようにも思えて。
Q:「連絡手段はLINEとメールのどちらがよいか」そうやって選べる選択肢があるとお客様にとってよいのでしょうか。電子契約もできるし紙の契約書もできますよと。いかがですか?
玉城さん:うーん、難しいところですね。私たち仲介会社のスタンスから言わせていただくと、業務効率は圧倒的に電子契約です。それはもう、圧倒的に。
――なるほど、アンティホームの玉城慎也店長、今日は貴重なお話をありがとうございました。






