「不動産×ビッグデータ」の過去、現在、未来。清水千弘氏インタビュー

- 不動産×ビッグデータのキーワードが注目度を高めつつある。
- キーワードのパイオニア的存在である、清水千弘氏にインタビュー。
- 不動産ビッグデータの「これまで」「これから」を研究者視点で紹介した記事。
はじめに
9月8日の日経電子版が、新たな、「不動産×IT」施策を報じました。国土交通省が、不動産物件にIDを発行する取り組みです。
日経電子版は、「IDにひもづく情報」の例として、過去の成約価格やリフォームの実績有無などを挙げています。本件についての検討会が2019年度に、実証実験が同年度中に開かれる予定とのこと。中古住宅の流通を促す目的とされています。
2018年5月にも、気になる法案が参院本会議で成立しています。国が主導する、「国勢調査」「家計調査」などの調査データを一般の研究者も使えるようにする、という改正統計法です。2つのニュースから浮かび上がるキーワードは、不動産×ビッグデータ。
不動産にIDを付与する取り組みや、国勢調査などのデータ利用範囲の広がりは、情報の透明化を促します。情報の透明化が進むことで、業界に培われるのが不動産のビッグデータ。今回の企画では、不動産業界において注目度を高めつつある、「不動産×ビッグデータ」というキーワードに焦点を当てます。
SUMAVEが取材で訪れたのは、清水千弘氏のいる日本大学です。
 清水氏は、ビッグデータの解析を専門にしています。国外の学術誌に掲載された学術論文の数は、50本以上。国内でも、「商業不動産価格はどのように測定すればいいのか?」「住宅価格指数の集計バイアス:ヘドニック価格法vs. リピートセールス価格法」など、不動産業界にかかわる研究論文を100本以上、公表しています。
清水氏は、ビッグデータの解析を専門にしています。国外の学術誌に掲載された学術論文の数は、50本以上。国内でも、「商業不動産価格はどのように測定すればいいのか?」「住宅価格指数の集計バイアス:ヘドニック価格法vs. リピートセールス価格法」など、不動産業界にかかわる研究論文を100本以上、公表しています。
清水氏は、日本大学で教鞭をふるうかたわら、LIFULLの『プライスマップ』を監修したり、リブセンスのマンション価格査定サイト『イエシル』で技術顧問に就いたりしています。米国では、マサチューセッツ工科大学(以下、MIT)の不動産研究センターで研究員として活動する一面も。2018年9月には、MITの教え子を招聘し、アメリカや国内のテクノロジートレンドを紹介していました。
 今回は、研究者という立場から、清水氏に、不動産×ビッグデータのキーワードを語ってもらいます。
今回は、研究者という立場から、清水氏に、不動産×ビッグデータのキーワードを語ってもらいます。
※以下、敬称省略。
リブセンスのイエシルに託された「想い」を明かす
 Q:まずは、現状からお聞かせください。国土交通省が、不動産物件にIDを発行しようとしています。こうした報道を含め、現状を研究者の立場から見たとき、不動産業界に思うところはありますか。
Q:まずは、現状からお聞かせください。国土交通省が、不動産物件にIDを発行しようとしています。こうした報道を含め、現状を研究者の立場から見たとき、不動産業界に思うところはありますか。
「2つ、あります。1つは、テクノロジー活用の先に何を想像しているかが大事である、ということ。もう1つは、先人が成し遂げたことへの敬意についてです。たとえば、リブセンスの場合は、(社長の)村上さんにしても(不動産ユニットのリーダー)芳賀さんにしても、「想い」があるじゃないですか。「生産性の低い、従来の産業に対して革命を起こしたいんだ」というような、想いです。それは、結果として消費者のメリットを見据えています。広義にいうと、日本をこう変えたいというような志が、彼らのなかにあるわけです。そういう想いを持った人から相談を受けたら、私は、自分なりに応援しています。リブセンスでIESHIL(イエシル)事業部を立ち上げるときに、「協力したいな」そう思ったのも同じ背景です。さらに、芳賀さんは、かなりのリスクを背負いましたよね。リスクを背負えたのは、核となる志が自分のなかにあるからです」
Q:リスクとはどんなものでしょうか。
「たとえば、一部屋ごとに参考価格をつけることです。これは非常にリスクがありました。「現在の商慣習から予想されるリスク」を私は芳賀さんに直接説明したんです。すると、彼はこう答えました。「そういうようなところも乗り越えないと、マーケットは変えられないと感じています」そうして誕生したのが、イエシルという不動産テックサービスです。2018年現在のイエシルは、一都三県というエリアに限られていますが、マンションの参考価格を一部屋ごとに示しています。この勇気はすごいです。感心した私は、彼へ尋ねました。どうしてそんなリスクを負うことができるのかと。その理由を「そうすることが父親の教えでもある」と、私に明かしてくれました」
Q:「教え」とは、なんでしょうか。
「「正しいと思ったことはちゃんとやれ」です。芳賀さんは私に、そう話してくれました。彼は、芯が通っているんですよね。リスクを背負ってでも貫きたい志、想いを持っています。それだけではないんです、彼に感心したのは。いわゆる、既存業界を攻撃したり破壊したりするわけではなく、「きちんと付き合っていきたい」という考えを彼は持っています。誤解が生じたときも、解決するための努力を惜しまない人物です。それは、一緒に仕事をするとわかります」
Q:つまり、テクノロジー活用の先に何を想像しているのかとは、「どんな世界・社会を実現したいのかというビジョンを持っているかどうか」ということですか。
「はい。ビジョンのなかの消費者が、どんな豊かさを享受しているのか、でもあります。高度なテクノロジーをビジネスに生かすことだけが目的になってしまうと、サービス利用者の豊かさや幸せが二の次になってしまうのではないかと、非常に気になります。芳賀さんは、イエシルで実現したい世界観も私に語ってくれ、そのビジョンに私は、共感することができました。テクノロジーが活用されるとき、その先にある、「人々の幸福度を押し上げることへつながるのか」というポイントは重要です。私たちのような研究者の立場からすると、根底にあるべき要素でもあります」
人間社会をおかしな方向へ進めてしまう危険性
 Q:2つ目の、先人が成し遂げたことへの敬意とは、どういうことでしょうか。
Q:2つ目の、先人が成し遂げたことへの敬意とは、どういうことでしょうか。
「たとえば、クローリングです。この25年間をかけて、私たちは不動産価格を推計するための新しい手法を多く開発してきました。新しい推計手法ができれば論文として公開し、作ったソースコードをインターネット上に絶えず公開してきたんです。こうした技術革新は、「研究、開発、公開、共有のサイクル」が繰り返されました。その結果、AIによる機械学習の精度は、以前とは比べ物にならないくらいに高精度です。精度が高いだけではありません、手軽にもなったのです。少し勉強をすれば、いまや、大学生や実務家でも、簡単な価格査定エンジンを”作ること”は、できるようになりました。テクノロジーを生かすために、不動産業界の先人たちは、業界のルールやデータ基盤などを作りづつけてきたのです。何十年もかけて、いろいろな人が知恵を出し合いながら、今日へとたどり着きました。すべては、消費者のためです。
IT化の進んでいない不動産業界において、テクノロジー活用から得られる恩恵は、今後も大きくなるでしょう。不動産テックは、不動産市場を活性化したり、業界関係者の業務効率を改善したりする、大きな可能性をまだまだ秘めています。同時に、想像もしていない、望まないような事態を招く危険性もあるのです。その危険が、消費者にふりかかることを危惧しています」
Q:たとえば、ビッグデータを悪用することで、消費者がだまされるのではないか、という危惧でしょうか。
「その通りです。私たち研究者は、多くの先人たちと一緒に研究開発をしてきました。それは、消費者をだますためではありません。生活を便利にしたり、豊かにしたりするためです。
不動産業界には、いま、いろいろな組織が立ち上がる動きもあるようですが、既存の業界や先人たちへの敬意を持ち、消費者が不利益をこうむらないよう、配慮を続けてほしいなというのが、私の個人的な想いです。今後は、これまで以上に、研究者、企業、業界組織、官公庁が手を取り合う時代となるでしょう。そのとき、どの立場においても、「相手への敬意」は重要だと考えています。敬意が欠けることで生まれてしまうのが、一方的な想いです。それぞれが一方的になることで、「消費者が望まないような、おかしな方向へ、人間社会が進んでしまうのではないか」と憂慮します。では、おかしくない方向、正しい方向とはどこかというと、テクノロジーが人の幸せに寄与する方向です。たとえば、企業なら、「テクノロジーが生かされたこのサービスは、人の幸せに寄与しているか」という点にあります」
マッチングビジネスは、家の価値を守る
 Q:研究者の立場からみて、「人の幸せに寄与している不動産テックサービス」とは、どういうことでしょうか。
Q:研究者の立場からみて、「人の幸せに寄与している不動産テックサービス」とは、どういうことでしょうか。
「たとえば、家を建てて売りたいと、そう思う人がいます。売れればよいですが、もし、売れなかったら、「売り手が幸せへ近づく」とは、思えません。しかも、家の価値は、【ゼロ】ではなく、【マイナス】です。空き家が問題になるのは、【マイナスな存在】だからですよね。そう考えると、家を流通させる仕事はとても重要で、建てた家の価値を【プラスな存在】として守っています。ここまでは、「売り手」「家という資産」の2つを考えた話です。
次は、「買い手」の立場で考えます。家を買いたいと、そう思う人がいたとします。背景にあるものは、「いまの家が狭い」「賃料を払い続けることが負担」などの理由です。理由の根底には、「もっともっと幸せになりたい」という人々の願いが芽吹いています」
Q:「ちょっと広い家に引っ越せたら、私や、私の家族は幸せに暮らせるんじゃないだろうか」そうした願いですか。
「そうですね。思い描く豊かさを実現したい。その願いの1つが、住まいへの、「想い」になります。「1人になってしまったから、小さな家・部屋に住み替えたい」というような想いもありますよね。あるいは、次のようなケースもあるでしょう」
住んでいる家を売却することでコスト削減し、維持費の負担が軽くなったことで経済的な余裕が生まれ、使えるお金が増え、そのお金で旅行へ行けたら幸せだろうな
「売り手、家という資産、買い手の3つを考えたとき、私は、それらをマッチングさせることを非常に大事な仕事だと考えています。
マッチングのために重要なことは、3つの情報を一か所に集めること。しかし、いまの日本は、3つの情報が、バラバラな状態で点在しています。1か所に集めるための手段として、極めて効率的なのがテクノロジーです。テクノロジーを生かし、3つを集積させることでマッチング精度は高まります。精度が高まるとは、3つを個別に、幸せへと近づけることです。こうした目的を不動産テック領域のテクノロジーが、しっかり果たしてくれることを期待しています」
ビッグデータとは3つの「V」

Q:そもそも、ビッグデータとは何を指しますか。定義などがあれば教えてください。
「私のシンガポール国立大学の講義では、「Laney D,(2001), 3D data management: Controlling Data Volume, velocity, and variety, US:META Group.」を紹介して、Volume、Velocity、Varietyの「3V」を挙げています。
- Volume(量)
- Velocity(即時性)
- Variety(多様性)
ビッグデータとは、データの量が重要であるだけでなく、「タイムリーに得ることができるか」「多様性がどの程度あるのか」ということも重要です。3つの要素が満たされたデータをビッグデータと呼び、そのデータ基盤を一人ひとりの宅建士、業界組織、企業が整備してきました。2000年代の前半までは、データの量が足りなかったり、即時性の乏しいデータだったり、限られた種類のデータだったりしたことで、ビッグデータの活用が思うように進みませんでした。しかし、いまの日本は違います。3Vを生かすためのテクノロジーも確立されている、というのが現状です」
Q:最後に、「不動産テック領域をさらに発展させるためのアドバイス」をお願いできますか。
「授業では、こんな話をすることがあります。学生に投資の話をするときです。わからないものを人は避けたがります。なぜ、避けるかというと、「わからないもの=リスク→危険」と思ってしまうからです。であるならば、「わからないもの→わかるもの」にすることで、「わかるもの=セーフティ→安全」と認識し、人は避けることがなくなります。つまり、不動産テックを「わかるもの」として、業界や関係者へ伝える(広める)ことができれば、この領域に、かかわろうとする人を増やせるのではないでしょうか。不動産テックをリスクと考える人がいても、理解を促せるかもしれません」
まとめ
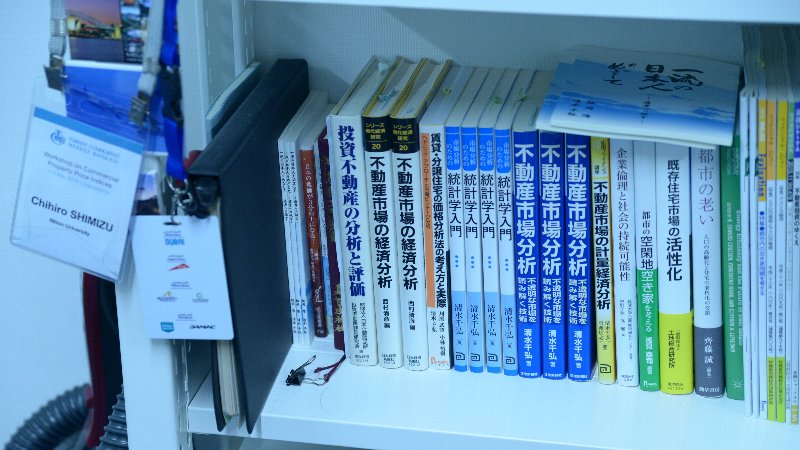 取材後、思い起こされたのが、先日に公開されたSUMAVEの記事です。不動産テック協会の理事・落合孝文氏が、SUMAVEのインタビュー取材で、次のように語っていました。
取材後、思い起こされたのが、先日に公開されたSUMAVEの記事です。不動産テック協会の理事・落合孝文氏が、SUMAVEのインタビュー取材で、次のように語っていました。
それぞれの立場によって、「見ている部分が違う」のは、仕方ないことだと思います。重要なことは、「違い」をそのままにせず、「どこは説明ができ、どこは譲ることができるか」を考えること。お互いが並走できるポイントを探っていく作業は欠かせません
不動産テック領域では、ベンチャー企業、既存の不動産企業、業界組織、官公庁だけでなく、研究者たちがはたす役割の大きさも見逃せません。さまざまな立場の人たちに、落合氏の指摘する、「立場による違い」があるとします。違いが原因で、並走できないのだとしたら、違いを知ることが最初です。知って初めて、並走できるポイントが探れるのではないでしょうか。そう考えると、「相手を理解しようとする努力」も重要なことに思えてきます。
不動産テック領域に、もし、顕在化していない、「違い」があるのだとしたら、今後もSUMAVEで取り上げていきたいと考えています。取り上げることで、多くの業界関係者に、「建設的なきっかけ」としてもらえたら幸いです。






