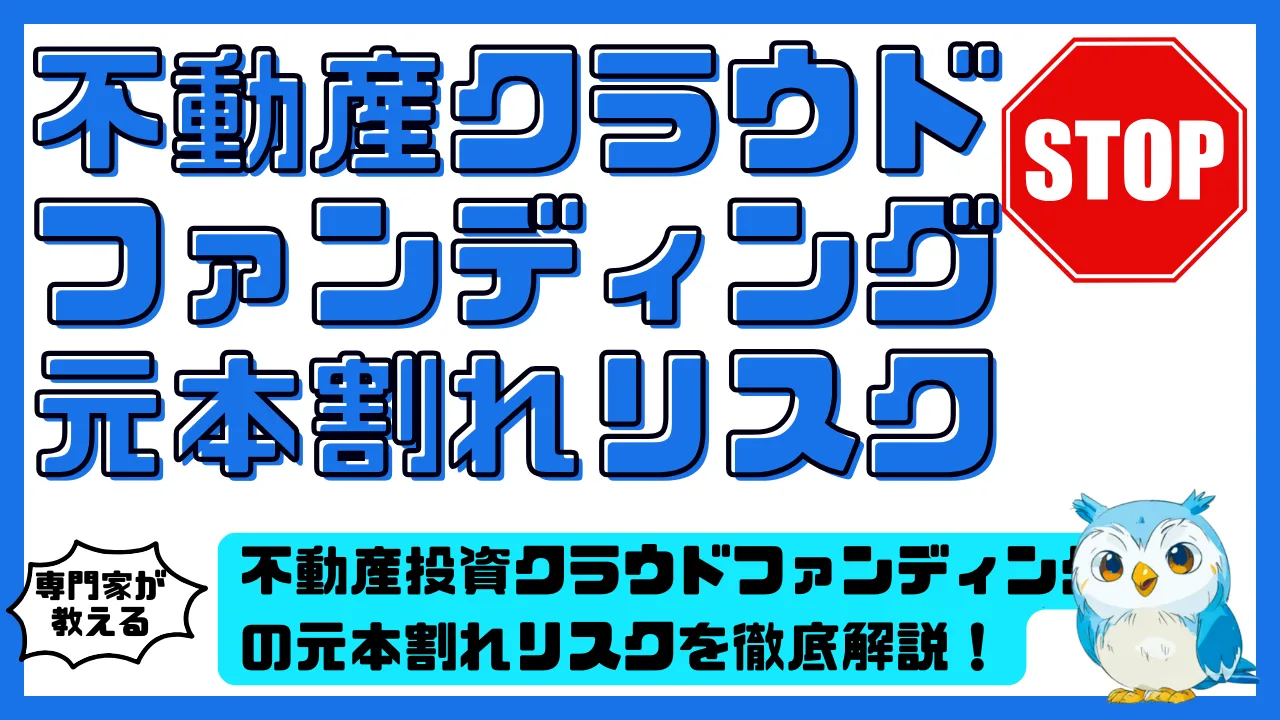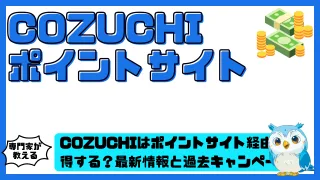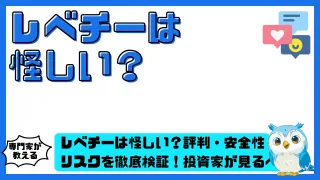本ページはプロモーションが含まれています。
目次
不動産投資クラウドファンディングの仕組みとリスク構造を理解する
不動産クラウドファンディングの基本構造
不動産投資クラウドファンディングは、インターネット上で複数の投資家から少額の資金を集め、その資金をもとに不動産を取得・運用して得られる利益を分配する仕組みです。
不動産特定共同事業法に基づいて運営されるため、法的な枠組みの中で透明性の高い投資モデルとして整備されています。
投資家は「出資者」としてファンドに資金を投じ、運営事業者が不動産の購入・管理・売却を担当します。運用期間中の賃料収入(インカムゲイン)や、売却益(キャピタルゲイン)から得られた収益が分配されるのが一般的です。
このように、現物不動産投資よりも手軽に、かつ少額から不動産市場に参入できる点が大きな特徴です。
元本保証がない理由と法的な位置づけ
不動産クラウドファンディングは「投資商品」であり、預金や保険のような元本保証はありません。
これは、不動産の価格や賃料収入が市場動向によって変動するためです。運営会社が破綻した場合や、物件価値が下落した場合には、投資額を下回る「元本割れ」が発生する可能性があります。
また、法的には「匿名組合契約」に基づいて運営されることが多く、投資家は出資者として利益を享受する立場にありますが、事業の損失も一定の範囲で負担します。
この仕組みにより、投資家はリターンを得るチャンスがある一方で、損失リスクも併せ持つことになります。
リスク構造を理解する
不動産クラウドファンディングのリスクは、複数の層で構成されています。主なリスクは次の通りです。
- 事業者リスク:運営会社の経営悪化や倒産により、出資金が返還されない可能性がある。
- 不動産市場リスク:景気後退や金利上昇による物件価格の下落。
- 運用リスク:入居率の低下や賃料滞納による収益悪化。
- 災害リスク:地震や火災などによる資産価値の毀損。
これらのリスクは個別に発生するだけでなく、複合的に影響し合うこともあります。たとえば市況悪化による賃料減少が続けば、事業者のキャッシュフローが悪化し、最終的に元本割れに至る可能性もあります。
優先劣後構造という安全弁
多くの不動産クラウドファンディングでは、投資家の損失リスクを軽減するために「優先劣後構造」を採用しています。
これは、事業者自身が投資家よりも劣後する立場(=先に損失を負担する立場)として資金を出資する仕組みです。
例えば、劣後出資比率が20%であれば、不動産価格が20%下落しても、投資家の元本は守られます。
ただし、これを超える損失が出た場合は、投資家の元本にも影響が及びます。
優先劣後構造はリスク低減の有効な仕組みですが、「完全な保険」ではありません。各ファンドの劣後比率や運用方針を確認し、リスク許容度に合った選択をすることが重要です。
不動産クラウドファンディングと他の投資手法の違い
現物不動産投資やJ-REITと比較すると、不動産クラウドファンディングは中間的な位置づけにあります。
現物投資よりも手軽でありながら、REITよりも個別案件の透明性が高いという特徴があります。
ただし、流動性はREITほど高くなく、原則として運用期間中の中途解約はできません。
そのため、余剰資金での長期的な投資として位置づけるのが現実的です。

リスクを理解したうえで仕組みを把握すれば、元本割れを防ぐための判断力が高まります。投資は「怖い」ものではなく、構造を知ることで「コントロールできる」ものになりますよ
元本割れとは何か。不動産クラウドファンディングで起こるケース
元本割れの基本的な意味
元本割れとは、投資によって得られる最終的な償還金や分配金の合計額が、投資した元本(出資金)を下回る状態を指します。不動産クラウドファンディングでは、ファンドの運用期間終了時に返還される金額と、それまでに受け取った分配金の合計が出資額より少ない場合、元本割れが発生したと判断されます。
不動産クラウドファンディングは金融商品取引法や不動産特定共同事業法に基づき運営されており、「元本保証型商品」ではありません。つまり、どのサービスも投資家の元本が必ず返ってくることを保証していないのが実情です。
元本割れが起こる典型的なパターン
不動産クラウドファンディングにおける元本割れは、主に以下のようなパターンで発生します。
- 不動産の売却価格が想定を下回った場合
- 運用期間中に想定よりも賃料収入が減少した場合
- 運営事業者の経営悪化や破産により出資金が返還されない場合
- 物件の損壊や法的トラブルによりコストが増加した場合
これらはいずれも、不動産市場や運営会社の健全性、物件の収益性など複数の要因が絡み合って発生します。特に、事業者の経営破綻は投資家側で制御できないリスクとして最も注意すべき要素です。
想定利回り未達との違い
投資家が誤解しやすいのが、「想定利回りを下回る」ケースと「元本割れ」は異なるという点です。利回り未達の場合は、当初予定していた配当率よりも少ない利益しか得られなかっただけで、元本そのものが減少したわけではありません。一方で、元本割れは出資した資金の一部または全部が失われる状態を指します。
例えば、10万円を出資して1万円の分配を得た後に償還金が8万円しか戻らなければ、合計9万円の返金となり1万円の元本割れとなります。対して、分配金が想定より少なくても、最終的に出資金が全額返還されれば元本割れではありません。
不動産クラウドファンディングに特有のリスク要因
不動産クラウドファンディングでは、株式や債券とは異なる特有のリスクがあります。
特に注意すべき要因は以下の通りです。
- 市場変動リスク:地価の下落や景気後退による物件価値の減少
- 運用リスク:賃貸需要の低下や入居者の家賃滞納などによる収益悪化
- 流動性リスク:運用期間中の中途解約が原則できないため、資金拘束が発生
- 事業者リスク:管理会社の経営不振や不正運用によるファンド破綻
- 法規制リスク:税制改正や建築基準法の変更などによる想定外の費用発生
これらは単独で起こることもあれば、複数が重なって損失を拡大させることもあります。特に昨今では、地価の変動に加え、建築コストや人件費の高騰が不動産収益性を圧迫する要因として注目されています。
現物不動産投資やREITとのリスクの違い
同じ不動産投資でも、クラウドファンディング・現物不動産・REITではリスク構造が異なります。
- 現物不動産投資:自己所有のため自由度が高い一方、物件価格の下落や空室リスクをすべて個人が負担します。
- REIT(不動産投資信託):市場で流通しているため流動性は高いが、株式市場の影響を受けやすい。
- 不動産クラウドファンディング:少額から分散投資できるが、中途換金性が低く、ファンド単位で元本割れが起きる可能性があります。
このように、不動産クラウドファンディングは“中間的なリスク・リターン型”の投資商品といえます。

投資では「元本割れ=悪」ではなく、「想定リスクの範囲内か」を見極めることが大切です。自分の資金計画に合ったリスク許容度を設定して投資判断を行いましょう。
実際に元本割れが発生した不動産クラウドファンディング事例
ダイムラー・コーポレーション破産事案の概要
2025年7月に発生したダイムラー・コーポレーションの破産は、不動産クラウドファンディング業界における初の「実質的な元本割れ」として大きな注目を集めました。
同社は「DAIMLAR FUND(ダイムラーファンド)」というブランドで不動産クラウドファンディングを運営していましたが、経営破綻により出資金が償還されない可能性が高まりました。
報道や関係者発表によると、負債総額は約3.3億円、債権者数は約300人。投資家の多くが数十万円から数百万円を出資しており、償還予定期日を迎えても分配や元本返還が行われない状態となりました。
不動産特定共同事業法のもとで登録された事業者による破産は極めてまれであり、投資家保護の枠組みや監督体制の見直しが求められています。
どのように元本割れが起きたのか
今回の事案の背景には、複数の要因が重なっていました。
まず、運営会社のキャッシュフロー悪化と経営の不透明化が進み、出資金の分別管理が適切に行われていなかった可能性が指摘されています。
さらに、運用対象の不動産についても市場価格が想定を下回ったことで、償還資金を確保できなかったとみられています。
不動産クラウドファンディングでは、本来、出資金と運営会社の資金は分別管理されることが法的に義務付けられています。しかし、実務上は運営企業の財務体質に依存する部分が大きく、倒産時には債権回収の優先順位が低くなる点がリスクとして浮き彫りになりました。
過去の類似トラブルと投資家保護の現状
ダイムラー・コーポレーション以前にも、不動産クラウドファンディング業界では軽微なトラブルがいくつか発生しています。
例えば、配当遅延や運用報告の未提出などの事例は複数の中小サービスで確認されていますが、最終的に元本割れに至るケースはほとんどありませんでした。
これは、多くの大手サービスが「優先劣後出資方式」を採用しており、事業者が損失の一部を先に負担することで投資家の元本を守る仕組みを設けているためです。
ただし、今回のように事業者そのものが破産してしまうと、優先劣後構造ではカバーしきれないリスクが存在することも明らかになりました。
金融庁や国土交通省は、こうした事例を受けて、業界全体のモニタリング強化や分別管理の実態調査を進めていますが、現時点では制度的な救済措置は限定的です。投資家が損失を最小限に抑えるためには、事業者選定時の自己防衛が不可欠といえます。
他サービスで元本割れが少ない理由
一方、他の有力サービスでは、これまで元本割れが発生した事例はほとんどありません。
特に「COZUCHI(コヅチ)」「CREAL(クリアル)」「TSON FUNDING(ティーソンファンディング)」といった大手事業者は、劣後出資比率を高めたり、上場企業グループとして透明性を確保したりすることで、リスク管理体制を強化しています。
これらの企業では、プロジェクトごとに監査や担保設定を行い、投資家資金が直接的に不動産取得に充てられるよう設計されています。
また、償還実績や投資家向けレポートを継続的に公開しており、情報開示の徹底も信頼性を支える要素です。
つまり、業界全体で見れば、今回のダイムラー破産はあくまで例外的な事案といえます。ただし、「リスクゼロではない」という現実を投資家が改めて認識する契機にもなりました。

不動産クラウドファンディングでも、元本割れは“理論上のリスク”ではなく“現実的な可能性”だと分かりましたね。信頼できる事業者を選ぶこと、そして分散投資を徹底することが、自分の資産を守る第一歩です
不動産クラウドファンディングが元本割れする主な原因
事業者の経営破綻と運営管理の失敗
事業者の資金繰り悪化やガバナンス不全は、償還や配当の遅延・不履行に直結します。分別管理が甘い、関連会社との取引が不透明、内部牽制が弱いといった兆候は早期警戒が必要です。優先劣後構造があっても、運営自体が止まると現金化プロセスが滞留し、結果的に元本割れの確率が上がります。
チェックすべきは、許認可や監査体制だけでなく、償還実績の開示粒度、遅延時の対応方針、資金調達の多様性などです。
- 直近の償還・分配の遅延履歴や理由の開示状況
- 監査報告書や第三者レビューの有無
- 資金の分別管理・信託保全・口座スキームの具体性
不動産価格の下落と出口戦略の失敗
キャピタルゲインを重視するファンドは、市況悪化や金利上昇で売却価格が想定を下回ると元本割れにつながります。出口時期がタイトで代替買い手が限られる、または想定より長期化して売却費用・金利負担が増えると、損失幅が拡大します。
立地や用途の需給、近隣供給計画、金利シナリオと出口バッファの設計の甘さが主因となりやすいです。
- 複数出口の確保(売却先レンジ、買取保証の有無)
- DCFのセンシティビティ(金利+賃料±)と下方ケースのIRR
- 売却費用・仲介手数料・税コストの織り込み
賃料収入の悪化とオペレーションリスク
インカム重視型では、空室増や賃料下落、滞納・回収遅延、更新率低下が分配原資を削ります。PM(プロパティマネジメント)やBM(ビルメンテ)の品質、入居者属性の偏り、フリーレント過多なども収益のブレを拡大させます。
一見高利回りでも、入替えコストやテナント改善費が膨らめば手取りは細ります。
- 物件ごとの入居率トラックレコードと賃料改定履歴
- 大口テナント依存度と解約予告期間の条件
- 修繕計画・CAPEXの積み上げの妥当性
レバレッジと金利・リファイナンスリスク
ノンリコースローン等の借入を用いるファンドは、金利上昇やLTV上振れでDSCRが悪化し、リファイナンス不能や追加担保要求に陥る可能性があります。返済期限が集中するのに、金利ヘッジや返済原資のプランが弱いと、売却を早期・安値で強いられます。
- 返済期限プロファイルとリファイ時の金利想定
- 金利ヘッジ比率・期間のアロケーション
- LTV・DSCRのコーブナンツとトリガー発動時の対応
評価・デューデリジェンスの偏り
鑑定評価が一物件・一手法に偏る、外部DDでリーシング難易度や法的瑕疵の洗い出しが不足すると、取得直後から想定乖離が顕在化します。開発余地や用途変更を前提にした「ストーリー先行」の査定は、許認可や近隣合意の遅れで頓挫しがちです。
- 複数鑑定・複数手法(収益還元・取引事例)の整合性
- リーガルDDの範囲(越境・増築未登記・用途規制)
- テナント需要調査の一次データと代替需要の裏取り
災害・事故・予期せぬコスト増
地震・台風・水害、建物事故や設備故障、アスベスト等の環境リスクは、突発的なCAPEX増や長期の賃料ダウンを引き起こします。保険の付保範囲や自己負担額、再保険の有無によって損失の波及度が大きく変わります。
法改正や制度変更で耐震・省エネ、用途制限が強化されると、想定外の追加投資や稼働制約が発生します。
- 保険の免責・限度額・不担保条項の把握
- 浸水・液状化・土砂災害のハザード評価
- 省エネ・耐震等級などレギュレーション対応コスト
契約・スキームの構造的制約
匿名組合や任意組合などスキームにより、損益配分・優先劣後・担保の位置づけが異なります。劣後比率が十分でも、評価額下落が想定を超えれば優先出資にも損失が及びます。運営報酬が成功報酬偏重だと、リスクの高い案件に資源が傾くインセンティブも生まれます。
- 優先劣後の水位と損失吸収メカニズム
- 担保設定・根抵当の順位と共同担保の競合
- 運営報酬の体系(固定+成功)と利益相反管理
海外案件・為替・税制の変動
海外不動産や外貨建てのキャッシュフローは、為替変動で円ベースの分配が減少します。源泉税や税制改正によりネット利回りが圧縮されることもあります。為替ヘッジが短期・部分的だと、出口期の為替逆風でトータルが毀損します。
- 為替ヘッジ方針とコスト、ヘッジ対象比率
- 国別の税制・源泉税・租税条約の影響
- 現地PMの実績とコンプライアンスリスク
情報非対称性と開示の遅れ
運用報告の頻度・精度が低い、KPI定義が曖昧、重要事象の開示が遅れると、投資家は悪化の初期シグナルを捉えられず、損失回避の選択肢を失います。IT基盤が脆弱だと、データ消失や不正アクセスも運用に影響します。
- 月次KPI(入居率・賃料改定・回収率・稼働率)の標準化
- 重大事象の臨時開示ポリシー
- サイバーセキュリティとバックアップ体制
資金拘束と流動性の欠如
原則途中解約不可で二次流通がない商品設計では、想定外の資金需要発生時に売却できません。資金需要とファンド期間のミスマッチは、機会損失や心理的な取り崩し圧力を生み、逆タイミングの売却判断を誘発します。投資家側の流動性管理不足も、結果的に損失拡大の要因になります。
- ファンド期間と個人のキャッシュフロー計画の整合
- セカンダリー機能の有無と手数料
- 早期償還条項・延長条項の条件

大事なのは「原因を個別に潰す視点」です。事業者の健全性、金利と出口のバッファ、賃料KPI、保険と法規制対応、スキームの優先劣後や担保順位、開示の質までをチェックリスト化して、想定外の連鎖を断ち切っていきましょう
元本割れを防ぐための3つの対策
不動産投資クラウドファンディングにおいて、元本割れを完全に防ぐことは難しいものの、事前にリスクを抑えるための具体的な対策を講じることは可能です。ここでは、多くの投資家が実践している3つの有効な方法を紹介します。
優先劣後出資システムを理解して利用する
不動産クラウドファンディングでは、投資家の元本を守るための仕組みとして「優先劣後出資システム」が採用されるケースが多くあります。
この仕組みは、損失が出た場合に、まず運営事業者(劣後出資者)が自己出資分で損失を吸収し、その範囲を超えて初めて投資家(優先出資者)の元本に影響が及ぶというものです。たとえば劣後出資比率が30%であれば、不動産価格が3割下落しても投資家の出資金には損失が発生しません。
サービスごとに劣後出資の比率や条件が異なるため、募集ページに記載された「優先劣後比率」や「出資構成表」を必ず確認しましょう。リスクを抑えたい投資家は、劣後比率が高めに設定されているファンドを選ぶのが基本です。
信頼できる事業者を厳選する
運営会社の経営基盤や過去のファンド実績を確認することも、元本割れを防ぐうえで欠かせません。
不動産クラウドファンディング事業者は、不動産特定共同事業法に基づく許可を得て運営されていますが、すべての事業者が同じレベルの安全性を持っているわけではありません。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 金融庁・国土交通省への正式登録・許可の有無
- 償還実績や分配遅延、元本割れの有無
- 上場企業または大手グループ企業との資本関係
- 監査法人による財務監査の有無
また、高利回りを強調する案件ほど、リスクも比例して高くなる傾向があります。利回りだけに惹かれず、事業者の信頼性と運営履歴を重視して判断することが、長期的な資産保全につながります。
複数ファンドへの分散投資でリスクを抑える
1つのファンドや不動産に投資を集中させると、運用中のトラブルや市況の変動によって、資産全体が損失を受けやすくなります。
このリスクを軽減するために有効なのが「分散投資」です。
分散投資の考え方は、以下のように複数の視点から行うのが理想です。
- 地域分散:都市部・地方・再開発エリアなど複数エリアに分ける
- 用途分散:住宅、商業施設、ホテル、オフィスなど複数タイプに投資する
- 事業者分散:複数の運営会社を利用し、経営破綻リスクを分散する
不動産クラウドファンディングは、1口数万円から投資できるものが多いため、リスク分散しやすい点が魅力です。資金を段階的に投入しながら、複数のファンドでポートフォリオを形成することが、堅実な運用につながります。

リスクを完全に避けることはできませんが、仕組みを理解し、信頼性の高い事業者を選び、複数のファンドで分散投資を実践することで、元本割れの可能性を大幅に下げることができます。焦らず、長期的な視点で判断していきましょう。
事業者の信頼性を見抜くための実践チェックリスト
不動産クラウドファンディングで最も重要なのは、事業者の健全性を見極めることです。どれほど優良な物件に投資しても、運用会社の経営管理がずさんであれば、投資家の資金が危険にさらされる可能性があります。以下のチェックリストを活用すれば、事業者の信頼性を客観的に評価できます。
金融庁登録・不動産特定共同事業許可を確認する
信頼性を判断する第一歩は、法的な認可の有無を確認することです。不動産クラウドファンディングを運営するには、「不動産特定共同事業法」に基づく許可、または小規模事業者としての登録が必要です。
公式サイトのフッターや「会社概要」ページに許可番号(例:国土交通大臣第●号)が明記されているかを必ず確認しましょう。登録がない場合、法的保護を受けられないリスクがあります。
運営実績と償還履歴を調べる
実績は信頼の裏づけです。
以下の点を確認すると、運用の安定性が見えてきます。
- 過去のファンド償還件数と遅延率
- 分配金の支払い遅延・元本毀損の有無
- 運用中ファンドの件数と規模
- 投資家数や累計調達額の推移
これらが公式サイトで定期的に更新されていれば、情報開示姿勢も良好といえます。特に「償還実績グラフ」や「分配完了一覧」が公開されている事業者は透明性が高い傾向があります。
上場企業グループかどうかを確認する
運営母体が上場企業、もしくは上場企業グループに属しているかは重要な信頼指標です。
上場企業は第三者監査を受けており、内部統制・資金管理が厳しく、情報開示も義務付けられています。経営基盤が安定しているため、投資家資金の流用リスクも低くなります。
一方で、未上場企業の場合は財務状況が不明なこともあるため、決算公告やIR資料が公開されているかを必ずチェックしてください。
経営者・運用担当者の経歴を確認する
代表者や運用責任者の経歴を見ることで、事業者の姿勢がわかります。不動産や金融業界での経験年数、過去の実績、宅地建物取引士・不動産鑑定士・金融関連資格の有無も判断材料です。
経営者インタビューや運営方針を発信している企業は、透明性への意識が高い傾向があります。
高利回り案件への注意
「想定利回り10%以上」といった高利回り案件は、一見魅力的に見えますが、裏には高いリスクが潜んでいます。
利回りが高いほど、開発型ファンドや再建型ファンドのように、価格変動や工期遅延の影響を受けやすくなります。
安全性を重視するなら、利回りよりも「劣後出資割合」「運用実績」「物件の立地・需要」を優先して評価しましょう。
分別管理・監査体制を確認する
万が一事業者が倒産しても、投資家の資金が保全されるよう「分別管理」が徹底されているかを確認する必要があります。
信託口座や第三者監査を導入している場合、投資資金と事業者の運営資金が明確に分けられ、資金流用のリスクを軽減できます。
監査法人の名称が明記されている場合は、会計の透明性も期待できます。
情報開示・サポート体制をチェック
投資家向けの情報提供が充実しているかも重要です。
運用報告書、物件写真、稼働状況、収支明細などを定期的に公開しているかを確認しましょう。
また、問い合わせへの対応スピードやカスタマーサポートの質も、信頼できる事業者を見分けるポイントです。

信頼できる事業者を選ぶ最大のコツは、「情報を隠さない会社を選ぶこと」です。実績・許可・体制の3点を確認すれば、元本割れリスクを大きく下げられますよ
元本割れリスクを抑えた注目サービスと特徴
不動産クラウドファンディングは、事業者の運用能力や仕組みによって、リスクの水準が大きく変わります。ここでは、元本割れリスクを低減する工夫を取り入れている主要サービスを紹介します。いずれも投資家保護に配慮した仕組みや実績を持ち、安定運用を重視した投資家に注目されています。
COZUCHI(コヅチ)|累計投資額1,000億円超・元本割れゼロの実績
COZUCHIは、不動産クラウドファンディング業界で最も知名度が高く、累計投資額が1,000億円を超える大手サービスです。
2025年時点で元本割れゼロの実績を維持しており、投資家からの信頼が厚い点が特徴です。
主な特徴は以下の通りです。
- 元本割れゼロの運用実績(2025年10月時点)
- 利回りが上振れする仕組み(実績平均23%)
- 中途解約が可能な柔軟なファンド構成
- 物件の権利構造が透明で、投資家への情報開示が充実
優先劣後構造の採用により、一定範囲内の損失は事業者側が負担する仕組みとなっており、投資家の元本保全性を高めています。高いリターンを目指しつつも、リスク管理体制の強さが評価されている代表的サービスです。
CREAL(クリアル)|不動産管理企業としての安定性と透明性
CREALは、上場企業であるクリアル株式会社が運営するサービスで、安定性とガバナンスの高さが魅力です。
自社で不動産の取得から運用・管理までを一貫して行っており、現場に近い運用ノウハウを活かした堅実なファンド運営が特徴です。
- 東証グロース上場企業による信頼性の高い運営
- ファンドの詳細情報や運用報告が丁寧で透明性が高い
- ホテル・賃貸住宅・保育施設など多様な物件に分散投資可能
- 劣後出資比率を開示し、投資家の安全性を可視化
CREALは、安定運用型ファンドを多く取り扱い、リスクを最小限に抑えたい投資家に向いています。
TSON FUNDING(ティーソンファンディング)|高い優先劣後比率で保全性を確保
TSON FUNDINGは、愛知県を拠点とする不動産開発企業TSONが運営するクラウドファンディングサービスです。
最大の特徴は、業界でも高水準の優先劣後比率を採用している点で、投資家の元本リスクを極力減らす設計になっています。
- 劣後出資比率が高く、損失吸収力が大きい
- 戸建・土地開発など、地価の下落リスクが限定的な案件を中心に構成
- 自社開発案件が多く、収益構造が明確
- 投資単位が低く、初心者でも参加しやすい
開発型案件に強い一方で、土地仕入から建築・販売までを自社で完結させているため、プロジェクトの透明性と管理精度が高く、元本保全の意識が徹底されています。
信頼できるファンドを選ぶための比較ポイント
元本割れリスクを抑えたい場合、利回りの高さだけでなく、以下のような指標を重視すると安心です。
- 償還実績と元本割れゼロの記録があるか
- 優先劣後出資制度を採用しているか
- 運営会社の財務基盤と上場有無
- ファンドの透明性(物件情報・運用報告・劣後割合の公開)
これらの基準をもとに、過去のトラブルや運営体制を比較検討することで、リスクを可視化しながら投資判断を行うことができます。

どんなに魅力的な利回りでも、まずは“安全性の裏付け”を確認することが大切です。リスクを把握して選べば、不動産クラウドファンディングは安定した運用の味方になりますよ
投資初心者が元本割れリスクを避けるための実践アドバイス
自分のリスク許容度を明確にする
投資を始める前に、まず「どの程度の損失まで許容できるか」を明確にしておくことが重要です。リスク許容度を把握していないと、利回りの高さだけに惹かれて危険な案件に投資してしまうことがあります。
特に不動産クラウドファンディングは、元本保証がない以上、リスクとリターンのバランスを取る判断力が求められます。
安定運用を重視するなら、利回り3〜6%程度の中リスク・中リターン案件を中心に選ぶと良いでしょう。
運用期間と資金拘束リスクを理解する
多くの不動産クラウドファンディングでは、運用期間中の中途解約ができません。
数ヶ月〜数年にわたり資金が拘束されるため、生活費や緊急資金とは切り離して、余剰資金で投資を行うのが鉄則です。
特に初心者は「短期運用型(6ヶ月〜1年)」から始めると、リスクを実感しながら経験を積むことができます。
契約前に開示書面・運用報告を必ず確認する
不動産特定共同事業法に基づくクラウドファンディングでは、契約前に「契約成立前書面」や「重要事項説明書」が交付されます。
この書面には、運用期間・想定利回り・物件所在地・優先劣後比率・リスク要因など、投資判断に欠かせない情報がすべて記載されています。
また、運用期間中の「運用報告書」や「償還報告」も定期的に確認し、事業者の透明性や報告姿勢を見極めることが大切です。
信頼できるファンド・事業者を選ぶ
実績や許認可の確認はもちろん、以下の観点で信頼性を判断しましょう。
- 金融庁登録・不動産特定共同事業の許可があるか
- 償還実績や分配遅延の有無
- 優先劣後出資比率が適切に設定されているか
- 過去にトラブル報告や行政処分がないか
上場企業や大手グループ傘下の事業者は、経営基盤が安定しており、情報開示の透明性も高い傾向にあります。
初心者は、COZUCHI(コヅチ)やCREAL(クリアル)のように実績と信頼性を兼ね備えた事業者から始めるのが安全です。
分散投資でリスクを平準化する
一つのファンドに集中投資せず、複数の物件や地域、運営会社に分散させることでリスクを分散できます。
たとえば、都心のレジデンス系・地方の商業施設・短期再開発型など異なるタイプのファンドを組み合わせると、特定の市場変動による影響を抑えられます。
また、株式や債券などの他資産と併用することで、ポートフォリオ全体の安定性も高まります。
初心者が陥りやすい失敗を避ける
初心者が元本割れを招きやすい行動として、次のようなものがあります。
- 利回りだけを見て高リスク案件に集中
- サービス比較をせず、1社のみで判断
- 契約内容を確認せずに出資
- 運用報告をチェックせず放置
これらを避けるには、「情報を鵜呑みにせず、自分で確認する姿勢」を持つことが重要です。

投資は“情報を読み解く力”が成績を左右します。焦らず、信頼できる情報源から一歩ずつ積み上げていけば、元本割れのリスクを最小限に抑えながら安定した資産運用ができますよ
| 順位 | 商品名 | 会社名 | 特徴 | 案件数 | 直近10件平均利回り | 直近10件直近最低利回り | 直近10件直近最高利回り | 直近10件募集割合平均 | 優先劣後方式 | 最低投資金額 | 募集方法 | 組合契約 | 物件の種類 | 優遇サービスあり | 物件の開示情報 | 出金手数料 | 運用レポートの共有あり | 運営会社設立年月 | 運営会社資本金 | 上場 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | COZUCHI(コズチ) | LAETOLI株式会社 | 投資募集のチャンスは業界上位。投資デビューに適した候補 | 139件 | 5.75% | 4.00% | 6.50% | 337.36% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 月1回まで無料(それ以降は330円) | ○ | 1999年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 2位 | CREAL(クリアル) | クリアル株式会社 | 募集口数が多く、新規案件の供給量も豊富 | 139件 | 5.13% | 0.00% | 6.50% | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス、保育所、学校、宿泊施設 | ○ | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 105円(楽天銀行の場合)、150円(楽天銀行以外で3万円未満の場合)、229円(楽天銀行以外で3万円以上の場合) | ○ | 2011年 | 1,273,520,500円 | ○ | 公式サイト |
| 3位 | 利回りくん | 株式会社シーラ | 年間新規案件数が安定。募集口数も一定水準 | 148件 | 4.71% | 3.00% | 6.00% | 89.80% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2010年 | 446,522,660円 | ○ | 公式サイト |
| 4位 | Rimple(リンプル) | プロパティエージェント株式会社 | 新規案件が充実。劣後出資割合の高い案件が多い | 112件 | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 270.75% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、事業内容 | 無料 | ○ | 2004年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 5位 | TECROWD(テクラウド) | TECRA株式会社 | 新興国不動産への投資が可能。高利回り案件が多い | 90件 | 10.40% | 8.50% | 12.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、オフィス | ○ | 住所、運営会社、財務情報、面積、事業内容 | 無料(楽天銀行)、振込手数料(楽天銀行以外) | ○ | 2001年 | 156,600,000円 | × | 公式サイト |
| 6位 | TSON FUNDING(ティーソン) | 株式会社TSON | 年間案件数が最多クラス。リスク軽減案件も豊富 | 230件 | 5.64% | 5.50% | 5.80% | 98.90% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、事業内容 | 無料(匿名組合ファンド)、振込手数料(任意組合ファンド) | ○ | 2008年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 7位 | 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス | 運営会社の信頼性が高く、新規案件も安定供給 | 109件 | 5.90% | 3.50% | 12.00% | 728.48% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛) | ○ | 1996年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 8位 | FUNDROP(ファンドロップ) | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 | 劣後出資割合の高い案件が多いが、投資機会は少なめ | 39件 | 5.66% | 5.50% | 5.80% | 119.09% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 52円(楽天銀行)、150円(他の金融機関で3万円未満)、229円(他の金融機関で3万円以上) | ○ | 2013年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 9位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 穴吹興産株式会社 | 低リスク案件が多いが、投資の機会は限定的 | 43件 | 3.25% | 3.00% | 5.00% | 99.98% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設 | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 1964年 | 755,790,000円 | ○ | 公式サイト |
| 10位 | ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 | 劣後出資割合の高い案件が多く、運営も安定傾向 | 10件 | 4.00% | 3.90% | 4.30% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(その他の金融機関) | ○ | 1991年 | 389,820,000円 | × | 公式サイト |
| 11位 | property+(プロパティプラス) | 株式会社リビングコーポレーション | 募集口数は平均的だが、新規案件がなかった点が課題 | 34件 | 3.20% | 3.00% | 3.40% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2015年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 12位 | ASSECLI(アセクリ) | 株式会社エボルゾーン | 高利回り案件が多いが、新規提供数は限られる | 45件 | - | 0.00% | 0.00% | 105.85% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 事業内容 | 無料 | × | 2011年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 13位 | LIFULL(ライフル) | 株式会社LIFULL | 大手不動産会社のクラウドファンディング。厳選された物件 | 3件 | 5.83% | 5.50% | 6.00% | 105.67% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション・グループホーム | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | × | 1997年 | 9,723,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 14位 | みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント | 」「公的年金に合わせた2ヵ月ごとの分配金」が特徴の、不動産クラウドファンディング | 290件 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、物件種別、アクセス、構造、総戸数、家賃保証有無 | 無料 | × | 2016年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 15位 | 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス | 高水準の利回り案件が豊富で、投資のチャンスも平均以上 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行あて) | ○ | 2023年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 16位 | らくたま | 株式会社日本保証 | リスクを抑えつつ高いリターンを狙える案件が多く、供給数も充実 | - | - | - | - | - | ○ | 10000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、商業施設、オフィス | ○ | 築年数、住所、面積 | 無料(GMOあおぞらネット銀行) | × | 2008年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 17位 | GALA FUNDING(ガーラ ファンディング) | 株式会社FJネクストホールディングス | 運営基盤が堅実で、劣後出資割合が高めの安心感ある案件が中心 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛て) | ○ | 1980年 | 2,774,400,000円 | ○ | 公式サイト |
| 18位 | トモタク | 株式会社イーダブルジー | 新規募集数は業界トップクラスで、高利回り案件が目立つ | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、オフィス | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 1回のみ無料(125円(GMOあおぞらネット銀行)、250円(GMOあおぞらネット銀行以外)) | ○ | 2009年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 19位 | LSEED(エルシード) | 株式会社LSEED | リスクとリターンのバランスは良好だが、案件数はやや少なめ | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、面積、事業内容 | 不明 | × | 1999年 | 706,139,500円 | ○ | 公式サイト |
| 20位 | トーセイ不動産クラウド | トーセイ株式会社 | 1万口超の大型案件が主体で、年間の提供数は限定的 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、129円(その他金融機関) | ○ | 1950年 | 6,624,890,000円 | ○ | 公式サイト |
| 21位 | KORYO Funding(コウリョウ ファンディング) | 株式会社興陵 | 安定したバランス型案件が揃う一方で、全体の件数は少ない | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容 | 無料 | × | 1981年 | 371,980,200円 | ○ | 公式サイト |