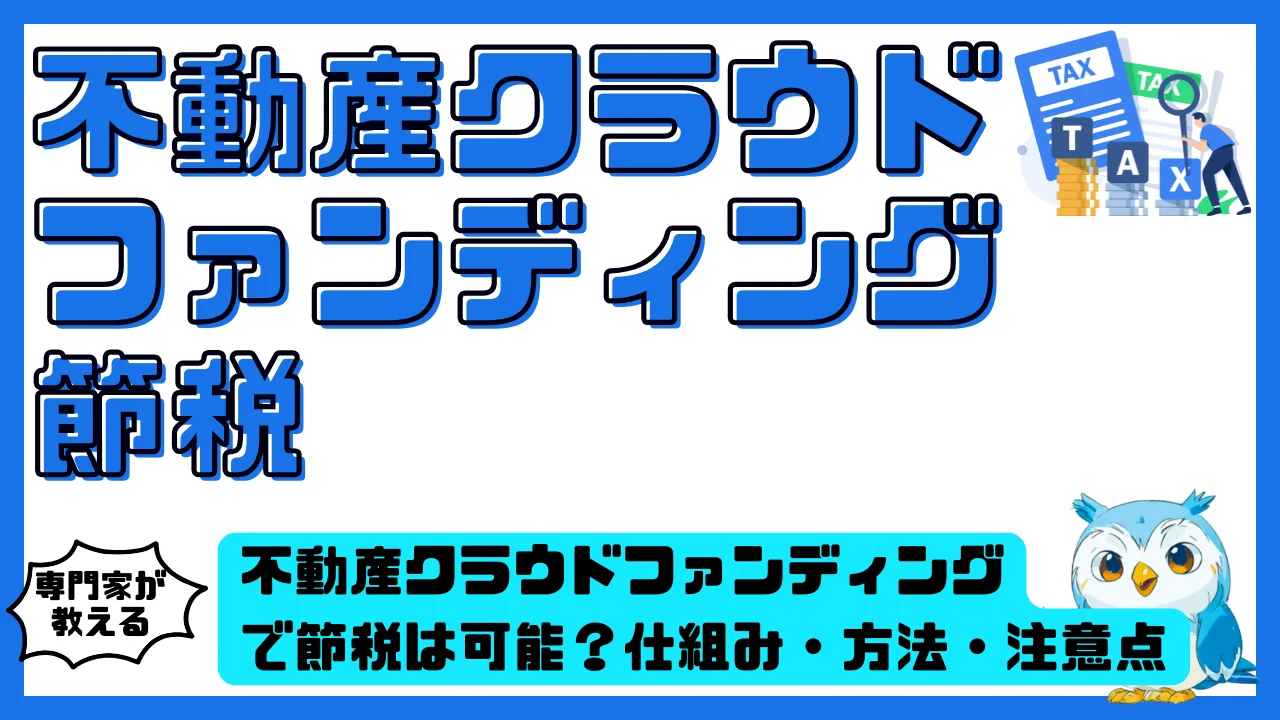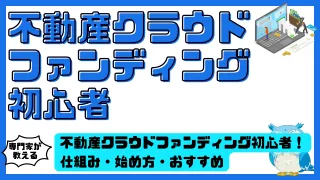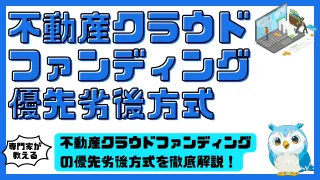本ページはプロモーションが含まれています。
目次
不動産クラウドファンディングの税金の基本を理解しよう
不動産クラウドファンディングで得られる利益は、投資である以上「税金」と切り離すことはできません。まずは、投資家として必ず知っておくべき税金の基本を押さえておきましょう。
分配金は「雑所得」として課税対象になる
多くの不動産クラウドファンディングでは、投資家が得る利益(分配金)は「雑所得」として扱われます。雑所得は給与所得や事業所得とは別に総合課税の対象となり、所得税と住民税が課されます。
この分配金は事業者が源泉徴収を行った上で支払われるため、投資家の手元にはすでに税金が引かれた金額が振り込まれます。
源泉徴収税率は一律20.42%
不動産クラウドファンディングの分配金は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%を合わせた「20.42%」の税率で源泉徴収されます。
このため、一般的には追加の納税手続きが不要ですが、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合や、一定の条件下では確定申告が必要になることがあります。
確定申告で税金が戻るケースもある
課税所得が694万円以下の人は、本来の所得税率が20%未満になることが多く、一律20.42%で源泉徴収されている分の「払いすぎた税金」が発生している可能性があります。
この場合、確定申告を行えば税金の一部が還付されることがあり、結果的に節税につながります。確定申告をしないと還付を受けられないため、所得状況に応じて申告を行うことが重要です。
雑所得の範囲と注意点
雑所得として申告する場合、分配金だけでなく、関連する収入や経費も含めて正確に計上する必要があります。例えば、不動産クラウドファンディングに関するセミナー費や通信費など、投資活動に直接関係する支出は「必要経費」として控除できる場合があります。
ただし、経費計上の範囲は税務署の判断によって異なることがあるため、領収書や明細は必ず保管しておきましょう。
任意組合型との違いに注意
税金の扱いは、クラウドファンディングの仕組みによっても異なります。
匿名組合型では分配金が雑所得として扱われる一方、任意組合型では投資家が不動産を共同所有するため「不動産所得」となり、損益通算や繰越控除といった節税メリットを得られる可能性があります。
どの仕組みのファンドに投資しているかによって税務処理が異なるため、契約形態を確認することが大切です。

不動産クラウドファンディングの税金は、仕組みの違いで課税方法が変わる点が重要です。特に「雑所得」扱いの場合は源泉徴収だけで終わらせず、確定申告で還付を受けられるケースを見逃さないようにしましょう。税金の基本を理解しておくことが、賢い節税の第一歩ですよ
節税が可能になる「任意組合型」とは
不動産クラウドファンディングの中でも、節税効果を期待できるのが「任意組合型」と呼ばれる方式です。これは、投資家が単なる出資者ではなく、不動産を共同で所有する立場になる仕組みです。法律上は「民法上の任意組合契約」に基づき、複数の投資家が共同で不動産事業を行う形になります。
任意組合型の仕組みと特徴
任意組合型では、投資家一人ひとりが不動産の持分を保有します。運営自体は事業者が代行しますが、投資家は不動産の共有者という位置づけになります。そのため、分配金は「不動産所得」として扱われ、現物不動産投資と同様の税務処理が可能です。
この「不動産所得」に分類される点が、節税効果を生む最大のポイントです。運用が赤字になった場合、その損失を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できるため、結果的に課税所得を減らすことができます。加えて、損失が生じた場合には翌年以降3年間の「繰越控除」も可能です。
節税効果の具体例
たとえば、任意組合型ファンドで50万円の損失が出た場合、その年の給与所得から50万円分を差し引いて税負担を軽減できます。これが匿名組合型ではできない任意組合型特有のメリットです。また、現物不動産を所有する扱いとなるため、減価償却費や修繕費などを経費として計上できる場合もあります。
相続・贈与時の評価圧縮効果
任意組合型のもう一つの特徴は、相続や贈与時の資産評価額が実勢価格より低く算定される点です。一般的に、不動産の相続税評価額は市場価格の約7割前後とされます。これにより、資産圧縮効果を通じて相続税や贈与税の節税にもつながります。匿名組合型のように現金や債権扱いではないため、資産税対策の一環としても注目されています。
代表的な任意組合型サービス
代表的な任意組合型の不動産クラウドファンディングとして知られているのが「COZUCHI(コヅチ)」です。COZUCHIは、投資家が不動産の権利を共同で保有する仕組みを採用しており、節税対策としても高い評価を得ています。損益通算や相続税対策を意識した設計がなされているため、節税メリットを求める投資家には適した選択肢です。
任意組合型の注意点
任意組合型は、節税効果の一方で「無限責任」が発生する点に注意が必要です。投資先の不動産事業が損失を出した場合、出資額を超える債務を負うリスクがあります。そのため、リスク許容度を確認した上で、資産規模や投資目的に合った判断を行うことが重要です。節税を目的とする場合も、リスクとのバランスを意識した運用が求められます。

任意組合型は、節税効果が高い一方でリスクも伴う投資形態です。税制上のメリットだけでなく、責任範囲や運用の透明性を確認して、自分に合った投資スタイルを選ぶのが大切ですね
匿名組合型との違いと税務上の取り扱い
不動産クラウドファンディングには主に「匿名組合型」と「任意組合型」の2つのスキームがあります。どちらも投資家から資金を集めて不動産を運用する点は同じですが、税務上の扱いと節税効果の有無という点で明確な違いがあります。
匿名組合型は「雑所得」として課税される
匿名組合型では、投資家は事業者に出資し、運用はすべて事業者が行います。不動産の所有権は事業者側にあり、投資家はその収益の一部を受け取る権利を持つのみです。この仕組みは、法律上「匿名組合契約」に基づくものです。
税務上、匿名組合型の分配金は「雑所得」として扱われます。投資家の手元に入る分配金には、あらかじめ20.42%の源泉徴収が行われ、事業者が税務処理を代行します。原則として、給与所得など他の所得との損益通算は認められていません。そのため、赤字が出ても他の所得と相殺できず、節税効果は限定的です。
匿名組合型は出資額を上回る損失を負うリスクがなく、有限責任という点で安全性は高いですが、節税面での柔軟性は低くなります。
任意組合型は「不動産所得」として扱われる
一方、任意組合型では、投資家が事業者と共同で不動産を所有する形式を取ります。不動産の持分が登記されることもあり、法律上は「共同事業者」としての位置づけになります。税務上、この場合の収益は「不動産所得」として扱われます。
不動産所得は、家賃収入や減価償却費、修繕費、管理費などを計上できるため、損益通算や繰越控除が可能です。たとえば、他の所得(給与や事業所得など)と不動産投資で発生した赤字を相殺することで、全体の課税所得を減らし、結果的に税負担を軽減できます。
ただし、任意組合型では投資家も不動産の実質的な所有者とみなされるため、無限責任を負うリスクが発生します。万が一、運用中に債務超過が起きた場合、出資額以上の負担を求められる可能性があります。
税務処理とリスク・リターンのバランスを見極める
匿名組合型と任意組合型では、税務上の取り扱いが根本的に異なります。節税効果を狙うなら任意組合型が有利ですが、リスク管理の観点では匿名組合型のほうが堅実です。投資目的が「節税」なのか「安定運用」なのかを明確にしたうえで、適切なスキームを選択することが重要です。
税務上の申告でも扱いが異なります。匿名組合型は「雑所得」として申告し、任意組合型は「不動産所得」として計上します。確定申告時に誤って区分を間違えると、税務署から指摘を受けるリスクもあるため、契約形態の確認は必須です。
区分のポイントまとめ
- 匿名組合型:事業者が運営、投資家は有限責任、分配金は雑所得扱い
- 任意組合型:共同所有、投資家は無限責任、不動産所得扱い
- 任意組合型は損益通算・繰越控除が可能で節税効果がある
- 匿名組合型は税務処理が簡単でリスクが低いが節税は限定的

匿名組合型は税務処理がシンプルで初心者向け、任意組合型は節税効果が高い反面リスク管理が求められます。自分の投資目的とリスク許容度をしっかり見極めて選ぶことが大切ですよ
不動産クラウドファンディングで活用できる主な節税方法4選
不動産クラウドファンディングでは、分配金に対して一律20.42%の源泉徴収が行われますが、確定申告を行うことで税金を抑えたり、還付を受けたりできるケースがあります。ここでは投資家が実践できる代表的な節税方法を4つ紹介します。
① 確定申告による還付申請
不動産クラウドファンディングの分配金は、原則として税率20.42%で源泉徴収されています。しかし、課税所得が694万円以下の人の場合、本来の税率はそれより低くなることが多く、税金を多く払いすぎている可能性があります。
確定申告で所得や源泉徴収額を正確に申告すれば、払いすぎた分が「還付金」として戻ってくることがあります。給与所得者でも、副業や投資を含めた年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。還付申請は5年間遡って可能なため、過去の年度も見直しておくと良いでしょう。
② 必要経費の計上による課税所得の圧縮
不動産クラウドファンディングに関する支出の中で、「利益を得るために直接要した費用」は必要経費として計上できます。課税対象は「収益−必要経費」で計算されるため、経費を正しく計上することで課税所得を減らし、結果として節税につながります。
経費として認められる可能性のある主な項目は以下のとおりです。
- 不動産クラウドファンディングに関する書籍・情報サイトの購読料
- オンラインセミナー・勉強会の参加費
- 投資管理用パソコン・スマホの一部費用
- 通信費・光熱費(按分計上)
- 税理士への相談費用
経費計上は領収書や明細の保管が前提となるため、証拠書類を整理しておくことが重要です。
③ 雑所得間での損益通算による節税
不動産クラウドファンディングで得た利益は「雑所得」として扱われます。雑所得は他の所得(給与所得など)とは通算できませんが、同じ雑所得の範囲内で損益通算が可能です。
たとえば、同一年に他の雑所得(暗号資産・ソーシャルレンディング・FXなど)で損失が出ている場合、それを不動産クラウドファンディングの利益と相殺できます。これにより、課税対象額を減らし、所得税・住民税の負担を軽くすることができます。
例として、不動産クラウドファンディングで50万円の利益が出て、仮想通貨投資で20万円の損失が出た場合、課税対象は差し引き30万円となり、税額を削減できます。
④ 損失の繰越控除による翌年以降の節税
損益通算をしてもなお損失が残る場合は、「繰越控除制度」を利用して翌年以降3年間にわたり利益と相殺することができます。これにより、翌年以降に利益が発生しても課税額を抑えられる可能性があります。
例えば、1年目に200万円の損失、2年目に50万円の利益、3年目に70万円の利益が出た場合、繰越控除を使えば2年目と3年目の税負担をゼロにできます。ただし、この制度を活用するには毎年の確定申告が必須です。損失を計上した年に申告を忘れると、翌年以降の繰越ができなくなる点に注意しましょう。

節税の基本は「知って活かす」ことです。確定申告や経費管理を怠らず、損益通算や繰越控除を上手に使えば、同じ利益でも手元に残る金額は大きく変わります。税金対策を意識した運用を続けることで、より効率的に資産を増やしていきましょう。
確定申告で節税効果を最大化するポイント
不動産クラウドファンディングの分配金は、事業者によって20.42%の源泉徴収が行われたうえで支払われます。しかし、確定申告を適切に行うことで、払いすぎた税金を還付できる場合があります。ここでは、節税効果を最大化するために押さえるべき具体的なポイントを解説します。
課税所得額が694万円以下なら還付の可能性を確認する
源泉徴収は一律20.42%ですが、所得税の実際の税率は累進課税制度により所得金額に応じて変動します。課税所得が694万円以下の人の場合、本来の税率より高い割合で源泉徴収されているため、確定申告を行えば税金が戻る可能性があります。給与所得者でも、副業や投資による雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
確定申告を行うことで、所得全体を正確に把握し、源泉徴収済みの税金との過不足を調整できます。自分の所得区分と控除内容を確認し、還付対象かを早めに判断することが重要です。
必要経費を正確に計上して課税所得を減らす
分配金は「雑所得」として課税されますが、収入から必要経費を差し引くことで課税対象額を減らせます。必要経費として認められる可能性がある主な項目は以下の通りです。
- 不動産クラウドファンディング関連のセミナー・勉強会参加費
- 投資に関する書籍や有料オンライン講座の費用
- インターネット通信費・パソコンの減価償却費の一部
- 専門家(税理士など)への相談料
領収書や請求書などの証憑をしっかり保管しておくことで、申告時にスムーズに経費計上が可能になります。
損益通算・繰越控除を活用する
任意組合型のクラウドファンディングにおいて、不動産所得が赤字となった場合は、給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することが可能です。これにより、所得全体の税負担を軽減できます。
また、損失が出た場合は「損失の繰越控除」を利用して翌年以降3年間にわたって利益と相殺できます。ただし、この特例を使うには毎年の確定申告が必須です。申告を怠ると翌年度に繰り越す権利が失われるため、忘れずに手続きを行いましょう。
書類の保管と記入内容の正確さが節税の鍵
確定申告では、クラウドファンディング事業者から発行される「取引明細書」や「源泉徴収票」が重要な証拠書類になります。これらを紛失すると正確な申告ができず、還付が遅れたり、税務署から問い合わせを受ける可能性もあります。
また、確定申告書の「所得区分」はファンドのタイプによって異なります。匿名組合型は「雑所得」、任意組合型は「不動産所得」として記載する必要があり、区分を誤ると申告内容が不正確となるため注意しましょう。
e-Taxの活用で効率的に申告
国税庁のe-Taxを利用すれば、自宅からオンラインで確定申告が完了します。マイナンバーカードを活用すれば、還付金の振込も迅速に行われます。特に投資家の場合、複数のクラウドファンディングや副業収入をまとめて申告するケースが多いため、デジタル管理を活用して効率的に節税手続きを進めることが重要です。

確定申告の工夫で節税額が大きく変わるんです。経費の漏れや損益通算の見落としをなくして、毎年の申告を「節税のチャンス」として活かしましょう
相続・贈与における不動産クラファンの節税メリット
不動産クラウドファンディングは、単なる運用益を狙う投資手段にとどまらず、相続税・贈与税対策としても注目されています。特に「任意組合型」のファンドを活用すれば、現物不動産と同様の扱いとなるため、評価額を下げて資産圧縮が可能です。
任意組合型で得られる相続税対策の効果
任意組合型の不動産クラウドファンディングでは、投資家が実質的に不動産の共有持分を所有します。したがって、税務上は「現物不動産」として評価され、相続や贈与の際には相続税評価額(路線価や固定資産税評価額)に基づいて課税されます。
通常、不動産の相続税評価額は市場価格(実勢価格)の約70%前後で算定されます。たとえば1億円の実勢価格の不動産を任意組合型で保有していた場合、課税対象は約7,000万円に抑えられる可能性があり、現金や匿名組合型のクラファン出資金(ほぼ100%評価)に比べて大きな節税効果が得られます。
匿名組合型との違いに注意
一方で「匿名組合型」では、不動産の所有権を持たないため、相続時には投資口(持分)自体が金融資産(現金等と同等)として評価されます。つまり、1口100万円で出資していれば、そのまま100万円として課税対象になります。
匿名組合型は手続きが簡便で、出資金以上のリスクを負わないというメリットはありますが、相続・贈与時の節税効果は限定的です。そのため、節税を重視する場合は任意組合型の方が有利といえます。
贈与時にも有効な「資産圧縮効果」
任意組合型ファンドの持分を家族などに贈与する場合にも、現物不動産と同じく評価額が実勢価格より低く算定されるため、贈与税負担を軽減できます。例えば、評価額7,000万円の持分を年間110万円ずつ数年に分けて贈与すれば、非課税枠を活用しながら効率的な資産移転が可能です。
このように、現金や有価証券をそのまま贈与するよりも、任意組合型不動産クラファンを利用することで評価圧縮による節税+スムーズな資産承継の両立が実現できます。
注意点とリスク管理
相続・贈与での節税効果を狙う場合には、以下の点に注意が必要です。
- 任意組合型は無限責任を伴うため、債務超過リスクを理解しておく
- 相続時に評価額が下がっても、実際の売却価値との差が大きいとトラブルになる可能性
- 税務署の判断で過度な節税スキームとみなされるリスクがあるため、税理士への相談が必須
相続税対策は単に「評価額を下げる」ことではなく、合法的な評価方法の範囲で最適化することが重要です。クラウドファンディングを使った資産承継を検討する際は、必ず専門家と連携しながら設計しましょう。

任意組合型を使えば、現物不動産と同様に「評価を下げて節税できる」仕組みが活用できます。ただし、相続・贈与は個別事情によって最適解が変わります。無理に節税を狙わず、専門家と一緒に安全なスキームを組み立てるのが賢明です
節税効果を得られる不動産クラファンおすすめサービス
不動産クラウドファンディングで節税を狙うなら、税務上「不動産所得」として扱われる任意組合型のサービスを中心に検討することがポイントです。以下では、節税効果を期待できる代表的なサービスを紹介します。
COZUCHI(コヅチ)
COZUCHIは、数少ない任意組合型の不動産クラウドファンディングです。投資家が不動産を共同で所有する形式のため、税務上は現物不動産と同じ「不動産所得」として扱われます。これにより、損益通算や繰越控除、経費計上などの節税が可能です。
また、相続や贈与の際には、保有資産が実勢価格より低い評価額(おおむね7割前後)で計算されるため、資産圧縮効果が期待できます。運用リターンだけでなく、税務面の優位性も重視する投資家に最も人気の高い選択肢です。
主な特徴:
- 任意組合型のため不動産所得として扱われる
- 損益通算・繰越控除が可能
- 相続・贈与時に評価額が下がるため節税効果が高い
- 都心再開発や再生案件など、資産価値の高い物件が多い
CREAL(クリアル)
CREALは上場企業が運営する匿名組合型のサービスです。節税効果という点では限定的ですが、源泉徴収後の分配金が安定しており、確定申告による還付を通じた実質的な節税が期待できます。
また、匿名組合型は有限責任のため、リスクを抑えつつ堅実に運用したい投資家に向いています。ファンド情報の開示が丁寧で、運用中の報告も透明性が高いのが特徴です。
主な特徴:
- 匿名組合型でリスクが低く初心者にも安心
- 安定した分配金と高い信頼性
- 確定申告で還付を受けられる可能性あり
- 教育・ホテル・レジデンスなど多様な案件を扱う
RENOSY(リノシー)
RENOSYは、不動産クラウドファンディングと現物不動産投資の両方を扱うハイブリッド型サービスです。匿名組合型のため直接的な節税効果は限定的ですが、投資設計を通じて損益通算や将来の不動産所得への切り替えを意識した長期的な税務戦略を立てやすい点が評価されています。
さらに、運営会社は上場企業であり、収益物件の管理や出口戦略にも強みがあります。節税を意識しながら安定的な資産形成を目指す中級者向けの選択肢です。
主な特徴:
- 不動産投資全体を見据えた税務設計が可能
- 上場企業運営で信頼性が高い
- 分配金の安定性と運用サポートが充実
- 現物不動産への移行も視野に入れた投資設計
節税効果を重視するなら任意組合型、安定運用なら匿名組合型
節税を最優先にするなら、損益通算や資産圧縮が可能な任意組合型(COZUCHI)が最も有利です。一方で、税務メリットよりも安全性や分配の安定性を重視する場合は、CREALやRENOSYのような匿名組合型を選ぶと良いでしょう。
どのサービスを選ぶにしても、投資目的と税務戦略を明確にし、必要に応じて税理士に相談することが大切です。

節税効果を狙うなら、まずは任意組合型をチェックしてみてください。仕組みを理解した上で、税務面とリスクの両方をバランスよく考えることが成功への第一歩ですよ
節税狙いの投資で失敗しないための注意点
節税を目的に不動産クラウドファンディングへ投資する際は、税制メリットだけに目を奪われず、リスクと制度の限界を正しく理解することが重要です。ここでは、実際に多い失敗事例や注意すべきポイントを整理します。
節税目的「だけ」で判断しない
節税効果を期待して投資を始めるのは悪いことではありませんが、「節税が目的化」してしまうと本来の投資判断を誤るリスクがあります。たとえば、損益通算を狙って赤字覚悟で投資を行うと、結果的に資金効率を悪化させるケースがあります。
不動産クラファンの本質は、安定した資産運用と分散投資にあります。節税効果は「結果として得られる副次的なメリット」と考えることが、長期的な成功につながります。
無限責任リスクを軽視しない
任意組合型ファンドでは、不動産を共同所有する代わりに「無限責任」が発生する可能性があります。万一、運用物件に大きな損失や債務が生じた場合、出資額を超える負担が発生することもあります。
実際の運用リスクは限定的とされますが、契約書や運営会社の開示情報を必ず確認し、出資先のリスク構造を理解したうえで投資判断を行うことが大切です。
経費の過剰計上に注意
節税対策として経費を計上できるのは有効ですが、根拠のない過剰計上は税務調査で否認されるリスクがあります。
たとえば、家賃や生活費など、明確に投資活動と関連性がない支出は経費に含められません。経費と認められるのは、以下のような「投資目的に直接関連する支出」に限られます。
- 投資セミナーや書籍購入費
- 投資管理用の通信費やパソコン費用の一部
- 税理士への相談料
計上の根拠となる領収書や明細は必ず保管し、確定申告時に説明できるよう整理しておきましょう。
損益通算・繰越控除の適用範囲を誤解しない
不動産クラファンで得た所得は「雑所得」または「不動産所得」として扱われます。
この区分を誤ると、損益通算や繰越控除が正しく適用されない場合があります。
特に匿名組合型ファンドの場合は「雑所得」に該当し、給与所得など他の所得との損益通算は認められません。税制上の取り扱いを正しく把握し、申告時の区分を間違えないよう注意が必要です。
税務・法務の専門家に相談する
税務処理は複雑であり、ファンドの契約形態によって扱いが異なります。自己判断で節税を進めると、申告ミスや過少申告加算税などのリスクを招く恐れがあります。
出資前に税理士やファイナンシャルプランナーへ相談し、税務面の影響を把握しておくことで、安心して運用を行うことができます。
まとめ
節税を意識した投資は効果的ですが、制度の仕組みや法的リスクを正確に理解しておくことが欠かせません。目先の税負担軽減よりも、長期的なリターンとリスク管理を重視する姿勢が重要です。

節税効果を狙うのは賢い戦略ですが、目的を“節税だけ”にしてしまうと本末転倒です。税制を正しく理解し、リスクとリターンを冷静に見極めることが、成功する投資家の共通点ですよ
| 順位 | 商品名 | 会社名 | 特徴 | 案件数 | 直近10件平均利回り | 直近10件直近最低利回り | 直近10件直近最高利回り | 直近10件募集割合平均 | 優先劣後方式 | 最低投資金額 | 募集方法 | 組合契約 | 物件の種類 | 優遇サービスあり | 物件の開示情報 | 出金手数料 | 運用レポートの共有あり | 運営会社設立年月 | 運営会社資本金 | 上場 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | COZUCHI(コズチ) | LAETOLI株式会社 | 投資募集のチャンスは業界上位。投資デビューに適した候補 | 139件 | 6.05% | 4.00% | 10.00% | 336.41% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 月1回まで無料(それ以降は330円) | ○ | 1999年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 2位 | CREAL(クリアル) | クリアル株式会社 | 募集口数が多く、新規案件の供給量も豊富 | 139件 | 5.67% | 5.00% | 6.50% | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス、保育所、学校、宿泊施設 | ○ | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 105円(楽天銀行の場合)、150円(楽天銀行以外で3万円未満の場合)、229円(楽天銀行以外で3万円以上の場合) | ○ | 2011年 | 1,273,520,500円 | ○ | 公式サイト |
| 3位 | 利回りくん | 株式会社シーラ | 年間新規案件数が安定。募集口数も一定水準 | 148件 | 4.26% | 3.00% | 5.12% | 76.70% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2010年 | 446,522,660円 | ○ | 公式サイト |
| 4位 | Rimple(リンプル) | プロパティエージェント株式会社 | 新規案件が充実。劣後出資割合の高い案件が多い | 112件 | 2.76% | 2.70% | 3.30% | 277.80% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、事業内容 | 無料 | ○ | 2004年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 5位 | TECROWD(テクラウド) | TECRA株式会社 | 新興国不動産への投資が可能。高利回り案件が多い | 90件 | 10.90% | 9.50% | 12.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、オフィス | ○ | 住所、運営会社、財務情報、面積、事業内容 | 無料(楽天銀行)、振込手数料(楽天銀行以外) | ○ | 2001年 | 156,600,000円 | × | 公式サイト |
| 6位 | TSON FUNDING(ティーソン) | 株式会社TSON | 年間案件数が最多クラス。リスク軽減案件も豊富 | 230件 | 5.81% | 5.50% | 6.00% | 96.30% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、事業内容 | 無料(匿名組合ファンド)、振込手数料(任意組合ファンド) | ○ | 2008年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 7位 | 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス | 運営会社の信頼性が高く、新規案件も安定供給 | 109件 | 5.90% | 3.50% | 12.00% | 728.48% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛) | ○ | 1996年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 8位 | FUNDROP(ファンドロップ) | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 | 劣後出資割合の高い案件が多いが、投資機会は少なめ | 39件 | 5.75% | 5.50% | 6.00% | 128.54% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 52円(楽天銀行)、150円(他の金融機関で3万円未満)、229円(他の金融機関で3万円以上) | ○ | 2013年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 9位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 穴吹興産株式会社 | 低リスク案件が多いが、投資の機会は限定的 | 43件 | 3.25% | 3.00% | 5.00% | 99.98% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設 | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 1964年 | 755,790,000円 | ○ | 公式サイト |
| 10位 | ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 | 劣後出資割合の高い案件が多く、運営も安定傾向 | 10件 | 4.00% | 3.90% | 4.30% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(その他の金融機関) | ○ | 1991年 | 389,820,000円 | × | 公式サイト |
| 11位 | property+(プロパティプラス) | 株式会社リビングコーポレーション | 募集口数は平均的だが、新規案件がなかった点が課題 | 34件 | 3.20% | 3.00% | 3.40% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2015年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 12位 | ASSECLI(アセクリ) | 株式会社エボルゾーン | 高利回り案件が多いが、新規提供数は限られる | 45件 | - | 0.00% | 0.00% | 105.85% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 事業内容 | 無料 | × | 2011年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 13位 | LIFULL(ライフル) | 株式会社LIFULL | 大手不動産会社のクラウドファンディング。厳選された物件 | 3件 | 5.83% | 5.50% | 6.00% | 105.67% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション・グループホーム | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | × | 1997年 | 9,723,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 14位 | みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント | 」「公的年金に合わせた2ヵ月ごとの分配金」が特徴の、不動産クラウドファンディング | 151件 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、物件種別、アクセス、構造、総戸数、家賃保証有無 | PayPay銀行への払い戻し:無料、PayPay銀行以外への払い戻し:145円 | × | 2016年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 15位 | 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス | 高水準の利回り案件が豊富で、投資のチャンスも平均以上 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行あて) | ○ | 2023年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 16位 | らくたま | 株式会社日本保証 | リスクを抑えつつ高いリターンを狙える案件が多く、供給数も充実 | - | - | - | - | - | ○ | 10000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、商業施設、オフィス | ○ | 築年数、住所、面積 | 無料(GMOあおぞらネット銀行) | × | 2008年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 17位 | GALA FUNDING(ガーラ ファンディング) | 株式会社FJネクストホールディングス | 運営基盤が堅実で、劣後出資割合が高めの安心感ある案件が中心 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛て) | ○ | 1980年 | 2,774,400,000円 | ○ | 公式サイト |
| 18位 | トモタク | 株式会社イーダブルジー | 新規募集数は業界トップクラスで、高利回り案件が目立つ | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、オフィス | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 1回のみ無料(125円(GMOあおぞらネット銀行)、250円(GMOあおぞらネット銀行以外)) | ○ | 2009年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 19位 | LSEED(エルシード) | 株式会社LSEED | リスクとリターンのバランスは良好だが、案件数はやや少なめ | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、面積、事業内容 | 不明 | × | 1999年 | 706,139,500円 | ○ | 公式サイト |
| 20位 | トーセイ不動産クラウド | トーセイ株式会社 | 1万口超の大型案件が主体で、年間の提供数は限定的 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、129円(その他金融機関) | ○ | 1950年 | 6,624,890,000円 | ○ | 公式サイト |
| 21位 | KORYO Funding(コウリョウ ファンディング) | 株式会社興陵 | 安定したバランス型案件が揃う一方で、全体の件数は少ない | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容 | 無料 | × | 1981年 | 371,980,200円 | ○ | 公式サイト |