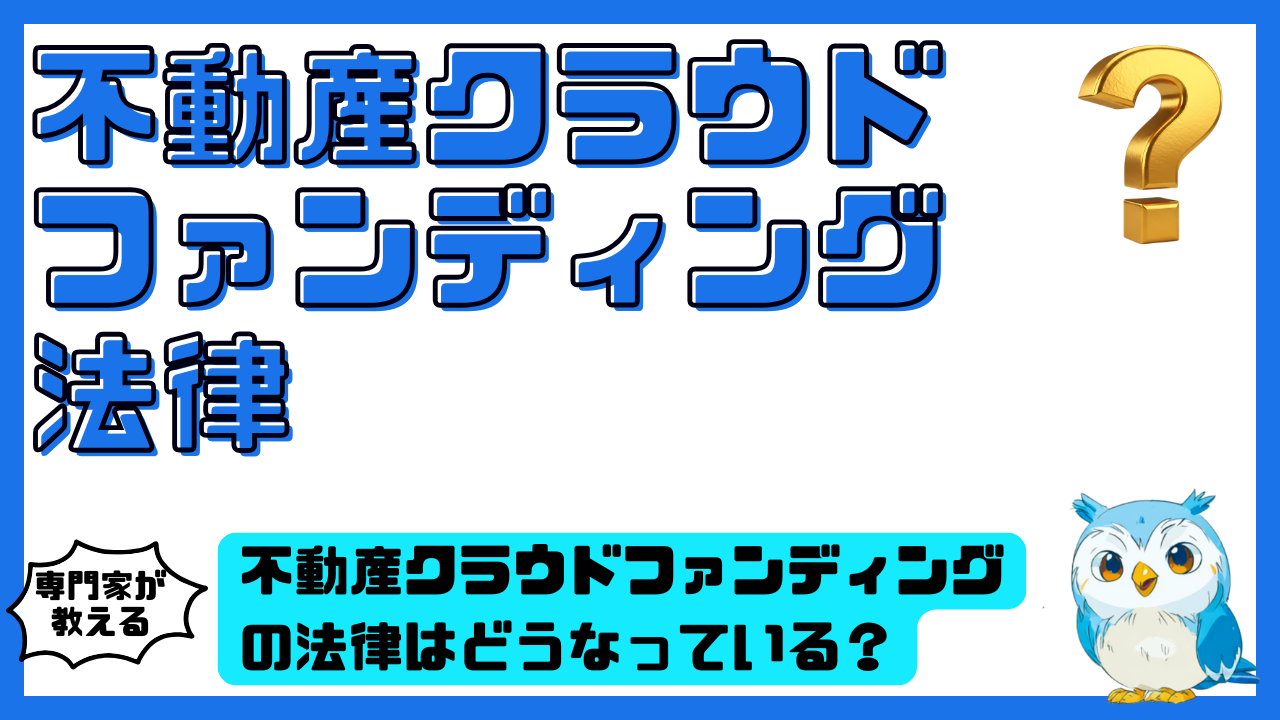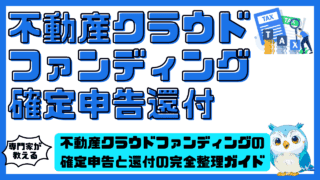本ページはプロモーションが含まれています。
目次
不動産クラウドファンディングに関係する主要な法律の全体像
不動産クラウドファンディングは、「インターネットで少額ずつ資金を集めて不動産に投資する」という、比較的新しい仕組みです。しかし法的にはまったくの新種ではなく、既存の複数の法律の“組み合わせ”として位置づけられています。ここを押さえておくと、各サービスの安全性やリスクを自分で見極めやすくなります。
投資型クラウドファンディングとしての位置づけ
まず前提として、不動産クラウドファンディングは「投資型クラウドファンディング」に分類されます。
投資家から集めたお金で事業者が不動産を取得・運用し、その収益を分配するため、金銭的なリターンを目的とした“投資商品”として扱われます。
この「①他人からお金を集めて、②そのお金で事業や投資を行い、③そこで生じた利益を出資者へ分配する」という仕組みは、法律上「集団投資スキーム持分」と呼ばれ、金融商品取引法の規制対象になります。
そのうえで、不動産を対象とするスキームであることから、不動産特定共同事業法の枠組みも同時に適用されます。
中心となる二つの法律の役割
不動産クラウドファンディングを理解するうえで、投資家が最低限押さえておきたい中核となる法律は次の二つです。
- 金融商品取引法
- 不動産特定共同事業法(不特法)
この二つは似ているようで役割が違います。
金融商品取引法は、株式や投資信託などと同じく「金融商品」としての側面を規制する法律です。
どのような説明を行い、どこまでリスクを開示し、どのような勧誘をしてはいけないのか、といった“金融商品としての売り方・説明の仕方”に細かいルールを課すことで、投資家保護を図っています。
一方、不動産特定共同事業法は、「複数の出資者から資金を集めて不動産を取得・運用し、その収益を分配する」という事業スキームそのものを規律する法律です。
どのような事業者だけがこのビジネスを行えるのか、資本金や財務基準、業務管理者の要件、契約約款の基準などを定めることで、事業運営の健全性と投資家の利益保護を目的としています。
イメージとしては、
- 金融商品取引法
→「投資商品としてどう売るか・どう説明するか」をチェックする法律 - 不動産特定共同事業法
→「不動産投資ビジネスとしてどんな会社が運営してよいか」をチェックする法律
という役割分担になっていると考えると整理しやすいです。
インターネットを使うからこそ必要な追加ルール
不動産クラウドファンディングは、申し込みから契約、入金、運用報告までをインターネット上で完結する「電子取引業務」として行われます。
このため、従来の対面型の不動産小口化商品よりも、次のようなポイントに追加のルールが設けられています。
- オンライン上での情報提供の方法やタイミング
- システム障害が起きた場合の対応方針
- クーリングオフ(契約解除)の手続きの案内
- 投資家の資金と事業者の資金を分けて管理する「分別管理」のルール
- 個人情報やログイン情報を守るための情報セキュリティ体制
これらは不特法本体に加えて、「電子取引業務ガイドライン」などで具体的に示されており、インターネット完結型のサービスであっても、対面以上のレベルで投資家保護を図ることが求められています。
他に関わってくる周辺の法律
不動産クラウドファンディングは、上記二つの法律が中心ですが、実際のサービス運営では次のような周辺法令も関係してきます。
- 宅地建物取引業法
不動産の売買や賃貸の仲介を行う場合に関わる法律で、宅建業の免許や重要事項説明などに関するルールが定められています。 - 資金決済関連のルール
投資家からの入出金や分配金の支払方法によっては、資金決済関連の規制や銀行・信託を使った分別管理のルールが絡みます。 - 個人情報保護法
会員登録・本人確認・マイページの運用などを通じて受け取った投資家の個人情報を、どのように保護・管理するかを定める法律です。
投資家としてすべてを細かく暗記する必要はありませんが、「複数の法律が重なり合いながら投資家を守る仕組みになっている」という全体像を持っておくことは重要です。
投資家目線で押さえておきたい“法的なチェックポイント”の考え方
法令の条文を読み込まなくても、投資家として最低限チェックしておきたいポイントは、次のように整理できます。
- このサービスは「どの法律のもとで運営されているのか」
→ 金融商品取引法上の登録(第二種金融商品取引業)や、不特法の許可・登録の有無など - 事業者は「どのタイプの不特法事業者」なのか
→ 第1号・第2号だけなのか、第3号・第4号や小規模事業者なのかによって、スキームやリスクの構造が変わります。 - 投資家保護のための仕組みが開示されているか
→ 倒産隔離スキーム(SPC利用)の有無、分別管理の方法、クーリングオフや中途解約のルールなど
これらは、各サービスの公式サイトの「重要事項」「契約締結前交付書面」「リスク・手数料等について」といったページに記載されていることが多く、法令に基づき開示が義務づけられている情報も含まれます。
つまり、どの法律に基づき、どこまでの投資家保護策がとられているのかは、単なる“会社の方針”ではなく、法律に裏付けられた仕組みとして確認できるということです。

不動産クラウドファンディングの法律は名前が難しいですが、実は「金融商品としての売り方を縛る法律」と「不動産投資ビジネスとしての運営を縛る法律」が組み合わさって投資家を守っているんだ、というイメージを持てれば十分です。サービスを選ぶときは、この二つの視点から「どの法律に基づき、どんな保護策があるのか」を冷静にチェックしていきましょうね
金融商品取引法で規制されるポイント
不動産クラウドファンディングは、投資家から資金を集めて運用し、その収益を分配するという構造を持つため、金融商品取引法(以下、金商法)の規制を強く受ける領域です。金商法の対象となる理由と、投資家が特に確認すべき規制ポイントを整理して解説します。
投資型クラウドファンディングは「集団投資スキーム持分」として扱われる
不動産クラウドファンディングでは、投資家が出資した資金を事業者がまとめて不動産に投資し、得られた収益を投資家へ配当します。このように
「出資」
「資金の一体運用」
「収益の分配」
の三つが揃う仕組みは、金商法上の“集団投資スキーム持分”に該当します。
集団投資スキームは投資家保護の観点で、株式や債券と同様に“みなし有価証券”として扱われるため、募集方法、情報開示、広告規制などが細かく定められています。結果として、不動産クラウドファンディングも広い意味で「金融商品」としての規律が適用されます。
第二種金融商品取引業の登録が必須となる
投資型クラウドファンディングの募集・運営を行う事業者は、金商法に基づく「第二種金融商品取引業」の登録が必要です。登録のハードルは低くなく、主に以下が求められます。
- 投資家保護のための十分な財務基盤
- 適切なリスク管理・コンプライアンス体制
- 運営スタッフの必要資格・経験
- 情報管理や分別管理の仕組みの整備
登録の有無は、法律順守姿勢を示す最も分かりやすい基準であり、投資家は必ず確認しておくべき要素です。
誤認を防ぐための「広告・勧誘規制」が非常に厳しい
金商法では、広告の記載内容から勧誘の方法まで細かくルール化されています。不動産クラウドファンディングでも同様で、以下のような行為が禁止されています。
- 実現可能性の低い利回りを断定的に示す
- 元本保証のように捉えられる表現
- 重要なリスク情報を故意に小さく記載する
- 投資判断に影響する事実を意図的に隠す
リスク説明や募集条件の開示も法律で義務付けられており、特に電子取引業務(オンライン完結型の申し込み)では、情報提供のタイミングや記載方法に関するガイドラインも設定されています。
情報開示義務により、投資家の判断材料が担保される
金商法では、有価証券の募集と同様に、投資家に必要な情報の開示が求められます。不動産クラウドファンディングの場合、主に以下が対象です。
- ファンドの資金使途
- 不動産の取得・運用・売却の方針
- 想定利回りの根拠
- 手数料・報酬体系
- 想定される主要リスク
- 匿名組合契約など契約スキームの構造
情報開示の質が低いファンドほど投資家の損失リスクは高まりやすいため、提供資料の透明性は重要な判断基準となります。
違反行為は行政処分の対象になる
金商法は罰則が強く、違反した場合は以下のような処分が行われます。
- 業務停止命令
- 行政指導
- 登録取消
- 刑事罰(悪質な場合)
不動産クラウドファンディング事業者にとっては重大事項であり、法律違反を起こす事業者は市場から排除されやすいため、結果的に投資家保護につながる仕組みとなっています。
投資家が特に確認すべき金商法関連のチェックポイント
投資前には、最低限次の項目を確認しておくことで“リスクの高い事業者”を避けられます。
- 第二種金融商品取引業の登録番号の記載があるか
- リスク説明が十分に行われているか
- 利回りや安全性の説明に誇張がないか
- 広告の文言に不自然な表現がないか
- 契約前に提供される書面(契約締結前交付書面)が適切か
金商法の規制は複雑ですが、これらが整備されているかどうかだけでも安全性の大きな判断材料になります。

不動産クラウドファンディングの金商法は、投資家を守るための“最低限のライン”です。登録の有無、広告の透明性、開示資料の質をしっかり見ることで、安心して選べるサービスがぐっと増えていきますよ
不動産特定共同事業法(不特法)とは何か
不動産特定共同事業法(不特法)は、複数の投資家から資金を集め、不動産を取得・運用し、そこから得られる収益を分配する事業モデルを規律する法律です。投資家資金を扱う仕組みである以上、透明性と公正性を担保する必要があり、そのために事業者の許可制度や運営ルールが細かく定められています。
この法律は1995年に施行され、当初は専門的な不動産小口化商品を対象としていましたが、2017年の改正でインターネットを使った取引「電子取引業務」が制度化され、不動産クラウドファンディングの仕組みが正式に整備されました。これにより一般の投資家でもオンラインで安全に不動産投資へ参加しやすくなりました。
不特法が規定する「不動産を用いた共同投資」の明確なルール
不動産クラウドファンディングは、投資家が直接不動産を所有するわけではなく、事業者が運用主体となって不動産取引を行います。そのため、以下のような明確な法的枠組みが不可欠です。
- 出資の募集方法と契約手続きのルール
- 投資家への情報開示の内容と頻度
- 投資家資産の分別管理
- 損失発生時の対応方針
- 広告・勧誘の適正性
これらの基準を満たすため、事業者は国土交通省や都道府県知事の許可または登録を受ける必要があります。
投資家保護のための厳格な許可・登録制度
不特法で事業を行うには、一定の財務基盤、宅建業の免許、内部統制プロセス、人材要件など、多岐にわたる基準を満たさなければなりません。特に「業務管理者」の存在は重要で、宅建士資格を有し、指定資格または不特事業の実務経験を備えた専門人材の配置が求められます。
主な許可・登録基準の例として、次のような項目があります。
- 事業者の資本金・財務基盤
- 事務所ごとの業務管理者の配置
- 契約約款の法令適合性
- 不動産取引を適切に遂行できる人的構成
- 宅建業免許の保有
このような高い参入基準があることで、不適切な運営による投資家の損失を未然に防ぐ狙いがあります。
法改正でクラウドファンディングに対応し、利便性が向上
2017年の改正では、クラウドファンディング型スキームを想定した「電子取引業務」が明文化されました。これにより、不動産クラウドファンディングは法律上の位置づけが確立し、
- オンラインでの契約締結
- クーリングオフ制度
- 電子開示の統一ルール
- システム障害時の対応基準
といった、投資家にとって重要な保護措置が整備されました。
従来の対面や紙面での契約が必要だった不動産投資に比べ、安全性を保ちながら利便性が大きく向上した点が特徴です。
不特法が投資家に提供するメリット
不特法が整備されていることで、投資家は以下のようなメリットを享受できます。
- 事業者の財務基盤や運用体制が法令により保証される
- リスク説明・契約条件が統一された基準で提供される
- 不正勧誘・誤認を招く広告の禁止により安心して判断できる
- 分別管理や倒産隔離スキームにより資産保全性が高まる
- 電子取引により手間なく参加できる
不動産という高額資産を扱う投資でも、法的な枠組みによって透明性が確保されている点が、不動産クラウドファンディングの強みと言えます。
事業者の種類によってリスクとスキームが変わる
不特法には「第1号〜第4号」という事業区分があり、どの種類の許可を取得しているかによってスキームの特徴や投資家保護のレベルが変わります。たとえば、倒産隔離スキームを備えた特例事業(第3号・第4号)では、投資家資産を事業者本体から切り離せるため、運営会社の信用に依存しづらい構造になります。
こうした事業区分を理解することは、投資家が安全性を見極める上で非常に重要です。

法律の枠組みを理解すると、不動産クラウドファンディングが「ただ便利なサービス」ではなく「制度として安全性が担保された投資商品」だと分かりますよ。まずは不特法の基本を押さえることが、リスクを避ける第一歩になります
不特法の「1号・2号・3号・4号」と小規模事業の違い
不動産クラウドファンディングにおいて、事業者がどの区分(1号・2号・3号・4号・小規模)で事業を行っているかは、投資家のリスクや保護水準を左右する極めて重要な要素です。区分によって不動産の保有主体、倒産時の資産保全、許可要件、利用できるスキームが大きく異なるため、投資判断に直結します。
不特法1号事業者の特徴
1号事業者は、不動産を自ら取得し運用し、そこで得られた利益を投資家に分配する最も基本的なスキームです。国内の不動産クラウドファンディングの多くがこの1号型を採用しています。
1号事業者は不動産の保有主体となるため、事業者本体の信用リスクが投資家に直接影響します。運営会社が破綻した場合、不動産が債権者の請求対象になる可能性があるため、財務基盤・グループ企業の強さ・業務管理体制のチェックが大切です。
不特法2号事業者の役割
2号事業者は、投資家と1号事業者の間で契約を代理・媒介する区分です。自ら不動産を取得・運用するわけではありませんが、募集・勧誘・リスク説明の要となる重要な役割を担います。
実務では、1号と2号を併せ持つ事業者が多く、投資家への説明責任や情報提供の質は、この2号事業者としての運営力によって左右される場合があります。
不特法3号事業者の役割と投資家へのメリット
3号事業者は、特例事業者(主にSPC)が行う不動産取引・運用業務を受託する区分です。ここで重要になるのが「倒産隔離スキーム(特例事業)」が使える点です。
SPC(特別目的会社)が不動産を保有し、運営会社とは独立した財務構造を持つため、万が一運営会社が破綻してもファンド資産が保全されやすく、投資家の信用リスクが大きく低減されます。
3号・4号を取得している事業者は少なく、SPC活用型のファンドを運用できるのは限られた事業者のみです。安全性の高さから、機関投資家や金融機関からの評価も高い傾向があります。
不特法4号事業者の役割
4号事業者は、特例事業者と投資家の契約締結を代理・媒介する区分です。3号同様、倒産隔離スキームを用いた特例事業を成立させるために必要な許可となります。
実務では3号と4号をセットで保有するケースが多く、このセットを取得している事業者は高度なスキームを扱える点で強い信頼性を持ちます。
小規模不動産特定共同事業の特徴
2017年に導入された小規模事業は、中小規模の事業者でも不動産クラウドファンディングへ参入しやすくするために設けられた登録制の枠組みです。
特徴は次の通りです。
- 投資家1人あたりの出資上限は100万円
- ファンド総額は1億円まで
- 資本金要件は1号・2号とも1,000万円
- 許可制ではなく登録制で参入しやすい
参入ハードルが低い一方で、大規模案件の扱いは難しく、倒産隔離など高度なスキームは利用できません。そのため、投資家は事業者の経験・財務基盤・過去の実績をより丁寧に見極める必要があります。
1号〜4号と小規模事業の違いが生む投資判断ポイント
不動産クラウドファンディングを比較する際、投資家が注目すべき重要ポイントは以下です。
- 不動産を誰が保有するか(1号は運営会社、3号・4号はSPC)
- 倒産時の資産保全(3号・4号は倒産隔離が可能)
- 許可要件の厳しさと事業者の信頼性
- ファンド規模の上限(小規模は最大1億円)
- レバレッジの有無(ノンリコースローン活用)
これらの要素により、投資対象ファンドのリスク構造は大きく変わります。

不特法の区分は、投資家のリスクや保護の強さを判断する上で本当に重要なんです。特に3号・4号は倒産隔離が可能で安全性が高い一方、小規模事業は柔軟でも見極めが必要です。仕組みの違いを理解して、自信を持って投資判断できるようにしてくださいね
倒産隔離スキームとSPC活用が生む投資家保護
不動産クラウドファンディングにおいて最も重視されるのが「万一の事業者倒産時に、投資家の資産が守られるか」という点です。この課題に対して法制度が用意したのが、倒産隔離スキームとSPC(特別目的会社)の活用です。とくに不特法の第3号・第4号事業では、この仕組みを本格的に採用できるため、投資家保護のレベルが大きく向上します。
倒産隔離スキームとは何か
倒産隔離とは、投資対象となる不動産や関連資産を事業者本体の財務リスクから切り離す仕組みです。不動産クラウドファンディングで一般的な第1号スキームでは、不動産を保有するのは運営会社であるため、運営会社が倒産すると以下のリスクが発生します。
- 運営会社の債権者に不動産が差し押さえられる可能性
- ファンドの運営継続が難しくなり、配当や元本返還に影響
- 投資家の出資金が毀損するリスクが高まる
この構造的な問題を解決するために導入されたのが特例事業(第3号・第4号)です。
SPC(特別目的会社)が果たす役割
倒産隔離型スキームでは、不動産を保有するのは運営会社ではなくSPCです。SPCはファンド運営のためだけに設立される独立した法人であり、事業会社の倒産リスクと切り離された存在として扱われます。
SPCを活用すると、次のような効果が得られます。
- 不動産がSPC名義で管理されるため、運営会社が破綻しても不動産は保持される
- 投資家のリスクが「SPCが保有する不動産の価値」に限定される
- 事業会社の財務状況がファンドに波及しにくくなる
- 不動産の所有がオフバランス化され、透明性の高い運用ができる
第3号・第4号事業者が提供する安全性の高さ
倒産隔離スキームを実現できるのは、不特法第3号・第4号事業者に限られます。これらの事業者が組成するファンドには、次のような特徴があります。
- 投資家資産の法的保護が最も強化されている
- 不動産単独での資金調達(ノンリコースローン)が可能
- 機関投資家も参入しやすく、大型案件の組成に向いている
- 不動産の収益性に連動した透明性の高いスキームを構築しやすい
一般的なクラウドファンディング(第1号・第2号)と比べ、信用リスクの構造が大きく異なります。
ノンリコースローンの活用で投資効率が上昇
SPCを主体とするスキームでは、金融機関からのノンリコースローンを導入しやすくなります。これにより、不動産を担保にして資金調達が可能になり、出資金だけでは実現できない規模のファンドを組成できます。
ノンリコースローンを活用することで得られる効果は次の通りです。
- ファンド規模の大型化が可能になる
- レバレッジ効果で投資家の利回り上昇が期待できる
- 運営会社の信用力に頼らず不動産そのものの価値で資金調達が可能
ただし、借入金を活用する分、物件収益が低下した場合の損失幅が広がるなどのリスクも存在するため、プロの運用体制が求められます。
投資家が見るべきチェックポイント
倒産隔離スキームが導入されているかどうかは、投資家が最初に確認すべき重要なポイントです。とくに以下は必ずチェックしておきたい項目です。
- ファンドの所有者が運営会社かSPCか
- 不特法の事業者区分(1号〜4号のどれか)
- ノンリコースローンの採用有無
- SPCの設計や監査体制が明確か
- 契約約款に倒産隔離の条項が記載されているか
これらが明確であればあるほど、投資家保護のレベルは高いといえます。

倒産隔離は難しく見えますが、要は「会社が破綻しても不動産は守られるか」を分ける仕組みです。SPCを使うファンドは投資家の安全度が一段上がりますので、投資判断の基準にしっかり入れておくと安心ですよ
電子取引業務(クラウドファンディング)が認められる条件
不動産クラウドファンディングの大きな特徴は、投資申し込みから契約締結、交付書面の閲覧、入出金管理までをインターネット上で完結できる点です。これは2017年の不動産特定共同事業法(不特法)改正により「電子取引業務」が正式に認められたことで実現しました。ただし、すべての事業者が自由に行えるわけではなく、投資家保護の観点から厳格な条件が課されています。
電子取引業務の実施に必要な根本条件
電子取引業務を行う事業者は、対面取引と同等以上の安全性・透明性が担保されていることを証明する必要があります。特に不動産クラウドファンディングは集団投資スキームに該当するため、投資家がオンラインで判断する際に不利益を被らない体制が必須です。
電子取引業務を認めるための主な条件には、次のようなものがあります。
- 電子交付される契約書面・重要事項説明の真正性を保証する仕組みがあること
- 投資家本人確認(eKYC)を含む適切な認証方式
- 情報提供・リスク説明がオンラインで完結し、書面交付と同等の内容とタイミングで実施されること
- 投資家からの問い合わせ・契約内容確認が随時可能であること
これらは、対面での説明が省略されるオンライン取引において、情報の非対称性を極力抑えるための重要な仕組みです。
システム障害への対応体制
電子取引業務ガイドラインでは、システム障害に対する“事前準備”が義務化されています。投資家の資金移動や契約締結がオンラインで行われるため、障害発生時の停止・復旧・連絡のフローが明確である必要があります。
システム障害の対応には、次の内容が求められます。
- 障害発生時の緊急連絡体制
- 障害の検知・原因分析・復旧の手順化
- 投資申込みが期限付きの場合の代替措置
- システム監査やログ管理による継続的な監視体制
- 障害が投資家に与える影響を最小限に抑えるリスク管理策
特に、申し込み期間が短いクラウドファンディングでは、システム停止の影響が大きいため、事業者の対応力は投資家保護の重要指標になります。
情報セキュリティと分別管理の体制
オンライン完結型である以上、事業者が備えるべき情報セキュリティ体制は高度です。内部監査やアクセス権限管理はもちろん、外部攻撃を想定した防御設計、通信の暗号化、データバックアップ体制などが欠かせません。
セキュリティ体制の評価ポイントとして、以下が挙げられます。
- 外部委託先(サーバー・決済代行)の管理基準が明確である
- 不正アクセス検知・ログ保存などのモニタリング体制
- 投資家の資金と事業者資金の分別管理ルール
- 個人情報保護方針に基づく取り扱いと監査記録
とくに分別管理は、事業者の破綻時に投資家資産を守るための最重要条件であり、クラウドファンディング運営者は例外なく遵守する必要があります。
クーリングオフ制度を含む消費者保護措置
オンラインで契約を行う場合、投資家が誤った判断をしてしまう可能性があるため、不特法では「クーリングオフ制度」が義務づけられています。
- 契約後一定期間は理由を問わず解除できる
- クーリングオフ手続きがオンラインで完了する
- クーリングオフ期間の起算時点を明確に表示する
- 契約締結前に必ずクーリングオフの存在を告知する
これらは消費者保護制度の中核であり、電子取引業務を導入する条件として不可欠です。
電子取引業務を行う事業者の内部管理体制
電子取引業務は、単なるオンライン化ではなく「リスク管理型の運営体制」が求められます。ガイドラインに従い、運営体制は次のような基準で評価されます。
- 内部監査・リスク管理部門の独立性
- 法務・コンプライアンス体制の整備
- 契約トラブル時の対応フローの明文化
- 投資家への定期的な運営報告
- 苦情処理や紛争解決のための窓口設置
投資家の保護を最優先にした仕組みであるかどうかは、運営会社ごとに大きな差が生まれる部分です。
投資家が確認すべきポイント
電子取引業務は便利ですが、すべての事業者が同レベルではありません。投資家は次の点を確認することで、安全性を判断できます。
- 電子取引業務ガイドラインに基づいた運営体制の説明がある
- 障害対応やセキュリティ体制について明記されている
- クーリングオフの手続きが分かりやすい
- 分別管理・監査体制の情報が開示されている
大手企業や上場企業であっても、電子取引業務の品質は事業者ごとに異なるため、公式サイトや交付書面を細かくチェックすることが重要です。

電子取引業務は便利な仕組みですが、条件を満たした事業者だけが提供できる制度なんです。確認するポイントを押さえておくと、安心してクラウドファンディングを選べますよ
投資家が確認すべき「法律チェックポイント」
不動産クラウドファンディングは、金融商品取引法と不動産特定共同事業法の2つの法律が同時に関係するため、投資家は“法律上の安全性”を自分で見極める必要があります。
ここを確認しないと、想定より高いリスクを負う可能性があります。特に、同じクラウドファンディングでも法的スキームが大きく異なるため、事業者ごとの差が最も出やすい部分です。
投資前に必ず押さえたいポイントを整理します。
事業者が「不特法の何号」で登録・許可されているか
不動産クラウドファンディングは、不特法の何号で事業を行っているかで安全性・リスク構造が大きく変わります。
代表的な違いは以下の通りです。
- 1号・2号事業者:事業者本体が不動産を保有し運用する
- 3号・4号事業者:SPCを用いる特例事業で、倒産隔離が可能
- 小規模不特法事業者:出資額・総額に制限があり参入しやすい分、事業者の経験値にばらつきがある
特に3号・4号事業者は数が少なく、倒産隔離スキームが組める点で安全性が高いとされています。
第二種金融商品取引業の登録の有無
不動産クラウドファンディングは「投資型クラウドファンディング」に該当し、金融商品取引法上の“金融商品”として扱われます。
そのため、以下を必ず確認します。
- 事業者が第二種金融商品取引業の登録を受けているか
- 登録番号や登録年月日が明記されているか
- 金商法に基づく広告規制・勧誘ルールが遵守されているか
登録されていない場合、投資家保護ルールが適用されず、重大なリスクになります。
契約約款とリスク説明が整備されているか
投資家保護の中核となるのが、契約書・約款・重要事項説明です。
特に確認すべき点は以下です。
- 損失リスクや分配金が保証されない点が明確か
- 中途解約の条件が適切に説明されているか
- 投資対象不動産の取得方法・運用方法が明記されているか
- 報酬や手数料の記載が曖昧になっていないか
説明が不十分な事業者は、トラブルの原因となります。
倒産隔離スキーム(SPC活用)の有無
事業者が倒産した場合に、投資家の資産がどこまで保護されるかは、法的スキームによって大きく異なります。
- SPCを活用した特例事業(3号・4号)
→ 不動産をSPCが保有するため、原則として運営会社の破綻影響を受けにくい - 1号・2号型(匿名組合型中心)
→ 事業者本体が不動産を保有しているため、破綻した場合に差し押さえのリスクがある
安全性を高めたい場合、倒産隔離スキームが整備されているかを必ず確認します。
分別管理・監査・内部統制の運用状況
電子取引業務が正式に認められたことで、事業者には情報提供・内部管理・システム安全性に関する詳細な基準が課されています。
特に確認すべきは次の点です。
- 投資家資金の分別管理(事業者資産と完全に区別)
- 業務管理者の配置状況(不特法で必須)
- 外部監査・内部監査の実施状況
- システム障害対策・情報セキュリティ体制
- 問い合わせ窓口の整備状況
これらの運用が明確に説明されている事業者は信頼性が高い傾向があります。
行政処分・トラブル履歴の確認
事業者が過去に行政処分を受けている場合、その内容は重要な判断材料になります。
- 金融庁の行政処分情報
- 国土交通省の不特法に基づく処分履歴
- 過去のシステム障害・遅延トラブルの公表状況
透明性の高い事業者ほど、過去の問題についても公表しています。
まとめて確認できるチェックリスト
以下を投資前に最低限確認するだけで、法律上の重大リスクを大きく減らせます。
- 事業者が不特法の何号か
- 第二種金融商品取引業の登録有無
- 契約約款・重要事項説明の質
- 倒産隔離スキームの有無
- 分別管理や内部管理体制の整備
- 行政処分歴・トラブルの公開状況
これらを総合的に見れば、同じ利回りの商品でも“安全性の質”が大きく違うことが分かります。

法律をチェックするのは難しそうに見えますが、今回のポイントを押さえていれば大丈夫ですよ。特に「不特法の号数」「金商法登録」「倒産隔離スキーム」は必ず確認して、安全性の高いサービスを選んでくださいね
法改正動向と今後の投資家が取るべき対応
不動産クラウドファンディングは、2017年以降の不特法改正をきっかけに一気に普及しましたが、市場規模の拡大に伴い、今後も制度面のアップデートが続くことが予想されています。とくに電子取引業務の高度化、参入事業者の多様化、投資家保護ルールの強化といった領域は、行政側が重点的に見直している分野です。投資家は“変わるルール”に敏感であるほど、リスクを減らし安全なサービスを選べるようになります。
不特法の改正は段階的に続いている
不特法は2013年から継続的に改正されており、クラウドファンディング市場の発展にあわせて制度がアップデートされています。とくに注目すべき点は、事業者の参入ハードル調整と投資家保護措置の強化です。
過去の大きな改正では以下のような変化がありました。
- 特例事業(倒産隔離型スキーム)の導入により、投資家の信用リスクが構造的に低減
- 電子取引業務の制度化によりオンライン完結型の不動産クラウドファンディングが合法化
- 小規模不特法の創設により、中小規模の事業者が参入しやすくなる一方で、事業者ごとの安全性に差が生まれやすくなる
- ガイドライン整備により、システム障害対策・情報提供・クーリングオフなど電子取引特有のリスク管理が厳格化
このように、不特法は“既存の仕組みを保護する”というより、“市場の成長と安全性の両立を進める”方向で頻繁に見直されています。
今後強化が見込まれる領域
行政資料や市場動向から見える、今後の重点ポイントは次のとおりです。
電子取引業務のガイドライン強化
投資家保護の観点から、以下の分野で追加的な規制・指針が強化される可能性があります。
- サーバー障害・アクセス集中への対応基準の明確化
- AIを活用した審査・説明画面の適正化
- 分別管理やシステム監査の実効性向上
オンライン完結型のサービスが一般化したことで、システム面の信頼性は法令レベルでも重視されつつあります。
小規模不特法の透明性向上
参入事業者の増加により、運営体制の差が大きくなりました。今後は以下が焦点になると見られます。
- 小規模事業者の開示義務強化
- 実績に基づく登録更新の厳格化
- 事業者の財務基盤や内部管理体制の明示化
小規模事業者が多い領域ほど、投資家が自ら見極める必要性が高まります。
倒産隔離スキームの普及と適正化
第3・4号事業者の取得企業はまだ多くないため、市場全体として以下が整備される可能性があります。
- SPCスキーム活用時の説明義務強化
- レバレッジ型ファンドのリスク開示明確化
- 運営会社の倒産時対応の標準化
特例事業型のファンドが増えれば、市場全体の安全性向上が期待できます。
投資家が今から取るべき対応
法改正は投資家にとって「より安全に投資できる環境」が整う一方、事業者ごとにルール順守のレベルが分かれやすくなります。以下の点を押さえておくことで、制度変化の影響を最小限に抑えられます。
事業者の許可区分を確認する
不特法の1〜4号、小規模事業、電子取引業務の許可状況は、投資家保護の強度に直結します。
- 第3・4号事業者か
- SPCスキームを採用しているか
- 小規模不特法か一般不特法か
許可区分は「リスクの高さ」を判断するもっとも客観的な指標です。
開示資料・運営レポートを必ず精査する
市場の拡大で、投資対象としての“質の差”が以前より大きくなっています。特に確認すべきは以下です。
- 物件情報の透明性
- リスク説明の具体性
- 期中レポートの頻度と内容
- 出資金の分別管理体制
開示内容が曖昧な事業者は、法改正後の規制強化に耐えられない可能性があります。
電子取引業務の運営体制をチェックする
クラウドファンディング特有のリスクは、システム・情報管理の質に大きく左右されます。
- 障害発生時の対応ルール
- 不正アクセス対策
- システム監査の有無
ここが弱い事業者は今後の規制強化で是正を求められる可能性が高く、悪い意味で“法改正の影響を受けやすい”企業ともいえます。
法改正の動向を定期的にウォッチする
行政からの通知、ガイドライン改訂、業界団体の発信などは、投資家保護に直結する重要なシグナルです。半年〜1年に一度は、最新情報を確認する習慣をつけると安心です。

市場が広がるほど制度は細かく整備されていきます。新しいルールは投資家にとって“安全性を高める味方”ですが、その分だけ事業者ごとの力量差も見えやすくなるんです。許可区分や開示情報をしっかり確認するだけで、リスクは確実に減らせますよ
| 順位 | 商品名 | 会社名 | 特徴 | 案件数 | 直近10件平均利回り | 直近10件直近最低利回り | 直近10件直近最高利回り | 直近10件募集割合平均 | 優先劣後方式 | 最低投資金額 | 募集方法 | 組合契約 | 物件の種類 | 優遇サービスあり | 物件の開示情報 | 出金手数料 | 運用レポートの共有あり | 運営会社設立年月 | 運営会社資本金 | 上場 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | COZUCHI(コズチ) | LAETOLI株式会社 | 投資募集のチャンスは業界上位。投資デビューに適した候補 | 139件 | 6.05% | 4.00% | 10.00% | 336.41% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 月1回まで無料(それ以降は330円) | ○ | 1999年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 2位 | CREAL(クリアル) | クリアル株式会社 | 募集口数が多く、新規案件の供給量も豊富 | 139件 | 5.67% | 5.00% | 6.50% | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス、保育所、学校、宿泊施設 | ○ | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 105円(楽天銀行の場合)、150円(楽天銀行以外で3万円未満の場合)、229円(楽天銀行以外で3万円以上の場合) | ○ | 2011年 | 1,273,520,500円 | ○ | 公式サイト |
| 3位 | 利回りくん | 株式会社シーラ | 年間新規案件数が安定。募集口数も一定水準 | 148件 | 4.26% | 3.00% | 5.12% | 76.70% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2010年 | 446,522,660円 | ○ | 公式サイト |
| 4位 | Rimple(リンプル) | プロパティエージェント株式会社 | 新規案件が充実。劣後出資割合の高い案件が多い | 112件 | 2.76% | 2.70% | 3.30% | 277.80% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、事業内容 | 無料 | ○ | 2004年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 5位 | TECROWD(テクラウド) | TECRA株式会社 | 新興国不動産への投資が可能。高利回り案件が多い | 90件 | 10.90% | 9.50% | 12.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、オフィス | ○ | 住所、運営会社、財務情報、面積、事業内容 | 無料(楽天銀行)、振込手数料(楽天銀行以外) | ○ | 2001年 | 156,600,000円 | × | 公式サイト |
| 6位 | TSON FUNDING(ティーソン) | 株式会社TSON | 年間案件数が最多クラス。リスク軽減案件も豊富 | 230件 | 5.81% | 5.50% | 6.00% | 96.30% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、事業内容 | 無料(匿名組合ファンド)、振込手数料(任意組合ファンド) | ○ | 2008年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 7位 | 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス | 運営会社の信頼性が高く、新規案件も安定供給 | 109件 | 5.90% | 3.50% | 12.00% | 728.48% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛) | ○ | 1996年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 8位 | FUNDROP(ファンドロップ) | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 | 劣後出資割合の高い案件が多いが、投資機会は少なめ | 39件 | 5.75% | 5.50% | 6.00% | 128.54% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 52円(楽天銀行)、150円(他の金融機関で3万円未満)、229円(他の金融機関で3万円以上) | ○ | 2013年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 9位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 穴吹興産株式会社 | 低リスク案件が多いが、投資の機会は限定的 | 43件 | 3.25% | 3.00% | 5.00% | 99.98% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設 | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 1964年 | 755,790,000円 | ○ | 公式サイト |
| 10位 | ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 | 劣後出資割合の高い案件が多く、運営も安定傾向 | 10件 | 4.00% | 3.90% | 4.30% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(その他の金融機関) | ○ | 1991年 | 389,820,000円 | × | 公式サイト |
| 11位 | property+(プロパティプラス) | 株式会社リビングコーポレーション | 募集口数は平均的だが、新規案件がなかった点が課題 | 34件 | 3.20% | 3.00% | 3.40% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2015年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 12位 | ASSECLI(アセクリ) | 株式会社エボルゾーン | 高利回り案件が多いが、新規提供数は限られる | 45件 | - | 0.00% | 0.00% | 105.85% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 事業内容 | 無料 | × | 2011年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 13位 | LIFULL(ライフル) | 株式会社LIFULL | 大手不動産会社のクラウドファンディング。厳選された物件 | 3件 | 5.83% | 5.50% | 6.00% | 105.67% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション・グループホーム | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | × | 1997年 | 9,723,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 14位 | みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント | 」「公的年金に合わせた2ヵ月ごとの分配金」が特徴の、不動産クラウドファンディング | 151件 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、物件種別、アクセス、構造、総戸数、家賃保証有無 | PayPay銀行への払い戻し:無料、PayPay銀行以外への払い戻し:145円 | × | 2016年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 15位 | 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス | 高水準の利回り案件が豊富で、投資のチャンスも平均以上 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行あて) | ○ | 2023年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 16位 | らくたま | 株式会社日本保証 | リスクを抑えつつ高いリターンを狙える案件が多く、供給数も充実 | - | - | - | - | - | ○ | 10000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、商業施設、オフィス | ○ | 築年数、住所、面積 | 無料(GMOあおぞらネット銀行) | × | 2008年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 17位 | GALA FUNDING(ガーラ ファンディング) | 株式会社FJネクストホールディングス | 運営基盤が堅実で、劣後出資割合が高めの安心感ある案件が中心 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛て) | ○ | 1980年 | 2,774,400,000円 | ○ | 公式サイト |
| 18位 | トモタク | 株式会社イーダブルジー | 新規募集数は業界トップクラスで、高利回り案件が目立つ | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、オフィス | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 1回のみ無料(125円(GMOあおぞらネット銀行)、250円(GMOあおぞらネット銀行以外)) | ○ | 2009年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 19位 | LSEED(エルシード) | 株式会社LSEED | リスクとリターンのバランスは良好だが、案件数はやや少なめ | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、面積、事業内容 | 不明 | × | 1999年 | 706,139,500円 | ○ | 公式サイト |
| 20位 | トーセイ不動産クラウド | トーセイ株式会社 | 1万口超の大型案件が主体で、年間の提供数は限定的 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、129円(その他金融機関) | ○ | 1950年 | 6,624,890,000円 | ○ | 公式サイト |
| 21位 | KORYO Funding(コウリョウ ファンディング) | 株式会社興陵 | 安定したバランス型案件が揃う一方で、全体の件数は少ない | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容 | 無料 | × | 1981年 | 371,980,200円 | ○ | 公式サイト |