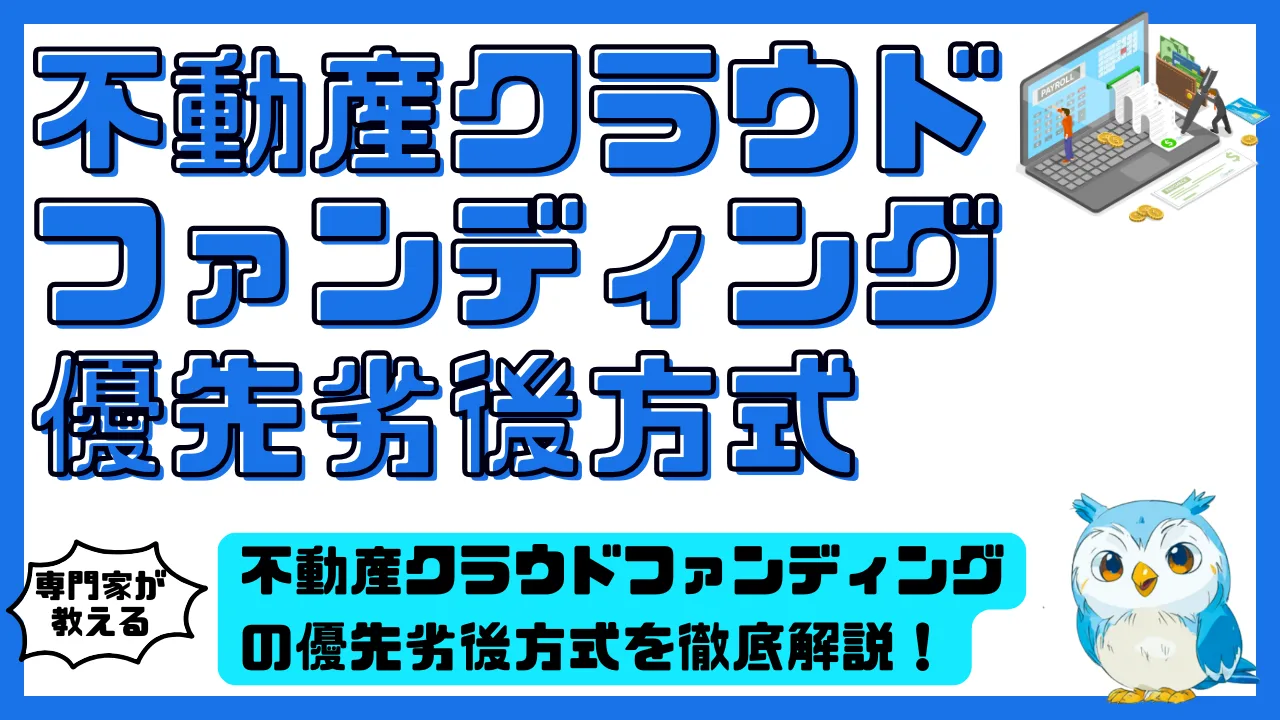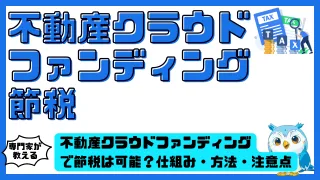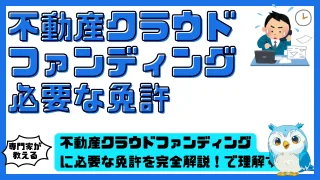本ページはプロモーションが含まれています。
目次
不動産クラウドファンディングとは?少額投資で不動産収益を得る仕組み
不動産クラウドファンディングとは、インターネットを通じて複数の投資家から少額の資金を集め、不動産の取得・運用・売却による収益を分配する仕組みです。従来の不動産投資のように数千万円単位の資金を用意する必要がなく、1万円前後の少額から参加できるのが最大の特徴です。これにより、初心者でも手軽に不動産投資のリターンを得る機会が広がりました。
不動産クラウドファンディングの運営主体は「不動産特定共同事業法(不特法)」に基づき、国や都道府県から許可を受けた事業者です。これらの事業者が投資家から集めた資金をもとに物件を購入し、賃貸や売却による利益を「分配金」として投資家に還元します。運用や管理はすべて事業者が代行するため、投資家は物件管理や契約手続きの手間を負うことなく、不動産収益を得られる点も魅力です。
不動産クラウドファンディングの基本的な仕組み
- 資金の募集
運営会社が投資案件を公開し、インターネット上で複数の投資家から出資を募ります。出資額は1万円や5万円などの小口単位が一般的です。 - 不動産の取得・運用
集まった資金で事業者が不動産を取得し、賃貸運用またはリノベーション後の販売などを行います。投資家は運営状況を専用サイトで確認できます。 - 収益の分配・償還
賃貸収入や売却益などの運用成果は「分配金」として投資家に支払われます。運用期間終了時には出資金(元本)が返還されます。
少額から始められる理由
クラウドファンディング型の仕組みを採用することで、多数の投資家が資金を出し合い、一つの不動産を共同で所有・運用することが可能になりました。これにより、従来のような高額な初期費用やローン審査のハードルがなくなり、資産運用の間口が大きく広がっています。特に副業や分散投資の一環として注目されています。
安心感を支える法的な仕組み
不動産クラウドファンディング事業者は「不動産特定共同事業法」によって、財務基準・業務管理体制・情報開示などの厳しい条件をクリアする必要があります。許可を受けた事業者のみが投資案件を提供できるため、無登録業者によるトラブルのリスクも抑えられています。また、投資家資金の分別管理や第三者による監査なども義務化されており、信頼性の高い仕組みとして整備されています。
投資家にとっての魅力
- 少額から始められるハードルの低さ
- 運営や管理をプロに任せられる手軽さ
- 複数ファンドへの分散投資が容易
- 不特法による一定の安全性・透明性
このように、不動産クラウドファンディングは「少額・分散・省労力」を実現した新しい不動産投資スタイルです。特に、実物資産への投資でありながらオンライン完結で参加できる点が、従来型の金融商品との差別化要因となっています。

不動産クラウドファンディングは、手軽さと透明性の両立が魅力です。実物不動産に裏付けられた安定収益を少額から得られる点を理解すれば、投資戦略の幅が一気に広がりますよ
優先劣後方式とは?投資家を守るリスク低減の仕組み
不動産クラウドファンディングで最も重要な仕組みの一つが「優先劣後方式」です。これは、ファンドの中で投資家と運営事業者の出資を分け、損失が出た際にどちらが先に負担するかを明確にすることで、投資家の元本リスクを軽減する仕組みです。多くの不動産クラウドファンディングが採用しており、投資家を守る安全装置として機能しています。
優先出資と劣後出資の基本構造
ファンドでは一般投資家の出資分を「優先出資」、運営事業者の出資分を「劣後出資」として区分します。
運用益の分配や元本償還の順番は、名前の通り「優先出資」から行われます。反対に、損失が発生した場合は「劣後出資」が先に損失を負担します。
つまり、
- 優先出資者(投資家)=利益を優先的に受け取る権利を持つ
- 劣後出資者(事業者)=損失を先に引き受けるリスクを負う
この二層構造によって、投資家は事業者よりも保護された立場で投資を行うことができるのです。
仕組みの具体的なイメージ
たとえば、総額1億円のファンドが「優先出資80%」「劣後出資20%」の割合で構成されている場合、投資家が8,000万円、事業者が2,000万円を出資します。
もし運用中に2,000万円の損失が発生したとしても、その損失はまず事業者の劣後出資分から補填されます。したがって、損失が劣後出資分に収まる限り、投資家の出資元本は守られる仕組みです。
一方で、損失が3,000万円に膨らんだ場合には、事業者の2,000万円に加えて残りの1,000万円が投資家の出資から差し引かれることになります。
このように、劣後出資の割合が投資家のリスク軽減のクッションとして機能しているのです。
優先劣後方式が投資家を守る理由
優先劣後方式の最大の目的は「損失吸収構造の明確化」にあります。運用中に不動産の評価額が下がったり、空室が増えたりして収益が減少しても、まずは事業者側の出資で損失をカバーします。これにより、投資家の元本毀損リスクを一定範囲で抑えることが可能になります。
また、運用がうまくいった場合でも、分配金や償還金の支払いは投資家が優先されるため、利益確保の安定性も高まります。
この仕組みは「投資家第一の保護構造」として、不動産クラウドファンディングを安心して始められる要因の一つになっています。
投資家と事業者の関係性が健全になる仕組み
優先劣後方式は単に投資家を守るだけでなく、事業者にも健全なインセンティブを生み出します。
事業者自身が劣後出資をしてリスクを負うため、運用成績が悪化すると自らの資金が失われます。
この「セイムボート効果(同じ船に乗る)」により、事業者は投資家と同じ方向を向き、慎重かつ誠実な運用を行う動機づけが強化されます。
結果として、
- 投資家はリスクを軽減しながら安定収益を目指せる
- 事業者は成果を出すことで自社の信頼とリターンを得られる
という、双方にとって合理的な関係が成立します。

投資家を守りながら事業者にも責任を持たせるのが、優先劣後方式の本質です。仕組みを理解しておくことで、安心してリスクを見極めた投資判断ができるようになりますよ
優先出資と劣後出資の違いを図解で理解
不動産クラウドファンディングの仕組みを理解するうえで、最も重要なのが「優先出資」と「劣後出資」の違いです。両者は投資の立場・リスク・リターンの配分方法がまったく異なります。ここでは、図解イメージを交えて整理していきます。
優先出資とは(投資家側の資金)
優先出資とは、一般投資家が出資する部分を指します。
特徴は「リスクを抑えつつ安定したリターンを得る」ことにあります。
- 投資家は利益や元本の返還を優先的に受け取れる立場
- 損失が発生した場合はまず事業者側(劣後出資)が先に負担
- 安定収益を狙う投資家向けの低リスク構造
つまり、ファンド運用で利益が出た場合、優先出資者は決められた利回りに基づいて先に分配金を受け取ります。
一方、損失が出た場合でも、一定の範囲内なら事業者の出資部分で吸収されるため、投資家の元本が守られる仕組みになっています。
劣後出資とは(事業者側の資金)
劣後出資とは、ファンドを運営する事業者が自ら資金を投じる部分を指します。
この出資は「投資家を守るクッション」のような役割を果たします。
- 損失が出た場合に先に負担するリスク側の資金
- 優先出資者の利益・元本返還を守る防波堤となる
- その分リスクが高く、成功時はより大きなリターンを得られる構造
事業者が自ら資金を投じることで「自社も損をする可能性がある」という責任が生まれ、
投資家と事業者が同じ方向(利益最大化)を目指す「セイムボート効果」が働きます。
優先出資と劣後出資の関係を図でイメージ
たとえば、1億円の不動産プロジェクトで「優先出資80%・劣後出資20%」の構成の場合を考えてみましょう。
[luft-comment-in]出資構造イメージ[luft-comment-out]
┌────────────────────────┐
│ 優先出資(投資家) 8,000万円 ─── 優先的に利益分配・償還 │
│ 劣後出資(事業者) 2,000万円 ─── 損失をまず負担 │
└────────────────────────┘このケースで、仮に1,500万円の損失が出た場合はどうなるでしょうか。
- まず劣後出資2,000万円の中から損失を補填
- 損失1,500万円はすべて事業者の劣後出資でカバー
- 優先出資者(投資家)の8,000万円は元本割れしない
一方、もし3,000万円の損失が出た場合、
劣後出資2,000万円を超える残り1,000万円が優先出資者の損失になります。
優先出資・劣後出資の比較表
| 比較項目 | 優先出資(投資家) | 劣後出資(事業者) |
|---|---|---|
| 出資の主体 | 一般投資家 | 運営事業者 |
| 損失負担の順番 | 後(守られる側) | 先(リスクを負う側) |
| 分配・償還の順序 | 優先的に受け取る | 後回しになる |
| リスク水準 | 低い | 高い |
| 期待リターン | 安定・控えめ | 高リスク高リターン |
| 主な役割 | 投資家の資金提供 | 投資家保護と責任共有 |
なぜこの仕組みが重要なのか
優先出資と劣後出資の関係は、投資家保護の根幹を支えています。
この二層構造があることで、リスクの所在が明確になり、投資家が安心して資金を預けられる環境が整います。
同時に、事業者も損失を負う立場になるため、運用に対して高いモチベーションと透明性が求められます。

リスクを事業者と分け合う構造があるからこそ、投資家は安心して投資できるんです。優先と劣後の関係を理解すれば、「守られる仕組み」がイメージしやすくなりますよ
優先劣後比率の目安と投資判断のポイント
不動産クラウドファンディングでは、投資家のリスクを抑えるために「優先出資」と「劣後出資」の割合(優先劣後比率)が設定されています。この比率は、投資家の元本がどの程度守られるかを判断する重要な指標です。
一般的な優先劣後比率の目安
多くの不動産クラウドファンディングでは、
- 優先8:劣後2(80:20)
- 優先7:劣後3(70:30)
が一般的な構成です。
この比率は、投資家(優先出資者)と事業者(劣後出資者)がどの程度リスクを分担するかを表しています。劣後出資が多いほど、事業者がリスクを多く負う仕組みになります。
たとえば、総額1億円のファンドで劣後出資が20%(2,000万円)の場合、不動産の売却損が2,000万円までなら投資家の元本は減りません。損失がそれを超えると、初めて投資家の資金に影響が出ます。
劣後出資比率が高いファンドの特徴
劣後出資比率が高いファンドは、投資家にとって以下のような安心感があります。
- 損失クッションが厚く、元本割れリスクが低い
- 事業者も多額の資金を負担しており、運用責任が重い
- リスクとリターンのバランスが明確
一方で、事業者が多くの資金を出資している分、投資家が出資できる枠が少なくなり、人気案件では募集がすぐ終了する傾向もあります。
劣後出資比率が低いファンドのリスク
劣後出資比率が低い場合(10%以下など)、投資家が負うリスクは高くなります。
- 不動産価格がわずかに下落しただけでも、元本割れが発生する可能性がある
- 事業者側の「セイムボート」意識(共にリスクを取る姿勢)が弱くなりがち
そのため、利回りだけで判断せず、劣後出資割合がどの程度リスクを吸収できるかを確認することが大切です。
投資判断時にチェックすべき3つのポイント
投資家が優先劣後比率を見る際には、以下の3点を意識するとよいでしょう。
- ① 劣後出資割合の具体的数値を確認する
→ ファンド情報に「劣後出資20%」「運営会社出資額〇万円」などの記載があります。 - ② 劣後出資者の属性を確認する
→ 運営会社自身が出資しているか、関連会社や別法人が出資しているかで信頼度が変わります。 - ③ 想定損失のシナリオを確認する
→ ファンドページにある「下落シミュレーション」や「価格下落時の影響」をチェックし、劣後出資でどの程度カバーできるかを把握します。
比率だけでなく運営会社の姿勢も重要
劣後比率が高くても、運営会社が過去に損失時の補填を適切に行っていない場合や、情報開示が不十分な場合には注意が必要です。
信頼できる運営会社は、劣後出資比率の明示・運用状況の透明性・過去実績の開示を徹底しています。
特に、損失が発生した場合の対応履歴(どこまで劣後出資で補填されたか)を確認することは、リスク管理上きわめて有効です。
投資リスクとリターンのバランスを見極める
劣後出資比率が高いファンドは、投資家の元本保全性が高まる一方で、利回りが低めに設定される傾向があります。
逆に、劣後出資が少ないファンドは高利回りを提示することもありますが、その分リスクも高まります。
安定重視なら「劣後20%以上・利回り4〜6%」、
リターン重視なら「劣後10〜15%・利回り6〜8%」など、目的に合わせた選択がポイントです。

劣後出資比率の高低は「安全性と収益性のバランス」をどう取るかという判断軸です。ファンドの構造を理解したうえで、自分のリスク許容度に合った案件を選びましょう
優先劣後方式の3大メリット
1. 元本割れしにくい構造でリスクを抑えられる
優先劣後方式の最大の特徴は、損失が出た際に事業者側(劣後出資者)が先に損失を負担する仕組みです。
たとえば不動産価格が下落しても、まずは劣後出資分で損失を吸収するため、投資家(優先出資者)の資金が守られる可能性が高くなります。
これは、投資家にとって「元本割れの起こりにくい仕組み」を意味します。
一般的なファンドでは「優先8:劣後2」や「優先7:劣後3」といった比率が採用されており、劣後出資比率が高いほどリスククッションが厚くなります。
投資家は、不動産クラウドファンディングにおいて最大のリスクである「元本毀損」を防ぐために、この劣後割合の大きさをひとつの安心材料として確認しておくことが重要です。
2. 分配金の安定性が高い
不動産クラウドファンディングでは、運用中に空室が発生したり、修繕コストが想定以上にかかったりすると、分配金が減ることがあります。
しかし、優先劣後方式では優先出資者が利益分配を優先して受け取る権利を持つため、たとえ収益が想定より低くても、分配金が安定しやすい傾向があります。
また、償還時(運用終了時)も同様に、優先出資者から先に元本が返還される仕組みです。
これにより、「運用益が予想を下回っても、分配と元本返還が優先される」という安心感を得られます。
長期的に安定した収益を求める投資家にとって、優先劣後方式は大きな魅力となります。
3. 事業者との利害一致「セイムボート効果」
優先劣後方式では、事業者自身も劣後出資として資金を投じている点が特徴です。
つまり、事業者にとっても損失が出れば自らの出資金が減るため、「投資家の資金を守ること=自社の損失を防ぐこと」になります。
この構造により、事業者と投資家が同じ船に乗る(セイムボート)関係となり、双方の利益が一致します。
この利害の共有は、事業者に対してより慎重で健全な運用を促す効果があります。
また、リスクを取る一方で高い透明性が求められるため、結果的に投資家側にも信頼性の高い運用環境が整うことになります。

こうして見ると、優先劣後方式は「守りながら増やす」投資モデルなんです。元本の保全・分配の安定・事業者との信頼関係、この3つがそろうことで、不動産クラウドファンディングをより安心して活用できるようになりますよ
優先劣後方式の注意点とリスク理解
不動産クラウドファンディングの「優先劣後方式」は、投資家の元本リスクを抑える優れた仕組みとして注目されていますが、誤解や過信は禁物です。仕組みを正しく理解していないと、想定外の損失や期待外れのリターンに直面する可能性があります。ここでは、投資家が押さえておくべき主な注意点とリスクを整理します。
元本保証ではないことを理解する
優先劣後方式は「リスクを軽減する仕組み」であり、「リスクをなくす仕組み」ではありません。劣後出資者(事業者)の出資分が損失を一定額までカバーしますが、それを超える損失が発生した場合、投資家の優先出資も減額されます。
不動産価格の急落や天災・地政学的リスクなど、市場全体を揺るがす事象では、優先出資であっても元本割れの可能性があります。
劣後出資比率の低いファンドはリスクが高い
一般的な優先劣後比率は「優先8:劣後2」や「優先7:劣後3」とされています。
この比率が小さいほど、劣後出資者の損失吸収余力は減り、投資家のリスクが高まります。
つまり、表面上の利回りだけで判断するのではなく、以下のような項目を確認することが重要です。
- 劣後出資割合(何%まで損失をカバーするのか)
- 運営会社の自己資本比率や財務健全性
- 同社が過去に運用したファンドでの損失発生状況
特に「劣後出資割合が10%未満」の案件では、軽微な下落でも元本割れに直結するリスクがあるため注意が必要です。
ファンドごとの運用スキーム差に注意
同じ「優先劣後方式」でも、ファンドによって設計は異なります。
例えば、賃貸型(インカム型)ファンドでは家賃収入を重視しますが、売却型(キャピタル型)では市況変動が利益に直結します。
後者は売却価格のブレが大きく、損失が劣後出資額を超える可能性もあります。
運用対象がどのタイプか、どのリスクが支配的かを把握しておくことが、安定した投資判断につながります。
分配金・償還時期の遅延リスク
不動産クラウドファンディングは実物資産に紐づくため、工期遅延や販売不振などにより、予定通りの分配や償還が行われないケースがあります。
「優先出資だから確実に利回りが得られる」と考えるのは誤りであり、分配遅延・元本償還の延期も発生しうる点を理解しておくべきです。
特にプロジェクト型(開発系)のファンドは、完工リスク・販売リスクが複合的に影響することが多いため、スケジュールや運営会社の報告体制も確認しましょう。
人気ファンドほど投資枠の競争率が高い
優先劣後方式は投資家保護の仕組みとして人気が高いため、劣後比率が高く安全性の高い案件ほど募集開始直後に枠が埋まりやすい傾向があります。
投資チャンスを逃さないためには、事前登録やファンド募集の通知設定などを活用して、タイミングを逃さない体制を整えておくことも重要です。
投資家が確認すべきポイントまとめ
- 優先劣後比率(劣後割合がどの程度あるか)
- 不動産の種類(賃貸型か売却型か)
- 想定利回りの根拠と運用期間
- 運営会社の実績・信頼性
- 契約成立前交付書面などのリスク開示内容
これらを確認することで、数字の表面だけでは見えない「リスクの質」を判断できるようになります。

優先劣後方式は安心材料ではありますが、過信は禁物です。どんな仕組みでも“どこまで守られるか”を自分の目で確かめることが、投資家としてのリスク管理の第一歩ですよ
事例で見る優先劣後の働き方
不動産クラウドファンディングの仕組みを理解するうえで、実際の「優先劣後方式」がどのように機能するのかを事例で見ることは非常に有効です。ここでは、都市型マンションの開発案件を例に、価格変動や収益結果に応じて投資家と事業者の出資がどのように影響を受けるのかを具体的に確認していきます。
事例:都市型マンション開発ファンドのケース
東京都心の中古マンションを1億円で取得し、1,000万円をかけてリノベーションを実施。再販価格1億円以上を目指す12カ月運用のファンドを想定します。
資金構成は「優先出資:8,000万円(投資家)」と「劣後出資:2,000万円(事業者)」です。想定利回りは年5%とします。
ケース1:想定以上に売却できた場合(1億1,000万円で売却)
市場環境やリノベ効果が奏功し、売却益は1,000万円となりました。
利益配分は以下の通りです。
- 優先出資者:想定利回り5%分の400万円が分配され、出資金8,000万円も全額償還。
- 劣後出資者:残りの利益600万円を受け取り、出資金2,000万円も返還されます。
このケースでは投資家は予定通りのリターンを確保し、事業者もリターンを得られる理想的な結果です。
ケース2:やや低価格で売却(1億400万円で売却)
思ったほど高く売れず、利益は400万円に留まりました。
- 優先出資者:想定利回り分(400万円)を優先的に受け取り、元本8,000万円も全額返還。
- 劣後出資者:利益を優先出資者の分配で使い切るため、分配はなし。ただし出資金2,000万円は返還されます。
投資家にとっては安定した収益を維持できる一方、事業者は配当を受け取れない結果となります。事業者の劣後出資が「リスクの緩衝材」として働いた好例です。
ケース3:損失が発生(8,500万円で売却)
不動産市況の悪化などで1,500万円の損失が出た場合のシナリオです。
- 優先出資者:投資家資金8,000万円は優先的に償還され、元本割れは発生しません。
- 劣後出資者:残りの500万円が返還され、出資金の一部を失います。
損失分は劣後出資によって全額吸収され、投資家の元本は守られます。まさに「優先劣後方式」がリスクを肩代わりする典型的なパターンです。
事例からわかる3つのポイント
- 投資家保護の仕組みが明確に働く
劣後出資が一定割合あることで、損失時も投資家の元本を保護するクッションとして機能します。 - 事業者の責任とインセンティブが高まる
自らの出資をリスクにさらすことで、事業者は安易な運用を避け、慎重かつ積極的なプロジェクト管理を行う動機が生まれます。 - 安定収益とリスクバランスの両立が可能
投資家は高利回りを狙うよりも、安定的な分配を重視できる点が特徴です。劣後出資の割合が高いほど安全性も高まります。
投資家が注目すべき実務ポイント
- ファンド概要に記載されている「優先劣後比率」を確認する
- 劣後出資比率が高いほど投資家保護の効果が強い
- 想定利回りだけでなく、事業者の出資姿勢や実績もリスク評価の指標となる

こうした実例を見ると、優先劣後方式が単なる理論ではなく、実際に投資家の資金を守る“防波堤”として機能していることがよくわかりますね。投資判断の際は、数字だけでなく、こうした構造的なリスク吸収メカニズムにも注目していきましょう
投資家が見るべきチェックリストと活用法
不動産クラウドファンディングの優先劣後方式を理解したうえで、実際のファンド選びや運用判断に活かすための実践的なチェック項目とその使い方を解説します。投資家がリスクを見抜き、安定運用につなげるための要点を整理します。
チェックすべき主要項目と注目ポイント
以下の観点を意識すると、ファンド間の比較精度が高まり、リスクとリターンのバランスを見極めやすくなります。
| 項目 | 着眼点 | 投資家が見るべき理由 |
|---|---|---|
| 優先/劣後比率 | 優先と劣後の比率(例:80:20、70:30)を確認し、適正範囲か判断する | 劣後比率が高いほど、事業者が損失を先に負担するため、投資家のリスクが軽減される |
| 劣後出資金の条件 | 劣後出資の返還順序・制約などを確認 | 劣後出資金が単なる形式出資ではなく、実際に損失補填の機能を果たすかを見極める |
| 運営会社の信用力 | 過去の運用実績・財務基盤・許可番号を確認 | 劣後出資を実行し続けられる資金力・誠実性があるかが重要 |
| 利回り・分配シミュレーション | 想定利回りだけでなく、空室や価格下落時の想定も確認 | 表面利回りに惑わされず、最悪シナリオでも元本が守られるかを把握する |
| 担保・保証・保険の有無 | 不動産担保や保険が設定されているかを確認 | 優先劣後に加えて、損失リスクを多層的に抑える構造かどうかを判断できる |
| 手数料・コスト構造 | 運用報酬・成功報酬・売却費用を確認 | 手数料が高いと実質利回りが下がり、優先出資者のリターンが圧迫される |
| 契約書・開示内容 | 契約成立前交付書面や募集要項の記載精度 | 優先劣後方式の定義や条件が明確でない案件は避けるべき |
| 出口戦略・流動性 | 売却時期・市場性・再販戦略の説明があるか確認 | 途中解約ができない投資のため、出口設計の透明性は極めて重要 |
チェックリストの活用ステップ
- ファンドごとの優先劣後比率を一覧化
Excelやスプレッドシートに比率・劣後金額・事業者名を並べて比較します。複数のサービスを横断的に見れば、平均的な劣後比率や利回り水準が見えてきます。 - 「信頼性×リスク軽減」のマトリクスで評価
信頼性(事業者・運用実績)とリスク軽減度(劣後比率・担保など)を2軸にマッピングすることで、自分に合ったリスク水準の案件を視覚的に把握できます。 - シミュレーションの「想定外」に注目
想定利回りだけでなく、価格下落10%・空室20%などの条件下での損失額を確認します。事業者がシナリオ分析を公開していない場合、その透明性にも疑問を持つべきです。 - 複数ファンドによる分散効果を計算
劣後比率が高い案件だけに集中せず、地域・物件タイプ・運用期間を分散させることでリスクを平均化します。優先劣後方式でも過度な集中投資は避けましょう。 - 募集要項の更新頻度と修正履歴を確認
劣後出資比率や運用方針が途中で変更される場合があります。募集要項の履歴や開示頻度から、情報の信頼性・管理体制をチェックします。
投資判断に役立つ比較の軸
チェックリストを整理する際は、以下の比較軸を意識すると客観的な評価がしやすくなります。
- 「劣後出資割合」>「想定利回り」
高い利回りよりも、高い劣後比率を優先するほうがリスク調整後リターンは安定しやすいです。 - 「運営実績」>「物件立地」
運営の透明性・実績は、短期的な地価よりもファンド成功率に直結します。 - 「手数料の明示性」>「キャンペーン特典」
初回特典などに惑わされず、運用報酬の内訳を必ず確認します。
活用のポイント
チェックリストは「安心できる投資先」を選ぶための防波堤です。
優先劣後比率や運営実績は数値で比べやすいですが、本質は「リスクの所在がどこにあるか」を把握することです。
数字の裏側にある運営姿勢・透明性まで踏み込んで確認することで、安定したリターンにつながります。

リストを形式的に埋めるだけじゃなく、なぜその条件があるのかを考えて選ぶと、投資判断の精度が一段上がりますよ
| 順位 | 商品名 | 会社名 | 特徴 | 案件数 | 直近10件平均利回り | 直近10件直近最低利回り | 直近10件直近最高利回り | 直近10件募集割合平均 | 優先劣後方式 | 最低投資金額 | 募集方法 | 組合契約 | 物件の種類 | 優遇サービスあり | 物件の開示情報 | 出金手数料 | 運用レポートの共有あり | 運営会社設立年月 | 運営会社資本金 | 上場 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | COZUCHI(コズチ) | LAETOLI株式会社 | 投資募集のチャンスは業界上位。投資デビューに適した候補 | 139件 | 5.75% | 4.00% | 6.50% | 337.36% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 月1回まで無料(それ以降は330円) | ○ | 1999年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 2位 | CREAL(クリアル) | クリアル株式会社 | 募集口数が多く、新規案件の供給量も豊富 | 139件 | 5.13% | 0.00% | 6.50% | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス、保育所、学校、宿泊施設 | ○ | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 105円(楽天銀行の場合)、150円(楽天銀行以外で3万円未満の場合)、229円(楽天銀行以外で3万円以上の場合) | ○ | 2011年 | 1,273,520,500円 | ○ | 公式サイト |
| 3位 | 利回りくん | 株式会社シーラ | 年間新規案件数が安定。募集口数も一定水準 | 148件 | 4.71% | 3.00% | 6.00% | 89.80% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2010年 | 446,522,660円 | ○ | 公式サイト |
| 4位 | Rimple(リンプル) | プロパティエージェント株式会社 | 新規案件が充実。劣後出資割合の高い案件が多い | 112件 | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 270.75% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、事業内容 | 無料 | ○ | 2004年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 5位 | TECROWD(テクラウド) | TECRA株式会社 | 新興国不動産への投資が可能。高利回り案件が多い | 90件 | 10.40% | 8.50% | 12.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、オフィス | ○ | 住所、運営会社、財務情報、面積、事業内容 | 無料(楽天銀行)、振込手数料(楽天銀行以外) | ○ | 2001年 | 156,600,000円 | × | 公式サイト |
| 6位 | TSON FUNDING(ティーソン) | 株式会社TSON | 年間案件数が最多クラス。リスク軽減案件も豊富 | 230件 | 5.64% | 5.50% | 5.80% | 98.90% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、事業内容 | 無料(匿名組合ファンド)、振込手数料(任意組合ファンド) | ○ | 2008年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 7位 | 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス | 運営会社の信頼性が高く、新規案件も安定供給 | 109件 | 5.90% | 3.50% | 12.00% | 728.48% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛) | ○ | 1996年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 8位 | FUNDROP(ファンドロップ) | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 | 劣後出資割合の高い案件が多いが、投資機会は少なめ | 39件 | 5.66% | 5.50% | 5.80% | 119.09% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 52円(楽天銀行)、150円(他の金融機関で3万円未満)、229円(他の金融機関で3万円以上) | ○ | 2013年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 9位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 穴吹興産株式会社 | 低リスク案件が多いが、投資の機会は限定的 | 43件 | 3.25% | 3.00% | 5.00% | 99.98% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設 | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 1964年 | 755,790,000円 | ○ | 公式サイト |
| 10位 | ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 | 劣後出資割合の高い案件が多く、運営も安定傾向 | 10件 | 4.00% | 3.90% | 4.30% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(その他の金融機関) | ○ | 1991年 | 389,820,000円 | × | 公式サイト |
| 11位 | property+(プロパティプラス) | 株式会社リビングコーポレーション | 募集口数は平均的だが、新規案件がなかった点が課題 | 34件 | 3.20% | 3.00% | 3.40% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2015年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 12位 | ASSECLI(アセクリ) | 株式会社エボルゾーン | 高利回り案件が多いが、新規提供数は限られる | 45件 | - | 0.00% | 0.00% | 105.85% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 事業内容 | 無料 | × | 2011年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 13位 | LIFULL(ライフル) | 株式会社LIFULL | 大手不動産会社のクラウドファンディング。厳選された物件 | 3件 | 5.83% | 5.50% | 6.00% | 105.67% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション・グループホーム | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | × | 1997年 | 9,723,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 14位 | みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント | 」「公的年金に合わせた2ヵ月ごとの分配金」が特徴の、不動産クラウドファンディング | 290件 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、物件種別、アクセス、構造、総戸数、家賃保証有無 | 無料 | × | 2016年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 15位 | 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス | 高水準の利回り案件が豊富で、投資のチャンスも平均以上 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行あて) | ○ | 2023年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 16位 | らくたま | 株式会社日本保証 | リスクを抑えつつ高いリターンを狙える案件が多く、供給数も充実 | - | - | - | - | - | ○ | 10000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、商業施設、オフィス | ○ | 築年数、住所、面積 | 無料(GMOあおぞらネット銀行) | × | 2008年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 17位 | GALA FUNDING(ガーラ ファンディング) | 株式会社FJネクストホールディングス | 運営基盤が堅実で、劣後出資割合が高めの安心感ある案件が中心 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛て) | ○ | 1980年 | 2,774,400,000円 | ○ | 公式サイト |
| 18位 | トモタク | 株式会社イーダブルジー | 新規募集数は業界トップクラスで、高利回り案件が目立つ | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、オフィス | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 1回のみ無料(125円(GMOあおぞらネット銀行)、250円(GMOあおぞらネット銀行以外)) | ○ | 2009年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 19位 | LSEED(エルシード) | 株式会社LSEED | リスクとリターンのバランスは良好だが、案件数はやや少なめ | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、面積、事業内容 | 不明 | × | 1999年 | 706,139,500円 | ○ | 公式サイト |
| 20位 | トーセイ不動産クラウド | トーセイ株式会社 | 1万口超の大型案件が主体で、年間の提供数は限定的 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、129円(その他金融機関) | ○ | 1950年 | 6,624,890,000円 | ○ | 公式サイト |
| 21位 | KORYO Funding(コウリョウ ファンディング) | 株式会社興陵 | 安定したバランス型案件が揃う一方で、全体の件数は少ない | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容 | 無料 | × | 1981年 | 371,980,200円 | ○ | 公式サイト |