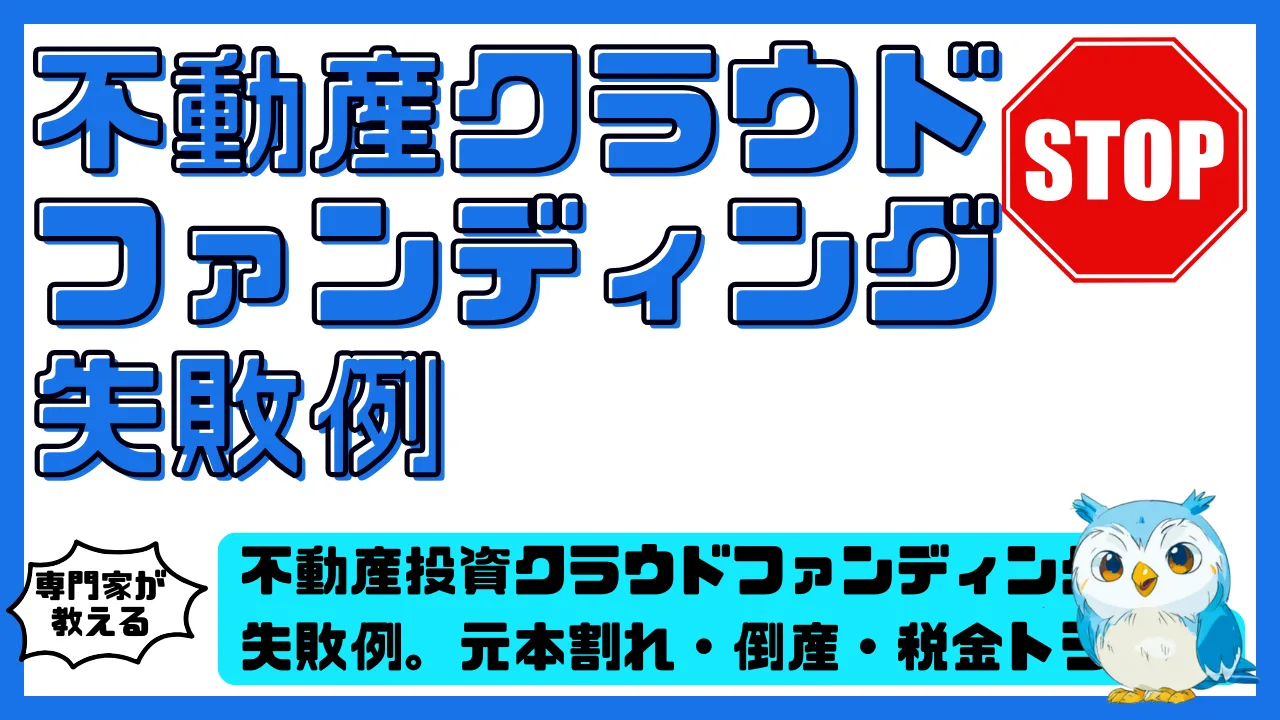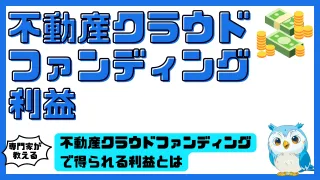本ページはプロモーションが含まれています。
目次
不動産投資クラウドファンディングで起こりやすい主な失敗例
不動産投資クラウドファンディングは少額から始められる手軽さが魅力ですが、実際には「思わぬ失敗」に直面する投資家も少なくありません。特に、仕組みを十分に理解せずに投資を始めた場合、元本割れや資金拘束など、避けられたはずのトラブルに巻き込まれることがあります。ここでは、実際に多く報告されている代表的な失敗例を解説します。
分配金が得られない・元本割れしてしまうケース
不動産クラウドファンディングでは、物件の運用や売却益に応じて分配金が支払われます。しかし、空室の発生や不動産価格の下落により想定通りの収益が得られず、分配金が減額、または支払われない場合があります。
さらに、売却価格が取得価格を下回ると「元本割れ」となり、投資額がそのまま損失になることもあります。特に「高利回り案件」をうたうファンドは、裏を返せばリスクの高い案件であることが多く、安易に飛びつくのは危険です。
事業者の経営破綻・倒産による資金回収不能
どれほど信頼性の高い事業者であっても、経営悪化や倒産リスクはゼロではありません。事業者が倒産した場合、投資家は法的に「匿名組合契約の出資者」という立場になるため、優先的に返金を受けることはできません。
結果として、投資元本がすべて失われる可能性もあります。事業者の財務状況や過去の償還実績を確認し、情報開示が不十分な企業には慎重な姿勢が求められます。
人気案件に申し込めず投資機会を逃すリスク
不動産クラウドファンディングは「先着式」や「抽選式」で募集が行われますが、人気ファンドは数分で満枠となることも珍しくありません。抽選式でも倍率が数十倍になるケースがあり、思うように投資できない状況が続くこともあります。
このような「投資できないリスク」は、複数のプラットフォームに登録し、募集スケジュールを事前に把握しておくことである程度軽減できます。
途中解約ができず資金が拘束されるトラブル
多くの不動産クラウドファンディングでは、運用期間中の途中解約が原則としてできません。運用期間は6カ月〜2年程度が一般的で、その間は資金を動かすことができず、急な出費に対応できないリスクがあります。
また、償還が予定より遅延するケースもあり、資金がさらに長期間ロックされる可能性があります。特に長期運用型のファンドでは、資金繰りに余裕を持つことが大切です。
想定外のトラブルによる運用遅延・償還遅延
建築の遅延、入居率の悪化、自然災害、行政手続きの停滞など、外的要因によって運用スケジュールが狂うこともあります。このような遅延は分配金の支払いにも影響を及ぼし、当初の想定利回りが実現できないこともあります。
特に、再開発地域や観光地など外部要因の影響を受けやすいエリアでは、このリスクが顕著です。
初心者が誤解しやすい心理的な落とし穴
投資初心者ほど、「1万円から投資できる」「利回りが高い」という手軽さや数字に惹かれ、案件の内容を十分に精査せずに投資してしまう傾向があります。特に、広告やSNSでの「成功体験談」をうのみにしてしまうと、事業者のリスク説明を見落とすこともあります。
また、少額投資で安心してしまい、複数案件に分散せず一つの案件に偏ることで損失リスクが集中するケースも見られます。

不動産クラウドファンディングの失敗例を見ると、「手軽さ」と「安全性」は必ずしも両立しないことが分かります。投資家として冷静に仕組みとリスクを理解し、案件選びと資金管理を徹底することが、失敗を防ぐ最初の一歩ですよ
失敗の背景にある仕組み上のリスクを理解する
不動産投資クラウドファンディングは、仕組みを正しく理解せずに参加すると、思わぬ損失を招く可能性があります。表面上は「少額・手軽・安全」と見えますが、実際には制度的な制約や構造的なリスクが複雑に絡み合っています。ここでは、失敗を防ぐために理解しておくべき3つの仕組み上のリスクを整理します。
不動産特定共同事業法がもたらす制約と限界
不動産クラウドファンディングは、「不動産特定共同事業法」に基づいて運営されています。この法律は、投資家を保護する目的で厳格なルールを定めていますが、同時に投資家の自由度を制約する側面もあります。
具体的には、投資家は出資後に途中解約が原則できず、運用期間中は資金がロックされます。また、事業者が倒産した場合でも、投資家は直接物件の権利を持たないため、資産の回収が難しいという構造的な弱点があります。
つまり、法制度が投資家の安全を担保する一方で、「資金の流動性」や「回収リスク」については、依然として投資家が負担する仕組みになっているのです。
匿名組合型と任意組合型の違いによる影響
不動産クラウドファンディングの投資スキームには「匿名組合型」と「任意組合型」の2種類があります。この違いは、税制やリスクの所在に直接影響します。
- 匿名組合型:多くのクラウドファンディングが採用。投資家は出資者でありながら「匿名扱い」となるため、物件に直接的な権利を持ちません。倒産時の資産回収は困難で、損失リスクが高いのが特徴です。
- 任意組合型:COZUCHIなど一部の事業者が採用。投資家が不動産の持分権を一部保有する形式で、法的には不動産所得扱いとなるため、一定の権利主張が可能です。その一方で、税務処理が複雑になり、リスク管理の知識が求められます。
つまり、同じ「クラウドファンディング投資」であっても、組合形態によって投資家の立場や保護の範囲が大きく異なります。匿名組合型を選ぶ場合は「倒産リスク」、任意組合型を選ぶ場合は「税務・契約リスク」を理解しておく必要があります。
利回り重視が引き起こす高リスク構造
高利回りをうたうファンドには、必ず「それに見合うリスク」が潜んでいます。不動産クラウドファンディングでは、利回りが高いほど、以下のような構造的リスクが高まる傾向にあります。
- 開発段階やリノベーションなど、未完成物件への投資が多い
- 地方や需要の不安定なエリアの物件を対象とするケースが多い
- 運営事業者が短期的なリターンを重視し、安定運用より高収益案件を優先する場合がある
このような案件では、空室率の上昇や不動産価格の下落によって、想定利回りを下回るリスクが高くなります。つまり、表面利回りの高さに惑わされるほど、元本割れの可能性を高めてしまうという逆説的な構造です。
リスクを把握するための視点
不動産クラウドファンディングは「不動産投資」と「金融商品投資」の中間的な性質を持つため、両方のリスクを併せ持ちます。失敗を防ぐには、次のような視点を持つことが重要です。
- 法的リスク:事業者倒産時にどこまで資金が保護されるか
- 構造的リスク:組合形式や優先劣後比率による損失負担の違い
- 運用リスク:市場変動や空室率の変化に対する耐性
これらのリスクは「運営会社を信頼する」だけでは回避できません。仕組みそのものを理解したうえで、制度・スキーム・利回りの3点を必ず照合することが求められます。

制度や仕組みを理解せずに投資するのは、地図を持たずに山登りをするようなものです。リスクの構造を把握していれば、トラブルの多くは事前に回避できますよ
実際に起きた不動産投資クラファンの失敗事例
不動産投資クラウドファンディング(クラファン)は、少額から始められる手軽さが魅力ですが、実際には「元本割れ」や「償還遅延」などのトラブルが現実に発生しています。ここでは、実際に投資家を悩ませた代表的な失敗事例をもとに、リスクの実像を掘り下げて解説します。
運用遅延や償還トラブルの実例
もっとも多いのが「運用遅延」や「償還トラブル」です。予定されたスケジュールで物件が売却できず、分配金の支払いが後ろ倒しになるケースが複数の事業者で報告されています。
例えば、商業ビルのバリューアップを目的としたファンドでは、想定よりもテナントの退去・改修が長引き、売却タイミングが半年以上遅延。結果として分配金も後ろ倒しになり、投資家は予定していた利回りを得られませんでした。
このようなケースでは、最終的に元本は償還されたとしても、投資期間中の資金拘束が長期化することで、他の投資チャンスを逃す「機会損失」が発生します。
想定外の空室率上昇による収益低下
住宅系や賃貸マンション型のファンドでは、「空室リスク」による収益悪化が失敗の典型例です。都心部のワンルーム投資で安定した入居率を想定していた案件が、近隣の競合物件増加で想定外の空室が続き、分配金がゼロまたは半減する結果となった事例があります。
運営側の賃料見積もりが楽観的すぎることもあり、実際の入居率が想定を下回ると収益モデルが崩れやすい構造になっています。特に、賃料保証(マスターリース契約)がない案件では、運用成績のブレが直接投資家の分配金に反映されるため注意が必要です。
自然災害や市況悪化による損失
自然災害や経済ショックによる不動産価格の下落も、過去に現実的な損失をもたらした要因です。ある地方リゾートホテルを対象としたファンドでは、コロナ禍で宿泊需要が急減。売却価格が大幅に下落し、元本割れが確定した事例がありました。
また、台風や地震などの自然災害による建物損傷・修繕費発生も、元本圧迫の一因です。こうしたリスクは、立地・用途・保険加入状況などによって影響度が異なりますが、どれも「想定外」ではなく、実際に発生しうるリスクとして把握すべきです。
事業者の経営難・倒産による損失
投資対象そのものではなく、事業者側の経営破綻が引き金となるケースもあります。過去には、不動産クラファン事業を運営する企業が資金繰り悪化で倒産し、投資家が出資金を回収できなかった事例も報告されています。
この場合、ファンドの仕組み上、投資家は「匿名組合契約」であり、破産債権者として優先順位が低く、全額損失となる可能性があります。上場企業や信託分離管理を導入している事業者であればこのリスクは軽減できますが、無登録・無許可業者が介在するケースでは特に危険です。
スキームの不透明さから生じた誤認リスク
一部の事業者では、匿名組合契約や優先劣後比率の説明が不十分なまま募集を行い、投資家が実際のリスクを把握できなかった事例があります。特に「劣後出資10%」と記載されていても、実際の資産評価が甘く、損失発生時に投資家側の負担が想定より大きくなったという報告もあります。
情報開示の透明性が低い事業者では、契約内容と実態が乖離しているケースもあるため、ファンド募集ページの「契約形態」や「リスク分担構造」は必ず精読することが重要です。
信頼性が高いと誤解された有名案件でのトラブル
過去には、有名人や大企業の名前を冠したファンドがSNS上で話題になり、多くの投資家が殺到したケースもありました。しかし実態としては、メディア露出による過信からリスク分析を怠り、結果的に償還遅延・分配停止となった事例もあります。
ブランドイメージやキャンペーン特典ではなく、「運用中の情報開示」「物件の実査」「損益シナリオの現実性」など、投資の本質的な部分に目を向ける姿勢が欠かせません。

現実に起きた失敗を見てわかるのは、「少額投資=低リスク」ではないということです。運用実績・契約形態・情報開示の透明度を見極めることが、最大のリスク対策になります。
初心者が陥りやすい失敗パターンと心理的落とし穴
不動産投資クラウドファンディングは、手軽に始められる魅力から多くの初心者が参入しています。しかし、その「手軽さ」が油断を生み、失敗の温床になることも少なくありません。ここでは、投資初心者が陥りやすい代表的なパターンと、その背景にある心理的な落とし穴を整理します。
高利回りの数字に惹かれてリスクを軽視する
「利回り10%以上」という魅力的な数字に惹かれて、案件の詳細を確認せず投資してしまうケースは非常に多いです。
高利回り案件の多くは、開発段階の物件や地方エリアなど、リスクの高いファンドである場合が多く、安定した収益を得られる保証はありません。
初心者ほど「お得」「高利回り」という言葉に安心感を覚えがちですが、投資はリスクとリターンが比例するものです。利回りだけで判断せず、物件の立地、運用期間、出資比率などを総合的に見極める必要があります。
事業者や物件情報を精査せずに申し込む
不動産クラウドファンディングの運営会社は、不動産特定共同事業の許可を受けているため「どこも信頼できる」と思い込む初心者も多いです。
しかし、過去に元本割れや償還遅延を起こした事業者も存在します。
また、同じ事業者でもファンドごとに劣後出資割合や対象物件のタイプが異なり、リスク水準に差があります。
特に注意すべきは、案件概要の開示が不十分なファンドです。運用レポートや過去の実績、償還履歴がしっかり公表されている事業者を選ぶことが、結果的にリスク回避につながります。
少額投資ゆえの油断と過信
1口1万円から始められるという「少額投資」の安心感が、逆に冷静な判断を鈍らせることもあります。
少額だからといって検証を怠ると、複数の高リスク案件に分散せず投資してしまい、損失が重なってしまうこともあります。
初心者ほど「どうせ1万円だから大丈夫」と考えがちですが、同じような判断を繰り返すことで結果的に大きな損失を生むことがあります。小額投資であっても、必ず「分散」「実績」「リスク」を確認する癖をつけましょう。
成功事例を鵜呑みにしてしまう集団心理
SNSや投資ブログでは、「○万円の利益が出た」「元本割れゼロ」などの成功事例が多く取り上げられます。
しかし、そうした投稿はあくまで一部の成功例であり、全体のリスクを代表するものではありません。
特に初心者は「みんなやっている」「上場企業が関わっているから安心」といった集団心理に流されやすく、自分のリスク許容度を見失いがちです。成功体験ばかりを基準にせず、自分の資金計画と目的に即した投資判断を行うことが重要です。
想定外の事態に動揺して損切りできない
投資後に運用遅延や分配金減少が発生すると、多くの初心者が「また戻るかもしれない」と期待を持ち続け、対応を誤ることがあります。
不動産クラウドファンディングは途中解約が原則できないため、損失を最小限に抑えるには「最初の判断」がすべてです。
事前にリスクシナリオを想定し、「最悪のケースでも許容できる金額」で投資することが、感情に左右されない投資行動を支える唯一の方法といえます。

投資初心者の方は、「利回り」「口コミ」「少額」という表面的な要素だけで判断しないことが大切です。どんなに小さな投資でも、仕組みを理解し、事業者の実績を調べ、分散する習慣を持つことで失敗はぐっと減ります。焦らず冷静に判断するクセをつけましょう。
失敗を未然に防ぐためのリスク対策ポイント
不動産投資クラウドファンディングは手軽に始められる一方で、投資である以上リスクは避けられません。実際に元本割れや遅延が発生した事例もあり、慎重なリスク管理が欠かせます。ここでは、失敗を未然に防ぐために投資家が取るべき具体的な対策ポイントを整理します。
優先劣後出資制度の仕組みを理解して選ぶ
最も基本的なリスク対策が、「優先劣後出資制度」を採用しているファンドを選ぶことです。
この制度では、投資家が「優先出資者」、事業者が「劣後出資者」として共同で出資します。万が一、運用不動産に損失が発生した場合でも、まず劣後出資部分(事業者の負担分)から損失が補填される仕組みです。
劣後出資比率が高いほど、投資家の元本割れリスクは低下します。たとえば「劣後出資30%」であれば、不動産価値が3割下落しても投資家の元本は保全されます。
案件選定の際には、「劣後出資比率」や「損失吸収構造」を必ずチェックしましょう。
運営事業者の信頼性と実績を最重視する
クラウドファンディングの成否は、物件よりも運営事業者の信頼性で左右されます。
実績が浅い事業者や、過去に償還遅延・元本割れを起こした企業には注意が必要です。チェックすべきポイントは以下の通りです。
- 金融庁への登録・「不動産特定共同事業」許可の有無
- 償還実績・元本割れ実績の開示状況
- ファンド募集頻度や運用継続年数
- 代表者・運営会社の財務基盤や上場状況
上場企業や監査体制の整った企業(例:CREAL、Jointo α、COZUCHIなど)は、透明性と継続性の面で安心感があります。特にIR情報を定期的に開示している事業者は信頼度が高い傾向です。
ファンド内容とスケジュールを精査する
ファンドの運用期間や償還スケジュールを軽視すると、資金拘束リスクを見落とします。
不動産クラファンは原則として途中解約ができないため、長期運用ファンドに安易に資金を投じると、急な出費時に対応できません。
事前に確認すべきは以下です。
- 運用期間(短期型か中長期型か)
- 償還日・分配日の明記
- 想定利回りの根拠と過去実績
- 物件所在地・入居率・マスターリース契約の有無
短期ファンドで資金の回転性を確保しながら、安定運用の中長期ファンドを組み合わせるとリスク分散になります。
複数の案件と事業者への分散投資
1つの案件や事業者に資金を集中させることは、損失を拡大させる最大の要因です。
「案件分散」「地域分散」「事業者分散」の3方向からリスクヘッジを行いましょう。
- 案件分散:複数の不動産タイプ(住宅・商業施設・ホテルなど)へ投資
- 地域分散:地方都市・首都圏などエリアの分散
- 事業者分散:複数のクラファンサービスを併用
1口1万円から始められる仕組みを活かし、少額で複数案件に分散すれば、特定案件の不調時にも安定したリターンを維持できます。
想定外リスクに備える「情報モニタリング」
クラファン投資は「投資したら放置」では危険です。
運用レポートやIR更新情報を定期的に確認し、運用状況・市場動向・法改正などを把握することが重要です。また、SNSや専門メディアの口コミ情報からも早期の異変を察知できます。
特にチェックすべきは次のポイントです。
- ファンド運用中の定期レポートの更新頻度
- 配当予定日の遅延や償還延期の発表
- 建物管理状況や修繕報告の透明性
「情報を追う投資家」が最も損を避けられる投資家です。
税務・手数料・現金化計画も含めた総合リスク管理
投資家が見落としがちなのが、税務処理・手数料・現金化タイミングの影響です。
分配金の雑所得課税、源泉徴収済みの申告漏れ、あるいは出金手数料や中途換金手数料が想定外に利益を圧迫するケースがあります。
税務区分(匿名組合型=雑所得、任意組合型=不動産所得)を把握し、年20万円を超える雑所得は確定申告を忘れずに行いましょう。
また、投資資金をどのタイミングで再投資・出金するかの計画を立てることで、キャッシュフローを健全に保つことができます。

リスクを恐れるより、仕組みを理解して味方にすることが大切です。優先劣後制度や分散投資を上手に活用すれば、不動産クラファンは安定収益の柱になり得ます。焦らず、仕組みを見抜く目を養っていきましょう
税務面で起こる「見落とし失敗」とは
不動産投資クラウドファンディングでは、運用実績や利回りだけでなく、税務処理の理解不足が思わぬ「見落とし失敗」につながることがあります。特に少額投資だからと油断してしまうと、確定申告漏れや追徴課税など、利益以上の損失を招くおそれがあります。
確定申告を怠ることで発生するリスク
不動産クラウドファンディングで得た分配金は、一般的に「雑所得」に区分されます。給与所得者であっても、年間の雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
しかし、多くの投資家が「源泉徴収されているから申告不要」と勘違いしてしまいます。これはよくある誤解で、源泉徴収はあくまで“前払い”の性質を持つものであり、他の所得と合算して税額を再計算する必要があるのです。
無申告のまま税務署に指摘されると、最大で15~20%の無申告加算税や延滞税が課される場合があります。特に複数のクラウドファンディングを利用している投資家は、所得合算による課税ライン超過に気づかず、追徴の対象になることが少なくありません。
ファンドの形式によって課税区分が異なる
不動産クラウドファンディングの税務で厄介なのが、「匿名組合型」と「任意組合型」で課税区分が異なる点です。
- 匿名組合型:投資家は営業活動に関与しないため、分配金は「雑所得」として扱われます。
- 任意組合型:投資家が組合員として事業に参加する形式のため、「不動産所得」または「事業所得」として扱われます。
この違いにより、控除の可否や申告書類の種類が変わるだけでなく、損益通算(他の所得と相殺できるかどうか)の可否にも影響します。
匿名組合型は原則として損益通算できませんが、任意組合型では赤字分を他の所得から差し引けるケースもあります。契約時にファンドのタイプを確認せず、税務区分を誤ったまま申告してしまうと、税務署から修正を求められるリスクがあります。投資前に運営会社の説明書や契約約款を確認し、税務上の扱いを理解しておくことが不可欠です。
住民税・副業扱いにも注意が必要
給与所得者が不動産クラウドファンディングで収益を得る場合、「副業所得」として扱われるケースがあります。申告を行わないまま住民税が自動的に加算されると、勤務先に副業収入が伝わる可能性もあります。
副業禁止規定がある会社に勤めている場合は、「普通徴収(自分で納付)」を選択して会社に通知されないようにすることが望ましいでしょう。
また、税務署からの問い合わせがきた際に曖昧な説明をすると、意図的な隠ぺいと判断される場合もあるため、必ず収支の記録を残しておくことが大切です。
税金トラブルを防ぐためのチェックポイント
- 年間の分配金額を一覧で管理し、合計が20万円を超えるかを確認する
- ファンドの契約形態(匿名組合型/任意組合型)を必ず把握する
- 複数事業者で投資している場合は、源泉徴収票を合算して確認する
- 副業扱いとなるケースでは「普通徴収」を選択する
- 税理士またはクラウド会計ソフトを活用して確定申告ミスを防ぐ
税務面での見落としは、利回りや運用実績に関係なく“損”につながります。特に近年は税務署によるデジタル監視体制が強化されており、クラウドファンディング事業者からの報告情報が自動的に紐づくようになっています。軽視せず、早めの対応を心がけましょう。

税金のルールは複雑ですが、事前に仕組みを理解しておけばトラブルは防げます。税務処理を「後回し」にしないことが、実は最も重要なリスク対策なんです。
信頼できる不動産クラウドファンディング事業者の見極め方
不動産投資クラウドファンディングのリスクを最小限に抑えるためには、「どの事業者を選ぶか」が最も重要です。表面的な利回りやキャンペーンだけに目を奪われるのではなく、運営実績・財務基盤・情報公開の姿勢などを総合的に評価する必要があります。
実績と運用履歴を確認する
まず注目すべきは、過去の運用実績とトラブル履歴です。ファンド数や運用金額が多いだけでなく、「元本割れ」「償還遅延」「分配遅延」などの発生有無を確認しましょう。特に複数年にわたり安定的に償還を続けている事業者は信頼度が高いといえます。
また、ファンド運用期間が短期から中長期まで幅広く展開されているかも重要です。短期案件しか扱っていない事業者は、キャッシュフロー中心の運用に偏りがちで、市況変動への耐性が弱い場合があります。
財務体質と企業規模の信頼性
事業者の財務基盤と経営の安定性もチェックすべきポイントです。上場企業が運営しているか、もしくは大手不動産会社の関連企業であるかどうかを確認しましょう。東証上場企業のように財務情報を公開している事業者は、投資家保護の観点からも信頼性が高い傾向があります。
さらに、運営会社の「自己資本比率」や「劣後出資割合」も重要です。事業者自身がリスクをどの程度負担しているかを見ることで、投資家に対する誠実さを判断できます。劣後出資割合が高いほど、事業者が責任を持って運営していると考えられます。
透明性のある情報開示をしているか
信頼できる事業者は、ファンドのリスクや不動産の評価方法、運用状況を定期的に開示しています。具体的には、以下のような情報を明確に提示しているかを確認しましょう。
- 物件所在地や用途などの詳細情報
- 収益見込みやリスク要因の説明
- 定期的な運用レポート・IR資料
- ファンド終了後の償還結果の公表
これらをきちんと公開している事業者は、投資家への誠実な姿勢がうかがえます。逆に、情報が乏しく運用経過の報告も少ない事業者は避けるべきです。
優先劣後出資制度やリスク軽減策の有無
「優先劣後出資制度」を導入しているかも、信頼性の判断材料となります。事業者自身が劣後出資を行い、損失が出た際に先に事業者側が損失を負担する仕組みを持っていれば、投資家の元本割れリスクは大幅に軽減されます。
また、マスターリース契約(空室保証)や地震保険加入など、リスク対策を明示している事業者は、リスクマネジメントが徹底されています。
信頼性の高い主要事業者の特徴
業界内で特に信頼度が高いとされる代表的な事業者には、以下のような特徴があります。
- COZUCHI(コヅチ):累計投資額No.1クラス。途中換金が可能で透明性の高い運用体制。
- CREAL(クリアル):上場企業が運営し、過去に元本割れ・配当遅延ゼロ。IR開示も充実。
- Jointoα(ジョイントアルファ):東証スタンダード上場企業・穴吹興産が運営。地方案件も豊富で分散投資向き。
これらの事業者はいずれも、運用実績の開示やリスク管理体制が明確で、投資初心者でも安心して利用しやすい特徴があります。
投資家が事前に行うべき確認ステップ
信頼できる事業者を選ぶためには、投資前に以下の手順を実践しましょう。
- 金融庁の「不動産特定共同事業者一覧」で登録状況を確認する
- 過去の償還実績・運用レポートを閲覧する
- 優先劣後割合・保険加入の有無をチェックする
- SNSや口コミサイトで投資家の評判を調べる
表面上のキャンペーンや想定利回りよりも、長期的に信頼できる運営姿勢を持つ事業者を選ぶことが、結果的に損失リスクを下げる近道です。

信頼できる事業者かどうかを見極めるコツは、数字よりも“透明性と実績”を見ることです。利回りよりも、事業者の誠実さに注目して判断していきましょう
失敗しないために今できる行動リスト
不動産投資クラウドファンディングは少額から始められる魅力的な投資手法ですが、「正しく準備をするかどうか」で成果は大きく変わります。ここでは、失敗を避けるために投資家が“今すぐできる実践的な行動”を整理しました。
口座開設前に「実績」「仕組み」「税金」を把握する
最初のステップは、投資の“構造理解”です。クラウドファンディングは銀行預金や株式とは異なり、不動産特定共同事業法に基づいた匿名組合契約という独自のスキームで成り立っています。
この仕組みを理解せずに始めると、「想定より償還が遅い」「分配金が少ない」といった状況に戸惑うことになります。
確認すべきポイントは次の3つです。
- 実績:元本割れや遅延の有無、過去の募集・償還件数
- 仕組み:優先劣後出資制度の有無、マスターリース契約の内容
- 税金:雑所得扱いか不動産所得扱いか、確定申告の要否
これらを事前に整理しておけば、案件選定や確定申告で慌てるリスクを減らせます。
少額キャンペーンを活用して「小さく試す」
知識を得たら、まずは少額から投資を体験してみましょう。
多くの主要事業者(CREAL、COZUCHI、Jointoαなど)は1万円から投資可能で、さらに登録時のキャンペーンでAmazonギフト券などがもらえるケースもあります。
小さく投資を始めるメリットは以下のとおりです。
- 手続きや分配金の流れを実体験で理解できる
- 運用期間やリスクの感覚を掴める
- 初心者特有の不安を軽減できる
初回は「リターンを狙う」よりも「仕組みに慣れる」ことを目的にするのが安全です。
複数サービスを比較して「自分の投資スタイル」を確立する
同じ不動産クラウドファンディングでも、各サービスには特徴の違いがあります。
利回り重視、安定性重視、短期運用重視など、自分の目的に合った組み合わせを選ぶことで、全体のリスクを抑えながら収益を安定させられます。
比較時のチェックポイントは次の通りです。
- 利回りと劣後割合のバランス
- 運用期間と資金拘束の長さ
- ファンド募集の頻度と応募しやすさ
- IR・実績開示の透明性
例えば、安定重視なら上場企業が運営するCREALやJointoα、積極運用型なら高利回り案件が多いCOZUCHIなど、目的別に選ぶのがおすすめです。
情報源を定期的にチェックする習慣をつける
投資後も「放置」は禁物です。事業者の公式サイトやマイページでは、運用報告や市況ニュースが随時更新されています。
また、金融庁や国交省による制度改正も不動産クラウドファンディングに影響します。定期的に確認し、リスクの兆候を早期に察知しましょう。
分散・リバランスを意識する
1つの案件やサービスに資金を集中させると、リスクが偏ります。
運用が進むにつれ、ファンドの償還時期や利回りがばらつくため、定期的に資金配分を見直すことが重要です。
不動産市場や金利環境が変化するタイミングでは、リバランス(再配分)を行うことで、リスクとリターンのバランスを保てます。
投資記録を残して「感覚に頼らない判断」を習慣化する
投資履歴や判断理由を記録しておくことで、「なぜその案件を選んだか」「結果はどうだったか」を客観的に振り返ることができます。
特にクラウドファンディングは複数案件を並行して運用するため、スプレッドシートや家計簿アプリでの管理が有効です。

焦らず、着実に一歩ずつ進めるのがコツです。小さく試して学び、確信を得てから資金を増やすことで、リスクを最小限に抑えられます。投資とは「行動の積み重ね」が信頼と経験値を生むものですよ。
| 順位 | 商品名 | 会社名 | 特徴 | 案件数 | 直近10件平均利回り | 直近10件直近最低利回り | 直近10件直近最高利回り | 直近10件募集割合平均 | 優先劣後方式 | 最低投資金額 | 募集方法 | 組合契約 | 物件の種類 | 優遇サービスあり | 物件の開示情報 | 出金手数料 | 運用レポートの共有あり | 運営会社設立年月 | 運営会社資本金 | 上場 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | COZUCHI(コズチ) | LAETOLI株式会社 | 投資募集のチャンスは業界上位。投資デビューに適した候補 | 139件 | 6.05% | 4.00% | 10.00% | 336.41% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 月1回まで無料(それ以降は330円) | ○ | 1999年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 2位 | CREAL(クリアル) | クリアル株式会社 | 募集口数が多く、新規案件の供給量も豊富 | 139件 | 5.67% | 5.00% | 6.50% | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス、保育所、学校、宿泊施設 | ○ | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 105円(楽天銀行の場合)、150円(楽天銀行以外で3万円未満の場合)、229円(楽天銀行以外で3万円以上の場合) | ○ | 2011年 | 1,273,520,500円 | ○ | 公式サイト |
| 3位 | 利回りくん | 株式会社シーラ | 年間新規案件数が安定。募集口数も一定水準 | 148件 | 4.26% | 3.00% | 5.12% | 76.70% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2010年 | 446,522,660円 | ○ | 公式サイト |
| 4位 | Rimple(リンプル) | プロパティエージェント株式会社 | 新規案件が充実。劣後出資割合の高い案件が多い | 112件 | 2.76% | 2.70% | 3.30% | 277.80% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、事業内容 | 無料 | ○ | 2004年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 5位 | TECROWD(テクラウド) | TECRA株式会社 | 新興国不動産への投資が可能。高利回り案件が多い | 90件 | 10.90% | 9.50% | 12.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、オフィス | ○ | 住所、運営会社、財務情報、面積、事業内容 | 無料(楽天銀行)、振込手数料(楽天銀行以外) | ○ | 2001年 | 156,600,000円 | × | 公式サイト |
| 6位 | TSON FUNDING(ティーソン) | 株式会社TSON | 年間案件数が最多クラス。リスク軽減案件も豊富 | 230件 | 5.81% | 5.50% | 6.00% | 96.30% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、事業内容 | 無料(匿名組合ファンド)、振込手数料(任意組合ファンド) | ○ | 2008年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 7位 | 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス | 運営会社の信頼性が高く、新規案件も安定供給 | 109件 | 5.90% | 3.50% | 12.00% | 728.48% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛) | ○ | 1996年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 8位 | FUNDROP(ファンドロップ) | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 | 劣後出資割合の高い案件が多いが、投資機会は少なめ | 39件 | 5.75% | 5.50% | 6.00% | 128.54% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 52円(楽天銀行)、150円(他の金融機関で3万円未満)、229円(他の金融機関で3万円以上) | ○ | 2013年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 9位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 穴吹興産株式会社 | 低リスク案件が多いが、投資の機会は限定的 | 43件 | 3.25% | 3.00% | 5.00% | 99.98% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設 | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 1964年 | 755,790,000円 | ○ | 公式サイト |
| 10位 | ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 | 劣後出資割合の高い案件が多く、運営も安定傾向 | 10件 | 4.00% | 3.90% | 4.30% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(その他の金融機関) | ○ | 1991年 | 389,820,000円 | × | 公式サイト |
| 11位 | property+(プロパティプラス) | 株式会社リビングコーポレーション | 募集口数は平均的だが、新規案件がなかった点が課題 | 34件 | 3.20% | 3.00% | 3.40% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2015年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 12位 | ASSECLI(アセクリ) | 株式会社エボルゾーン | 高利回り案件が多いが、新規提供数は限られる | 45件 | - | 0.00% | 0.00% | 105.85% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 事業内容 | 無料 | × | 2011年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 13位 | LIFULL(ライフル) | 株式会社LIFULL | 大手不動産会社のクラウドファンディング。厳選された物件 | 3件 | 5.83% | 5.50% | 6.00% | 105.67% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション・グループホーム | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | × | 1997年 | 9,723,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 14位 | みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント | 」「公的年金に合わせた2ヵ月ごとの分配金」が特徴の、不動産クラウドファンディング | 151件 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、物件種別、アクセス、構造、総戸数、家賃保証有無 | PayPay銀行への払い戻し:無料、PayPay銀行以外への払い戻し:145円 | × | 2016年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 15位 | 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス | 高水準の利回り案件が豊富で、投資のチャンスも平均以上 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行あて) | ○ | 2023年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 16位 | らくたま | 株式会社日本保証 | リスクを抑えつつ高いリターンを狙える案件が多く、供給数も充実 | - | - | - | - | - | ○ | 10000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、商業施設、オフィス | ○ | 築年数、住所、面積 | 無料(GMOあおぞらネット銀行) | × | 2008年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 17位 | GALA FUNDING(ガーラ ファンディング) | 株式会社FJネクストホールディングス | 運営基盤が堅実で、劣後出資割合が高めの安心感ある案件が中心 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛て) | ○ | 1980年 | 2,774,400,000円 | ○ | 公式サイト |
| 18位 | トモタク | 株式会社イーダブルジー | 新規募集数は業界トップクラスで、高利回り案件が目立つ | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、オフィス | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 1回のみ無料(125円(GMOあおぞらネット銀行)、250円(GMOあおぞらネット銀行以外)) | ○ | 2009年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 19位 | LSEED(エルシード) | 株式会社LSEED | リスクとリターンのバランスは良好だが、案件数はやや少なめ | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、面積、事業内容 | 不明 | × | 1999年 | 706,139,500円 | ○ | 公式サイト |
| 20位 | トーセイ不動産クラウド | トーセイ株式会社 | 1万口超の大型案件が主体で、年間の提供数は限定的 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、129円(その他金融機関) | ○ | 1950年 | 6,624,890,000円 | ○ | 公式サイト |
| 21位 | KORYO Funding(コウリョウ ファンディング) | 株式会社興陵 | 安定したバランス型案件が揃う一方で、全体の件数は少ない | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容 | 無料 | × | 1981年 | 371,980,200円 | ○ | 公式サイト |