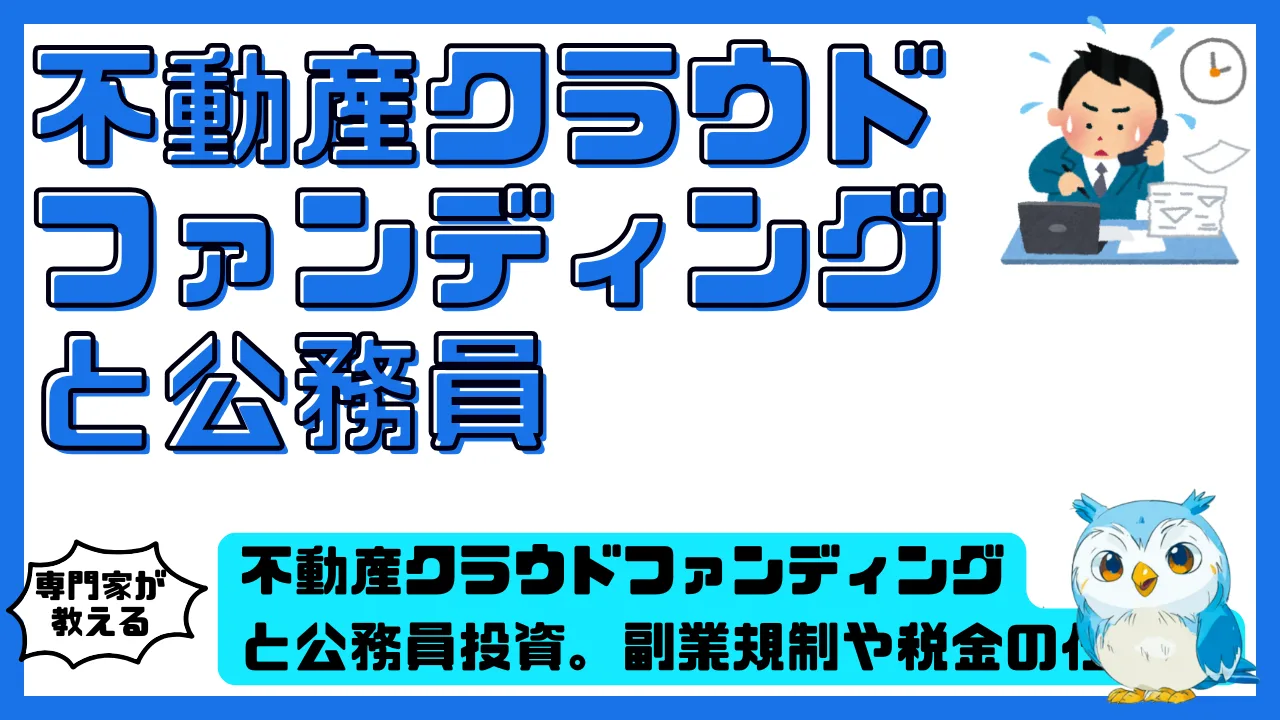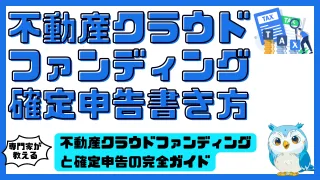本ページはプロモーションが含まれています。
目次
公務員が不動産クラウドファンディングに関心を持つ理由
公務員が不動産クラウドファンディングに注目する背景には、現職に影響を与えず資産形成の可能性を広げられる点が大きく関係しています。安定した収入が得られる一方で、給与の伸びや将来の退職金に不安を感じる方も少なくありません。そのため、リスクを抑えつつ少額から始められる投資手段として、不動産クラウドファンディングが選択肢に浮上しています。
低金利環境で資産形成が難しいから
銀行預金や国債といった従来の安全資産では利回りが非常に低く、資産を増やす手段としての魅力が薄れています。不動産クラウドファンディングは、想定利回りが年数%程度の案件も多く、資産を効率的に育てたい公務員にとって魅力的な存在となっています。
少額から始められる手軽さ
現物不動産投資は数百万円から数千万円単位の資金が必要で、ローンを組むと勤務先への申告や信用問題にも関わります。一方、不動産クラウドファンディングなら1万円程度から出資できるため、生活費や家計に大きな負担をかけずに投資体験が可能です。
勤務に支障をきたさない投資スタイル
株式やFXのように相場を常時チェックする必要がなく、案件選びと申込の手続きを済ませれば、基本的に運用は事業者に任せられます。勤務時間中に作業が発生せず、職務専念義務を損なわない投資方法として安心して取り組めます。
安定収入との相性の良さ
公務員は給与が安定しているため、長期的な資産形成に適しています。毎月の分配金を給与収入に上乗せすることで、将来に備えた資産形成を着実に進められる点も、多くの公務員が関心を持つ理由です。

公務員の方が不動産クラウドファンディングに関心を持つのは、安定収入を土台にリスクを抑えながら資産を増やせるからなんです。勤務に支障を与えない仕組みや少額で始められる特徴は、安心感につながりますよ
国家公務員法や地方公務員法における副業規定の基本
公務員が投資や副業を行う際に最も気をつけなければならないのが、国家公務員法や地方公務員法で定められた副業に関する規定です。これらの法律は、公務員の職務の中立性や公平性を守るために制定されており、私的な営利活動が公務に影響を及ぼさないよう厳格なルールが設けられています。
国家公務員法での制限
国家公務員法では主に第103条と第104条で副業に関する規定が定められています。具体的には、以下のような制限があります。
- 営利企業の役員や顧問に就任することの禁止
- 自ら営利を目的とする事業を経営することの禁止
- 報酬を伴う業務に従事することの禁止
これらの規定に違反すると、懲戒処分の対象となる可能性があります。特に「経営に関与するかどうか」「報酬が労務の対価であるかどうか」が判断の分かれ目になります。
地方公務員法での制限
地方公務員については地方公務員法第38条で副業の制限が設けられています。基本的な考え方は国家公務員と同じであり、営利を目的とする事業の経営や報酬を得る活動は制限されます。違いとしては、各自治体の条例や規則により、詳細な運用基準が追加される場合がある点です。例えば、副業許可の申請手続きや判断基準が自治体ごとに異なる場合があります。
禁止される副業と認められる資産運用の違い
大切なのは、法律が禁止しているのは「事業経営」や「報酬労働」であって、全ての収益活動ではないという点です。株式や投資信託、不動産投資、そして不動産クラウドファンディングなどの「資産運用」は、あくまでも労働の対価ではなく投資リターンとして扱われます。そのため、基本的には副業には該当しないと解釈されています。
ただし、注意すべきは投資の規模や関与度合いです。例えば、不動産賃貸業を個人事業主として営む規模にまで拡大すれば「事業」とみなされ、違法と判断される可能性があります。資産運用と事業経営の境界を意識し、規定を逸脱しない範囲で取り組むことが重要です。

つまり、公務員の場合は「報酬を得る仕事」と「投資リターンによる資産運用」を明確に区別して考えることが大事なんです。国家公務員法や地方公務員法が禁じているのは事業や労務であって、資産運用までは制限されていません。安心して投資するためには、この線引きを理解した上で、勤務先の服務規程や自治体ごとの細かいルールも確認しておくと良いですよ
不動産クラウドファンディングが副業に該当しない理由
公務員の投資活動において大きな関心を集めるのが「副業規制との関係」です。結論から言えば、不動産クラウドファンディングは副業には該当せず、資産運用として扱われます。その理由を具体的に解説します。
事業経営に関与しない仕組み
不動産クラウドファンディングは、事業を直接経営するものではなく、出資者として資金を預けて運用を委託する仕組みです。投資家は物件の運営や管理に携わることはなく、企業側が一括してプロジェクトを進めます。つまり、営利企業の役員や経営者として活動することにはあたらないため、国家公務員法や地方公務員法が禁止する「営利活動」とは区別されます。
勤務時間に作業を要しない
副業と判断される要素の一つは、勤務時間中に作業や労務提供を行うかどうかです。不動産クラウドファンディングは投資申込を済ませれば基本的に「ほったらかし」で運用され、日常的に管理や手続きが必要になることはありません。勤務時間中に株価のように常時チェックする必要もなく、公務専念義務を妨げない点が副業に該当しない理由となります。
投資リターンとしての収益
副業と資産運用を分ける重要なポイントは収益の性質です。副業収入は「労働の対価」や「事業報酬」として得られるのに対し、不動産クラウドファンディングで得られる分配金はあくまで「投資によるリターン」です。これは株式や投資信託と同じ位置づけであり、報酬ではなく資産運用の成果とみなされます。そのため、副業規制の対象とはされません。
補足的な安心材料
- 投資は資産運用の範囲として法律上認められている
- 募集時点で必要な情報が開示され、投資家は選択だけを行う
- 運用中の労働提供や経営参加が不要
これらの点から、不動産クラウドファンディングは公務員の副業禁止規定に抵触せず、適法な投資活動として位置づけられます。

つまり、不動産クラウドファンディングは「働いて稼ぐ副業」ではなく「お金を運用する投資」だから大丈夫なんです。勤務時間に影響せず、収益も報酬ではなく投資リターンとして扱われるので、副業規制にひっかかる心配はありませんよ
公務員が投資する際に注意すべきポイント
不動産クラウドファンディングは副業規定に抵触しないとされる投資手法ですが、公務員が安心して取り組むためにはいくつかの注意点があります。ここを押さえておくことで、不必要なリスクやトラブルを回避することができます。
職務専念義務を損なわないこと
公務員は勤務時間中に職務に専念する義務があります。株式やFXのように頻繁に売買を行う必要はありませんが、投資に関連した作業を勤務時間中に行うことは避けるべきです。ファンドの応募や情報収集は、勤務外の時間に計画的に行うようにしましょう。
服務規程との整合性を確認すること
所属先によっては服務規程に投資に関する独自の規定を設けている場合があります。とくに投資規模が大きくなると「事業性」と判断される可能性もあるため、事前に就業規則や人事担当部署に確認することが重要です。トラブルを未然に防ぐためにも、制度や規程を理解した上で行動することが求められます。
投資額や運用スタイルの偏りを避けること
不動産クラウドファンディングは少額から始められる一方で、元本保証がない投資です。安定収入を持つ公務員であっても、一つの案件に資金を集中させるのはリスクが高いといえます。複数案件に分散投資したり、他の金融商品と組み合わせたりしてリスクを分散することが大切です。
公務員としての信用を損なわないこと
投資は個人の資産形成手段である一方、社会的な立場にも影響を与える可能性があります。公務員は公共の利益を担う職務にあるため、万一投資トラブルに巻き込まれると職務への信頼性にも影響しかねません。リスクを理解し、過度なリターンを追わない姿勢が必要です。

公務員が不動産クラウドファンディングを始めるときは、「職務に支障をきたさないこと」「服務規程を必ず確認すること」「投資を一極集中させないこと」を意識してほしいんです。安定した立場だからこそ、堅実で計画的な投資姿勢が将来の安心につながりますよ
税金と確定申告の仕組み
不動産クラウドファンディングで得られる分配金は、給与所得とは別に「雑所得」として扱われます。会社員や公務員を含むすべての投資家は、この所得区分を理解しておくことが必要です。分配金は支払時に源泉徴収が行われるため、一定のケースでは追加の確定申告を省略できますが、条件によっては申告が必要になるため注意が必要です。
分配金と源泉徴収の仕組み
投資家が受け取る分配金には、20.42%の税金が自動的に差し引かれます。内訳は以下のとおりです。
- 所得税:20%
- 復興特別所得税:0.42%
例えば、分配金が5万円の場合、1万210円が源泉徴収され、実際に受け取れるのは3万9,790円となります。源泉徴収は事業者側で処理されるため、投資家は手続き不要で課税済みの金額を受け取れます。
確定申告が必要となるケース
源泉徴収があるからといって、すべてのケースで確定申告が不要になるわけではありません。次の条件に該当する場合は、必ず確定申告を行う必要があります。
- 1年間の雑所得が20万円を超える場合
- 年収が2,000万円を超える場合
- 他の理由で確定申告義務がある場合(複数の収入源があるなど)
公務員の場合も同様で、分配金が年間20万円を超えると申告対象になります。少額投資なら申告が不要なケースもありますが、複数のクラウドファンディングに分散投資していると合計で20万円を超える可能性があるため、事前に計算しておくことが重要です。
住民税の申告と自治体対応
住民税については、金額に関わらず申告が必要となるケースが多くあります。自治体によって運用が異なるため、勤務先に投資の事実が通知されるのを避けたい場合には、住民税の「普通徴収」を選ぶことも検討すべきです。これにより、給与天引きではなく自宅に納付書が届く形式になり、職場に知られるリスクを軽減できます。
他の雑所得との通算
不動産クラウドファンディングの分配金は、同じ雑所得に分類される他の収入と合算されます。たとえば、暗号資産取引で損失が出ている場合、損益通算することで納税額を減らせる可能性があります。ただし、事業所得や給与所得との通算はできないため、仕組みを誤解しないよう注意が必要です。

税金の仕組みは難しく感じますが、ポイントは「分配金は雑所得」「20.42%が自動で引かれる」「20万円を超えたら確定申告」という3点です。さらに住民税の申告方法を工夫すれば、勤務先への影響を最小限にできます。投資を安心して続けるためにも、税金のルールを早めに押さえておくのが大切ですよ
公務員に適した不動産クラウドファンディングの特徴
公務員が安心して取り組める不動産クラウドファンディングには、いくつかの共通した特徴があります。副業規定に抵触せず、安定した資産形成を目指す上で、投資先を選ぶ際に注目すべき点を整理します。
少額から投資できる仕組み
現物の不動産投資は数百万円から数千万円規模の資金が必要ですが、クラウドファンディングなら1万円程度から始められるサービスも多くあります。公務員のように給与収入が安定していても、投資に大きな資金を割くのはリスクが高いため、少額から分散投資できる仕組みは適しています。
情報開示の透明性
投資対象となる不動産の情報がどれだけ詳しく開示されているかは重要です。物件概要や所在地、収益シミュレーションに加え、外部の不動産鑑定士による評価やリスク分析が公開されているサービスは、情報の非対称性を小さくし、投資判断を下しやすくします。特に勤務の合間にじっくり調べられない公務員にとっては、事前に十分な情報が整っているサービスが安心です。
劣後出資によるリスク軽減
クラウドファンディングでは、事業者や運営会社が投資家よりも後に損失を負担する「劣後出資」の仕組みを採用しているケースがあります。これにより、万が一運用がうまくいかなくても、投資家の元本が一定程度守られる可能性が高まります。元本保証ではないものの、公務員が大きなリスクを取らずに投資できる点で適した構造といえます。
運用の手間がかからない
株やFXのように常に相場をチェックする必要がなく、一度出資すれば運用は事業者に任せられる点も魅力です。勤務時間中に売買を行う必要がないため、職務専念義務を妨げずに続けられます。公務員の立場にとって、ほったらかし運用が可能な投資手段は大きな安心材料となります。
社会的意義のある案件
保育園や介護施設、地域再生につながる物件など、社会的意義を持つファンドも多くあります。公務員にとって「社会貢献性」と「資産形成」を両立できる点は、選択の動機付けとして強く働きます。

公務員の方が投資を選ぶときは「少額から始められること」「情報が十分に公開されていること」「リスクを軽減する仕組みがあること」をしっかり確認すると安心ですよ。大きなリターンを狙うよりも、安定的に資産を積み上げる姿勢が大切です
公務員が感じるメリットとデメリット
公務員が不動産クラウドファンディングに投資する場合、法的な制約をクリアできるだけでなく、資産形成の選択肢として魅力があります。しかし一方で、見落としてはいけないデメリットも存在します。ここでは、公務員投資家の目線からメリットとデメリットを整理します。
メリット
- 安定収入に上乗せできる資産形成
公務員は安定した給与を得られる職業ですが、その収入に加えて定期的な分配金を受け取ることができます。給与と投資収入を組み合わせることで、将来のライフプランに余裕を持たせられます。 - 少額からのスタートが可能
数万円単位から投資できるサービスが多く、住宅ローンや多額の借入を伴う現物不動産投資に比べてハードルが低い点は大きな利点です。初心者でも始めやすく、分散投資にも適しています。 - 社会貢献性の高さ
保育園や福祉施設、地域再生を目的としたファンドに投資すれば、経済的リターンだけでなく社会的な意義も得られます。公務員として社会貢献を意識する方にとっては魅力的な側面です。 - 勤務に影響しない仕組み
投資後は基本的に「ほったらかし」で運用できるため、勤務中に作業が発生せず、職務専念義務を妨げるリスクが小さいのも安心材料です。
デメリット
- 元本保証がない
不動産クラウドファンディングは金融商品である以上、元本割れリスクを避けられません。過去に元本割れのない実績を持つ事業者も存在しますが、将来も同じ保証があるわけではなく、損失リスクは常に伴います。 - 案件の競争率が高い
利回りの高い人気ファンドは応募が集中し、抽選や先着で落選することもあります。思うように投資できず、資金を寝かせてしまうリスクがある点はデメリットです。 - 情報格差による判断難易度
各事業者が情報開示に力を入れていても、不動産市場の専門知識がなければ判断に迷うケースがあります。表面的な利回りだけで選んでしまうと、リスクを過小評価してしまう恐れがあります。 - 税務面の煩雑さ
分配金は雑所得に区分されるため、条件によっては確定申告が必要です。勤務先への副業申告と誤解されることを避けるため、税務処理には慎重さが求められます。

公務員の方にとって不動産クラウドファンディングは、安定収入にプラスして資産形成を進められる有効な手段ですが、リスクを冷静に把握することが不可欠です。メリットに飛びつくのではなく、元本割れや投資機会の偏りといったデメリットを理解したうえで、少額・分散・慎重な判断を意識するのが大切ですよ
公務員が感じるメリットとデメリット
公務員が不動産クラウドファンディングに投資する場合、法的な制約をクリアできるだけでなく、資産形成の選択肢として魅力があります。しかし一方で、見落としてはいけないデメリットも存在します。ここでは、公務員投資家の目線からメリットとデメリットを整理します。
メリット
- 安定収入に上乗せできる資産形成
公務員は安定した給与を得られる職業ですが、その収入に加えて定期的な分配金を受け取ることができます。給与と投資収入を組み合わせることで、将来のライフプランに余裕を持たせられます。 - 少額からのスタートが可能
数万円単位から投資できるサービスが多く、住宅ローンや多額の借入を伴う現物不動産投資に比べてハードルが低い点は大きな利点です。初心者でも始めやすく、分散投資にも適しています。 - 社会貢献性の高さ
保育園や福祉施設、地域再生を目的としたファンドに投資すれば、経済的リターンだけでなく社会的な意義も得られます。公務員として社会貢献を意識する方にとっては魅力的な側面です。 - 勤務に影響しない仕組み
投資後は基本的に「ほったらかし」で運用できるため、勤務中に作業が発生せず、職務専念義務を妨げるリスクが小さいのも安心材料です。
デメリット
- 元本保証がない
不動産クラウドファンディングは金融商品である以上、元本割れリスクを避けられません。過去に元本割れのない実績を持つ事業者も存在しますが、将来も同じ保証があるわけではなく、損失リスクは常に伴います。 - 案件の競争率が高い
利回りの高い人気ファンドは応募が集中し、抽選や先着で落選することもあります。思うように投資できず、資金を寝かせてしまうリスクがある点はデメリットです。 - 情報格差による判断難易度
各事業者が情報開示に力を入れていても、不動産市場の専門知識がなければ判断に迷うケースがあります。表面的な利回りだけで選んでしまうと、リスクを過小評価してしまう恐れがあります。 - 税務面の煩雑さ
分配金は雑所得に区分されるため、条件によっては確定申告が必要です。勤務先への副業申告と誤解されることを避けるため、税務処理には慎重さが求められます。

公務員の方にとって不動産クラウドファンディングは、安定収入にプラスして資産形成を進められる有効な手段ですが、リスクを冷静に把握することが不可欠です。メリットに飛びつくのではなく、元本割れや投資機会の偏りといったデメリットを理解したうえで、少額・分散・慎重な判断を意識するのが大切ですよ
| 順位 | 商品名 | 会社名 | 特徴 | 案件数 | 直近10件平均利回り | 直近10件直近最低利回り | 直近10件直近最高利回り | 直近10件募集割合平均 | 優先劣後方式 | 最低投資金額 | 募集方法 | 組合契約 | 物件の種類 | 優遇サービスあり | 物件の開示情報 | 出金手数料 | 運用レポートの共有あり | 運営会社設立年月 | 運営会社資本金 | 上場 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | COZUCHI(コズチ) | LAETOLI株式会社 | 投資募集のチャンスは業界上位。投資デビューに適した候補 | 139件 | 6.05% | 4.00% | 10.00% | 336.41% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 月1回まで無料(それ以降は330円) | ○ | 1999年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 2位 | CREAL(クリアル) | クリアル株式会社 | 募集口数が多く、新規案件の供給量も豊富 | 139件 | 5.67% | 5.00% | 6.50% | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス、保育所、学校、宿泊施設 | ○ | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 105円(楽天銀行の場合)、150円(楽天銀行以外で3万円未満の場合)、229円(楽天銀行以外で3万円以上の場合) | ○ | 2011年 | 1,273,520,500円 | ○ | 公式サイト |
| 3位 | 利回りくん | 株式会社シーラ | 年間新規案件数が安定。募集口数も一定水準 | 148件 | 4.26% | 3.00% | 5.12% | 76.70% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2010年 | 446,522,660円 | ○ | 公式サイト |
| 4位 | Rimple(リンプル) | プロパティエージェント株式会社 | 新規案件が充実。劣後出資割合の高い案件が多い | 112件 | 2.76% | 2.70% | 3.30% | 277.80% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、事業内容 | 無料 | ○ | 2004年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 5位 | TECROWD(テクラウド) | TECRA株式会社 | 新興国不動産への投資が可能。高利回り案件が多い | 90件 | 10.90% | 9.50% | 12.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、オフィス | ○ | 住所、運営会社、財務情報、面積、事業内容 | 無料(楽天銀行)、振込手数料(楽天銀行以外) | ○ | 2001年 | 156,600,000円 | × | 公式サイト |
| 6位 | TSON FUNDING(ティーソン) | 株式会社TSON | 年間案件数が最多クラス。リスク軽減案件も豊富 | 230件 | 5.81% | 5.50% | 6.00% | 96.30% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、事業内容 | 無料(匿名組合ファンド)、振込手数料(任意組合ファンド) | ○ | 2008年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 7位 | 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス | 運営会社の信頼性が高く、新規案件も安定供給 | 109件 | 5.90% | 3.50% | 12.00% | 728.48% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛) | ○ | 1996年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 8位 | FUNDROP(ファンドロップ) | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 | 劣後出資割合の高い案件が多いが、投資機会は少なめ | 39件 | 5.75% | 5.50% | 6.00% | 128.54% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 52円(楽天銀行)、150円(他の金融機関で3万円未満)、229円(他の金融機関で3万円以上) | ○ | 2013年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 9位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 穴吹興産株式会社 | 低リスク案件が多いが、投資の機会は限定的 | 43件 | 3.25% | 3.00% | 5.00% | 99.98% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設 | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 1964年 | 755,790,000円 | ○ | 公式サイト |
| 10位 | ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 | 劣後出資割合の高い案件が多く、運営も安定傾向 | 10件 | 4.00% | 3.90% | 4.30% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(その他の金融機関) | ○ | 1991年 | 389,820,000円 | × | 公式サイト |
| 11位 | property+(プロパティプラス) | 株式会社リビングコーポレーション | 募集口数は平均的だが、新規案件がなかった点が課題 | 34件 | 3.20% | 3.00% | 3.40% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2015年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 12位 | ASSECLI(アセクリ) | 株式会社エボルゾーン | 高利回り案件が多いが、新規提供数は限られる | 45件 | - | 0.00% | 0.00% | 105.85% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 事業内容 | 無料 | × | 2011年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 13位 | LIFULL(ライフル) | 株式会社LIFULL | 大手不動産会社のクラウドファンディング。厳選された物件 | 3件 | 5.83% | 5.50% | 6.00% | 105.67% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション・グループホーム | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | × | 1997年 | 9,723,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 14位 | みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント | 」「公的年金に合わせた2ヵ月ごとの分配金」が特徴の、不動産クラウドファンディング | 151件 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、物件種別、アクセス、構造、総戸数、家賃保証有無 | PayPay銀行への払い戻し:無料、PayPay銀行以外への払い戻し:145円 | × | 2016年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 15位 | 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス | 高水準の利回り案件が豊富で、投資のチャンスも平均以上 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行あて) | ○ | 2023年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 16位 | らくたま | 株式会社日本保証 | リスクを抑えつつ高いリターンを狙える案件が多く、供給数も充実 | - | - | - | - | - | ○ | 10000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、商業施設、オフィス | ○ | 築年数、住所、面積 | 無料(GMOあおぞらネット銀行) | × | 2008年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 17位 | GALA FUNDING(ガーラ ファンディング) | 株式会社FJネクストホールディングス | 運営基盤が堅実で、劣後出資割合が高めの安心感ある案件が中心 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛て) | ○ | 1980年 | 2,774,400,000円 | ○ | 公式サイト |
| 18位 | トモタク | 株式会社イーダブルジー | 新規募集数は業界トップクラスで、高利回り案件が目立つ | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、オフィス | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 1回のみ無料(125円(GMOあおぞらネット銀行)、250円(GMOあおぞらネット銀行以外)) | ○ | 2009年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 19位 | LSEED(エルシード) | 株式会社LSEED | リスクとリターンのバランスは良好だが、案件数はやや少なめ | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、面積、事業内容 | 不明 | × | 1999年 | 706,139,500円 | ○ | 公式サイト |
| 20位 | トーセイ不動産クラウド | トーセイ株式会社 | 1万口超の大型案件が主体で、年間の提供数は限定的 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、129円(その他金融機関) | ○ | 1950年 | 6,624,890,000円 | ○ | 公式サイト |
| 21位 | KORYO Funding(コウリョウ ファンディング) | 株式会社興陵 | 安定したバランス型案件が揃う一方で、全体の件数は少ない | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容 | 無料 | × | 1981年 | 371,980,200円 | ○ | 公式サイト |