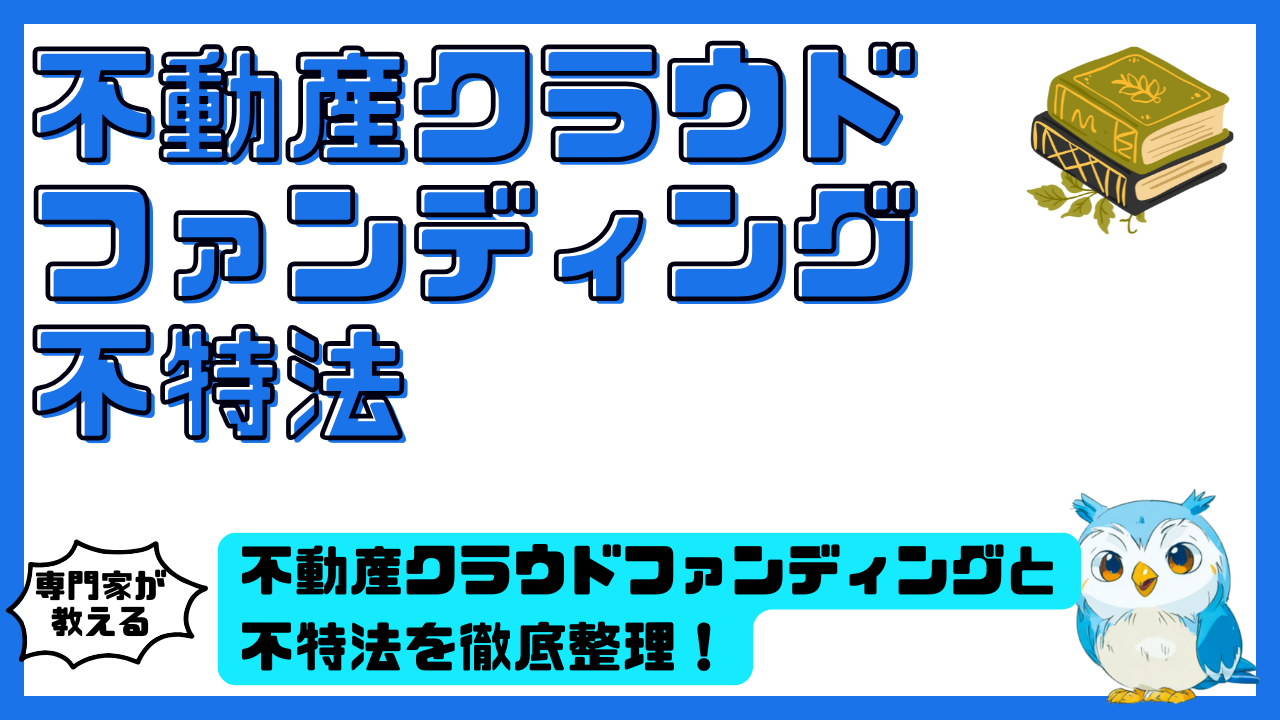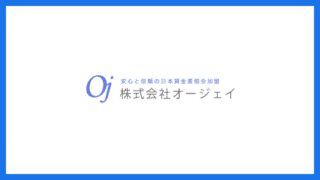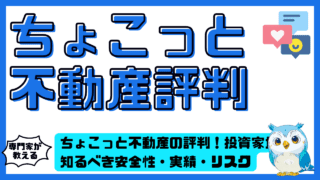本ページはプロモーションが含まれています。
目次
- 不動産クラウドファンディングを資金調達に使う仕組みを整理
- 不特法とは何か。なぜ不動産クラウドファンディングに必須なのか
- 不特法の第1号~第4号の違いと事業スキームの特徴
- 第1号事業の特徴(不動産の取得・運用主体)
- 第2号事業の特徴(契約締結の代理・媒介)
- 第3号事業の特徴(SPCによる倒産隔離スキーム)
- 第4号事業の特徴(特例事業の代理・媒介)
- 4つの区分の比較と資金調達者の活用イメージ
- 資金調達者にとってのポイント
- 不動産保有者が知るべき倒産隔離スキームのメリット
- 資金調達の観点で見る「小規模不特法」の利点
- 不特法に基づくクラウドファンディング運営で必要な準備
- 不動産保有者がクラウドファンディングで資金調達するメリット
- 不動産保有者が失敗しないための注意点
不動産クラウドファンディングを資金調達に使う仕組みを整理
不動産を保有したまま資金を調達したい場合、不動産クラウドファンディングは柔軟性の高い選択肢になります。物件を売却せずに資金を確保でき、投資家を広く募ることでスピーディな調達が可能になるためです。この仕組みを正しく理解しておくことで、自社物件の価値をより効果的に活用できます。
保有不動産を小口化して資金を集める仕組み
不動産クラウドファンディングでは、保有不動産の価値を小口に分割し、投資家から出資を募ります。小口化された持分に投資家が参加することで、一件あたりの資金負担は小さく、多くの投資家を集めやすいのが特徴です。
事業者側は、物件の運用益や売却益を原資に投資家へ分配を行い、その過程で必要な資金を先に確保できます。物件を売却せずに資金化できるため、事業継続や新規プロジェクトの立ち上げを両立させやすい点が強みです。
匿名組合方式と任意組合方式の違い
資金調達のスキームは主に次の二つがあります。
- 匿名組合方式
事業者が不動産を所有し、投資家は運用による利益を受け取ります。投資家は不動産の権利を持たず、出資金に応じた分配を受けるだけのため、運営の自由度が高い方式です。 - 任意組合方式
投資家が不動産の共有持分を保有する形で参加します。権利関係が明確である一方、組合員全体が不動産所有者になるため、手続きの複雑さが増す点が特徴です。
資金調達を重視する場合は、運用主体を事業者側に集約できる匿名組合方式が採用されるケースが多くなります。
運営者と投資家の役割分担
不動産クラウドファンディングでは、事業者が運営の中心を担います。
投資家は資金提供者として参加し、不動産の運営判断は事業者に委ねる形になります。
- 事業者の役割
- 不動産の取得・運用・管理
- 投資家への情報提供
- 分配金の計算と支払い
- 法令遵守やシステム管理
- 投資家の役割
- 小口出資によるファンド参加
- 運用成果に応じた分配の受領
事業者が専門性を活かして物件運営を行い、投資家は成果に応じてリターンを受け取るシステムで成立しています。
借入型との違いと資金調達スピード
資金調達手段として、銀行融資等の借入と比較されることがあります。不動産クラウドファンディングの特徴を整理すると、次のような違いがあります。
- 審査基準
融資では事業者の与信が重視されますが、小口出資型では物件の収益性やプロジェクト内容が評価されます。 - 返済方法
借入は元本返済が必須ですが、クラウドファンディングでは出資金は返済義務を伴わず、運用終了後の原則返還に依存します。 - 調達スピード
銀行手続きと比べ、オンラインで募集できるためスピーディに調達しやすいケースがあります。 - 資金使途の柔軟性
投資家に説明された範囲内であれば、比較的自由度の高い資金活用が可能です。
特に、既存物件の再生や運転資金の確保など、売却以外の選択肢を残しながら資金を用意したい事業者に向いている仕組みです。

資金調達の仕組みを理解しておくと、今ある不動産を「眠らせずに使う」戦略が立てやすくなります。小口化のモデルは融資だけでは実現しづらい柔軟な資金調達手段なので、事業内容に合う形で活かしていきましょう
不特法とは何か。なぜ不動産クラウドファンディングに必須なのか
不動産クラウドファンディングを使って資金調達をしたい不動産保有者にとって、不動産特定共同事業法(不特法)は避けて通れない法律です。単に「法律上の形式を整えるための許可」ではなく、投資家保護と事業者の信頼性を確保するための根幹を担う仕組みとして機能しています。不特法の目的と、クラウドファンディングに必須とされる理由を整理します。
不特法の目的は「投資家保護」と「適切な事業運営の担保」
不特法は、不動産を小口化して投資家から資金を集める事業に対し、透明性の高い運営を強制するために制定されました。過去には、不透明な小口化商品により投資家が損失を被る事例が多く、法的枠組みの整備が強く求められていました。
不特法が定める中心的なポイントは次の通りです。
- 投資家資金の保全とリスクの明確化
- 事業者の破綻時に備えた仕組み(倒産隔離や分別管理など)
- 契約書・重要事項の詳細な提示義務
- 不正な勧誘や不適切な管理を防止する内部体制の整備
これらは、投資家から資金を預かる以上、事業者として最低限クリアすべき基準であり、信頼獲得の前提条件でもあります。
不動産クラウドファンディングと電子取引業務の関係
クラウドファンディングはオンラインで資金を集めるビジネスモデルのため、「電子取引業務」の許可を前提に運営されます。不特法の電子取引業務では、次のような厳格な管理体制が求められます。
- 契約書・重要事項説明書の電子交付
- セキュアな投資家情報管理
- システム障害時の復旧体制
- 外部委託先(システム事業者など)の監督義務
- 出金時の名義確認・不正防止策
オンライン完結型の不動産クラウドファンディングでは、システムの不備がそのまま投資家の損害につながるため、電子取引業務の基準をクリアすることは必須といえます。
不動産小口化ビジネスに不可欠なコンプライアンス要件
不動産クラウドファンディングの実態は、投資家から集めた資金で不動産を取得・運用し、その利益を分配する共同事業です。そのため、不特法における以下のコンプライアンス要件を満たす必要があります。
- 宅建士を含む人員体制の整備
- 業務管理者の設置(一定の資格や実務経験が必要)
- リスク説明・重要事項のオンライン掲示
- 投資家資金と事業者資金の分別管理
- 利害関係取引の開示ルール
これらは金融機関の審査に近いレベルで求められるため、不特法に基づいた体制を整える事業者は「一定の健全性と管理能力を持つ」と評価されます。
不特法を取得した事業者が信頼される理由
不特法の許可取得は、単なる手続ではなく、次のような厳しい審査を通過した証明でもあります。
- 資本金・財務体力の要件
- 事業計画の合理性
- システムの安全性
- リスク管理体制の十分性
- 適切な情報開示が可能な運営体制
特に、投資家保護に直結する「倒産隔離スキーム」や「分別管理」は、許可を受けた事業者にしか実施できません。
不動産保有者にとっては、こうした信頼性が投資家からの資金を集めやすくし、ファンドの成立スピードや募集成功率に直結します。不特法に基づいて運営することで、投資家は安心して出資し、事業者は安定的な資金調達を行える環境が整うのです。

不特法は「面倒な法律」ではなく、投資家保護と事業の信用を裏付ける大事な仕組みです。不動産クラウドファンディングで資金調達をするなら、まずこの枠組みを理解しておくことが第一歩ですよ
不特法の第1号~第4号の違いと事業スキームの特徴
不動産クラウドファンディングを使って資金調達を行いたい不動産保有者にとって、不特法の「第1号~第4号」の違いを正しく理解することは重要です。それぞれが担う役割やリスク分担の方法が異なるため、採用できるスキームや投資家への訴求力が大きく変わります。ここでは、資金調達という視点から、4つの区分がどのように機能し、どのスキームがどのような場面で適しているのかを整理します。
第1号事業の特徴(不動産の取得・運用主体)
第1号事業は、不特法の中心的な事業形態であり、事業者自身が不動産を取得・運用し、家賃や売却益を原資に投資家へ分配します。
事業者が不動産の運用主体となるため、投資家からみれば事業者の経営状況がダイレクトにリスクとして影響します。匿名組合型が中心で、投資家は権利を持たず、事業者がすべての管理運営を行います。
事業者にとっては、不動産を直接保有するため意思決定の自由度が高く、小規模案件でも組成しやすい利点があります。一方で、事業者の財務に物件がオンバランスされるため、資金調達の余力や融資の枠にも影響が出やすい構造です。
第2号事業の特徴(契約締結の代理・媒介)
第2号事業は、不動産特定共同事業契約の「代理・媒介」を担う事業形態です。自ら不動産を保有したり運用したりはせず、投資家募集や契約の締結をサポートする役割を果たします。
不特法に基づくクラウドファンディング事業者の多くは、第1号と第2号をセットで取得し、
- 第1号:不動産の保有・運用
- 第2号:募集・契約手続き(オンラインも含む)
という形で一体運営を行っています。
資金調達者にとっては、2号事業者の存在により募集・契約のプロセスが効率化され、オンライン完結型のクラウドファンディングとして成立しやすくなります。
第3号事業の特徴(SPCによる倒産隔離スキーム)
第3号事業は、特例事業スキームに基づいて「SPC(特別目的会社)」を活用するための許可です。これは資金調達を目的とする不動産保有者にとって特に重要な仕組みです。
第3号の最大の特徴は、倒産隔離が可能になる点です。対象不動産はSPCが保有し、運営会社と切り離されるため、運営会社の倒産リスクが投資家へ直接波及しにくくなります。このため、金融機関からも資金調達の透明性が高く評価され、大型案件への拡張が容易になります。
資金調達者にとっては以下のような利点があります。
- 不動産をSPCに移すことで、事業会社の貸借対照表から外し(オフバランス)、財務体質を軽く見せられる
- ノンリコースローンの活用がしやすくなり、レバレッジを使った資金調達も可能
- 不動産の信用力をベースにしたスキームが組める
一方で、SPC設立や3号スキームの組成には一定のコストや専門性が必要になります。
第4号事業の特徴(特例事業の代理・媒介)
第4号事業は、特例事業(SPCスキーム)における契約締結の代理・媒介を行うための許可です。第3号とセットで取得されるケースがほとんどです。
第4号があることで、SPCスキームでも投資家募集をオンラインで効率的に行えるようになります。第3号だけでは「運用」部分しか担えないため、第4号と組み合わせることでクラウドファンディングとしての完成度が高まります。
倒産隔離スキームを実現しつつ、投資家との契約を一括して行えるため、大型案件・機関投資家向けファンドにも対応しやすくなります。
4つの区分の比較と資金調達者の活用イメージ
4つの事業区分の役割イメージ
- 第1号:不動産を取得・運用し、収益配分する主体
- 第2号:投資家募集・契約手続きを担う
- 第3号:SPCを活用して不動産の運用・売買を行う
- 第4号:SPCスキームの募集と契約を代理・媒介する
資金調達の活用イメージ
- 迅速に小規模案件で資金調達したい
→ 第1号+第2号スキームが適している - 大型案件・複数物件の資金調達を同時に検討したい
→ 第3号+第4号スキーム(SPC型)が有効 - 財務リスクを切り離しつつ資金調達したい
→ 第3号による倒産隔離が有効 - 投資家からの信頼性をさらに高めたい
→ 第3号・4号取得事業者と組むことで透明性が高まる
資金調達者にとってのポイント
- 小規模〜中規模の資金調達なら「第1号+第2号」でシンプルかつスピーディ
- 大型案件や金融機関と連携したい場合は「第3号+第4号」
- リスク分離・財務強化を並行したいならSPCスキームが最適
- 投資家への訴求や信頼性確保はスキーム選びで大きく変わる
不動産クラウドファンディングを活用する際、どの事業区分を持つ事業者と組むかによって資金調達の戦略は大きく変わります。特に、倒産隔離やレバレッジの活用など、高度なスキームが必要な場合には第3号・第4号事業者の存在が不可欠です。

不特法の仕組みは複雑に感じますが、ポイントは「自社のリスクをどこまで切り離したいか」「どれだけ大きな資金を調達したいか」で最適なスキームが決まる、というところです。事業規模や資金調達の目的に合わせて、無理のないスキームを選んでいきましょう
不動産保有者が知るべき倒産隔離スキームのメリット
不動産クラウドファンディングを本格的な資金調達手段として使う場合、「倒産隔離スキーム」を理解しているかどうかで、設計できるスキームの選択肢が大きく変わります。
特に第3号・第4号事業スキームで用いられるSPC(特別目的会社)を活用した倒産隔離は、「投資家保護のためのもの」としてだけでなく、不動産を保有する側にとっても資金調達・財務戦略の両面で大きなメリットがあります。
ここでは、不動産保有者の視点から倒産隔離スキームのポイントと、実務上どのようなメリットがあるのかを整理します。
SPCを使った倒産隔離で何が変わるのか
倒産隔離スキームでは、対象不動産を事業会社が直接保有するのではなく、SPCが保有し、運営会社やスポンサーはそのSPCを通じて事業に関与します。
これにより、次のようにリスクの「入れ物」を分けることができます。
- 運営会社やスポンサー本体の事業リスク
- 対象不動産そのものに紐づくリスク(賃貸市場、価格変動など)
通常の第1号スキームでは、運営会社のバランスシート上に不動産が計上されるため、万が一運営会社が経営不振に陥った場合、その不動産が他の債権者との関係の中で処理される可能性があります。
一方、SPCが不動産を保有する倒産隔離スキームでは、適切な設計を前提に、不動産と投資家資金を「プロジェクト単位」で切り出しやすくなり、運営会社本体の倒産リスクが投資家に波及しにくい構造を作りやすくなります。
不動産保有者にとっては、
「自社の信用リスク」と「特定の物件プロジェクトのリスク」を切り分けて説明できるようになる点が大きなポイントです。
保有者の信用リスクと物件リスクを切り分けて説明できる
倒産隔離スキームを用いると、投資家や金融機関に対して、次のような整理で説明がしやすくなります。
- スポンサー企業の事業全体のリスク
- 対象不動産の賃料収入や売却価値に基づくプロジェクトリスク
これにより、不動産保有者にとっては次のようなメリットが期待できます。
- 自社の事業リスクによらず、物件単体の収益力を前面に出して資金調達を検討しやすい
- 投資家も「この不動産プロジェクトに対して、どの程度のリスク・リターンか」を評価しやすくなり、募集がスムーズになりやすい
- 将来、スポンサー側の事業構造を変える場合にも、SPC単位での売却や再編がしやすくなる
特に、既存の不動産を使って新規事業や開発計画の資金を調達したい場合、「スポンサー企業に依存しすぎないストラクチャー」を提示できるかどうかは、投資家・金融機関の納得感を大きく左右します。
オフバランス処理により財務指標をコントロールしやすくなる
SPCを活用した倒産隔離スキームでは、一定の条件を満たす場合、対象不動産や関連借入金をスポンサー企業のバランスシートの外に置く、いわゆるオフバランス処理が可能になるケースがあります。
会計・税務・支配関係の前提によって個別判断が必要ですが、うまく機能すると、次のような効果が期待できます。
- 自己資本比率や有利子負債比率などの指標を圧迫せずに、外部からの資金を呼び込める
- 既存の銀行与信枠を温存したまま、新たなプロジェクトの資金調達チャネルを追加できる
- プロジェクトファイナンスとして金融機関と対話しやすくなり、条件交渉の余地が広がる
不動産を多く保有している事業者ほど、「すべてを自社バランスシートで抱える」のか、「一部をSPCに切り出して機動的に動かす」のかは、中長期の経営戦略に直結します。
倒産隔離スキームは、このバランスを調整するための有力な選択肢の一つになります。
大型案件・開発案件に向いたスキーム構造
倒産隔離スキームは、特に次のような案件との相性が良いとされています。
- 数十億〜百億円規模を想定する大型の開発案件
- 竣工までのリードタイムが長く、開発リスクと運営リスクを整理したい案件
- 機関投資家や金融機関からの資金を組み合わせたいプロジェクト
SPCを中心にストラクチャーを組むことで、
- ノンリコースローン(物件を主な返済原資とする融資)を活用し、レバレッジを効かせた資金調達が検討しやすくなる
- プロジェクト単位でファンドサイズを大型化しやすくなり、個人投資家に加えて機関投資家マネーも取り込める可能性が出てくる
- 竣工後にSPC持分の売却や、REITや別ファンドへの組み替えなど、多様な出口戦略を描きやすくなる
不動産保有者の立場から見ると、「単一の物件を売って終わり」ではなく、「開発→運営→売却・リファイナンス」といったライフサイクル全体を前提にした資金戦略を組み立てやすくなる点が、非常に大きなメリットです。
ITシステムと組み合わせることで運営負荷を抑えられる
倒産隔離スキームは、法的・会計的な設計だけでなく、実務面では「案件数に応じて管理対象のSPCやファンドが増えていく」ことを意味します。
ここで重要になるのが、不動産クラウドファンディングの基盤となるITシステムです。
- SPCごとにファンド情報・キャッシュフロー・投資家情報を一元管理できる
- 電子取引業務の要件に沿った本人確認(eKYC)、重要事項説明、契約書面交付をオンラインで完結できる
- 配当や元本償還をシステム上で自動集計し、投資家マイページで可視化できる
このような仕組みと組み合わせることで、倒産隔離スキーム特有の複雑さをシステム側で吸収し、不動産保有者は「案件の組成・物件運営」といった本質的な業務に集中しやすくなります。
不動産保有者が倒産隔離スキームを検討すべきケース
最後に、不動産保有者の立場から「倒産隔離スキームを真剣に検討した方がよい典型的なケース」を整理します。
- 自社名義で複数の収益不動産を抱えており、バランスシートの圧縮や与信枠の温存が課題になっている
- 大型の開発案件やリノベーション案件で、金融機関・外部投資家と共同で資金を組みたい
- 物件ごとにリスク・リターンを整理し、オンラインのクラウドファンディングを通じて投資家を広く募りたい
- 将来的にプロジェクト単位での売却・事業承継・再編を視野に入れており、「切り出しやすい器」を事前に作っておきたい
一方で、数千万円規模の小型案件や、少数の物件だけで完結する事業の場合は、倒産隔離スキームの設計・SPC設立・専門家報酬などのコストが重くなりやすい側面もあります。
「どの規模・どのフェーズの案件からこのスキームを使うべきか」は、会計士・税理士・弁護士といった専門家や、不特法第3号・第4号の実務に慣れたクラウドファンディング事業者と相談しながら検討することが重要です。

倒産隔離スキームは難しい専門用語に聞こえますが、要するに「自社の倒産リスク」と「物件プロジェクトのリスク」をきちんと分けて説明できる箱を作る仕組みだと理解しておくとイメージしやすいです。特に金額が大きい案件ほどメリットが出やすいので、ある程度の規模になってきた段階で、第3号・第4号に強いパートナーや専門家と一緒に具体的なスキーム設計を検討してみてくださいね
資金調達の観点で見る「小規模不特法」の利点
小規模不特法は、一般的な不動産特定共同事業よりも参入ハードルが低く、不動産保有者がスモールスタートで資金調達を行う際に非常に相性の良い制度です。特に、既存物件を活用して事業の立ち上げ資金を確保したい方や、地方の中小事業者にとっては、実務負担を抑えつつ、投資家から直接資金を募る仕組みを整えられる点が大きな魅力です。
資本金要件の緩和で参入しやすい
通常の不特法では、第1号事業に1億円、第3号事業に5,000万円と高額な資本金要件が求められます。一方、小規模不特法では資本金1,000万円から参入可能です。これにより、銀行融資に頼らずに新しい物件活用モデルを試したい事業者や、スタートアップ段階での慎重な資金計画を求める事業者にとって実現の幅が大きく広がります。
資本金要件が抑えられることで、次のような効果が期待できます。
- 許認可に向けた初期コストを削減できる
- 既存事業の規模に合わせて無理なく検討できる
- 小規模事業者でも投資家からの直接調達が可能になる
資金調達を第一の目的とする事業者にとっては、制度上のハードルが下がることで、クラウドファンディングを「実際に検討できる現実的な選択肢」へ変える力があります。
出資枠が小規模だからこその安心感と柔軟性
小規模不特法は「1人100万円」「総額1億円」という明確な上限が定められています。これは一般投資家への過度な負担を避けるための仕組みですが、事業者側にとってもメリットが大きい制度設計です。
- 比較的早い資金調達を実現しやすい
- 小規模案件に適した資金量でファンドを組成できる
- 投資家保護の枠が事業者への信頼形成につながる
特に、初めて不動産クラウドファンディングを活用する事業者にとっては、この「小さく始められる」という制度が、事業リスクを抑えながらスムーズに運営経験を積む基盤となります。
地方不動産に適した制度背景
国が小規模不動産特定共同事業を創設した目的のひとつが「地方不動産の資金循環促進」です。大都市圏ほど資金の流れが強くない地域でも、クラウドファンディングを通じて投資家の資金を集められるようにするため、小規模制度が整備されました。
そのため、地方物件を保有する事業者にとっては強力な追い風となります。
- 小規模なアパート・戸建・店舗などでもファンド化しやすい
- 空き家・空き店舗の再生事業と相性が良い
- 地域の収益不動産の活用モデルとして自治体との連携も進めやすい
人口減の地域では、銀行融資だけに依存しない資金調達手段を確保することが重要であり、小規模不特法はその環境整備に直結する制度となっています。
スモールスタートで資金調達したい事業者に向く理由
クラウドファンディング事業の本格展開を目指していても、初期から大規模なスキーム構築を行うのは負担が大きく、実務や法務体制の整備にも時間がかかります。小規模不特法は、事業者にとってリスクが抑えられた段階的な成長ステップを用意してくれます。
小規模不特法がスモールスタートに向く理由
- 初期投資と運営コストを最小限に抑えられる
- 小規模ファンドによる経験獲得で、将来的な第1号・第3号取得を視野に入れられる
- 投資家に対して実績を積み重ね、信頼を形成できる
- 物件単位での資金調達設計がしやすく、資金用途を明確化しやすい
特に、既存物件のバリューアップ資金や、部分的な改修・再生プロジェクトなど、銀行融資とは異なる柔軟な用途での資金調達に向いています。事業規模を一気に拡大したくない事業者でも、クラウドファンディングという新たな収益モデルを無理なく取り入れられます。

小規模不特法は、小さく始めながら必要な資金だけを確実に集められる“段階的成長のための制度”と言えますよ。資金調達を急ぎつつもリスクは抑えたい、そんな不動産保有者にとってとても扱いやすい仕組みです
不特法に基づくクラウドファンディング運営で必要な準備
不動産クラウドファンディングの運営には、不特法で定められた法的要件と、投資家保護の観点で求められる運用体制を整えることが欠かせません。ここでは、不動産保有者が資金調達のために自らクラウドファンディング事業を立ち上げる場合、どのような準備が必要になるのかを、実務目線で整理します。
事業計画と資金使途の明確化
クラウドファンディングは物件単位での資金調達が基本となるため、事業計画の精度がそのまま審査の通りやすさや投資家からの信頼に直結します。
投資家への説明責任を果たすためにも、次の点を整理しておくことが重要です。
- 調達する資金の使途(取得・改修・運転資金など)
- 想定収益の根拠(賃料相場・販売想定・稼働率等)
- 運用期間と出口戦略(売却見込み、再調達計画)
- リスク要因と回避策
不特法の審査では、事業計画の合理性や、資金使途が不動産価値に比して過大でないかどうかも確認されます。
電子取引業務に対応するシステム体制
オンライン完結型の投資募集を行う場合は、不特法の「電子取引業務」ガイドラインに沿ったシステムが必須です。
求められる要件は多岐にわたり、一般的なECサイトや会員サイトよりも高度です。
電子取引業務で求められる主なシステム要件
- セキュリティ対策
- 不正アクセス防止、アクセス制御、ログ管理、脆弱性への定期対応
- 情報管理体制
- 個人情報保護とデータ暗号化、バックアップ体制
- システム障害時の対応
- 復旧手順、監視体制、行政への報告フロー
- 外部委託管理
- 開発・運用会社に対する監督と評価
- 顧客財産の保護
- 出金先口座の名義確認、振込先変更時の厳格な認証
投資家保護の観点から、システム要件は厳格に定められているため、専門のクラウドファンディングシステム会社と連携するケースが一般的です。
業務管理者の選任と必要資格の整備
不特法では、事務所ごとに最低1名の「業務管理者」を配置することが義務付けられています。
業務管理者には一定の実務経験や資格が求められるため、準備に時間がかかる場合もあります。
主な要件
- 不特事業の実務経験3年以上、または指定資格の保有
- 業務管理者講習の修了
- 宅建業免許と財務基盤の整備
指定資格には以下が含まれます。
- ARESマスター
- 不動産コンサルティングマスター
- ビル経営管理士
- 宅地建物取引士(補完的資格として活用)
小規模不特法での参入でも、業務管理者の確保は避けられないため、早めの人材確保が重要です。
契約書・約款・重要事項説明書の整備
投資家に交付する書面(契約成立前書面、成立時書面など)はすべて不特法の規定に沿った内容で作成する必要があります。
特にクラウドファンディングの場合、書面交付は電子データで行うため、次の点が必須になります。
- 契約書式のリーガルチェック
- 電磁交付の仕組み(ダウンロード通知機能など)
- クーリングオフ期間の起算日を特定するシステム機能
- 重要事項のオンライン閲覧環境の整備
契約書作成は専門性が高く、法務・行政書士・弁護士との連携が重要です。
投資家審査と内部管理体制の構築
金融商品に近しい性格を持つため、投資家保護のための審査体制と内部統制の整備が求められます。
審査部門は営業部門から独立している必要があり、次の点がチェックされます。
- 投資家の適合性審査(属性・投資経験・資産状況)
- 反社チェック、本人認証(eKYC)
- 審査の透明性と記録の保存
- 審査結果のウェブ上における公開(概要の開示)
内部管理体制が弱い場合、許可取得の段階で改善指導が入ることが多いため、準備なしでの参入は困難です。
分別管理と資金の預託ルールの整備
クラウドファンディングでは、投資家から預かった資金と事業者の資金を厳密に分けて保管する必要があります。
不特法では、以下が義務化されています。
- 投資家資金と自己資金の完全分別管理
- 預託金の状況通知(少なくとも3ヶ月に1回)
- 送金フローの明確化
- 出資金の受け入れ先金融機関の管理
資金管理は監督官庁からの指導も厳しいため、銀行との連携体制構築が不可欠です。
専門家・外部パートナーとの連携
不特法参入は、不動産・金融・ITが交差する高度な領域であり、自社のみでは対応が難しいケースがほとんどです。
次の分野を外部パートナーとして確保すると運営が安定します。
- 法務(弁護士、行政書士)
- システム開発会社(電子取引業務対応)
- 税務・会計専門家
- 不動産評価・デューデリジェンス専門家
外部パートナーとの連携は事業運営の信頼性にもつながり、投資家の募集にも良い影響があります。

不特法に基づくクラファン運営は、法律・IT・不動産の三つを同時に満たす準備が必要になります。最初は難しく感じても、一つずつ体制を整えていけば実現できますので、焦らず丁寧に進めてみてくださいね
不動産保有者がクラウドファンディングで資金調達するメリット
不動産クラウドファンディングは、不動産を保有している事業者が「銀行融資以外の調達ルート」を確保するうえで、極めて有効な選択肢です。特に、不特法を活用したスキームは投資家保護の仕組みが整っており、資金提供者が集まりやすい点で資金調達の成功率を高めます。ここでは、資金調達を目的とする不動産保有者にとっての実務的・経営的なメリットを整理します。
銀行融資に依存しない柔軟な資金調達ができる
クラウドファンディングは、金融機関の与信審査とは別の軸で資金が集まるため、銀行融資の枠に左右されにくいことが最大の特徴です。
過去の収支、担保余力、返済比率など、融資審査でネックになりやすい要素があっても、投資家にとって魅力的なプロジェクト設計ができれば資金が集まる可能性があります。融資枠を温存したい場合にも有効です。
物件単位で完結するため、既存の法人財務に影響が出にくい
クラウドファンディングは「物件ごとのプロジェクト」として募集が行われるため、法人全体のバランスシートを圧迫しない点が支持されています。
特に、
- 既存事業とは切り離したい
- 資産入替を検討したい
- 追加投資だけを独立して調達したい
といったケースでメリットが大きく、資金調達の柔軟性が高まります。
SPC(特別目的会社)を用いる特例事業スキームを選択すれば、倒産隔離によって法人本体のリスク切り分けが可能となり、経営上の安定性も確保しやすくなります。
投資家向けのリターン設計を柔軟に最適化できる
クラウドファンディングでは、投資家のニーズに合わせたリターン設計が可能です。
例えば、
- 配当重視型
- 売却益重視型
- 安定収益を求める短期運用型
- 成長性を打ち出す中長期運用型
など、プロジェクトの内容に応じた設計が自由にできます。銀行融資のように返済期間が固定されないため、キャッシュフロー戦略に合わせた設計ができる点も大きなプラスです。
投資家の共感を得やすく、地方物件でも資金が集まりやすい
不動産クラウドファンディングでは、投資家がプロジェクトの背景や再生ストーリーに共感して出資するケースが多いことが特徴です。
特に、
- 地域の空き家再生
- 古民家ホテル化
- 地方の賃貸住宅の改修
- 小規模商業施設の再生
といった“地域経済に価値のある”プロジェクトは、都市部の投資家から出資が集まりやすい傾向が見られます。
銀行融資では評価されづらい案件でも、クラウドファンディングなら十分に資金需要を満たせる可能性があります。
調達だけでなく、物件の価値向上・長期戦略にも好影響
クラウドファンディングで資金を集めると、投資家への定期報告や運営状況の開示が求められます。この運営体制を整える過程で、物件管理・経営管理の精度が上がりやすく、結果として物件価値が高まるケースもあります。
さらに、複数回のファンド実績を積み上げると、
- 投資家からの信頼性向上
- プロジェクトの継続調達の成功率アップ
- 企業ブランド価値の向上
につながります。
資金調達の手段にとどまらず、中長期の不動産戦略全体に良い影響を与える点は、銀行融資にはない強みです。
スモールスタートで試験的に調達できる
小規模不特法(1人100万円、総額1億円以内)を利用すれば、小規模物件や試験的プロジェクトで調達の可能性を探ることができます。
- まずは小規模
- 実績を積んでから大型化
というステップが踏めるため、初めて資金調達を行う不動産保有者でも導入しやすい制度です。

不動産クラウドファンディングは、銀行融資とは違う発想で資金を集められる仕組みです。小さく始めて実績を積み、次のプロジェクトにつなげる使い方もできますよ。資金調達の選択肢を広げたい方には、とても相性の良い手法だと思います
不動産保有者が失敗しないための注意点
不動産クラウドファンディングを活用した資金調達は、仕組みを正しく理解し、適切な準備を行えば強力な資金戦略になります。しかし、制度・運営・法務・開示の各面で重要な注意点を押さえないまま進めると、後から大きなトラブルに発展するリスクがあります。不動産保有者が失敗しないために必ず確認すべきポイントを整理します。
ファンド組成コストと業務負担の見極め
クラウドファンディングは“少額から投資家を集められる”点が強みですが、その裏側では多くの事務・法務手続きが必要です。
特に初めて取り組む場合、運営コストと必要工数を正確に把握していないことが失敗の原因になりやすいです。
考慮すべき主なコストは次の通りです。
- 契約書・重要事項説明書の作成費用
- 電子取引業務に対応したシステム導入費用
- 運用レポート作成や投資家対応に関する人的コスト
- SPCを使う場合の設立費・会計処理費用
- 不動産の評価・デューデリジェンス費
これらは案件の規模に関係なく発生するため、「資金調達額に対してコストが重くなる」ケースが発生します。収支モデルを作成し、コストを適切に織り込んだ設計が欠かせません。
不特法に違反しない運営体制の構築
不動産クラウドファンディングは、不特法に基づく厳格な運営が求められます。特に電子取引業務では、書面交付・審査体制・情報管理への高い遵守義務が課されています。
違反した場合、業務停止や許可取消につながる重大なリスクがあるため、最低限次の点は確実に整える必要があります。
- 審査部門を含む独立した内部管理体制
- 電子情報処理組織(システム)の管理規程
- 重要事項説明や契約書面の適切な電子交付
- 投資家との分別管理・クーリングオフ対応
- 適切な広告・勧誘基準の順守
これらは法令上の義務であり、違反すれば罰則だけでなく投資家からの信用失墜にも直結します。
情報開示の正確性と継続性
情報開示の不備は最もトラブルにつながりやすい領域です。特に運用中のレポートや重要変更事項の通知が遅れると、投資家からの信頼を失うだけでなく、監督官庁からの指導や行政処分の対象にもなります。
注意すべき開示項目の例は以下です。
- 事業計画に変更があった場合の迅速な開示
- 運用状況・配当見込みの定期レポート
- 利害関係人取引(関連当事者)の開示
- 不動産価値の下落・空室率上昇などのネガティブ情報
リスク情報も含め「隠さず、正確に、タイムリーに」開示することが必須です。
外部パートナー選定の品質が事業の成否を決める
不動産クラウドファンディングは、不動産だけでなくシステム、法律、税務、会計など複数の専門分野が関わる複雑な事業です。
外部パートナーの経験やクオリティが低いと、ファンド設計の不備や違法リスクに直結します。
信頼できるパートナーを選ぶ基準として、次の観点を持つと失敗を防ぎやすくなります。
- 不特法案件の実績がある法律事務所・税理士
- 電子取引業務に精通したシステム会社
- ファンド運営の実績を持つ不動産管理会社
- SPC運営に慣れた会計事務所
特にシステム会社の品質は投資家保護に直結するため、安さだけで選ぶのは危険です。
投資家へのリターン設計の“過剰さ”に注意
資金調達を目的にリターンを高く設定しすぎると、実際の運用とのギャップが生じ、結果的に投資家からのクレームや信頼低下につながります。
よくある失敗例として次があります。
- 想定利回りが高すぎて運用中のキャッシュフローが逼迫する
- リフォーム費用・売却期間を楽観的に見積もってしまう
- 空室率・修繕リスクの想定が甘い
- 出口戦略(売却時期・価格)が未確定のままプロジェクトを開始する
出資者は配当遅延に敏感なため、保守的かつ実現可能なリターン設計が重要です。

慎重に準備すれば安全に活用できます。無理のない計画と信頼できるパートナー選びを心がければ、不動産クラウドファンディングは強力な資金調達手段になりますよ
| 順位 | 商品名 | 会社名 | 特徴 | 案件数 | 直近10件平均利回り | 直近10件直近最低利回り | 直近10件直近最高利回り | 直近10件募集割合平均 | 優先劣後方式 | 最低投資金額 | 募集方法 | 組合契約 | 物件の種類 | 優遇サービスあり | 物件の開示情報 | 出金手数料 | 運用レポートの共有あり | 運営会社設立年月 | 運営会社資本金 | 上場 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | COZUCHI(コズチ) | LAETOLI株式会社 | 投資募集のチャンスは業界上位。投資デビューに適した候補 | 139件 | 5.75% | 4.00% | 6.50% | 337.36% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 月1回まで無料(それ以降は330円) | ○ | 1999年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 2位 | CREAL(クリアル) | クリアル株式会社 | 募集口数が多く、新規案件の供給量も豊富 | 139件 | 5.13% | 0.00% | 6.50% | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス、保育所、学校、宿泊施設 | ○ | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 105円(楽天銀行の場合)、150円(楽天銀行以外で3万円未満の場合)、229円(楽天銀行以外で3万円以上の場合) | ○ | 2011年 | 1,273,520,500円 | ○ | 公式サイト |
| 3位 | 利回りくん | 株式会社シーラ | 年間新規案件数が安定。募集口数も一定水準 | 148件 | 4.71% | 3.00% | 6.00% | 89.80% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2010年 | 446,522,660円 | ○ | 公式サイト |
| 4位 | Rimple(リンプル) | プロパティエージェント株式会社 | 新規案件が充実。劣後出資割合の高い案件が多い | 112件 | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 270.75% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、事業内容 | 無料 | ○ | 2004年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 5位 | TECROWD(テクラウド) | TECRA株式会社 | 新興国不動産への投資が可能。高利回り案件が多い | 90件 | 10.40% | 8.50% | 12.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、オフィス | ○ | 住所、運営会社、財務情報、面積、事業内容 | 無料(楽天銀行)、振込手数料(楽天銀行以外) | ○ | 2001年 | 156,600,000円 | × | 公式サイト |
| 6位 | TSON FUNDING(ティーソン) | 株式会社TSON | 年間案件数が最多クラス。リスク軽減案件も豊富 | 230件 | 5.64% | 5.50% | 5.80% | 98.90% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、事業内容 | 無料(匿名組合ファンド)、振込手数料(任意組合ファンド) | ○ | 2008年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 7位 | 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス | 運営会社の信頼性が高く、新規案件も安定供給 | 109件 | 5.90% | 3.50% | 12.00% | 728.48% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛) | ○ | 1996年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 8位 | FUNDROP(ファンドロップ) | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 | 劣後出資割合の高い案件が多いが、投資機会は少なめ | 39件 | 5.66% | 5.50% | 5.80% | 119.09% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 52円(楽天銀行)、150円(他の金融機関で3万円未満)、229円(他の金融機関で3万円以上) | ○ | 2013年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 9位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 穴吹興産株式会社 | 低リスク案件が多いが、投資の機会は限定的 | 43件 | 3.25% | 3.00% | 5.00% | 99.98% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設 | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 1964年 | 755,790,000円 | ○ | 公式サイト |
| 10位 | ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 | 劣後出資割合の高い案件が多く、運営も安定傾向 | 10件 | 4.00% | 3.90% | 4.30% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(その他の金融機関) | ○ | 1991年 | 389,820,000円 | × | 公式サイト |
| 11位 | property+(プロパティプラス) | 株式会社リビングコーポレーション | 募集口数は平均的だが、新規案件がなかった点が課題 | 34件 | 3.20% | 3.00% | 3.40% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2015年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 12位 | ASSECLI(アセクリ) | 株式会社エボルゾーン | 高利回り案件が多いが、新規提供数は限られる | 45件 | - | 0.00% | 0.00% | 105.85% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 事業内容 | 無料 | × | 2011年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 13位 | LIFULL(ライフル) | 株式会社LIFULL | 大手不動産会社のクラウドファンディング。厳選された物件 | 3件 | 5.83% | 5.50% | 6.00% | 105.67% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション・グループホーム | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | × | 1997年 | 9,723,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 14位 | みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント | 」「公的年金に合わせた2ヵ月ごとの分配金」が特徴の、不動産クラウドファンディング | 290件 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、物件種別、アクセス、構造、総戸数、家賃保証有無 | 無料 | × | 2016年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 15位 | 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス | 高水準の利回り案件が豊富で、投資のチャンスも平均以上 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行あて) | ○ | 2023年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 16位 | らくたま | 株式会社日本保証 | リスクを抑えつつ高いリターンを狙える案件が多く、供給数も充実 | - | - | - | - | - | ○ | 10000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、商業施設、オフィス | ○ | 築年数、住所、面積 | 無料(GMOあおぞらネット銀行) | × | 2008年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 17位 | GALA FUNDING(ガーラ ファンディング) | 株式会社FJネクストホールディングス | 運営基盤が堅実で、劣後出資割合が高めの安心感ある案件が中心 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛て) | ○ | 1980年 | 2,774,400,000円 | ○ | 公式サイト |
| 18位 | トモタク | 株式会社イーダブルジー | 新規募集数は業界トップクラスで、高利回り案件が目立つ | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、オフィス | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 1回のみ無料(125円(GMOあおぞらネット銀行)、250円(GMOあおぞらネット銀行以外)) | ○ | 2009年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 19位 | LSEED(エルシード) | 株式会社LSEED | リスクとリターンのバランスは良好だが、案件数はやや少なめ | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、面積、事業内容 | 不明 | × | 1999年 | 706,139,500円 | ○ | 公式サイト |
| 20位 | トーセイ不動産クラウド | トーセイ株式会社 | 1万口超の大型案件が主体で、年間の提供数は限定的 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、129円(その他金融機関) | ○ | 1950年 | 6,624,890,000円 | ○ | 公式サイト |
| 21位 | KORYO Funding(コウリョウ ファンディング) | 株式会社興陵 | 安定したバランス型案件が揃う一方で、全体の件数は少ない | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容 | 無料 | × | 1981年 | 371,980,200円 | ○ | 公式サイト |