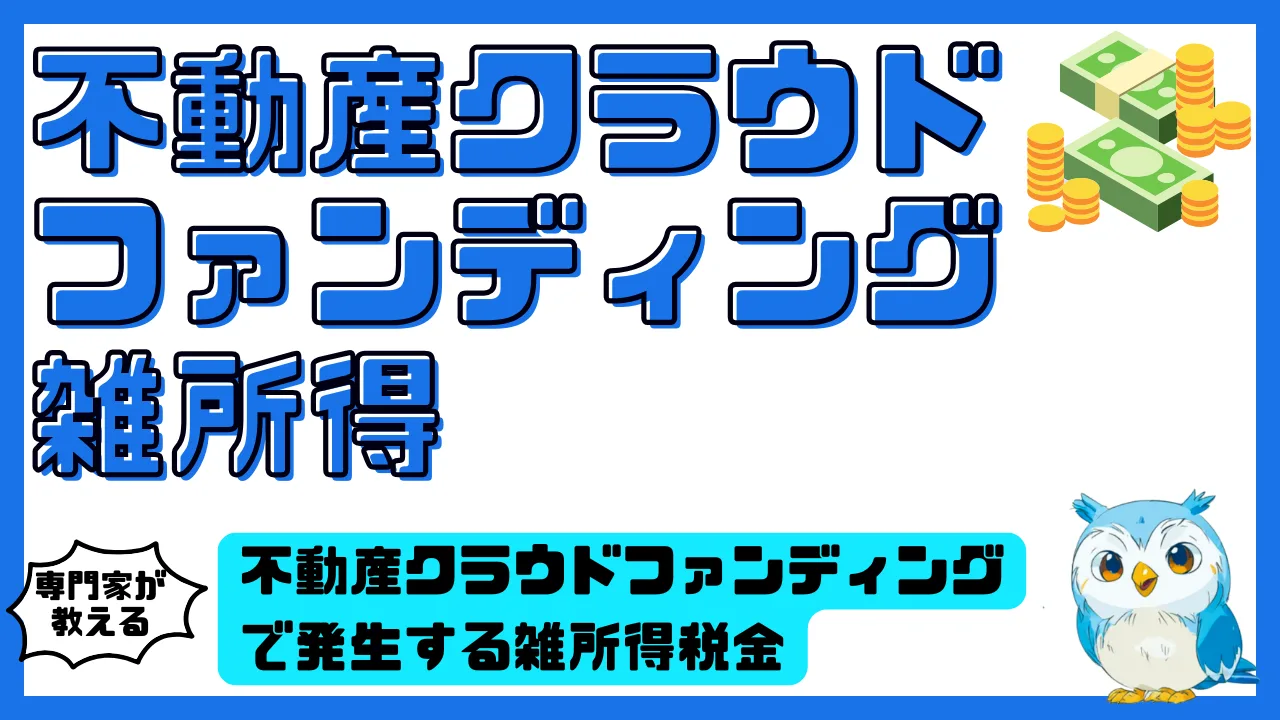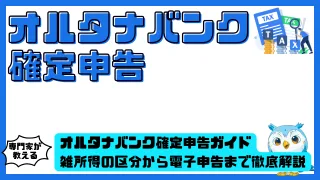本ページはプロモーションが含まれています。
目次
不動産クラウドファンディングの分配金は雑所得に該当する理由
不動産クラウドファンディングで得られる分配金は、原則として「雑所得」に分類されます。これは、投資家が実際に不動産を所有せず、クラウドファンディング事業者との契約形態が「匿名組合契約」であることに起因します。
匿名組合型の仕組みと税務上の位置づけ
多くの不動産クラウドファンディングは、金融商品取引法に基づく「匿名組合型」のスキームを採用しています。投資家は出資金を事業者に預け、事業者が不動産の取得・運用を行い、その成果に応じて分配を受け取ります。
この場合、投資家は不動産の所有権を持たず、あくまで「事業の成果に応じた利益分配を受ける立場」となります。したがって、不動産所得や事業所得ではなく、給与や年金と同じ「雑所得」に区分されます。
税務上の根拠として、所得税法第35条における「雑所得」は、給与・不動産・譲渡などのいずれにも該当しない所得と定義されています。匿名組合型の分配金は、これらのいずれの所得にも該当しないため、雑所得に分類されるのです。
不動産所得や事業所得に該当しない理由
不動産クラウドファンディングの分配金が不動産所得に該当しないのは、投資家自身が不動産を所有しておらず、賃貸収入を直接得ていないためです。
また、事業所得に該当しないのは、投資家が自ら不動産の管理・運用を行っておらず、事業としての独立性がないためです。つまり、投資家の立場は「事業への資金提供者」であり、事業の経営主体ではありません。
この構造により、税務上は「事業参加に対する配当」として処理され、結果的に雑所得となります。
匿名組合型と任意組合型の税務上の違い
一方で、「任意組合型」を採用している不動産クラウドファンディングも存在します。任意組合型では、投資家が不動産の共有持分を取得し、所有者としての権利を有します。この場合、得られる収益は不動産所得として扱われ、損益通算などの節税効果が期待できます。
しかし、任意組合型は契約リスクや損失負担の範囲が広く、一般的なクラウドファンディングでは採用が少ないのが現状です。
他の所得区分との比較でみる位置づけ
不動産クラウドファンディングの分配金を正しく理解するためには、他の所得区分と比較することが重要です。
- 譲渡所得:資産を売却して得た利益に対して課税。クラウドファンディングでは対象外。
- 配当所得:株式の配当などに該当。匿名組合の分配金はこれに当たらない。
- 不動産所得:不動産の賃貸や売却益による所得。投資家が所有権を持たないため非該当。
- 雑所得:上記のいずれにも属さない所得。匿名組合型の分配金が該当。
このように、不動産クラウドファンディングの分配金は、投資家が間接的に得る報酬であり、税法上は「雑所得」として処理されるのが一般的です。

つまり、不動産クラウドファンディングの分配金が雑所得に分類されるのは、投資家が不動産の所有者ではなく、あくまで事業成果への出資者だからです。税務上の整理を正しく理解することで、確定申告や節税判断をより的確に行えるようになります。
雑所得として扱われた場合の課税の基本ルール
不動産クラウドファンディングで得た分配金が「雑所得」に分類される場合、その課税方法は給与所得や事業所得とは異なるルールが適用されます。ここでは、投資家が理解しておくべき課税の仕組みや確定申告の基準、所得合算時の注意点について詳しく解説します。
源泉徴収の仕組みと税率
不動産クラウドファンディングの分配金は、運営会社から支払われる際に 20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%) が源泉徴収されます。
この時点であらかじめ税金が差し引かれているため、一定の条件を満たさない限り確定申告は不要です。
例として、5万円の分配金を受け取る場合には「5万円 × 20.42% = 1万210円」が自動的に控除され、手取りはおよそ3万9,790円となります。
この源泉徴収により、投資家が税務処理を行う手間が省かれる反面、所得全体に応じた税率とのズレが生じる場合もあります。
年間20万円の壁と確定申告の要否
不動産クラウドファンディングの収益を含む 雑所得の合計が年間20万円を超える場合、原則として確定申告が必要になります。
この「20万円ルール」はサラリーマンなど給与所得者に適用される基準であり、副収入が少額であれば申告を省略できる仕組みです。
ただし、以下のような場合には20万円以下でも申告が必要になることがあります。
- 個人事業主やフリーランスとして活動している場合
- 年収2,000万円を超える給与所得者
- 医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税などの控除申請を行う場合
これらに該当する場合、源泉徴収の有無にかかわらず確定申告が求められます。
他の所得との合算による総合課税
雑所得は総合課税の対象です。つまり、給与所得や事業所得など他の所得と合算して、課税所得全体に対して税率が決まります。
税率は累進課税で、所得が増えるほど段階的に上がっていきます。
| 課税所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ~195万円 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超~695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
給与所得者が不動産クラウドファンディングで追加収入を得ると、課税所得が合算されるため、結果的に税率が上がるケースもあります。
特に所得税率が20%未満の層(課税所得695万円未満)では、源泉徴収で多く税金を払い過ぎている可能性があり、確定申告で還付を受けられるケースもあります。
住民税の申告義務と注意点
所得税とは別に、住民税の申告も必要です。
源泉徴収済みでも、住民税については自治体ごとに取り扱いが異なるため、雑所得の金額を申告する必要があります。
申告を怠ると、後日自治体から追加納税の通知が届くこともあるため注意しましょう。
また、副業など複数の収入源がある場合は、「特別徴収」から「普通徴収」への変更を選ぶことで勤務先に副収入が知られにくくなります。申告書作成時に忘れずに選択しておきましょう。
課税の全体像を整理すると
- 不動産クラウドファンディングの分配金には、支払時点で20.42%が源泉徴収される
- 年間の雑所得が20万円を超えると確定申告が必要
- 雑所得は総合課税で、他の所得と合算して税率が決まる
- 所得が少ない場合は還付の可能性、所得が高い場合は追加納税の可能性
- 住民税の申告は自治体ごとに必要
これらを正しく理解することで、無駄な納税や申告漏れを防ぎ、効率的な税務管理が可能になります。

雑所得の課税はシンプルに見えて、実際は「他の所得」との兼ね合いで税負担が変わります。自分の所得構成を正確に把握し、確定申告を上手に活用することが、賢い投資家への第一歩ですよ
確定申告が必要となる典型的なケース
不動産クラウドファンディングで得た分配金は「雑所得」に分類されます。多くの投資家にとって、確定申告の要否を判断するポイントは曖昧になりがちですが、典型的なパターンを理解しておくことで、余分な納税や申告漏れを防ぐことができます。
雑所得の合計が年間20万円を超える場合
会社員など給与所得者に最も多いのがこのケースです。
不動産クラウドファンディングによる分配金に加え、原稿料・講演料・ネット副業・FX・暗号資産などの収入を合算し、年間の雑所得合計が20万円を超えると確定申告が必要になります。
たとえば分配金15万円、副業収入10万円で合計25万円なら申告対象です。源泉徴収で税金が差し引かれていても、20万円を超えると申告義務が生じるため注意しましょう。
元々確定申告が必要な人
雑所得の金額に関わらず、もともと確定申告の義務がある人もいます。
個人事業主やフリーランスはもちろん、年収2,000万円を超える給与所得者も対象です。
また、ふるさと納税・医療費控除・住宅ローン控除などを利用するために確定申告を行う人も、雑所得を含めて申告する必要があります。「少額だから不要」と判断せず、必ず合算して記載しましょう。
還付申告が有利になる場合
確定申告は「義務」ではなく「メリット」になることもあります。
不動産クラウドファンディングの分配金には20.42%の源泉徴収税率(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が適用されていますが、課税所得が695万円未満の人は実際の税率が20%未満になるため、払い過ぎた分が還付されるケースがあります。
たとえば年収300万円の会社員が分配金10万円を受け取った場合、申告により数千円単位で還付される可能性があります。確定申告を行うかどうかは「税率の差」に着目して判断すると良いでしょう。
住民税の申告が必要なケース
雑所得が20万円未満で確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。
自治体によっては、雑所得の有無を住民税申告書で報告する義務があるため、少額でも自治体の公式案内を確認してください。特に副業収入や分配金がある場合、申告漏れがあると後から通知が届くこともあります。
契約形態による違いに注意
不動産クラウドファンディングは「匿名組合型」と「任意組合型」に分類され、税務上の扱いが異なります。
多くのサービスは匿名組合型で、分配金が雑所得扱いとなります。一方、任意組合型は不動産の所有権を持つため、不動産所得として扱われ、損益通算が可能になることもあります。
契約書に明記された「組合型」の種類を確認し、どの税区分に該当するかを把握しておきましょう。

不動産クラウドファンディングの税金は、「20万円ルール」だけで判断してはいけません。年収・契約形態・還付の有無・住民税の仕組みなど、条件によって結果が大きく変わります。自分がどのケースに該当するかを整理し、必要な書類を早めに準備しておくことが大切です。
雑所得として申告した場合の節税・還付の可能性
不動産クラウドファンディングの分配金は「雑所得」として扱われ、原則として20.42%(所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されます。しかし、確定申告を行うことで、払い過ぎた税金が還付される可能性があります。とくに課税所得が一定水準以下の投資家や、他の所得とのバランスによっては節税効果を得られるケースもあります。
還付が発生するケースの基本構造
源泉徴収はあくまで一律20.42%の仮払いです。確定申告により、実際の税率がこれより低ければ、その差額が還付されます。たとえば課税所得が695万円未満の人は所得税率が20%以下のため、申告によって数千円から数万円単位の還付を受け取れる場合があります。
さらに、給与所得者で源泉徴収済の給与と雑所得を合算しても、全体の所得税率が低く抑えられる場合には、払い過ぎた分の税金が戻ることになります。還付金を得るためには、確定申告書に不動産クラウドファンディングの分配金明細を添付し、総合課税として計算する必要があります。
他の雑所得との損益通算の可能性
不動産クラウドファンディングの収益が雑所得である以上、同じ雑所得区分に属する他の収入・損失と通算できる場合があります。例えば以下のような組み合わせです。
- 仮想通貨やFX取引での損失
- アフィリエイト収入や副業収入との通算
- その他のクラウドファンディングや貸付投資での損失
ただし、税法上「業務としての雑所得」と「その他の雑所得」では扱いが異なることがあり、損益通算が認められないケースもあります。損益通算を行う場合は、同一の所得区分内で行うことが条件であり、証憑類(支払調書や取引明細)を保存しておくことが重要です。
控除や特例を活用した節税方法
確定申告時には、次のような所得控除を組み合わせることで課税所得を減らすことができます。
- 基礎控除(48万円)
- ふるさと納税による寄附金控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
これらの控除を最大限活用することで、雑所得が一定額あっても課税対象から除外される可能性があります。特に会社員で給与所得以外の収益が少ない場合、控除を組み合わせれば税負担を大幅に減らすことが可能です。
法人化による税率引き下げの検討
不動産クラウドファンディングで安定的に利益を得る場合、法人を設立して投資を行うことで節税効果を得られるケースがあります。法人税率は最大でも23.2%(中小法人の年800万円以下の利益部分は15%)と、個人の所得税率(最大45%)より低いためです。
法人化することで、以下のような節税余地も広がります。
- 経費計上による課税所得の圧縮
- 家族への役員報酬支払いによる所得分散
- 利益の繰越や設備投資による翌期の減税
ただし、設立コストや会計処理の負担が生じるため、投資額や運用規模に応じて専門家への相談が望ましいです。
節税を目的としたリスク管理のポイント
節税・還付を狙う際は、次の点に注意する必要があります。
- 還付対象になるかは課税所得の総額次第であり、一律ではない
- 雑所得は総合課税のため、他の所得と合算して税率が上がる可能性がある
- 損益通算を行う場合は「雑所得内」での整合性が必要
- 法人化は長期的な利益見込みがある場合にのみ有効
節税や還付を得るには、確定申告の手間を惜しまず、控除や損益の管理を継続的に行うことが鍵となります。

節税や還付は「うまくやれば得する」ものではなく、正しく手続きを行えば自然と生まれる結果です。無理に節税を狙うより、自分の所得構造を理解しておくことが一番の防御策ですよ
匿名組合型と任意組合型を税務視点で比較
不動産クラウドファンディングでは、ファンドの契約形態によって課税区分や節税効果が大きく変わります。代表的な「匿名組合型」と「任意組合型」は、いずれも投資家が事業に出資して分配金を得る点では同じですが、法的・税務的な位置づけはまったく異なります。投資前に両者の違いを理解しておくことで、課税リスクや節税の可否を正しく判断できます。
匿名組合型:雑所得として課税されるスタンダードな形式
多くの不動産クラウドファンディングサービスが採用しているのが「匿名組合型」です。投資家は運営会社に出資し、事業の成果に応じた分配金を受け取りますが、投資家自身は不動産の所有権を持ちません。そのため、得られる収益は「不動産所得」ではなく「雑所得」として扱われます。
この仕組みの特徴は以下の通りです。
- 投資家は不動産の所有者ではなく出資者
- 分配金は源泉徴収(20.42%)済みで支払われる
- 損益通算や減価償却ができないため、節税効果は限定的
- 元本保証はないが、優先劣後構造によりリスクは抑制されている
つまり、匿名組合型は少額から投資を始めたい個人投資家向けの仕組みです。節税よりも「リスク分散」「手間の少ない運用」を重視する人に向いています。
任意組合型:不動産所得扱いで節税・相続対策も可能
一方、「任意組合型」は投資家が不動産の共有持分を直接保有する形式です。クラウドファンディング事業者と投資家が共同事業体を形成し、不動産運用による利益・損失をそれぞれの持分に応じて分配します。このため、課税区分は「不動産所得」となり、現物不動産と同じ税務処理が可能です。
任意組合型の特徴は次の通りです。
- 投資家が不動産の所有権(持分)を取得
- 収益は不動産所得として申告
- 減価償却や損益通算が可能(事業所得や給与所得との通算も)
- 相続時には評価額の圧縮効果が得られる場合がある
- 優先劣後方式がないため、リスクは高め
不動産所得となることで、他の所得(給与・事業など)と損益通算ができ、節税や還付のチャンスが広がります。加えて、資産としての評価額を調整できるため、相続税対策にも活用できる点が魅力です。ただし、匿名組合型に比べてリスク負担が大きく、投資額も比較的高額になりがちです。
税務上の主な違いを比較
| 項目 | 匿名組合型 | 任意組合型 |
|---|---|---|
| 所有権 | なし | あり(持分所有) |
| 所得区分 | 雑所得 | 不動産所得 |
| 源泉徴収 | あり(20.42%) | なし(自己申告) |
| 損益通算 | 不可 | 可能 |
| 節税効果 | 限定的 | 高い(減価償却・損益通算可) |
| 相続税対策 | 不可 | 可能 |
| リスク | 低め(優先劣後あり) | 高め(無限責任の可能性) |
| 投資ハードル | 低い(1万円〜) | やや高い(数十万円〜) |
投資家が選ぶ際の実務的ポイント
匿名組合型は、税務手続きの煩雑さがなく、源泉徴収済みで簡便に運用できる点がメリットです。確定申告の必要性が低く、所得が20万円以下であれば申告不要となるケースもあります。一方、任意組合型は税務の取り扱いが複雑な反面、損益通算や相続対策など、総合的な資産戦略に活かせるスキームです。
IT投資家としては、
- 税務処理を簡略化したい場合 → 匿名組合型
- 中長期的に資産形成・節税効果を狙いたい場合 → 任意組合型
という棲み分けで考えると良いでしょう。

匿名組合型は「シンプルで手間のない投資」、任意組合型は「税務戦略を意識した本格投資」になります。どちらを選ぶかは、リスク許容度と税務知識のバランス次第ですよ
IT投資家が押さえるべき確定申告の手続きと流れ
不動産クラウドファンディングで得た分配金が雑所得に該当する場合、一定条件を満たすと確定申告が必要になります。とくにIT投資家の場合、複数の収入源やデジタル資産を持つことが多いため、申告漏れを防ぐには手続きの全体像を正確に把握しておくことが大切です。
確定申告の基本ステップ
不動産クラウドファンディングの雑所得を申告するための流れは、次の5ステップで整理できます。
- 所得の確認と区分の整理
まず、1年間に得た分配金の総額を確認します。クラウドファンディング運営会社から送付される「支払調書」や「分配金明細書」に記載された金額をもとに、他の雑所得(副業、FX、暗号資産など)と合算して集計します。 - 必要書類の準備
確定申告に必要な書類を整理します。主なものは次の通りです。
- 不動産クラウドファンディング運営会社からの支払調書
- 源泉徴収票(給与所得がある場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 控除証明書(生命保険料控除、小規模企業共済など)
- 還付金受取用の銀行口座情報
- 所得と控除の入力(e-Taxまたは書面)
e-Taxを利用すれば、国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」で自動計算が可能です。 雑所得は「収入金額−必要経費=所得金額」で算出します。経費として認められるのは、取引手数料、通信費、クラウドファンディング関連の書籍購入費など合理的な範囲に限られます。 - 提出と納付または還付申請
申告書を電子提出(e-Tax)または郵送で税務署に提出します。還付金が発生する場合は、申告から約1〜1.5ヶ月で指定口座に振り込まれます。追加納税が必要な場合は、納期限(通常3月15日)までに納付します。 - 住民税の申告と翌年度対応
所得税の確定申告をすれば、原則として住民税も自動で計算されます。ただし、副業の収入を会社に知られたくない場合は「住民税は自分で納付(普通徴収)」を選択する必要があります。
e-Taxを使う際の実務ポイント
e-Taxを利用する場合、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式があります。スマートフォン対応も進んでおり、クラウドファンディング運営会社から届く電子データをそのまま入力できるケースもあります。
また、雑所得が複数ある場合は、ファンド別・プラットフォーム別に収支を整理しておくと、次年度以降の申告がスムーズです。
副業収入との合算シミュレーション例
たとえば、給与所得が500万円、クラウドファンディング分配金が30万円、仮想通貨収益が10万円の場合、雑所得は40万円となり確定申告が必要です。
この場合、所得控除(基礎控除48万円)を適用すると、課税所得額は(500万円+40万円−48万円)=492万円となり、税率は20%帯に該当します。源泉徴収済みの20.42%との差額によっては、還付を受けられる可能性もあります。
よくある申告ミスと対策
- 分配金の源泉徴収後金額をそのまま入力してしまう
→「源泉徴収前の金額」で入力し、源泉徴収税額を別途記載します。 - 複数ファンドの合算漏れ
→運営会社ごとの明細を年度単位でまとめておくとミス防止になります。 - 還付口座の誤入力
→口座番号・名義のチェックを最後に必ず行いましょう。

確定申告は手間に感じるかもしれませんが、一度流れを理解しておくと翌年以降はスムーズに進められます。特にe-Taxを活用すれば自動計算や控除反映も簡単です。IT投資家としては、取引履歴や明細データをクラウド管理しておくことが最大の効率化ポイントですよ
不動産クラウドファンディングを選ぶ際に税務で確認すべきポイント
不動産クラウドファンディングは、契約形態や運用スキームによって税務処理が異なります。投資前に税務上の位置づけを理解しないまま契約すると、想定外の課税や還付の取り逃しにつながるため、税務面での確認は極めて重要です。
契約形態と課税区分の確認
最初に確認すべきは、そのファンドが「匿名組合型」か「任意組合型」かという点です。税務上の扱いが大きく異なります。
- 匿名組合型:分配金は雑所得扱いとなり、源泉徴収(20.42%)が行われます。損益通算はできず、節税効果は限定的です。
- 任意組合型:不動産所得として扱われる可能性があり、赤字による損益通算や相続時評価の引き下げなど、税務上の優遇が受けられる場合があります。
多くの不動産クラウドファンディングは匿名組合型を採用していますが、節税を意識する投資家は任意組合型ファンドの有無をチェックしておくと良いでしょう。
源泉徴収と確定申告の扱い
ファンドによっては、分配金が源泉徴収済みかどうかも異なります。源泉徴収済みならば、一定条件を満たす場合を除き確定申告は不要ですが、非課税扱いになるわけではありません。
一方、源泉徴収が行われないファンドでは、受け取った分配金を自ら確定申告する必要があります。運営会社のFAQや契約書の「税務」欄に必ず明記されていますので、事前確認を怠らないようにしましょう。
住民税の取り扱いと所在地の確認
不動産クラウドファンディングでは、投資家の居住地によって課税方法が微妙に異なる場合があります。特に地方税(住民税)は自治体ごとに取扱が違うため、居住地をまたいだ転居がある場合は注意が必要です。
また、法人化している場合は、登記所在地によって適用される地方税率や均等割が異なります。税務署だけでなく市区町村への確認も大切です。
税制改正・法制度変更のリスク
税制は毎年のように見直されるため、長期運用型ファンドでは税制改正リスクも考慮が必要です。
たとえば、復興特別所得税の延長や、雑所得区分の見直し(デジタル資産関連の扱い変更など)は、不動産クラウドファンディングにも波及する可能性があります。
契約期間が数年に及ぶ案件を選ぶ際は、運営会社がどのように税制改正リスクを開示・対応しているかを確認しておきましょう。
IT活用による税務管理の効率化
投資口座や分配履歴を自動で記録・集計できるプラットフォームを選ぶことも、実務的な税務対策です。
領収書・支払明細・源泉徴収票などをPDFでダウンロードできる環境が整っていれば、確定申告の準備が格段にスムーズになります。
また、e-Taxや会計ソフト(マネーフォワード、freeeなど)との連携があるサービスなら、複数ファンドを運用しても申告漏れのリスクを減らせます。
税務リスクを抑えるためのチェックポイント
投資家が確認すべき税務上の要点を整理すると、次のようになります。
- 契約形態(匿名組合型/任意組合型)を確認する
- 分配金が源泉徴収されるかどうかを確認する
- 居住地(または法人所在地)による税率の違いを把握する
- 税制改正・制度変更リスクへの運営会社の対応方針を確認する
- 電子明細・会計ソフト連携など、IT管理機能を備えた運営会社を選ぶ
これらを事前にチェックすることで、余計な税負担や手続きの手間を大幅に減らせます。

投資を始める前に、税金の扱いを「契約形態・源泉徴収・所在地・改正リスク」の4点で整理しておくと安心です。ITツールを活用すれば、申告もスムーズに進められますよ。
実例&ケーススタディ:雑所得として扱われた投資シナリオ
不動産クラウドファンディングで得た分配金が「雑所得」として課税された場合、所得区分や税率、確定申告の要否は投資家の収入構成によって大きく異なります。ここでは、代表的な3つのケースをもとに、課税の流れと実際の税負担の違いを整理します。
ケース1:副業収入と合わせて確定申告が必要になった会社員
年収400万円の会社員が、不動産クラウドファンディングの分配金30万円と、原稿料などの副業収入10万円を得た場合、合計40万円が雑所得に該当します。
雑所得が20万円を超えているため、確定申告の対象になります。
源泉徴収された20.42%(約6万円)はすでに納税されていますが、給与所得と合算して総合課税で再計算されるため、課税所得によっては追徴または還付が発生します。
所得控除を差し引いた課税所得が695万円未満であれば、源泉徴収よりも税率が低くなり、払い過ぎた税金の一部が還付されることがあります。
一方で、副業収入を含めた合算課税によって所得税率が上がる可能性もあるため、確定申告ソフトや国税庁のシミュレーションで確認しておくことが重要です。
ケース2:給与所得が高い層の税率上昇リスク
給与所得が400万円の会社員が、不動産クラウドファンディングで年間50万円の分配金を得た場合、合算後の課税所得が330万円を超え、所得税率は10%から20%に上昇します。
この場合、源泉徴収済みの20.42%は適正またはやや高めの水準ですが、確定申告を行うと住民税を含めてトータルの税額が増加するケースもあります。
つまり、雑所得が一定額を超えると「還付を受ける」よりも「追加納税が発生する」可能性が高くなる点に注意が必要です。
特に年収600万円〜900万円層では、雑所得を合算した課税所得が695万円を超えるラインに入りやすく、源泉徴収済みの金額よりも実際の税率が高くなるケースがあります。
節税目的であれば、青色申告が可能な副業や個人事業としての事業所得化、または資産管理法人の設立なども検討余地があります。
ケース3:法人を設立して不動産クラウドファンディングに投資した場合
個人ではなく、資産管理法人を通じて不動産クラウドファンディングに投資するケースも増えています。
法人化した場合、分配金は「法人所得」として扱われ、法人税率(年800万円以下は15%、超過部分は23.2%)が適用されます。
仮に法人で年間900万円の利益を得た場合、税額は約143万円程度にとどまり、個人の最高税率(45%)よりも大幅に軽減されます。
ただし、法人設立には設立費用や会計処理コストが発生するため、一定以上の投資規模(年間500万円〜1,000万円以上の収益)がある場合に効果が現れます。
また、法人化によって損益通算の柔軟性が高まり、他の投資損失を同一年度内で相殺できる点も大きな利点です。
節税・相続対策を兼ねた長期運用を考えるなら、専門家と相談のうえ法人投資を選択するのが現実的です。
ケース比較まとめ
| ケース | 投資額・収入構成 | 税務区分 | 申告要否 | 結果・特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 会社員+副業 | 分配金30万+副業10万 | 雑所得(総合課税) | 必要 | 年収695万円未満なら還付の可能性 |
| 高年収会社員 | 給与400万+分配金50万 | 雑所得(総合課税) | 必要 | 税率上昇で追加納税のリスク |
| 法人設立 | 分配金900万 | 法人所得 | 法人申告 | 税率軽減・損益通算が柔軟 |

投資の税務は「仕組みを理解しているか」で差が出ます。雑所得は単に課税されるだけでなく、所得構成や申告の仕方で還付を受けたり、逆に追加納税になったりします。IT投資家としては、数字をシミュレーションしながら税務戦略を組み立てるのがポイントですよ
| 順位 | 商品名 | 会社名 | 特徴 | 案件数 | 直近10件平均利回り | 直近10件直近最低利回り | 直近10件直近最高利回り | 直近10件募集割合平均 | 優先劣後方式 | 最低投資金額 | 募集方法 | 組合契約 | 物件の種類 | 優遇サービスあり | 物件の開示情報 | 出金手数料 | 運用レポートの共有あり | 運営会社設立年月 | 運営会社資本金 | 上場 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | COZUCHI(コズチ) | LAETOLI株式会社 | 投資募集のチャンスは業界上位。投資デビューに適した候補 | 139件 | 6.05% | 4.00% | 10.00% | 336.41% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 月1回まで無料(それ以降は330円) | ○ | 1999年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 2位 | CREAL(クリアル) | クリアル株式会社 | 募集口数が多く、新規案件の供給量も豊富 | 139件 | 5.67% | 5.00% | 6.50% | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス、保育所、学校、宿泊施設 | ○ | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 105円(楽天銀行の場合)、150円(楽天銀行以外で3万円未満の場合)、229円(楽天銀行以外で3万円以上の場合) | ○ | 2011年 | 1,273,520,500円 | ○ | 公式サイト |
| 3位 | 利回りくん | 株式会社シーラ | 年間新規案件数が安定。募集口数も一定水準 | 148件 | 4.26% | 3.00% | 5.12% | 76.70% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2010年 | 446,522,660円 | ○ | 公式サイト |
| 4位 | Rimple(リンプル) | プロパティエージェント株式会社 | 新規案件が充実。劣後出資割合の高い案件が多い | 112件 | 2.76% | 2.70% | 3.30% | 277.80% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、事業内容 | 無料 | ○ | 2004年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 5位 | TECROWD(テクラウド) | TECRA株式会社 | 新興国不動産への投資が可能。高利回り案件が多い | 90件 | 10.90% | 9.50% | 12.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、オフィス | ○ | 住所、運営会社、財務情報、面積、事業内容 | 無料(楽天銀行)、振込手数料(楽天銀行以外) | ○ | 2001年 | 156,600,000円 | × | 公式サイト |
| 6位 | TSON FUNDING(ティーソン) | 株式会社TSON | 年間案件数が最多クラス。リスク軽減案件も豊富 | 230件 | 5.81% | 5.50% | 6.00% | 96.30% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、事業内容 | 無料(匿名組合ファンド)、振込手数料(任意組合ファンド) | ○ | 2008年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 7位 | 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス | 運営会社の信頼性が高く、新規案件も安定供給 | 109件 | 5.90% | 3.50% | 12.00% | 728.48% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛) | ○ | 1996年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 8位 | FUNDROP(ファンドロップ) | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 | 劣後出資割合の高い案件が多いが、投資機会は少なめ | 39件 | 5.75% | 5.50% | 6.00% | 128.54% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 52円(楽天銀行)、150円(他の金融機関で3万円未満)、229円(他の金融機関で3万円以上) | ○ | 2013年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 9位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 穴吹興産株式会社 | 低リスク案件が多いが、投資の機会は限定的 | 43件 | 3.25% | 3.00% | 5.00% | 99.98% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設 | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 1964年 | 755,790,000円 | ○ | 公式サイト |
| 10位 | ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 | 劣後出資割合の高い案件が多く、運営も安定傾向 | 10件 | 4.00% | 3.90% | 4.30% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(その他の金融機関) | ○ | 1991年 | 389,820,000円 | × | 公式サイト |
| 11位 | property+(プロパティプラス) | 株式会社リビングコーポレーション | 募集口数は平均的だが、新規案件がなかった点が課題 | 34件 | 3.20% | 3.00% | 3.40% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2015年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 12位 | ASSECLI(アセクリ) | 株式会社エボルゾーン | 高利回り案件が多いが、新規提供数は限られる | 45件 | - | 0.00% | 0.00% | 105.85% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 事業内容 | 無料 | × | 2011年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 13位 | LIFULL(ライフル) | 株式会社LIFULL | 大手不動産会社のクラウドファンディング。厳選された物件 | 3件 | 5.83% | 5.50% | 6.00% | 105.67% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション・グループホーム | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | × | 1997年 | 9,723,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 14位 | みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント | 」「公的年金に合わせた2ヵ月ごとの分配金」が特徴の、不動産クラウドファンディング | 151件 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、物件種別、アクセス、構造、総戸数、家賃保証有無 | PayPay銀行への払い戻し:無料、PayPay銀行以外への払い戻し:145円 | × | 2016年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 15位 | 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス | 高水準の利回り案件が豊富で、投資のチャンスも平均以上 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行あて) | ○ | 2023年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 16位 | らくたま | 株式会社日本保証 | リスクを抑えつつ高いリターンを狙える案件が多く、供給数も充実 | - | - | - | - | - | ○ | 10000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、商業施設、オフィス | ○ | 築年数、住所、面積 | 無料(GMOあおぞらネット銀行) | × | 2008年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 17位 | GALA FUNDING(ガーラ ファンディング) | 株式会社FJネクストホールディングス | 運営基盤が堅実で、劣後出資割合が高めの安心感ある案件が中心 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛て) | ○ | 1980年 | 2,774,400,000円 | ○ | 公式サイト |
| 18位 | トモタク | 株式会社イーダブルジー | 新規募集数は業界トップクラスで、高利回り案件が目立つ | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、オフィス | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 1回のみ無料(125円(GMOあおぞらネット銀行)、250円(GMOあおぞらネット銀行以外)) | ○ | 2009年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 19位 | LSEED(エルシード) | 株式会社LSEED | リスクとリターンのバランスは良好だが、案件数はやや少なめ | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、面積、事業内容 | 不明 | × | 1999年 | 706,139,500円 | ○ | 公式サイト |
| 20位 | トーセイ不動産クラウド | トーセイ株式会社 | 1万口超の大型案件が主体で、年間の提供数は限定的 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、129円(その他金融機関) | ○ | 1950年 | 6,624,890,000円 | ○ | 公式サイト |
| 21位 | KORYO Funding(コウリョウ ファンディング) | 株式会社興陵 | 安定したバランス型案件が揃う一方で、全体の件数は少ない | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容 | 無料 | × | 1981年 | 371,980,200円 | ○ | 公式サイト |