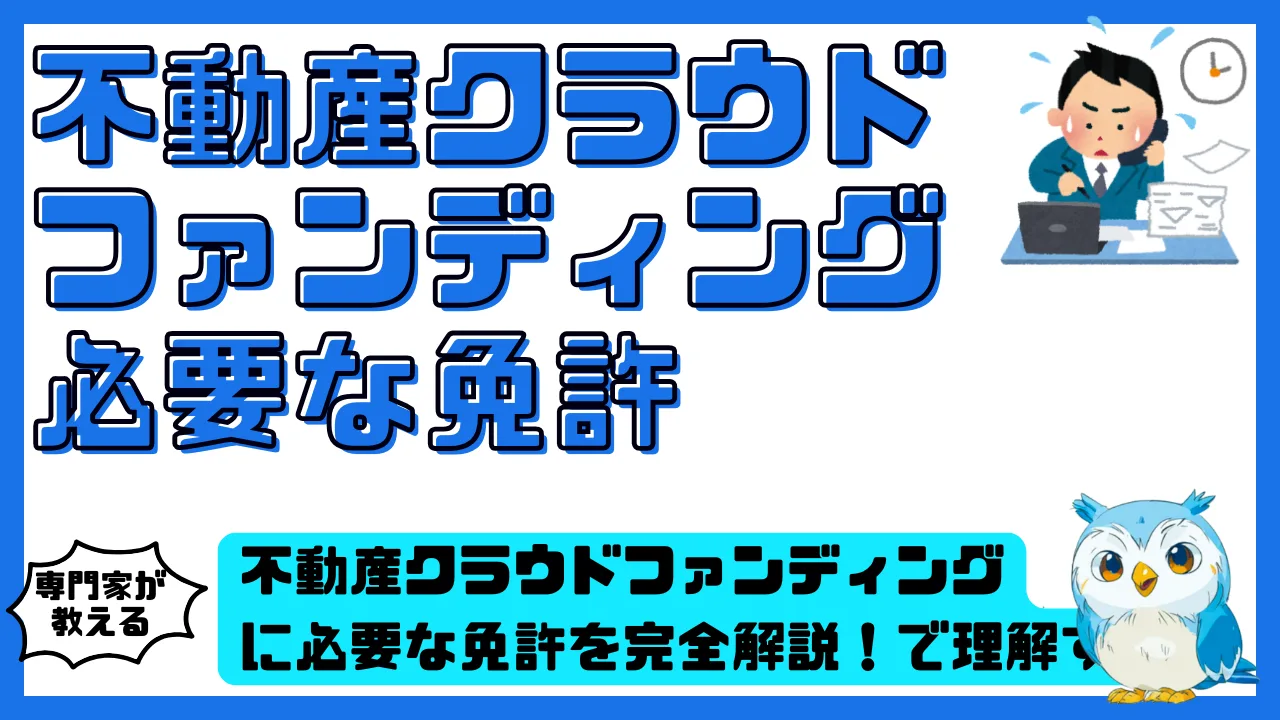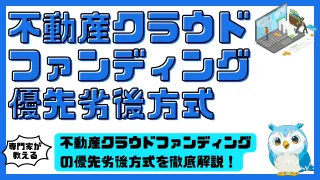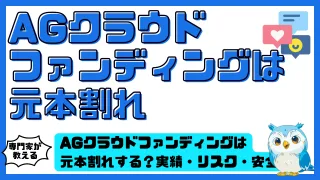本ページはプロモーションが含まれています。
目次
不動産クラウドファンディングに必要な免許の全体像
不動産クラウドファンディングの仕組みは、複数の投資家が少額ずつ出資し、集めた資金をもとに不動産の取得・運用・売却を行い、その利益を分配するというものです。このスキームは一見シンプルに見えますが、実際には複数の法律が関係し、それぞれに対応する免許や登録が必要です。投資家の資金を扱う以上、法令遵守と信頼性の確保が不可欠となっています。
投資型クラウドファンディングの4分類と法的根拠
投資型クラウドファンディングは、扱う資金や対象によって次の4つに分類されます。
- 融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)
投資家から集めた資金を借り手企業へ融資する仕組み。金融商品取引法に基づき「第二種金融商品取引業」の登録が必要です。 - 不動産クラウドファンディング
投資家資金で不動産を購入・運用する事業。不動産特定共同事業法(不特法)の許可が求められます。 - ファンド型クラウドファンディング
投資家資金を使って事業やプロジェクトに投資する形式。こちらも「第二種金融商品取引業」に該当します。 - 株式投資型クラウドファンディング
未上場企業の株式に投資する仕組みで、「第一種」または「小規模第一種金融商品取引業」の登録が必要です。
このように、クラウドファンディングのタイプごとに適用される法律が異なり、該当する免許を取得しなければ事業の運営はできません。
免許が必要な理由と投資家保護の仕組み
不動産クラウドファンディングに免許が必要な最大の理由は、投資家の資金を安全に守るためです。
事業者が破綻した場合や不正行為があった場合でも、法的な枠組みによって投資家の損失を最小限に抑えることが目的とされています。
特に不特法では、匿名組合契約を通じて出資が行われ、投資家の権利や責任範囲が明確に定義されています。また、監督官庁(国土交通省や財務局)が登録・監査を行うことで、運営の透明性が確保されています。これにより、無登録事業者による詐欺的スキームの防止や、過度なリスク商品への投資抑制が図られています。
運営会社が守るべき法律と監督官庁の関係
不動産クラウドファンディングの運営会社は、主に次の法律と監督体制のもとで事業を行います。
- 不動産特定共同事業法(不特法)
監督官庁:国土交通省または都道府県知事
不動産を共同で取得・運用する事業を規制する法律で、不動産クラウドファンディングの中心的な法的基盤です。 - 金融商品取引法(金商法)
監督官庁:財務局・金融庁
投資型商品の販売・募集に関する法律で、電子募集や取引の透明化を義務付けています。 - 宅地建物取引業法(宅建業法)
不動産取引そのものを取り扱うために必要な免許。宅建業免許を有することが、不特法1号事業者の前提条件となります。
これらの法律はそれぞれ独立した管轄下にありますが、実際の事業運営では密接に関連しています。
たとえば、不特法の許可を取得するには宅建業免許が必須であり、電子募集を行う場合には金商法上の登録も求められるケースがあります。
投資家が理解しておくべき「免許の全体構造」
不動産クラウドファンディングの免許構造を俯瞰すると、次のような階層構造になります。
- 基盤免許:宅建業免許
- 共同事業免許:不動産特定共同事業(国交省)
- 募集・販売免許:第二種金融商品取引業(金商法)
- 電子募集免許:電子申込型電子募集(オンライン募集専用)
これらをすべて取得・維持するためには、財務基盤・社内ガバナンス・法務体制が整備されている必要があります。
特に「不特法1号事業者」は資本金1億円以上が条件となるため、参入障壁が高い分、信頼性のある事業運営が期待されます。

投資家としては、運営会社の公式サイトで「不特法の許可番号」や「金商法登録番号」を確認し、無登録業者に注意することが大切です
不動産クラウドファンディングに適用される法律
不動産クラウドファンディングは、インターネットを通じて多くの投資家から資金を集め、不動産を取得・運用し、その収益を分配する仕組みです。この構造は「不動産取引」と「投資商品」の両側面を持つため、複数の法律が重なって適用されます。主に関係するのは「不動産特定共同事業法(不特法)」と「金融商品取引法(金商法)」です。これらの法制度を理解することは、投資家が安全に参加するうえで欠かせません。
不動産特定共同事業法(不特法)
不特法は、複数の投資家から資金を集めて不動産を共同運用し、その利益を分配する仕組みを規定した法律です。不動産クラウドファンディングではこの法律に基づいて事業を行う必要があります。目的は、投資家保護と事業の健全な運営を確保することです。
この法律に基づく事業は「不動産特定共同事業」と呼ばれ、匿名組合契約や任意組合契約などの形で投資家と出資契約を結びます。さらに、オンライン上で契約を勧誘・締結する場合には「電子取引業務」に該当し、国土交通省への追加的な届出が必要となります。
事業区分は主に次の3種類です。
- 第1号事業(通常型):最も一般的で、広く一般投資家が参加可能。国交大臣または都道府県知事の「許可制」
- 特例事業:一定条件を満たした場合に、許可ではなく届出で実施可能
- 小規模不動産特定共同事業:事業規模や出資金額が小さい案件向けの制度で、登録制により参入ハードルが低い
不特法に基づく許可を得るためには、以下のような基準を満たす必要があります。
- 資本金や純資産など、安定した財務基盤を有していること
- 宅建業の免許を保有していること
- 契約書や約款が投資家保護に配慮した内容であること
- 各事務所に「業務管理者」を配置していること(実務経験・資格要件あり)
このように、不特法は「不動産クラファンの根幹」となる法律であり、投資家の資金を預かる事業者に厳格な許可基準を課しています。
金融商品取引法(金商法)
不動産クラウドファンディングの中でも、特に「出資を通じて収益を得る権利」を投資家に与える仕組みの場合、金商法の適用も受けます。これは、出資契約が「有価証券」に該当する可能性があるためです。
金商法の対象となるケースは主に以下の通りです。
- 信託受益権など、権利性の高い商品を扱うスキーム
- 出資契約の形態が「みなし有価証券」に該当する場合
- ウェブ上で募集・申込を受け付ける「電子申込型電子募集」を行う場合
この場合、運営会社は「第二種金融商品取引業」の登録を行う必要があります。電子申込型電子募集とは、ウェブサイトなどを通じて有価証券の募集を行う方式であり、クラウドファンディングの大半がこの形式に該当します。
金商法の目的も投資家保護にあり、リスク開示や契約情報の適正表示、顧客への重要事項説明義務などが定められています。これにより、オンライン上の勧誘でも透明性を確保することが求められています。
その他関連する法律
宅地建物取引業法
不特法の許可条件の一つとして、宅建業の免許を取得していることが義務付けられています。不動産の売買・賃貸に関わる行為を行う以上、この免許がなければ不特法許可も受けられません。
信託法
信託受益権を投資対象とするスキームでは、信託法上のルールに従う必要があります。受託者の責任、受益者保護、契約構造などの観点から、金融商品としての適正性が問われます。
個人情報保護法・犯罪収益移転防止法
クラウドファンディングのオンライン取引では、本人確認(eKYC)や情報保護が不可欠です。投資家情報の取り扱いは、これらの法律の遵守が求められます。

不動産クラウドファンディングに関係する主要法律は、不特法と金商法が中心です。不特法は不動産を共同で運用する仕組みを規制し、金商法は投資商品としての側面をカバーしています。さらに宅建業法や信託法、個人情報保護法などが実務の裏で関わり、全体として投資家を守る仕組みが形成されています。
不特法1号事業者の許可要件を詳しく解説
不動産クラウドファンディングが不特法の枠内で運営される場合、最も代表的なのが「第1号事業者」としての許可を受けるスキームです。これは複数の投資家から出資を募り、不動産を取得・運用・売却して得た収益を分配するモデルであり、許可を得るためには厳格な条件を満たす必要があります。ここでは、投資家として知っておくべき主要な許可要件を整理します。
資本金1億円以上が必要な理由
不特法第1号事業者になるには、最低資本金1億円が義務付けられています。これは、不動産の取得・運用に伴うリスクを吸収し、投資家への分配を安定的に行うための資本的な裏付けを確保する目的があります。
資本が十分でない事業者では、想定外の修繕費用や市場変動に対応できず、投資家の出資金や分配に影響が及ぶおそれがあります。そのため、資本金要件は「財務的健全性」と「投資家保護」を両立させるための最低基準と位置づけられています。
なお、2020年以降は「小規模不動産特定共同事業」の創設により、1,000万円以上の資本金でも登録できる枠組みが用意されています。ただし、対象となる事業規模や募集額に制限があるため、本格的なクラウドファンディング事業を行う場合は1億円要件を満たすことが実務上の前提です。
宅建業免許と業務管理者の配置
不特法1号事業者として許可を得るには、宅地建物取引業免許を持っていることが前提です。これは、不動産を取得・売買・賃貸などで扱う際に必要な基本的な免許であり、不動産取引の正当性を担保するために必須とされています。
また、各事務所ごとに業務管理者の配置が義務付けられています。この業務管理者は以下の条件を満たす必要があります。
- 不動産特定共同事業の実務経験が3年以上あること
- 国土交通省が認める実務講習を修了していること
- 登録証明資格(ARESマスター、不動産コンサルティングマスター、ビル経営管理士など)を有すること
この業務管理者は、投資家との契約手続き、重要事項説明、事業運営の法令遵守などを統括する責任者であり、資格や経験の質が審査時の重要なポイントになります。
財務的基盤と内部統制体制の整備
資本金だけでなく、事業の安定運営を裏付ける「財務的基盤」も求められます。審査では、複数年の決算内容や債務状況を通じて、継続的な経営が可能かどうかを判断されます。債務超過や赤字傾向がある場合、許可は非常に難しくなります。
また、人的体制として、業務部門・審査部門・コンプライアンス部門などを分離し、内部牽制が機能する構造を整えておくことが重要です。これは、投資家資金の管理・契約審査・分配業務の透明性を確保するための仕組みです。
加えて、情報セキュリティや個人情報保護の観点から、システム運用や電子契約の管理体制も評価対象となります。これらを疎かにすると、許可後の監督検査で業務停止命令を受ける可能性もあります。
契約約款と投資家保護ルール
不特法に基づく契約約款には、投資家の権利を保護するための条項を明記する必要があります。主な内容は次のとおりです。
- 出資額、分配方法、解約条件などの透明なルール設定
- 投資リスクや損失発生時の対応方針の明示
- 管理報酬・運営費用・成功報酬の内訳と算出基準
- 投資家への情報開示や電子契約の通知方法
- 事業者が破綻した場合の資金分配・清算の手続き
これらを不明確にすると、契約が不適切と判断されるほか、投資家へのトラブルリスクが高まり、事業運営上の信頼性を損ないます。そのため、弁護士や専門士業の監修を受けた上で契約書を整備することが不可欠です。
許可申請と審査の流れ
不特法1号事業の許可申請は、国土交通省または都道府県知事に対して行います。審査では、次のような観点が総合的に評価されます。
- 財務内容(資本金、純資産、債務状況)
- 宅建業免許および実績
- 管理者・役員の経歴と法令遵守姿勢
- 内部管理体制・システム設計の整備状況
- 契約約款およびリスク開示内容
申請から許可までの期間はおおむね3〜6か月程度ですが、書類の修正指示や補足要求が入ることが多く、準備段階で半年以上かかるケースもあります。
実務上の難易度と準備のポイント
不特法1号事業者としての登録は、制度上も実務上も難易度が高いです。特に、業務管理者の資格取得や財務的証明の整備、内部管理規程の策定、システム監査対応など、複数の専門分野を横断した対応が必要です。
そのため、弁護士・行政書士・公認会計士・システムベンダーなどの専門家と連携しながら、事業計画の初期段階から体制構築を進めることが求められます。投資家にとっても、こうした厳格な許可要件を満たしている事業者は信頼性が高く、安心して出資できる基準になります。

不特法1号事業者は、資本金・資格・体制の3拍子が揃って初めて認可されます。投資家としては、許可番号や管理者資格を確認することで、安心して投資判断ができるようになります。
金商法による免許が必要なケース
不動産クラウドファンディングでは、スキームの内容によっては金融商品取引法(金商法)の規制対象となり、「第二種金融商品取引業」の登録が必要になるケースがあります。投資家が理解すべきは、「どんな形の募集なら金商法が関係するのか」という点です。
第二種金融商品取引業が必要となる仕組み
不動産クラウドファンディングでも、出資契約の内容や募集手法によっては、金融商品取引法上の「有価証券」を扱う行為と見なされます。特に、投資家が持つ出資持分が「みなし有価証券」に該当する場合、事業者は第二種金融商品取引業の登録を受けなければなりません。
この登録は、出資を募る行為が「金融商品の募集」にあたる場合に必要であり、たとえば匿名組合やファンド型のスキームなどがこれに該当します。不特法に基づく1号事業の枠を利用していても、実質的にファンド持分を販売していると判断されれば、金商法の適用対象になります。
電子申込型電子募集に該当する場合
インターネットを通じて投資家を募る仕組みでは、「電子申込型電子募集」に該当するケースが多くあります。これは、ホームページや電子メールなどを使って投資家に情報を提供し、電子的に申込を受け付ける形態のことです。
この場合、事業者は「電子申込型電子募集取扱業務」としての登録を受ける必要があります。登録には、最低資本金500万円以上、十分な知識と経験を持つ役員・担当者の配置、内部管理体制の整備などが求められます。
信託受益権やファンド持分を扱うケース
出資者に付与される権利が「信託受益権」や「ファンド持分」といった有価証券性を持つ場合も、金商法の適用対象になります。信託受益権の販売や媒介は、金商法上の「募集取扱い」として扱われるため、第二種金融商品取引業の登録が不可欠です。
特に、SPC(特別目的会社)を用いた不動産投資スキームでは、実質的に投資家がSPCの発行する持分を購入する構造になることが多く、ここでも金商法上の規制が適用されます。
登録が必要になる代表的な条件
以下のような場合は、金商法による登録が必要になる可能性があります。
- 投資家に付与される権利が有価証券やみなし有価証券に該当する
- 募集や申込が電子的に完結する(オンラインプラットフォームを利用)
- 信託受益権やSPCの持分を投資対象とするスキームを採用している
- ファンド型の投資スキームで複数投資家の資金を集める
登録後の運営に求められる管理体制
金商法に基づく登録を受けた後は、事業者に厳格な管理体制が求められます。具体的には、勧誘方法・顧客管理・情報開示・利益相反防止・内部監査などの体制整備が義務付けられます。財務局による定期的な報告義務や業務改善命令の対象にもなるため、法令遵守の徹底が不可欠です。
投資家にとっては、登録業者であるかどうかを確認することが安全性の判断材料になります。公式サイトには「第二種金融商品取引業者 登録番号」が明記されているため、必ずチェックしておくと安心です。

金商法の登録が必要になるケースは、不特法の枠組みを超えて“金融商品を募集している”と見なされる場合です。特にオンライン勧誘型のクラウドファンディングは該当しやすく、投資家は登録番号と開示体制を必ず確認しておきましょう
融資型・ファンド型・株式型クラウドファンディングとの違い
不動産クラウドファンディングの仕組みや免許制度を正しく理解するためには、他のクラウドファンディングとの違いを明確に把握することが重要です。ここでは「融資型」「ファンド型」「株式型」の3形態と比較しながら、不動産クラウドファンディングの特徴を整理します。
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)との違い
仕組みと資金の流れ
融資型クラウドファンディングは、投資家から集めた資金を借り手企業に貸し付け、利息と元本の返済を通じてリターンを得る仕組みです。投資家は匿名組合契約を結び、事業者が仲介して融資を行います。
一方、不動産クラウドファンディングは集めた資金で不動産を取得・運用し、賃料収入や売却益を分配するモデルです。貸付ではなく、不動産の実物資産を基盤にした運用が特徴です。
必要な免許と法的根拠
融資型クラウドファンディングは、金融商品取引法上の「第二種金融商品取引業(電子申込型電子募集)」に該当します。
不動産クラウドファンディングは、不動産特定共同事業法(不特法)の許可を受けることが原則であり、対象資産や出資構造によっては金商法の登録も必要になります。
リスクと保護制度
融資型は貸倒リスクが中心であり、借り手が返済不能となれば元本回収が困難です。
不動産クラウドファンディングは、物件価格の下落や空室リスクなど不動産特有の要因が影響します。ただし、優先劣後構造を採用することで、劣後出資者(運営側)が損失を先に負担する仕組みが多く、投資家保護の強度が高い点が特徴です。
流動性の違い
どちらも途中解約が困難ですが、融資型は満期時に一括償還、不動産クラウドファンディングは物件売却や運用終了時に分配される点が異なります。
ファンド型クラウドファンディングとの違い
投資対象とリターン構造
ファンド型クラウドファンディングは、特定の事業やプロジェクトに投資し、その事業の成果や利益に応じて分配を受ける方式です。場合によっては、金銭以外のモノやサービスがリターンになることもあります。
不動産クラウドファンディングは、収益源が不動産運用に限定される点が最大の違いであり、事業リスクよりも資産価値リスクが中心となります。
法的区分と免許
ファンド型も金融商品取引法に基づく「第二種金融商品取引業」の登録が必要です。
不動産クラウドファンディングは、不特法の1号事業者としての許可を得ることが基本で、信託受益権など証券性を持つ場合に限り金商法登録が求められます。
投資家保護とリスク
ファンド型は事業そのものの成功・失敗に左右されるため、リターンの不確実性が高く、元本割れリスクも大きいです。
不動産クラウドファンディングは、実物資産が裏付けとなるため安定性が相対的に高く、法律上も不動産の専門免許(宅建業・不特法)によって監督が厳格化されています。
株式型クラウドファンディングとの違い
仕組みと権利関係
株式型クラウドファンディングは、未上場企業が資金調達を行い、投資家がその企業の株主となる仕組みです。
投資家は議決権を持つ株主として企業の成長に応じた配当や株価上昇益を期待できますが、倒産すれば出資金を失うリスクもあります。
不動産クラウドファンディングでは、投資家は株主ではなく出資者であり、経営参加権は持ちません。
必要な免許と監督体制
株式型クラウドファンディングを運営するには、「第一種金融商品取引業」または「小規模第一種金融商品取引業」の登録が必要です。
これは有価証券の募集・販売を行うため、資本金5,000万円以上や内部統制体制の整備が求められるなど、他形態よりも厳しい登録要件が課されます。
リターンの方向性
株式型は企業の成長やIPOによって大きなリターンを得られる可能性がある一方、成功率は低くハイリスク・ハイリターンです。
不動産クラウドファンディングは安定性を重視する投資家向けで、賃料収益や売却益など実現性の高いキャッシュフローを基盤としています。
比較まとめ(投資家目線)
| 種類 | 主な投資対象 | 適用法令・免許 | 主なリスク | 投資家保護の仕組み |
|---|---|---|---|---|
| 不動産クラウドファンディング | 不動産取得・運用 | 不特法1号事業者許可/金商法登録 | 不動産市場・空室・管理コスト | 優先劣後方式・業務管理者設置・監督官庁審査 |
| 融資型クラウドファンディング | 企業への貸付 | 金商法 第二種(電子申込型電子募集) | 貸倒・返済遅延 | 登録業者による開示・分別管理 |
| ファンド型クラウドファンディング | 特定事業・プロジェクト | 金商法 第二種 | 事業失敗・収益不安定 | 金商法による説明義務・契約開示 |
| 株式型クラウドファンディング | 非上場企業の株式 | 金商法 第一種/小規模第一種 | 企業倒産・株価変動 | 開示義務・投資上限規制 |

クラウドファンディングの分類を理解することで、投資家は「どの法律の保護下で運営されているのか」「どの程度のリスクを取っているのか」を客観的に判断できるようになります。特に不動産クラウドファンディングは、不特法による厳格な管理と優先劣後構造により、安定志向の投資先として注目されています。
免許を取得するまでのステップと必要書類
不動産クラウドファンディング事業を始めるには、単に不動産やITの知識だけでなく、法律・財務・組織体制を含めた総合的な準備が求められます。ここでは、不特法や金商法に基づく免許を取得するまでの具体的なステップと、提出が必要な書類の内容を詳しく解説します。
ステップ1:事業スキームと法令適用の整理
まず行うべきは、自社のクラウドファンディング事業がどの法律の枠組みに該当するかを明確にすることです。
たとえば、現物不動産を対象とする場合は「不動産特定共同事業法(不特法)」、信託受益権など金融商品を扱う場合は「金融商品取引法(金商法)」が適用されます。
この段階で、弁護士や行政書士などの専門家と連携し、事業スキーム図を作成しながら適切な登録区分(不特法1号、金商法第2種など)を確定させます。
ステップ2:社内体制と業務管理者の整備
不特法1号事業者を目指す場合、国土交通省または都道府県知事の許可を受けるために、一定の人的・組織的体制を整える必要があります。
主な条件は以下の通りです。
- 資本金1億円以上の確保
- 宅建業免許を保持していること
- 各事務所に「業務管理者」を1名以上配置(3年以上の不特事業経験やARESマスターなどの資格が必要)
- 財務健全性を示す監査報告書や決算書の準備
この段階で多くの企業がつまずくのは、「業務管理者」の要件を満たす人材確保です。ARESマスターや不動産コンサルティングマスターの資格取得を計画的に進めておくことが重要です。
ステップ3:申請書類・添付書類の作成
免許申請に必要な書類は非常に多く、形式的な書類不備で差し戻されるケースもあります。
代表的な提出書類には以下のものがあります。
- 不特法事業登録申請書または金融商品取引業登録申請書
- 会社定款および登記簿謄本
- 資本金・財務状況を示す決算書類
- 役員・主要株主の略歴書および誓約書
- 業務管理者資格証明書(ARESマスター・ビル経営管理士等)
- 事業計画書(資金の流れ、リスク管理体制、出資者保護策を明記)
- 契約約款・匿名組合契約書(電子申込対応を含む)
- ITシステムのセキュリティ・KYC体制に関する説明資料
書類作成には法令知識だけでなく、金融庁や財務局の審査観点を理解した実務経験が求められます。行政書士・弁護士とともにドラフトを精査するのが安全です。
ステップ4:財務局・国交省への申請と審査
書類が整ったら、所管官庁に正式に提出します。
不特法の場合は国土交通省(または都道府県)、金商法関連の場合は各財務局が窓口となります。
申請から許可までの期間は、通常3〜6か月ほどかかりますが、修正指摘や追加提出が発生した場合は1年程度に及ぶこともあります。
この期間中、監督官庁は「内部管理体制」や「投資家保護措置」が実効性を持つかを重点的に確認します。たとえば、電子申込の際の本人確認(eKYC)、資金分別管理、情報開示システムの安全性などが評価対象です。
ステップ5:登録完了・運用準備
許可が下りた後は、実際のファンド募集や運用を始めるための最終準備段階に入ります。
社内規程やシステムの運用テスト、KYC・AML体制の最終確認、外部監査法人との契約などを完了させることが求められます。
投資家向けのサイトを立ち上げる際は、以下の実務項目も必須です。
- 重要事項説明書・契約締結前交付書面の自動生成
- 投資家本人確認・反社チェック機能
- ファンド情報の表示と分配履歴の開示
- コンプライアンス研修および内部監査体制の構築
これらを満たして初めて、正式に不動産クラウドファンディングの募集・運営を行うことが可能になります。
申請プロセスを成功させるための実務ポイント
- 初期段階でスキーム設計を誤ると、免許区分の変更が必要になる場合がある
- 契約約款・匿名組合契約書の文言は、実際のシステム仕様と整合させること
- 財務的な裏付けと同時に、ITセキュリティと投資家保護体制を明文化しておくこと
特に近年は、財務局が「電子募集プラットフォームの安全性」を重視しており、クラウド環境・暗号化通信・ログ管理の説明資料を求められるケースが増えています。

免許取得はゴールではなくスタートです。書類を整えるだけでなく、投資家保護を意識したシステム・人材・内部統制の三位一体の体制づくりを意識して準備してくださいね
免許を取得して運営する企業の実例と傾向
不動産クラウドファンディングは、法令上のハードルが高いため、免許を取得して実際に運営している企業には明確な共通点があります。ここでは、主要事業者の実例と、そこから見える市場全体の傾向を整理します。
代表的な事例:Jointoα(ジョイントアルファ)
穴吹興産が運営する「Jointoα」は、不動産クラウドファンディング事業の代表例です。不動産特定共同事業法の許可を受けており、賃料収入や売却益を投資家に分配するモデルを採用しています。
この事業者は以下のような特徴を持ちます。
- 不特法の3号・4号事業者として登録し、電子取引による募集を実施
- 金融商品取引法上の「第二種金融商品取引業」登録も併用
- 投資家向けポータルサイトや契約・分配管理を自動化したシステムを導入
- 優先出資・劣後出資のリスク分担構造を明確化
上場企業が母体であり、財務基盤と透明性の高さから信頼性が高く、投資家からの支持も厚いモデルです。
利回り不動産・CREALなどの主要プレイヤー
「利回り不動産」や「CREAL(クリアル)」といった事業者も、免許を取得して本格的に運営しています。
利回り不動産は中規模デベロッパーが運営しており、案件数や運用実績を増やしながら、より小口の投資を可能にする体制を構築しています。
一方、CREALは電子取引型不動産クラウドファンディングの草分け的存在であり、IT基盤と内部統制を重視した運営を行っています。
共通点として以下が挙げられます。
- 不特法の1号または3号・4号事業者として許可を取得
- 自社が宅建業免許を保有し、開発・募集・運用をワンストップ化
- 投資家登録・契約・配当までをオンライン完結させる電子取引対応
- 出資者保護のため、劣後出資や倒産隔離構造を採用
これらの事業者は、許可取得に加え、ITシステムと法令遵守を両立させた運営を実現しています。
特例事業(SPC型)を活用する新しい潮流
一部の事業者では、特例事業スキーム(SPC型)を用いた構造が広がっています。これは、運営会社自身が不動産を保有せず、特定目的会社(SPC)が資産を保有・運用する形をとるものです。
この方式には以下の利点があります。
- 事業者の倒産リスクとファンド資産のリスクを分離できる
- 運営会社の財務負担を軽減できる
- 投資家への透明性を高められる
SPC型はまだ少数派ですが、リスク管理の高度化を目的として、今後採用が増えると見込まれています。
事業者に共通する運営傾向
免許を取得している事業者には、次のような共通点が見られます。
- 上場企業または財務基盤の強い不動産会社が中心
- 不特法と金商法の両方を組み合わせたスキームを採用
- 契約や分配を電子化し、業務効率化と内部統制を強化
- 専門システムや外部ベンダーと提携し、法令対応を継続的に行う
- 投資家保護を目的に、優先・劣後出資比率を明確に設計
これらの傾向は、投資家保護・運営効率・信頼性の三要素を高次元で両立させるための仕組みづくりの表れです。
投資家が注目すべきポイント
投資家の立場から見て、事業者選定で注目すべき要素は次の通りです。
- 取得している免許区分(1号・3号・4号など)
- 優先劣後構造や倒産隔離の設計
- システム化・電子契約対応の有無
- 財務基盤や上場企業との関係性
- 案件数・運用実績・分配遅延の有無
免許の有無だけでなく、「どのレベルの運営体制を構築しているか」を確認することが重要です。

免許を取っている企業の多くは、単に法令を満たすだけでなく、システム整備やリスク管理まで踏み込んだ運営を行っています。投資家としては、免許区分・内部管理・出資設計などを比較しながら、長期的に信頼できる事業者を選ぶ目を養うことが大切です
投資家が知っておくべき免許情報の見分け方
不動産クラウドファンディングの世界では、運営会社がどの免許を持っているかが信頼性の判断材料になります。
投資家自身が免許情報を正しく読み取れるようになることで、トラブルや詐欺被害を未然に防ぐことができます。
免許番号の確認方法と信頼できる表記
まず最初に確認すべきは、公式サイトに記載された「免許番号」や「登録番号」です。
これが曖昧な表記だったり、具体的な番号が載っていなければ注意が必要です。
主な確認ポイントは次の通りです。
- 免許番号が具体的に明記されている(例:「国土交通大臣許可 第〇号」など)
- 行政庁の公式リスト(国土交通省・財務局など)と一致している
- サイトのフッターや会社概要ページなど、見やすい位置に掲載されている
不特法に基づく事業者は、国土交通省の公開リストに登録されています。
このリストと会社名を照合すれば、実際に許可を得ているかを確認できます。
免許区分と運営スキームの整合性を確認
免許を持っていても、その内容と事業スキームが一致していなければ適正とは言えません。
たとえば次のようなケースに注意が必要です。
- 不特法1号事業者の許可を掲げながら、特例事業(3号型)を運営している
- 電子的な募集を行っているのに、金商法上の登録番号がない
- 免許番号が古く、更新日や有効期間が明示されていない
このような不一致は、運営体制の未整備や法令理解不足を示している可能性があります。
公開情報の透明性と網羅性をチェック
免許番号が確認できても、企業情報が不十分であれば信頼性は下がります。
以下の項目がしっかり開示されているか確認しましょう。
- 会社所在地・代表者名・資本金などの基本情報
- 業務管理者の資格(ARESマスター、不動産コンサルティングマスターなど)
- 契約約款や重要事項説明書の公開状況
- 行政処分歴・報告書提出実績などの有無
情報開示が充実している企業ほど、法令遵守意識が高い傾向にあります。
無登録・グレー事業者の特徴
中には、免許を取得していないまま運営しているケースもあります。
次のような特徴が見られる事業者には要注意です。
- 「免許申請中」「準備中」などの表現で逃げている
- 公式サイトに登録番号が一切ない
- 「保証付き」「元本安全」など過度に安心感を強調している
- 運営会社の所在地・電話番号・担当者が曖昧
- 募集が短期間で終了し、詳細情報の公開がない
これらの特徴が複数当てはまる場合は、投資対象から外すのが賢明です。
免許取得済み企業を選ぶメリット
正規の免許を取得している企業を選ぶことで、次のような安心感が得られます。
- 行政監督下での運営により不正リスクが低い
- トラブル時に行政庁への相談や救済が受けやすい
- 財務基盤・運営体制などが一定水準以上に整っている
特に初心者の投資家は、登録事業者リストに掲載されている企業を優先的に選ぶことが推奨されます。
投資家が実践すべき確認ステップ
- 公式サイトで免許番号を確認
- 行政庁の公開リストで照合
- 登録区分(1号・2号・3号)と運営内容が一致しているか確認
- 不明点があれば直接問い合わせ、回答の丁寧さを確認
- 情報開示が不十分な事業者は避ける
これらを習慣化することで、投資判断の精度が大きく向上します。

免許番号が明確で、行政リストでも確認できる事業者を選ぶこと。それだけで投資リスクは一段下がります。慣れてきたら、免許区分と募集方式の整合性まで見抜けるようになりましょう。
| 順位 | 商品名 | 会社名 | 特徴 | 案件数 | 直近10件平均利回り | 直近10件直近最低利回り | 直近10件直近最高利回り | 直近10件募集割合平均 | 優先劣後方式 | 最低投資金額 | 募集方法 | 組合契約 | 物件の種類 | 優遇サービスあり | 物件の開示情報 | 出金手数料 | 運用レポートの共有あり | 運営会社設立年月 | 運営会社資本金 | 上場 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | COZUCHI(コズチ) | LAETOLI株式会社 | 投資募集のチャンスは業界上位。投資デビューに適した候補 | 139件 | 5.75% | 4.00% | 6.50% | 337.36% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 月1回まで無料(それ以降は330円) | ○ | 1999年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 2位 | CREAL(クリアル) | クリアル株式会社 | 募集口数が多く、新規案件の供給量も豊富 | 139件 | 5.13% | 0.00% | 6.50% | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス、保育所、学校、宿泊施設 | ○ | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 105円(楽天銀行の場合)、150円(楽天銀行以外で3万円未満の場合)、229円(楽天銀行以外で3万円以上の場合) | ○ | 2011年 | 1,273,520,500円 | ○ | 公式サイト |
| 3位 | 利回りくん | 株式会社シーラ | 年間新規案件数が安定。募集口数も一定水準 | 148件 | 4.71% | 3.00% | 6.00% | 89.80% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2010年 | 446,522,660円 | ○ | 公式サイト |
| 4位 | Rimple(リンプル) | プロパティエージェント株式会社 | 新規案件が充実。劣後出資割合の高い案件が多い | 112件 | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 270.75% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、事業内容 | 無料 | ○ | 2004年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 5位 | TECROWD(テクラウド) | TECRA株式会社 | 新興国不動産への投資が可能。高利回り案件が多い | 90件 | 10.40% | 8.50% | 12.00% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、オフィス | ○ | 住所、運営会社、財務情報、面積、事業内容 | 無料(楽天銀行)、振込手数料(楽天銀行以外) | ○ | 2001年 | 156,600,000円 | × | 公式サイト |
| 6位 | TSON FUNDING(ティーソン) | 株式会社TSON | 年間案件数が最多クラス。リスク軽減案件も豊富 | 230件 | 5.64% | 5.50% | 5.80% | 98.90% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、事業内容 | 無料(匿名組合ファンド)、振込手数料(任意組合ファンド) | ○ | 2008年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 7位 | 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス | 運営会社の信頼性が高く、新規案件も安定供給 | 109件 | 5.90% | 3.50% | 12.00% | 728.48% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛) | ○ | 1996年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 8位 | FUNDROP(ファンドロップ) | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 | 劣後出資割合の高い案件が多いが、投資機会は少なめ | 39件 | 5.66% | 5.50% | 5.80% | 119.09% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 52円(楽天銀行)、150円(他の金融機関で3万円未満)、229円(他の金融機関で3万円以上) | ○ | 2013年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 9位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 穴吹興産株式会社 | 低リスク案件が多いが、投資の機会は限定的 | 43件 | 3.25% | 3.00% | 5.00% | 99.98% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設 | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 1964年 | 755,790,000円 | ○ | 公式サイト |
| 10位 | ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 | 劣後出資割合の高い案件が多く、運営も安定傾向 | 10件 | 4.00% | 3.90% | 4.30% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(その他の金融機関) | ○ | 1991年 | 389,820,000円 | × | 公式サイト |
| 11位 | property+(プロパティプラス) | 株式会社リビングコーポレーション | 募集口数は平均的だが、新規案件がなかった点が課題 | 34件 | 3.20% | 3.00% | 3.40% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2015年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 12位 | ASSECLI(アセクリ) | 株式会社エボルゾーン | 高利回り案件が多いが、新規提供数は限られる | 45件 | - | 0.00% | 0.00% | 105.85% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 事業内容 | 無料 | × | 2011年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 13位 | LIFULL(ライフル) | 株式会社LIFULL | 大手不動産会社のクラウドファンディング。厳選された物件 | 3件 | 5.83% | 5.50% | 6.00% | 105.67% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション・グループホーム | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | × | 1997年 | 9,723,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 14位 | みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント | 」「公的年金に合わせた2ヵ月ごとの分配金」が特徴の、不動産クラウドファンディング | 290件 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、物件種別、アクセス、構造、総戸数、家賃保証有無 | 無料 | × | 2016年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 15位 | 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス | 高水準の利回り案件が豊富で、投資のチャンスも平均以上 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行あて) | ○ | 2023年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 16位 | らくたま | 株式会社日本保証 | リスクを抑えつつ高いリターンを狙える案件が多く、供給数も充実 | - | - | - | - | - | ○ | 10000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、商業施設、オフィス | ○ | 築年数、住所、面積 | 無料(GMOあおぞらネット銀行) | × | 2008年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 17位 | GALA FUNDING(ガーラ ファンディング) | 株式会社FJネクストホールディングス | 運営基盤が堅実で、劣後出資割合が高めの安心感ある案件が中心 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛て) | ○ | 1980年 | 2,774,400,000円 | ○ | 公式サイト |
| 18位 | トモタク | 株式会社イーダブルジー | 新規募集数は業界トップクラスで、高利回り案件が目立つ | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、オフィス | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 1回のみ無料(125円(GMOあおぞらネット銀行)、250円(GMOあおぞらネット銀行以外)) | ○ | 2009年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 19位 | LSEED(エルシード) | 株式会社LSEED | リスクとリターンのバランスは良好だが、案件数はやや少なめ | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、面積、事業内容 | 不明 | × | 1999年 | 706,139,500円 | ○ | 公式サイト |
| 20位 | トーセイ不動産クラウド | トーセイ株式会社 | 1万口超の大型案件が主体で、年間の提供数は限定的 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、129円(その他金融機関) | ○ | 1950年 | 6,624,890,000円 | ○ | 公式サイト |
| 21位 | KORYO Funding(コウリョウ ファンディング) | 株式会社興陵 | 安定したバランス型案件が揃う一方で、全体の件数は少ない | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容 | 無料 | × | 1981年 | 371,980,200円 | ○ | 公式サイト |