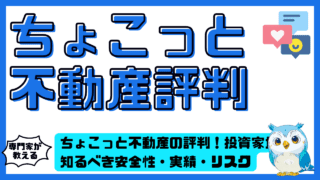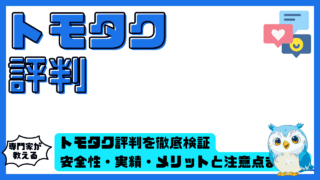本ページはプロモーションが含まれています。
目次
不動産担保ローン金利の相場を整理
不動産担保ローンの金利は、金融機関の種類や審査基準、資金使途によって大きく幅が生まれます。投資家が最も気になる「相場」を正しく把握しておくことで、金融機関との交渉力が高まり、無駄な高金利を避ける判断がしやすくなります。
銀行の金利相場の特徴
銀行の不動産担保ローンは、総じて低金利帯に位置しています。特に、資金使途が比較的自由であるタイプでも、下限は1%台が一般的で、長期の借入でも安定して低水準が維持されやすい傾向があります。
一方で、審査が厳格なため、申込者の信用力や担保評価に応じて上限は8〜9%台まで広がります。金利の幅が大きいのは、個々のリスク評価に基づいて適用金利が細かく分かれるためです。
また、資金使途に制限を設ける銀行も多く、事業性資金や運転資金を目的とした場合、金利が高めに設定されるケースが多く見られます。
ノンバンクの金利相場の特徴
ノンバンクは銀行と比べて審査が柔軟で、事業性資金や借入整理用途などにも幅広く対応している点が特徴です。下限は2%台からで、銀行よりもわずかに高い水準からスタートします。
ただし、上限金利は5〜7%台が中心で、銀行の上限と比べても極端に高いわけではありません。審査のスピードや資金使途の自由度を考慮すると、投資家にとってバランスの良い選択肢になるケースもあります。
金利幅が大きくなる主な理由
不動産担保ローンは担保が付くため一見「条件は単純」と思われがちですが、実際には複数の要素が絡み合って金利が決まります。
特に影響が大きいポイントは以下の通りです。
- 融資先の信用力(年収・利益・返済履歴など)
- 担保不動産の評価額と担保掛目
- 借入金額と融資可能枠の差(担保余力の有無)
- 資金使途が明確かどうか
- 借入期間と金利タイプの選択
これらの条件が揃っていると、同じ金融機関でも下限金利に近づきやすくなります。一方で、信用力が弱い場合や、融資枠いっぱいの借入を希望する場合は上限付近になりやすくなります。
投資家が知っておくべき「相場の見方」
不動産担保ローンの金利相場は、単に「何%〜何%」という表示を比較するだけでは不十分です。相場の中でどの金利が適用されるかは、投資家自身の条件によって大きく変わるからです。
そのため、投資判断を行う際は次の点を押さえることが重要です。
- 下限金利は「最優良条件」でのみ適用される
- 多くの利用者は相場の中間〜上限寄りに位置する
- 複数社の審査結果を比較すると、自分がどの位置に評価されているかが見えやすくなる
金融機関ごとに得意領域が異なるため、信用力の見られ方や担保評価方法にも差が出ます。相場を踏まえて複数社の見積もりを取ることで、自分の適正金利を把握しやすくなります。

相場を知っておくと、どの金利が“適正”なのかを冷静に判断できますよ。投資家としては、まず自分の条件が相場のどの位置にあるのかを把握してから比較を進めるのが大切です
金利に影響する主要要素を総まとめ
不動産担保ローンの金利は「どの金融機関を選ぶか」だけでなく、申込者自身の条件や担保評価、借入条件の設定によって大きく変わります。低金利で借りるには、金融機関が判断の材料とする評価ポイントを体系的に理解することが欠かせません。ここでは、投資家が特に押さえておくべき“金利に直結する要素”を整理します。
融資先の信用力(属性)
金融機関は、担保が十分にある場合でも、申込者の信用力を細かくチェックします。信用力が高いほど返済リスクは低いと見なされ、金利は下がりやすくなります。
金融機関が重視する要素としては以下があります。
- 安定した収入や利益水準
- 勤続年数・事業の継続年数
- 信用情報(延滞・返済履歴)
- 他社借入の状況
- 取引実績や完済歴
返済比率(返済負担率)も重要で、年収や利益に対して返済負担が高すぎると、金利が上昇する傾向があります。投資家にとっては、事業構造の説明や財務の透明性を高めることで評価を引き上げる余地があります。
担保不動産の評価額と特性
担保物件の評価額は不動産担保ローンの核となる要素で、評価額が高いほど金利は低くなりやすいです。評価は以下の点から総合的に判断されます。
- 路線価や周辺取引事例による土地評価
- 建物の再調達価格・耐用年数
- 築年数や管理状態
- エリアの発展性や流動性
特に、評価額に対して借入額が小さいほど金融機関が受けるリスクは下がり、金利引き下げの余地が生まれます。
担保掛目(LTV)の水準
担保評価額に対して何%まで融資するかを示す担保掛目は、金利に大きな影響を与えます。一般的な水準は70〜80%ですが、借入金額が限度額に近づくほど金利は上昇します。
担保余力がある状態を作ることは、投資家にとって金利交渉の大きな武器になります。
資金使途の明確さと妥当性
金融機関は「何のために借りるのか」を重視します。資金使途が不明確、あるいは返済原資の裏付けが弱いと判断された場合、金利は上がりやすくなります。
評価されやすいポイントは以下です。
- 事業の成長に必要な運転資金であることを説明できる
- 売掛金増加など、健全な理由で資金需要が生じている
- 帳簿や事業計画書で根拠を示せる
ノンバンクは用途に柔軟な傾向がありますが、銀行はより厳格な判断を行うため、資金使途の説明力が金利に直結します。
借入期間と金利タイプの違い
借入期間や金利タイプの選択も金利を左右する大きな要素です。
- 固定金利は期間が長いほど金利が高くなる傾向
- 変動金利は期間による金利差が小さく比較的安定
- 固定期間選択型は金融機関の融資方針により有利な期間が存在
金融機関ごとに「融資したい期間帯」が異なる場合があり、そこをうまく活用すると低金利が実現しやすくなります。
まとめて考えるべきポイント
金利は単純に「相場」だけで決まるものではなく、申込者の信用力、担保物件の余力、資金使途の透明性、借入条件の最適化など複数要素の掛け合わせで決まります。投資家にとっては、その仕組みを理解して“金融機関がリスクを感じにくい申込条件”を設計することが最大のポイントになります。

金利に影響する要素は一つではなく、信用力・担保余力・資金使途・借入期間の組み合わせで決まるんです。どれか一つが弱くても他で補えるので、全体のバランスを意識して準備すると低金利に近づきますよ
低金利を実現するための具体的な対策
低金利を引き出すためには、金融機関が重視する審査項目をこちら側でコントロールし、評価ポイントを確実に積み上げることが重要です。単純に「金利の低い金融機関を選ぶ」だけではなく、投資家自身の条件をどこまで整えられるかで提示金利は大きく変わります。
以下では、競合サイトが触れていない実務的なポイントも加え、投資家が実際に取れる具体策を体系的にまとめます。
返済負担を抑えて信用力を引き上げる
返済比率(返済負担率)が低いほど、金融機関は「余力のある借り手」と判断し、金利を下げやすくなります。収入を急に増やすことは難しいため、返済負担そのものを調整した方が現実的です。
- 既存ローンの繰上げ返済で返済額を圧縮する
- カードローンやリボ残高をゼロにする
- 個人・法人の固定費を整理して資金繰りを改善する
内部留保の増加やキャッシュフローの改善は、法人での審査において強力な「信用力の強化」として作用します。
借入希望額を担保評価額の範囲に抑える
金融機関は、担保評価額に対して借入額が大きいほどリスクが高いと判断します。逆に言えば、担保余力を確保するほど、低金利は引き出しやすくなります。
例えば、評価額4,000万円・掛目80%のケースでは、限度額3,200万円ですが、あえて2,800~3,000万円に抑えるだけで金利が下がることは珍しくありません。
借入額の調整は、もっとも即効性があり、審査でも重視される要素です。
資金使途の資料を「証拠」として固める
資金使途の妥当性が説明できると、金融機関はリスクが低いと判断しやすくなります。ここを曖昧にしたまま申請するのは損です。
法人の場合は、以下の資料の提出が効果的です。
- 月次試算表
- 資金繰り表
- 売掛金や仕入れ増加の根拠となる契約書
- 投資計画書(不動産購入・事業拡張など)
使途の整合性が取れているほど、金利は下がりやすくなります。
担保不動産の状態を整えて評価を高める
担保評価は「立地だけでは決まらない」のが重要なポイントです。不動産の外観、維持状態、法的クリアランスなども影響を与えます。
価値を高めるための現実的な施策としては次があります。
- 外壁や共用部の清掃・軽微な補修
- 違法建築要素の解消(増築部分の是正など)
- 賃貸中物件の場合、賃料収入の安定性を示す資料の用意
中でも「収益不動産は稼働率と賃料水準」が評価に直結します。空室対策を行い、直近の入居率を改善してから申し込むのも効果的です。
金融機関の得意分野を見極めて調整する
銀行とノンバンクでは得意とする案件が異なります。案件との相性が合うほど金利条件は良くなります。
- 銀行が得意:自己資金が厚い投資家・借入比率が低い案件・資金使途が明確な購入資金
- ノンバンクが得意:事業資金・スピード重視・法人の資金繰り対策・赤字決算の改善案件
「投資家」「案件」「金融機関」の三点セットの相性が良いと、同じ借入金額でも1%以上金利が変わるケースがあります。
金利タイプ・期間の組み合わせで低金利を狙う
特に固定期間選択型は、金融機関の融資残高バランスの都合で、特定期間だけ金利が下がっていることがあります。
- 3年固定だけが異常に低い
- 5年・10年で逆転している
- 一部の期間のみキャンペーン金利が設定されている
借入期間を柔軟に調整できる投資家ほど、こうした「低金利ゾーン」を拾いやすくなります。期間の延長・短縮を交渉材料にするのも有効です。
完済履歴を活用して優遇を引き出す
過去に同じ金融機関で借り入れを行い、延滞なく完済している場合、金融機関側は「返済実績のある優良顧客」と判断します。
この信頼性は、信用情報以上に強力に作用し、最初の提示金利から0.2〜0.5%程度の引き下げ余地が生まれることがあります。

低金利を狙うときは“準備の丁寧さ”で差がつきますよ。特に資金使途や借入額の調整はすぐ実践できるので、まずはここを固めると金利交渉がかなり有利になります
担保不動産の価値を高めるための工夫
担保不動産の評価が高まるほど、融資担当者が判断する「担保余力」は大きくなり、金利の引き下げ交渉がしやすくなります。投資家にとっては、資金効率の改善にも直結するため、計画的に取り組む価値があります。ここでは、金融機関が実際に評価するポイントに沿って、無駄なく価値を引き上げるための具体策を整理します。
建物の印象を改善して評価ロスを防ぐ
建物評価は年数とともに下落しますが、状態の良し悪しで数十万〜数百万円単位の差が生まれることもあります。過剰投資は不要ですが、評価を落とさないための最低限の整備は効果的です。
最低限やっておくべき外観・設備の手入れ
- 外壁クリーニングやコーキング補修など、短期間でできるメンテナンス
- 玄関・アプローチの簡易整備
- 雨樋・排水設備の詰まり除去
- 屋根の劣化チェックと簡易補修
建物が老朽化している場合でも、「適切に管理されている物件」と評価されることで減点幅が縮小され、担保価値が底上げされるケースがあります。
リフォームで加点を狙える領域を優先する
築年数が法定耐用年数を超えていても、内部状態によっては評価が上がる場合があります。金融機関が評価で重視するのは、「耐用年数を延ばす改善」か「市場価値の上昇につながる改善」です。
金融機関が評価しやすいリフォーム例
- 水回り設備(キッチン・浴室・トイレ)の刷新
- 配管・電気系統の更新など、建物寿命を延ばす改修
- 断熱・防犯性能向上などの機能改善
- 大規模劣化の予防につながる基礎・外壁の補強
見た目のアップデートだけよりも、「建物寿命を延ばす工事」は融資担当者の評価に反映されやすいため、費用対効果が高い判断材料になります。
土地の価値を左右する「周辺環境」の見落としをなくす
金融機関の担保評価では、土地は建物より比重が高い部分です。特に商業施設・公共施設・交通網の変化など、第三者による利便性向上は即座に評価へつながる可能性があります。
周辺環境の変化があれば、金融機関との面談時に積極的に説明することが重要です。担当者が気付いていない利便性の向上を補足できれば、実質的な評価が改善する余地が生まれます。
説明材料として活用できるポイント
- 新しい商業施設・公共施設の開業
- 徒歩導線の改善(歩道整備・街灯増設など)
- 周辺の再開発事業の進行
- 地域の人口動態の改善(転入増加・若年層増加など)
特に投資用物件では、募集賃料や入居率の向上が確認できれば土地・建物の市場価値が同時に上昇し、評価アップの説明材料として使えます。
土地評価のルールを理解し“上がりやすい要素”を把握する
土地の担保評価は、主に路線価、公示地価、基準地価の3つを基準とした金融機関独自の算定方法で決まります。評価の仕組みを理解しておくと、改善可能な余地が見えてきます。
チェックしておくと有利になる項目
- 路線価の上昇トレンドと発表時期
- 近隣の取引価格の変動
- 接道状況(間口改善やセットバックの可能性)
- 地形の評価(形状、旗竿地の扱い、間口の広さ)
接道状況の改善は自力で変えられない場合が多いですが、地役権設定や隣地との協議によって評価が上がるケースもあります。不動産事業としての経験や交渉力が発揮される場面でもあります。
評価資料を揃えて金融機関に“加点材料”を伝える
評価は担当者の判断要素も多いため、所有者の説明の質が評価を変えることがあります。数値や改善資料が揃っているほど、「担保価値の裏付けが明確」と判断され、金利交渉にも有利です。
準備しておくと効果的な資料
- 直近の修繕履歴・写真・見積書
- 周辺の地価動向・統計データ
- 入居率や収益改善データ(投資用物件の場合)
- 施工保証書や耐震補強の証明書
特に投資家の場合、収益性の改善データは担保評価だけでなく、事業計画の信頼性を高める材料にもなり、総合的に金利が下がりやすくなります。

担保不動産の価値を高める工夫は、専門的な話に見えて、実は手を入れられるポイントが多いんです。劣化を止める、寿命を延ばす、周辺環境の変化を正しく伝える。この3つを押さえるだけでも評価は変わりますので、できるところから取り組んでみてくださいね
担保掛目の仕組みと金利への影響
担保掛目(LTV:Loan to Value)は、不動産担保ローンの金利を決めるうえで重要な基準です。金融機関は担保となる不動産に「どこまで価値を認めるか」を掛目で判断し、その水準が高いほど金利に直接影響します。投資家が最も見落としやすいポイントでもあるため、仕組みと金利の関係を明確に整理します。
担保掛目の基本構造と評価の流れ
担保掛目とは、不動産評価額に対して金融機関が融資可能と判断する割合のことです。多くの金融機関は70〜80%を標準としていますが、実際の計算には次のステップがあります。
- 不動産評価額(時価・路線価・収益還元など)を算出
- 金融機関が基準とする掛目を適用
- 算出された「実質的担保価値」が融資限度額となる
例えば評価額5,000万円で掛目80%なら担保価値は4,000万円です。この4,000万円が、金融機関がリスク管理の観点から安全と判断する“最大ライン”になります。
LTVが金利に与える圧倒的な影響
金融機関はLTV(融資額 ÷ 担保評価額)が低いほどリスクが小さいと判断します。
そのため、同じ信用力の投資家でもLTVによって金利が大きく変わります。
LTVが低いケース(例:60%以下)
・担保余力が大きいため延滞・破綻時の売却リスクが小さい
・金融機関のリスクが減るため金利は下がりやすい
・条件次第で基準金利からの優遇が適用されることも多い
LTVが高いケース(例:80〜90%)
・担保価値の下落や売却期間の長期化に耐えられない
・金融機関は損失リスクが増加
・上限金利に近づく、または追加担保を求められるケースもある
LTVと金利決定の実務プロセス
金融機関はLTVを単独で判断するのではなく、他の審査要素と組み合わせて総合的に評価します。
- 信用情報・返済能力
- 収益性(法人の場合はPL/BSの健全性)
- 資金使途の妥当性
- 担保物件の流動性
特に投資用不動産の場合は「売却しやすさ」によって掛目が変わるため、築古・特殊用途・地方物件などはLTVが下がり、金利も上昇しやすくなります。
実際の金利差が生まれるポイント
借入額を調整するだけで金利が下がるケースが多い
一般的には、融資限度額いっぱいを借りるとリスクが最大化されるため、金融機関は金利を高めに設定します。
一方で、限度額から数百万円〜1割程度抑えるだけで金利が下がることがあります。
例:評価5,000万円、掛目80% → 限度額4,000万円
・限度額4,000万円で申込み → 高金利帯
・申込額3,600万円に調整 → 余力400万円が評価され金利が低下
投資家にとって最も実務的な金利調整ノウハウです。
金利を下げるための担保掛目の使い方
担保掛目は投資家側でも工夫できる余地が大きいポイントです。
金利引き下げに役立つ工夫
- LTVを下げるために借入額を意図的に抑える
- 評価額が上がる見込みのある改善(外壁補修・用途変更など)を行う
- 収益還元法の改善を狙い、賃料調整・稼働率の向上を図る
- 売却流動性のあるエリア・用途の物件を担保に選定する
注目すべきは「担保余力」という概念
金融機関は担保価値の“余力”を非常に重視します。
余力がある場合、将来の追加融資も見込めるため、優遇金利を提示しやすくなります。
投資家が押さえるべきポイント
- LTVの高さは金利に直結する
- 限度額ぴったりの借入は避けた方が低金利を狙いやすい
- LTV改善は借入額調整だけでも可能
- 収益物件は流動性が評価を左右するため、物件選びが金利に影響

担保掛目は、投資家がコントロールしやすい数少ない金利要因なんです。借入額を調整したり、担保余力を残すだけでも金利は変わってきます。リスクと利息のバランスを見ながら、最適なLTVを意識してみてくださいね
資金使途の良否が金利を左右する理由
不動産担保ローンでは「資金使途の妥当性」が金利に大きな影響を与えます。担保評価や信用情報と同様、資金使途は金融機関にとって返済リスクを測る重要な材料であり、曖昧さや不自然さがあると金利は上昇し、反対に合理的で透明性が高いほど低金利が提示されやすくなります。
なぜ資金使途が金利に直結するのか
資金使途が信用判断のカギになるのは、金融機関が「資金の流れ」と「返済可能性」を具体的に把握できるからです。金利はリスクの大きさで決まるため、何のために借りるのかが明確であるほど、リスクは低く評価されやすくなります。
資金使途が金利に影響する主な理由は次のとおりです。
- 資金回収までの見通しが立つと返済リスクが下がる
- 必要額の妥当性が判断できるため、過剰融資を避けられる
- 透明性が高い案件は不正利用リスクが低い
- 財務状況・事業状況との整合性が取れていると信用力が上がる
用途と返済原資の関係が合理的であれば、金融機関は「安全性が高い」と判断し、金利を引き下げる余地を持ちます。
用途別で変わる金利の傾向
資金使途は「良い」「悪い」という単純な話ではなく、金融機関の融資方針と整合しているかどうかが重要です。特に銀行とノンバンクでは判断軸が異なります。
銀行が低金利を提示しやすい用途
銀行は返済原資が明確で、事業の安定性が高い用途に対して金利を抑えやすい傾向にあります。
- 設備投資(投資効果が数字で示せる)
- 不動産取得・建築関連(担保価値と連動しやすい)
- 借換目的(返済履歴が評価しやすい)
一方、運転資金など回収の根拠が弱い用途は、銀行では制限される場合もあります。
ノンバンクが柔軟に対応する用途
ノンバンクは用途の幅が広く、事業性資金にも積極的です。
ただし、柔軟である分リスクも踏まえた金利設定になるため、用途説明の精度が低いと銀行より金利が上がるケースがあります。
金利を下げるために必要な資金使途の「説明力」
金融機関は、資金使途そのものよりも「説明が的確か」「裏付けがあるか」を重視します。
とくに投資家が低金利を狙ううえで意識したいのは、次の3点です。
1. なぜその用途で資金が必要なのかを数値で説明できるか
- 売掛金の増加による一時的運転資金
- リフォームにより賃料が上がる見込み
- 購入物件の表面利回りと返済計画の整合性
数字が伴うと、資金需要の必然性が伝わりやすくなります。
2. 必要額が過不足なく妥当であるか
適切な金額設定は金融機関の警戒心を下げ、金利引き下げの対象になります。
過剰借入は返済能力を圧迫するため、金利が高く設定されやすくなります。
3. 根拠資料の提出で透明性を高められるか
- 財務諸表
- 帳簿・売掛金管理資料
- 事業計画書
- リフォーム見積書
- 売買契約書
これらは資金使途の妥当性と返済可能性の裏付けとなるため、低金利獲得に非常に有効です。
投資家が注意したい「金利が上がりやすい資金使途」
資金使途の説明が不十分なケースや、不透明性が高い用途は、金融機関が「返済原資が読みづらい」と判断し金利が上昇する原因になります。
- 赤字補填など返済原資が不明確な資金
- 説明が曖昧で、必要額の妥当性が判断できないケース
- 将来収益の裏付けが弱い投機的な投資資金
- 借入状況との整合性が取れない用途
これらは審査上の不利につながりやすく、低金利を狙う投資家は特に注意が必要です。
金利を下げたい投資家のための最適なアプローチ
資金使途の良否で金利が変わる以上、投資家に求められるのは「金融機関が安心して融資できる状態を、資料と説明で作り込むこと」です。
- 資金使途と返済原資の因果を整理
- 数字(売上・利益・回収期間・利回り)を添えて説明
- 必要額の根拠を資料で提示
- 不要な借入を避け、過剰感を出さない
- 実現性の高い改善計画・事業計画を準備
特に投資案件では、賃料収入・利回り・返済比率・LTVなど、金融機関が重視する項目と資金使途が一致しているかどうかが決定的です。

資金使途の整理は「返済の見える化」に直結します。金融機関が安心できる材料を提示できれば、金利は自然と下がりやすくなりますよ
借入期間と金利タイプの選び方
不動産担保ローンの金利を左右する要素の中でも、「借入期間」と「金利タイプ」の選び方は、投資家にとって戦略そのものと言ってよい重要ポイントです。金利そのものだけを見るのではなく、キャッシュフローの安定性や出口戦略との整合性まで含めて設計することが大切です。
固定金利・変動金利・固定期間選択型の基本的な考え方
まずは代表的な3つの金利タイプの特徴を整理しておきます。
- 固定金利
借入時に決まった金利が完済まで変わらないタイプです。将来の金利上昇リスクを金融機関側が負うため、一般的には変動金利より高めの水準になります。特に借入期間が長くなるほど、予測不能なリスクを織り込む必要があるため、金利は高くなりやすい傾向があります。 - 変動金利
一定のタイミング(半年ごと・年ごとなど)で金利が見直されるタイプです。借入当初の金利は低めに設定されることが多く、借入期間による金利差も小さい場合が一般的です。ただし、将来の金利上昇リスクは投資家側が負うことになります。 - 固定期間選択型
「3年固定」「5年固定」「10年固定」など、一定期間だけ金利を固定するタイプです。固定期間が長くなるほど金利は高くなる傾向がありますが、金融機関の資金運用方針や金利環境によって、特定の期間だけ金利が低く設定されているケースもあります。固定期間終了後は、多くの場合、変動金利または再度の固定選択に切り替わります。
投資家にとって重要なのは、「どのタイプが一番有利か」ではなく、「自分の投資戦略とキャッシュフローに最も整合的なタイプはどれか」を軸に選ぶことです。
借入期間が長くなるほど総利息はどう変わるか
借入期間を長くすると、毎月の返済額は抑えられる一方で、総利息の負担は必ず増えます。これは、元本が長い期間残ることで、その分だけ利息が積み上がっていくためです。
ただし、固定金利と変動金利では「借入期間」と「適用金利」の関係が異なります。
- 固定金利の場合
借入期間が長くなるほど、1年あたりの適用金利自体が高くなりやすく、さらに返済期間が長いため、総利息は二重の意味で増えやすくなります。 - 変動金利の場合
借入期間の長さによって金利水準が大きく変わらないことも多く、当初の金利だけを見ると「長期でも負担が軽そう」に見えます。ただし、将来の金利上昇で返済額が増えるリスクが積み上がっていきます。
投資家としては、「毎月いくらまでなら無理なく返済できるか」と「トータルでどこまで利息を許容するか」を分けて考え、シミュレーションで両方のバランスを確認しておくことが重要です。
投資家のキャッシュフローと投資期間に合わせた期間設定
不動産担保ローンを使う投資家の場合、「投資の出口」がどこにあるかによって、適切な借入期間は大きく変わります。
例えば、以下のようなパターンが考えられます。
- 売却前提の短期〜中期投資
バリューアップ後の売却(いわゆる出口戦略)を3〜7年程度で想定している場合、ローン期間を長く取りすぎると、売却時点で多くの元本が残り、手取りキャッシュが圧縮される可能性があります。 一方で、期間を短くしすぎると毎月返済が重くなり、投資全体のキャッシュフローが悪化します。 そのため「売却予定時期+少し余裕を持たせた期間」を設定し、繰上返済で柔軟に調整できるようにしておく考え方が有効です。 - 保有・賃貸運用を前提とした長期投資
インカムゲイン目的で長期保有を前提とする場合、空室リスクや修繕費の発生など、キャッシュフローのブレも大きくなります。 このケースでは、あえて返済期間を長めに取り、毎月返済額を抑え、DSCR(返済余裕倍率)を厚めに確保しておく方が安全な場合もあります。
投資家にとってベストなのは、「ローンの完済時期」と「投資の出口時期」を、できるだけ近いレンジにそろえつつ、「もし予定通りにいかなかった場合」のバッファも確保しておく期間設計です。
金利タイプ別の向き・不向き
金利タイプは、投資スタイルやリスク許容度によって向き・不向きが分かれます。
- 固定金利が向いているケース
- 長期保有を前提とし、家賃収入で安定的に返済していきたい
- 金利上昇局面に入っている、もしくは今後の金利上昇リスクが高いと判断している
- キャッシュフロー計画をできるだけブレなく設計したい
- 変動金利が向いているケース
- 当面の金利は低めに抑え、投資初期のキャッシュフローを重視したい
- 中期的な売却を予定しており、長期的な金利上昇リスクをあまり取りたくない
- 金利上昇局面に入った場合には、繰上返済や借り換えで機動的に対応する方針がある
- 固定期間選択型が有効なケース
- リノベーションや賃料増額など、数年以内に価値向上のイベントを予定している
- 当面の数年間だけ返済負担を安定させ、その後は売却・借り換えなどで再設計する可能性が高い
- 金融機関側が特定の固定期間に低めの金利を設定しており、その期間内に出口を取りにいくシナリオが描ける
単に「固定は安全」「変動は危険」といった単純な二分ではなく、「自分の投資シナリオを実現するために、どのタイプをどう組み合わせるか」という視点で見ていくことがポイントです。
金融機関が融資しやすい条件を踏まえた選び方
実務上は、「金融機関が融資しやすい借入期間・金利タイプ」を把握しておくと、金利条件の交渉余地が広がります。
金融機関は、自社の貸出ポートフォリオのバランス(固定金利と変動金利の比率、償還時期の分布など)を見ながら、新規のローン条件を調整しています。そのため、次のようなスタンスで情報を取りに行くことが有効です。
- 事前相談の段階で「どの金利タイプ・何年くらいの期間が、今は融資しやすいか」を率直に聞いてみる
- 固定期間選択型の場合、3年・5年・10年など複数パターンで金利を提示してもらい、「金融機関が特に出したがっている期間」を見極める
- 借入期間にある程度融通が利く場合、金融機関の提示する「低めの金利が出しやすい期間」に合わせることで、条件を引き出しやすくする
単に希望条件を一方的に伝えるのではなく、「金融機関側が扱いやすい条件」と「投資家側の投資戦略」をすり合わせるイメージで期間と金利タイプを決めていくと、結果として有利な金利を引き出せるケースが多くなります。
実務での検討ステップ
借入期間と金利タイプを選ぶ際には、次のようなステップで整理していくと判断しやすくなります。
- 投資の出口(売却・長期保有・借り換え)と想定年数を明確にする
- 賃料収入・運営費・修繕費などを踏まえ、無理なく維持できる毎月返済額の上限を把握する
- 複数の期間・金利タイプで返済シミュレーションを行い、総利息とキャッシュフローのバランスを比較する
- 金融機関に「出しやすい」条件をヒアリングし、自分の投資シナリオと重なる期間・金利タイプを選ぶ
- 金利上昇や空室が発生した場合の「バッファ」を組み込んだ上で最終決定する
このプロセスを踏んでおくことで、「なんとなく固定」「とりあえず変動」といった感覚的な選び方を避けることができ、金利交渉でも論理的に話を進めやすくなります。

借入期間と金利タイプの選び方は、正解が一つだけではなくて「自分の投資シナリオとの相性」が決め手になるんです。出口のタイミングとキャッシュフローをまず固めたうえで、固定・変動・固定期間選択型を組み合わせていくと、金融機関との交渉でも主導権を握りやすくなりますよ。「返済額の安さ」だけに目を奪われず、「総利息」と「リスク許容度」のバランスを意識して設計していきましょう
投資家が金利比較で失敗しないポイント
不動産担保ローンは「金利の見え方」が複雑で、表面上の数字だけで判断すると本質的なコスト差を見落とすリスクがあります。特に投資家の場合、資金調達スピード・返済条件・過去取引実績などが金利に大きく影響します。ここでは、金利比較で失敗しがちなポイントと、投資家が押さえておくべき判断基準を整理します。
表面金利だけの比較は危険
金融機関が提示する金利には「表面金利」と「実質コスト」の差があります。特に不動産担保ローンは、以下の付帯コストによって総負担額が大きく変わります。
- 事務手数料(定額・定率の違い)
- 保証料の有無(銀行は保証料型が多い)
- 繰上げ返済手数料の有無と金額
- 印紙税や登録免許税の扱い
- 毎月の返済方式(元利均等・元金均等)
同じ1.9%の表示でも、手数料や保証料の違いで年数十万円の差が生まれることは珍しくありません。投資家は金利だけでなく「総支払額の差」で比較することが鉄則です。
シミュレーションは最低3社で比較する
複数社比較は基本ですが、不動産担保ローンは審査ロジックが金融機関ごとに大きく異なります。同じ担保評価でも、A社は75%掛目、B社は80%掛目ということもあり、実際の借入額と金利が変動します。
最低でも「銀行1〜2社+ノンバンク1社」を組み合わせると、幅広い金利帯を把握でき、交渉材料としても有効です。
過去の完済履歴が優遇されるケースを見逃さない
投資家が見落としがちな重要ポイントとして、完済履歴がある金融機関は金利が下がりやすい傾向があります。金融機関から見ると「返済実績が確認できる投資家」は信用度が高く、審査が柔軟になります。
初めて借りる金融機関よりも、過去に正常完済している金融機関の方が有利な条件を提示されるケースは多いため、比較対象に必ず含めておくことがおすすめです。
金利条件だけでなく「審査スピード」と「柔軟性」を評価軸に加える
投資家にとって資金調達タイミングは成果を左右します。最も低金利の金融機関が、最も良い選択肢とは限りません。
- 担保評価のスピード
- 仮審査の回答までの時間
- 書類提出の柔軟さ
- 事業性融資に慣れているか
- 担当者のコミュニケーションレベル
こうした要素は、投資機会の損失防止やプロジェクト推進に直結します。特にノンバンクはスピード・柔軟性が強く、投資案件によっては金利差以上の価値があります。
金利タイプと借入期間の組み合わせを最適化する
金利比較をするとき、最も誤解が生まれやすいのが「金利タイプと期間設定」です。
- 固定型は長期ほど高金利
- 変動型は期間による金利差が小さい
- 固定期間選択型は金融機関ごとに有利な期間が異なる
同じ金融機関でも「10年固定が最安」「5年固定が最安」などのケースが存在します。商品性を理解しないまま金利比較をすると、自身のキャッシュフローに不利な選択をする可能性があります。
手数料・返済条件・スピードを踏まえた“総合点”で判断する
総合評価を行うときは、以下の整理が有効です。
- 表面金利
- 事務手数料・保証料などの実質コスト
- 借入可能額(掛目の違い)
- 審査スピード
- 担当者の柔軟性
- 過去取引実績の有無
- 繰上げ返済のしやすさ
金利だけでは判断できない「事業としての最適解」が見えるため、投資家目線での比較が可能になります。

金利だけを追うと本質を見落としますよ。総支払額、審査スピード、柔軟性まで含めて“投資としての最適解”を考えることが成功の近道です
| 順位 | 商品名 | 会社名 | ポイント | 下限実質年率 | 上限実質年率 | 提供企業の種類 | 対応地域 | 融資金額 | 最大返済期間 | 事務手数料 | 解約料 | 対象 | 第三者の担保利用 | 審査スピード | 融資スピード | 融資条件備考 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | SBIエステートファイナンス不動産担保ローン | SBIエステートファイナンス | SBIグループの安心の不動産担保ローン。低金利・一都三県 | 年3.70% | 年7.80% | SBIグループ、大手ノンバンク | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を中心に展開 | 300万円~10億円 | 35年 | 融資金額の2.20%~2.75% ※ご成約(ご融資)時にのみ頂戴いたします。実質年率15.00%以下※支払利息・各種手数料などを含め、全ての支払いの合計額を年率で換算したもの。 | 元金入金額の3.00% | 個人・個人事業主・法人 | ○親族名義 | 最短即日 | 申し込みから最短翌日 | 登録番号:関東財務局長(3)第01516号・日本貸金業協会会員 第003635号、登録電話番号:0368514649、融資年率:変動金利3.70%~7.80%(みずほ銀行が公表する短期プライムレート+1.575%~5.675%)※お借入れ後の適用年率は年2回見直しを行います。、返済期間:1年~35年、返済回数:12回~420回、返済の方式:元利均等返済、実質年率:15.00%以下※支払利息・各種手数料などを含め、全ての支払いの合計額を年率で換算したもの。、遅延損害金:年率19.80%、担保:不動産 | 公式サイト |
| 2位 | りそな銀行りそなフリーローン(有担保型) | りそな銀行 | 大手都市銀行の不動産担保ローン。低金利かつ長期借り入れが可能 | 年3.175% | 年10.30% | 大手都市銀行(メガバンク) | 全国 | 100万円~1億円 | 30年 | 110,000円 | 11,000円 | 個人 | ○親族(三親等以内) | - | - | - | 公式サイト |
| 3位 | 東京スター銀行スター不動産担保ローン | 東京スター銀行 | 地方銀行の不動産担保ローン。変動金利と固定金利あり | 年1.26% | 年9.45% | 地方銀行 | 全国 | 100万円~1億円 | 30年 | 融資額の2.20% | 借入期間5年以内:返済元金の1.10%,借入期間5年超:返済元金の0.55%(税込) | 個人 | ○配偶者、実父母、実兄弟姉妹 | 1週間前後 | - | - | 公式サイト |
| 6位 | 楽天銀行不動産担保ローン | 楽天銀行 | ネット銀行の不動産担保ローン。下限金利が低金利 | 年1.83% | 年10.59% | 楽天グループ、ネット銀行 | 全国 | 100万円~1億円 | 25年 | 融資額の2.20% | 無料 | 個人 | ○親族(三親等以内) | 最短翌営業日 | 最短3週間 | - | 公式サイト |
| 7位 | 住信SBIネット銀行不動産担保ローン | 住信SBIネット銀行 | ネット銀行の不動産担保ローン。仮審査はWEB完結 | 年3.45% | 年9.40% | SBIグループ、ネット銀行 | 全国 | 300万円~1億円 | 35年 | 融資額の2.20% | 繰り上げ返済額の3.143% | 個人 | ○家族名義 | - | 3週間から1カ月程度 | - | 公式サイト |
| 8位 | オリックス銀行不動産担保ローン | オリックス銀行 | 信託銀行の不動産担保ローン。固定金利が低金利 | 年3.90% | 年7.375% | オリックスグループ、信託銀行 | 首都圏・近畿圏・名古屋市・福岡市 | 1,000万円~2億円 | 35年 | 融資額の1.10% | 繰上返済元金金額に対する2.00% | 個人 | ○家族名義 | 約1週間 | - | - | 公式サイト |
| 9位 | 新生インベストメント&ファイナンス不動産担保ローン | 新生インベストメント&ファイナンス | 新生グループの不動産担保ローン。上限金利が低金利 | 年2.95% | 年5.90% | 新生グループ、大手ノンバンク | 東京、神奈川、千葉、埼玉 | 300万円~10億円 | 35年 | 融資額の2.20% | 元金残高の2.00~3.00% | 個人・個人事業主・法人 | ○親族 | - | 最短1週間 | - | 公式サイト |
| 10位 | 三井住友トラストL&F不動産活用ローン | 三井住友トラストL&F | 三井グループの不動産担保ローン。最大10億円の借り入れが可能 | 年3.39% | 年6.80% | 三井住友グループ、大手ノンバンク | 全国 | 300万円~10億円 | 35年 | 融資額の2.20% | 元金入金額の~3.00% | 個人・個人事業主・法人 | ○他人名義 | 2営業日以内 | 最短1週間 | - | 公式サイト |
| 11位 | アサックス不動産担保ローン | アサックス | 独立系大手ノンバンクの不動産担保ローン。上限金利が低金利 | 年1.95% | 年7.80% | 大手ノンバンク | 東京、神奈川、千葉、埼玉 | 300万円~10億円 | 30年 | 融資額の0%~3.3% | 元金入金額の~3.00% | 個人・個人事業主・法人 | ○親族 | 最短即日 | 最短3日 | - | 公式サイト |
| 12位 | 岡村商事不動産活用ローン | 岡村商事 | 関西エリアのノンバンクの不動産担保ローン。関西の方におすすめ | 年3.50% | 年9.50% | 中小ノンバンク | 高知県、愛媛県、香川県、徳島県、岡山県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、三重県、愛知県 | ~1億円 | 25年 | 融資額の0%~3.3% | 元金入金額の~2.00% | 個人・個人事業主・法人 | ○家族名義 | 最短即日 | 最短2日 | - | 公式サイト |
| 15位 | 日宝不動産活用ローン | 日宝 | ノンバンクの不動産担保ローン。高金利だが審査に強み | 年4.00% | 年9.90% | 中小ノンバンク | 全国 | 50万円~5億円 | 30年 | 不明 | 不明 | 個人・個人事業主・法人 | - | - | - | - | 公式サイト |
| 16位 | マテリアライズ不動産担保ローン | マテリアライズ | ノンバンクの不動産担保ローン。高金利だが審査に強み | 年5.00% | 年15.00% | 中小ノンバンク | 全国 | 100万円~1億円 | 20年 | 融資額の0%~5.0% | 不明 | 個人・個人事業主・法人 | - | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | - | 公式サイト |
| 17位 | つばさコーポレーション不動産スーパーサポートローン | つばさコーポレーション | ノンバンクの不動産担保ローン。高金利だが審査に強み | 年3.80% | 年7.80% | 中小ノンバンク | 全国 | ~5億円 | 30年 | 融資額の0%~5.0% | 元金入金額の~5.00% | 個人・個人事業主・法人 | - | 最短7日 | 最短7日 | - | 公式サイト |
| 18位 | ジェイ・エフ・シー不動産活用ローン | ジェイ・エフ・シー | ノンバンクの不動産担保ローン。高金利だが審査に強み | 年5.86% | 年15.00% | 中小ノンバンク | 全国 | 300万円~5億円 | 10年 | 融資額の0%~5.0% | 元金入金額の~5.00% | 個人・個人事業主・法人 | - | 最短3日 | 最短3日 | - | 公式サイト |
| 19位 | トラストホールディングス不動産活用ローン | トラストホールディングス | ノンバンクの不動産担保ローン。高金利だが審査に強み | 年3.45% | 年7.45% | 中小ノンバンク | 全国 | 100万円~10億円 | 30年 | 融資額の0%~5.5% | 元金入金額の~5.50% | 個人 | - | 最短即日 | 最短即日 | - | 公式サイト |
| 4位 | セゾンファンデックス事業者向け不動産担保ローン | セゾンファンデックス | セゾンファンデックス | 年3.15% | 年9.90% | セゾングループ、大手ノンバンク | 全国 | 500万円~10億円 | 30年 | 残元金に対して最大3.3%(税込) | 11,000円 | 個人事業主・法人 | ○代表者の親族(三親等以内)が所有する不動産 | 最短3営業日審査回答 | 最短1週間 | - | 公式サイト |
| 5位 | AGビジネスサポート不動産担保ローン | AGビジネスサポート | AGビジネスサポート | 年2.49% | 年14.80% | アイフルグループ、大手ノンバンク | 全国 | 100万円~5億円 | 30年 | 融資額の0~3.00% | - | 個人事業主・法人 | ○ | 最短3日 | - | - | 公式サイト |