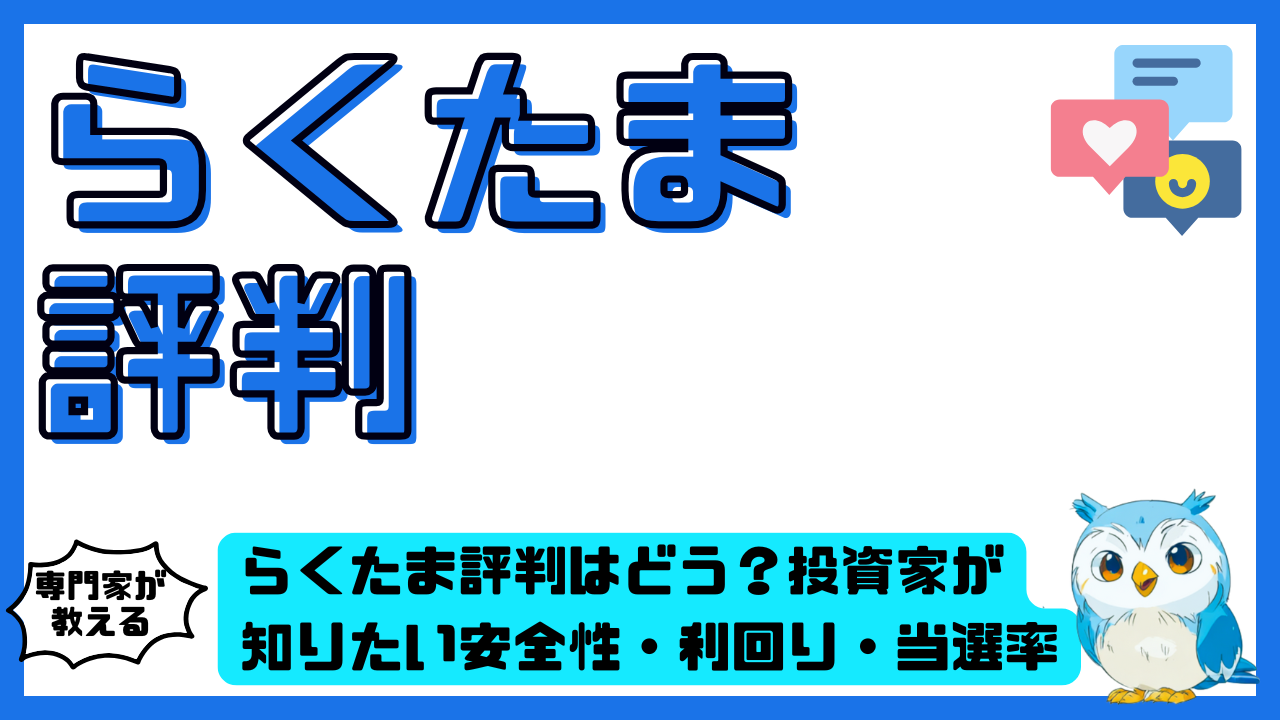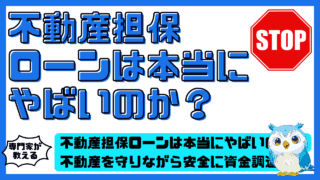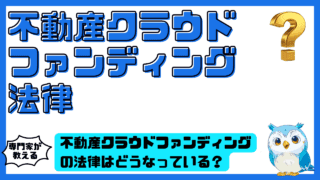本ページはプロモーションが含まれています。
目次
らくたまの基本情報と押さえておくべき特徴
らくたまはどんな不動産クラウドファンディングか
らくたまは、インターネット上で複数の投資家から資金を集め、その資金で不動産を取得・運用し、そこで得られた賃料収入や売却益の一部を投資家に分配する不動産クラウドファンディングサービスです。
会員登録から本人確認、ファンドへの応募、出資確定、入金、償還の確認まで、基本的な手続きはすべてオンラインで完結します。店舗に行く必要がないため、忙しい会社員や副業で資産運用をしたい投資家でも利用しやすいサービス設計になっています。
投資家側は、不動産を直接購入して管理するのではなく、ファンドを通じて「間接的に」不動産事業に参加するイメージです。そのため、少額から分散投資しやすい一方で、不動産市況や運営状況の影響はしっかり受ける点も押さえておく必要があります。
投資条件とファンドの基本スペック
らくたまのファンドは、少額から始められることと、条件が比較的シンプルで把握しやすいことが特徴です。代表的なスペック感は次のようなイメージです。
- 最低投資額は1万円程度から
- 想定利回りはおおむね年5〜6%台の高めゾーンが中心
- 運用期間は数ヶ月〜1年程度の短期案件が多い
- 募集方式は抽選式が中心で、一部先着方式の案件もある
- 投資対象はマンション、オフィス、店舗ビル、物流施設、土地など幅広い
「1万円から」「短期×高めの利回り」という組み合わせのため、いきなり大きな金額を投じるのではなく、少額を複数ファンドに分散しながら慣れていきたい投資家とも相性が良いサービスです。
らくたま特有のルールと運用設計のポイント
らくたまを語るうえで外せないのが、独自に設計された各種ルールです。単純に「利回りが高い」だけでなく、「どういうルールでその利回りを支えるのか」という部分まで作り込まれている点が特徴的です。
代表的なものとして、早期償還時でも予定されていた運用期間ぶんの配当が支払われる「全期間配当保証付きファンド」や、資金が拘束される日数を短くするための「5日ルール」「翌日償還」の運用方針があります。
こうした仕組みにより、
「思ったより早く売却されてしまい、利回りが下振れする」
「運用が終わっているのに、なかなか償還されず資金が動かせない」
といった投資家の不満を抑えようとしている点が、らくたまの大きな特徴です。
また、ファンド延長や償還遅延を極力出さない方針や、償還用にあらかじめ資金をプールしておく体制など、投資家保護を前面に出したルール群も整備されています。詳細な数字や実績は別のセクションで深掘りすることになりますが、らくたまの評判を理解するうえで「ルール設計そのものが特徴になっている」という視点は押さえておくと良いでしょう。
リスク管理の土台となる優先劣後構造
らくたまのファンドは、基本的に「優先劣後方式」という構造を採用しています。これは、投資家が「優先出資」、事業者側が「劣後出資」として出資する方式で、損失が出た場合にはまず劣後出資(事業者側)が先にダメージを受け、一定の範囲までは投資家の元本が守られる仕組みです。
一般的な不動産クラウドファンディングでも広く使われている仕組みですが、らくたまの場合は、この劣後出資割合が比較的厚めに設定されているファンドが多いことがポイントです。劣後出資割合が厚いほど、不動産価格の下落や運用のブレを吸収できる余地が大きくなり、優先出資者である投資家にとっての「クッション」が分厚くなります。
さらに、運用期間そのものが短めに設計されているため、「長期で市況が大きく変動してしまい、想定より大きなダメージを受ける」というリスクも、ある程度抑えやすい構造になっています。もちろん、元本割れリスクがゼロになるわけではありませんが、「優先劣後構造×短期運用」の組み合わせは、らくたまのリスク管理を理解するうえで重要なポイントです。
運営会社のバックグラウンドと信頼性の見方
らくたまの運営会社は、不動産事業で長年の実績を持つ不動産会社グループです。不動産クラウドファンディング専業の新興企業ではなく、既存の不動産投資・開発・運用事業を行ってきたうえで、そのノウハウとネットワークを活かしてクラウドファンディング事業を展開しているポジションと言えます。
不動産投資の世界では、運営会社の「目利き力」と「資金力」「ネットワーク」が案件の質に直結します。らくたまの場合も、これまで蓄積してきた不動産投資の実績や、保有資産・含み益などを背景にして、
- 償還用のリザーブ資金の準備
- ファンド延長に頼らない運用方針
- 自社買戻しを含めた出口戦略
といった投資家保護策を打ち出している点が特徴です。
投資家がらくたまの安全性を評価する際には、「利回りの高さ」だけでなく、「運営会社がどの程度の規模・実績を持ち、その資金力をどう投資家保護に振り向けているのか」という視点も合わせてチェックしておくと判断しやすくなります。

らくたまは、1万円から参加できる不動産クラファンの中でも、ルール設計と運営会社のバックボーンまで含めて“投資家側に寄せた”作り込みが強いサービスです。まずはここで紹介した基本情報と特徴を押さえたうえで、自分のリスク許容度や投資スタイルとどこまで相性が良いかを冷静に見ていくのがおすすめですよ
投資家が最も気になる評判まとめ。良い口コミの傾向
らくたまの評判には、投資家が実際に感じた「運用のしやすさ」「利回りの納得感」「サービス品質」への評価が濃く反映されています。特に良い口コミは、特定の機能や実績に対して集中しており、投資家がメリットを実感しやすい構造になっている点が特徴です。
早期償還でも実質利回りが上振れする仕組みへの満足度が高い
良い口コミで最も多いのが、早期償還でも利回りが下がらず、むしろ実質リターンが伸びる点を評価する声です。
全期間配当保証により、想定以上の利回りを得られた投資家が多く、X(旧Twitter)でも「利回りが跳ね上がった」「資金効率が抜群」といった投稿が頻出しています。
全期間配当保証を採用するサービスは一般的ではないため、「短期運用×利回り上振れ」というメリットは、らくたまの口コミで突出して評価されるポイントになっています。
抽選と先着、両方の方式があることで「投資機会の取りやすさ」が好評
募集倍率が高いサービスでありながら、「抽選式でも先着式でも応募機会がある」という点は、多くの投資家がメリットとして挙げています。
特に以下のような傾向が見られます。
- 先着募集でうまく入れた投資家が「クリック合戦を勝てた喜び」を共有
- 抽選で当選した投資家が「部分当選でもありがたい」という評価を投稿
- 抽選落ちからの繰り上げ当選報告も多く、救済措置に対する満足度が高い
投資家によって応募スタイルが異なるため、複数方式の採用が「不公平感の少なさ」につながっている印象です。
運用会社の信頼性や開示情報の多さへの安心感
不動産クラウドファンディングでは、運営会社の透明性は評判を左右する大きな要素です。
らくたまについては、以下のような投稿が多く見られます。
- ファンドページの情報量が多く、収支や運用シナリオが具体的で分かりやすい
- 運用会社の決算資料や不動産の含み益などを積極的に開示しており、説明責任が明確
- 投資家保護に関する方針が頻繁にアップデートされる
「とにかく開示が丁寧」「初心者でも判断しやすい」という評価が多く、投資判断のしやすさが口コミでも重要な評価軸になっています。
独自の投資家保護制度への強い評価
良い口コミの中でも、「らくたまを選ぶ理由」として最も多く挙がるのが独自ルールへの評価です。
代表的なものとして、
- 償還用リザーブ資金の存在
- ファンド延長ゼロの運用方針
- 劣後出資割合が40〜60%と高く、元本保全力が強い
- 翌日償還と5日ルールで資金拘束が短い
などがあります。
特に「投資家プロテクトルール」への共感が強く、他サービスで遅延や延長を経験した投資家ほど「安心して預けられる」という口コミが多い傾向です。
優待サービス「ハッピーパスポート」の価値を評価する声
利回り以外の付加価値として、会員ランクごとに優待サービスが使える点も、口コミで注目されています。
- ベネフィット・ステーションが使える
- 優待ポイントが定期的にもらえる
- 投資額によって体験価値が高まる
など、「副次的メリット」に魅力を感じる投資家が一定数存在します。
利回り以外の“実感しやすい特典”が、らくたまの総合的な満足度を押し上げていると言えます。
総合的に見た良い口コミの傾向
良い口コミには次のような共通点があります。
- 高利回り×リスク抑制が両立している点への高評価
- 資金効率の良さが実感できる仕組みがある
- 運用会社の透明性と開示量が多く、安心して申請できる
- 投資家向けの制度や優待が厚く、“投資家ファースト”を感じる
らくたまは「利回り」「安全性」「開示」「利便性」という複数の要素が揃っているため、良い口コミは単一ポイントではなく、多方面からの評価が多い点が特徴的です。

良い口コミは「利回り」と「投資家保護」だけでなく、運用の安心感やサービス全体の使いやすさに対する総合的な満足度が高い印象ですね。投資家が“ストレスなく利用できる仕組み”を評価している点が、他社にはない強みだと感じます
悪い評判に多い落選問題と投資しづらさの実情
らくたまの評判で最も目立つネガティブ要素は、サービス自体の品質ではなく「当選しづらさ」です。実際の口コミを整理すると、投資家が感じている不満は「投資したいのに投資できない」という一点に集約されます。利回りや安全性に満足しているからこそ、応募が殺到し、倍率が上がり続けている状況が背景にあります。
募集倍率が高騰し続ける理由とその影響
らくたまのファンドは、人気ファンドで募集率900%以上に達した事例が複数あります。特に短期×高利回り×高い劣後比率が揃ったファンドは応募が集中しやすく、抽選に申し込めば必ず落選するという投資家もいます。
倍率上昇の主な要因は以下が挙げられます。
- 高利回り(5.5〜6.5%)のファンドが連続して提供されている
- 全期間配当保証や翌日償還など独自ルールが投資効率を高めている
- 償還遅延ゼロ・元本割れゼロという実績が信頼を強めている
- 短期ファンドの増加により資金が循環しやすい構造になっている
このように、サービスの質が高いことが倍率上昇につながり、結果として「投資しづらい」という状況を生んでいます。
部分当選が続く投資家が感じているストレス
らくたまでは、応募額に対して希望通りの金額が割り当てられない「部分当選」のケースも多く見られます。部分当選は投資家側にとって必ずしも悪い仕組みではありませんが、一定額をまとめて運用したい投資家にとっては“資金の置き場所が定まらない”という不満につながりやすい特徴があります。
特に多く見られた声は次の通りです。
- 「300万円応募しても5万円しか当選しない」
- 「部分当選なら応募する意味がない」という投資回避の判断
- 「複数の落選が続いて資金が眠る」
部分当選はリスク分散としては機能するものの、資金効率を重視する投資家にとっては運用計画の調整が必要になる点が課題です。
抽選中心の募集が増えたことによる競争激化
らくたまは先着形式と抽選形式を併用していますが、人気化に伴い抽選主体のファンドが増えています。先着方式ではアクセス集中による「秒で完売するクリック競争」が起き、抽選方式では“運”に左右されるため、どちらの方式にも一定のストレスが残りがちです。
抽選方式への移行が進むことで、次のような変化が起きています。
- 抽選倍率が継続的に高止まりしている
- 新規投資家の増加により当選枠が希薄化
- 会員ランクによる優遇があるものの、倍率差を打ち消すほどではないケースがある
結果として「資金は用意しているのに投資できない」という状況に悩む投資家が増えています。
それでも離脱しづらい理由
落選の多さが不満として挙がる一方、らくたまから完全に離脱する投資家は多くありません。その理由には、以下のような強みが挙げられます。
- 償還実績が安定しており、リスク低減策が豊富
- 他社より高利回りで、利益の上振れも発生しやすい
- 会員特典(ハッピーパスポート)の魅力が強い
- ファンド情報の開示量が多く、安心感がある
不満はあるものの「外れ続けても次のファンドに応募したくなるだけの魅力がある」という独特のバランスが働いているといえます。
投資しづらさを軽減するための現実的な工夫
投資家の口コミから読み取れる、当選確率を高めるための行動は次のようなものです。
- 先着募集のファンドを狙い、開始時刻に合わせて事前にログインしておく
- 大口応募ではなく複数の中口応募に分散する
- 応募するファンドの種類(短期・キャピタル型など)を広げる
- らくたま以外のクラウドファンディングを併用し、資金の回転を落とさない
これらの工夫を取り入れることで、落選ストレスの緩和と資金効率の維持が期待できます。

今回の内容を一言でいうと、倍率の高さは「不人気ではなく人気過多」が原因で、投資家にとってはチャンスと課題が同居している状況ですね。落選が続いても仕組みを理解して行動すれば、狙ったタイミングでうまく投資枠を確保できる可能性は十分ありますよ
らくたまを選ぶ投資家が評価するメリット
らくたまは、単に「利回りが高い」だけではなく、投資家が感じやすい不安や不満をあらかじめ解消する仕組みが多く組み込まれている点が、強く評価されています。ここでは、投資家目線で特に満足度が高いポイントに焦点を当ててまとめます。
想定利回り5.5〜6.5%の安定したリターンが狙える
らくたまの多くのファンドは、想定利回り5.5〜6.5%という水準で設計されています。不動産クラウドファンディング全体の平均が3〜5%前後であることを考えると、継続的に高利回り帯のファンドに応募できる点は、投資家が最も評価する理由のひとつです。
利回りを過度に吊り上げるのではなく、劣後出資割合やマスターリース契約など、収益源がブレにくい仕組みと組み合わせて提供されているため「高利回りだけど堅い」という安心感も生まれています。
高い劣後出資割合による元本保護力の強さ
らくたまの特徴として挙げられるのが、40%前後を基本とする高い劣後出資割合です。案件によっては60%を超える場合もあり、万一物件の価値が下落しても、損失はまず事業者が負担する構造となっています。
一般的な不動産クラファンの劣後割合が10〜30%である中、らくたまは「安全性重視の投資家」が最も評価する設計です。実際、元本割れゼロ・延長ゼロという実績が安心材料となり、継続して応募する投資家も増えています。
翌日償還+5日ルールによる圧倒的な資金回転の速さ
投資家が驚くポイントとして、資金拘束の短さがあります。多くのサービスでは償還日の数日後に振り込まれるケースがありますが、らくたまはファンド終了日の翌日に償還されます。
さらに「5日ルール」により、応募〜償還までに発生する待機期間も極小化されています。
- 資金が止まる期間が短い
- 再投資のサイクルを回しやすい
- “実質利回り”が高まりやすい
この仕組みは毎回の運用効率に直結するため、複数のクラファンを併用している投資家ほど評価しています。
全期間配当保証による利益の上振れ
らくたまを象徴する仕組みが「全期間配当保証」です。早期売却で運用期間が短縮されても、投資家には予定された期間分の配当が支払われます。
過去の事例では想定利回り6%が、早期償還により二桁〜三桁利回りへ跳ね上がったケースも確認されています。もちろん毎回発生するわけではありませんが、早期償還=損ではなく、むしろアップサイドに変わる点はらくたま独自の魅力です。
ハッピーパスポートによる優待の豊富さと実用性
投資家から意外と評価が高いのが、ベネフィット・ステーションを使える「ハッピーパスポート」です。投資額が一定基準に達すると、全国の飲食店や映画館、レジャーなどの優待が利用可能になります。
- 投資で得た利回り以外に、生活コストの削減という実利がある
- 会員ランクに応じてポイントが付与され、電子マネーにも交換できる
「リターン+αのメリット」を求める層には特に響いており、長期で利用する動機にもつながっています。
投資家保護制度が充実しているため安心して預けられる
投資家プロテクトルールの存在や10億円規模の償還リザーブ、物件の含み益80億円といった財務の「安全マージン」は、サービスの信頼性として強く支持されています。リスクゼロにはなりませんが、「不動産クラウドファンディングでここまで守りを固める会社は少ない」という声が多く見られます。
ファンド情報の開示が丁寧で判断しやすい
らくたまのファンドページは、想定収支やリスク要因、出口戦略が細かく書かれているため、初心者でも判断しやすい設計です。他社では読み解きづらい部分が多い中、情報開示の丁寧さは投資家の信頼を集めています。
メリットのポイント(簡単まとめ)
- 高利回り帯のファンドが継続的に登場する
- 劣後出資割合が大きく元本保護力が高い
- 翌日償還で資金効率が非常に良い
- 全期間配当保証で利益上振れの可能性がある
- 優待サービスが豊富で実用的
- 開示情報が丁寧で判断しやすい
これらの要素が組み合わさり、「不動産クラファンの中で最も投資家に寄り添ったサービス」という評価につながっています。

らくたまの仕組みは“利回りの高さ”だけじゃなく、“投資家にとって不利になりやすいポイントをどう消すか”を徹底して作られているところが魅力ですよ。安全性と資金効率の両方を取りたい人には、かなり相性が良いサービスだと思います
リスクとデメリット。投資前に理解したい注意点
らくたまは投資家保護の仕組みが充実している一方で、投資前に把握しておきたい注意点もあります。ここでは、投資判断に直接影響する実質的なデメリットを整理しつつ、なぜ注意が必要なのか、どのようにリスクを受け止めるべきかを丁寧に解説します。
希望額で投資しづらい高倍率リスク
らくたま最大のデメリットは「当選しづらさ」です。人気が高すぎるため、応募倍率が数百%に達するファンドが珍しくありません。
抽選中心のファンドでは全額落選のほか、部分当選になるケースもあり、意図した資金配分を組みにくくなることがあります。
短期運用で資金効率を高めたい投資家ほど、この“入れたいのに入れられない”というストレスを受けやすい点は押さえておくべきです。
こうした倍率は今後も続く可能性が高いため、らくたま専一本で運用するより、複数サービスを併用することでポートフォリオの安定度を高められます。
出資金の振込手数料は自己負担
出資金の振込時には銀行手数料が発生し、これは投資家負担となります。
頻繁に応募・償還を繰り返す運用スタイルの場合、手数料の積み上がりが無視できなくなる可能性があります。
ただし、入金口座がGMOあおぞらネット銀行のため、同銀行間の利用であれば手数料は無料です。
長期的に活用するなら、コスト最適化として口座開設を検討する価値があります。
原則として中途解約できない
らくたまのファンドは原則中途解約不可です。これは不動産クラウドファンディング全般に共通する特徴ですが、流動性の低さとして理解しておく必要があります。
クーリングオフや会員間での持分譲渡は可能なものの、日常的に利用できる仕組みではなく、一定の手続きや手数料が伴います。
急な資金需要が発生する可能性がある方は、短期ファンド中心に組む、資金全体の一部だけを投資に回すなどの対応が求められます。
不動産市況の変動による元本割れリスク
らくたまは優先劣後構造により元本保護性が高い設計ですが、元本が保証されているわけではありません。
市場環境が大きく悪化した場合、劣後出資で吸収できない損失が発生すれば、投資元本が毀損する可能性はゼロではありません。
ただし、平均40〜60%という高水準の劣後割合、不動産含み益の保有、償還リザーブ資金の積立など、多段階の防御策があるため、実際のリスクは低めに抑えられています。
それでも、不動産価格の急落や外部ショックが起きた場合のリスクは理解したうえで投資判断を行うべきです。
投資タイミングの自由度が低い
超短期運用×高利回りという特性から、償還は素早いものの、次の投資先を確実に確保できるとは限りません。
資金は翌日戻るのに、次のファンドに入れられない状況が生まれ、結果として「資金はあるのに稼働させられない」という非効率が生じやすくなります。
この特性は、運用計画を立てる投資家にとって見逃されがちなデメリットで、投資スケジュールの組み方に工夫が必要です。

投資を検討する時は、メリットだけでなく“運用時に起こりがちな不便さ”にも目を向けておくと判断を誤りにくくなりますよ。特にらくたまは当選しづらさが運用効率を左右するので、ここを把握した上で活用することが大事です
実績から見る信頼性と投資家保護制度の強さ
らくたまが高い評価を得ている背景には、数字で裏付けられた堅実な実績と、業界でも例を見ない手厚い投資家保護制度があります。表面的な「安全性」ではなく、具体的なデータで投資家が安心できる理由を示している点が強みです。
元本割れゼロと償還遅延ゼロという明確な実績
2025年時点で、らくたまは元本割れゼロ・償還遅延ゼロを継続しています。運用終了日の翌日に償還される運用体制が徹底されており、投資家が最も不安を感じる「資金拘束の長期化」や「償還遅延」のリスクを回避しています。
特に、ファンド延長ゼロを宣言し実行している点は、不動産クラウドファンディング業界でも稀です。市況変動で売却が難しくても延長せず、運営会社自らが買い戻しを行い償還を確実にする方針は、投資家保護を最優先とする姿勢の象徴です。
自社買戻しを含む強固な投資家保護制度
らくたまは「投資家プロテクトルール」という独自制度を整備しており、複数の安全網で元本の保護を図っています。
主な保護制度
- 償還用リザーブ資金10億円の確保
あらゆるトラブルを想定し、事前に償還のための資金を積み立てています。資金繰り不安を理由に償還が遅れるリスクをほぼ排除できる仕組みです。 - 自社買戻し制度によるファンド延長ゼロ
想定外の市況悪化や売却困難時にも、運営会社が物件を買い戻し、償還を遅らせない方針を徹底しています。 - 優先劣後構造の厚さ(40〜60%)
一般的なクラウドファンディングの劣後割合を大きく上回り、事業者出資の比率が高いため投資家の元本は厚く守られます。
制度設計の段階から「投資家が損をしにくい仕組み」を最優先している点は、短期運用型ファンドが中心のらくたまにとって大きな強みだと言えます。
不動産含み益80億円と安定した財務基盤
運営会社フロンティアグループは、不動産事業で培った資産と実績を土台にしており、特に注目されているのが不動産含み益80億円です。
含み益を多く持つ企業は市況悪化にも耐性があり、必要に応じて資金調達や物件売却の選択肢を柔軟に確保できます。不動産市況の急変に強く、買戻しや償還を支える実体的資産の厚さが信頼性に直結しています。
また、15年以上黒字経営を維持している運営会社の安定性も、継続的なファンド提供と安全性の裏付けとして投資家から評価されています。
安定運用を支える“延長しない”運営カルチャー
償還延長は他サービスでたびたび課題になりますが、らくたまは運用開始時から延長しない前提でファンド設計を行う運営方針を採用しています。
出口戦略の複線化、買戻し体制、リザーブ資金の確保など、最初から“延長リスクをゼロにする設計”でプロジェクトが立ち上がるため、投資家は資金の見通しを立てやすくなります。
実際、この運営姿勢を評価して「他社よりも安心感がある」「遅延しないサービスは貴重」という投資家の声も多く見られます。
信頼性を支える透明性の高い開示
らくたまはファンドページでの開示量が非常に多く、運用シミュレーション、リスクシナリオ、出口戦略などが明確に示されています。投資家が判断に迷う部分を丁寧に補い、納得した上で投資できる環境が整っている点も特徴です。

安全に投資したい人は“数字を伴う実績”を重視しますよね。らくたまは、元本割れゼロ・延長ゼロ・遅延ゼロという明確な実績と、制度面の厚い保護が揃っているため、安心して判断しやすいサービスになっていますよ
どんな投資家に向いているか。相性の良い活用パターン
らくたまは「とりあえず高利回りだから誰にでもおすすめ」というタイプのサービスではなく、仕組みや独自ルールの特徴と相性が良い投資家像がはっきりしているサービスです。
自分の投資スタイルや資産状況と照らし合わせて、「本当に自分向きかどうか」を具体的にイメージしておくことが重要です。
短期運用で資金を効率よく回したい投資家
運用期間が比較的短く、償還タイミングも読みやすいファンドが多いため、「資金を寝かせっぱなしにしたくない」投資家と相性が良いです。
短期運用と相性が良いのは、例えば次のようなケースです。
- 数十万〜数百万円の余剰資金を、普通預金より高い利回りで回したい人
- 1年単位で教育費・住宅購入頭金などの支出予定があり、資金拘束期間を長くしたくない人
- ボーナスや臨時収入を、数カ月〜1年程度だけ効率よく運用したい人
このタイプの投資家は「資金回転の速さ」と「利回り」のバランスを重視することが多いため、早めの償還が見込まれるファンドや、運用期間が明確なファンドを中心に組み合わせると、らくたまの強みを活かしやすくなります。
株式の値動きに疲れた分散投資家
株式・投資信託のように価格が日々動く資産だけでポートフォリオを組んでいると、相場が荒れた局面で精神的な負担が大きくなりがちです。
そうした「値動きの激しさに疲れてきた」投資家にとって、不動産クラウドファンディングは次のような意味を持ちます。
- 日々の価格チェックが不要で、値動きを気にしすぎずに済む
- 不動産という別の資産クラスを組み入れることで、ポートフォリオ全体のブレを抑えられる
- 配当・償還のスケジュールがあらかじめ見えやすく、将来キャッシュフローの見通しを立てやすい
株式や投信で一定のリスクを取りつつも、「守りの部分」を厚くしたい人が、らくたまのファンドをポートフォリオの一部として組み込むことで、値動きストレスの緩和とリスク分散を両立しやすくなります。
安定したインカム収入を積み上げたい長期志向の投資家
毎月・四半期ごとに入るインカム(配当)を着実に増やしたい長期志向の投資家とも、らくたまは相性が良いサービスです。
- 給与以外の定期的なキャッシュフローを作りたい人
- 将来のセミリタイアやFIREに備えて、配当収入の「土台作り」をしたい人
- 退職金の一部を、安定したインカム源に振り向けたいミドル〜シニア層
こうした投資家は、一度に大きな利益を狙うよりも、「着実な利回り」と「極端に長くない運用期間」の組み合わせを重視します。
運用中ファンドの数を増やし、分配タイミングをずらしながら複数本を並行させていくことで、年間を通じてインカムをならしていくイメージで活用すると、らくたまを長期戦略の中に組み込みやすくなります。
優待・ポイントも含めてトータルリターンを重視する投資家
らくたまは、金銭的な配当だけでなく、優待サービスやポイントといった「+αのベネフィット」も用意されているのが特徴です。
そのため、単純な利回り比較だけでなく、トータルのリターンを重視する投資家に向いています。
例えば次のような人です。
- ベネフィット・ステーションなどの優待サービスを日常生活で積極的に使いたい人
- 家族でレジャー・外食・映画などを楽しむ機会が多く、優待をフル活用できる人
- 投資によるリターンを「配当+節約効果」として捉えたい家計目線の投資家
同じ利回りでも、「優待やポイントを使い切れる人」と「ほとんど使わない人」とでは、実質的なリターンが大きく変わってきます。
すでに優待サービスを使いこなしている人、家族での外出が多い人ほど、らくたまの付帯サービスとの相性は良くなります。
相性の良い活用パターンの具体例
らくたまを自分の投資プランに組み込むときは、「どんな目的のための資金か」を決めてから活用パターンを設計すると、ブレにくい運用になりやすいです。
ボーナス・特別収入の“目的別バケット”として使うパターン
ボーナスや副業収入などを、目的ごとの「バケット(資金の箱)」に分け、その一部をらくたまで運用するイメージです。
- 1年後の家電買い替え資金
- 数年後の旅行・教育費用の一部
- 将来のリフォーム費用の準備金
このように「使い道が決まっている中期資金」を預貯金から切り出し、短期〜中期のファンドに割り当てることで、インフレや低金利に負けにくい形で資金を温めておくことができます。
老後資金・セミリタイア資金の“クッション”として使うパターン
老後資金やセミリタイア資金を株式・投信のみに依存していると、市場急落時の評価額のブレが大きくなります。
そこで、ポートフォリオ全体の一部をらくたまのような不動産クラウドファンディングに振り向けることで、次のような効果が期待できます。
- 毎月の生活費の一部を配当で賄い、取り崩しペースを抑える
- 株式市場が不調な局面でも、不動産由来のインカムで精神的な安心感を確保する
- 株式を安値で売らざるを得ない状況を避ける「クッション」として機能させる
「すべてを預貯金に逃がす」のではなく、「一部をインカム重視の不動産クラウドファンディングに振る」という発想が、長期の資産寿命を伸ばすうえで有効になります。
他社クラファンと組み合わせて“当選確率と分散”を両立するパターン
らくたまは人気の高さゆえに、ファンドによっては応募倍率が高くなり、希望通りに投資できないケースもあります。
そのため、他の不動産クラウドファンディングやJ-REITと併用しながら、次のようなポートフォリオを組む投資家も想定されます。
- コア:J-REITや上場インフラファンドなど、流動性の高い商品
- サテライト:らくたまを含む不動産クラウドファンディング複数社で利回りを上積み
こうした組み合わせで、当選機会の分散と、事業者リスクの分散を同時に図るイメージです。
らくたまに「当たった分だけ」投資するというスタンスであれば、落選による機会損失も限定的になり、メンタル的なストレスも抑えやすくなります。
らくたまと相性が悪くなりやすい投資家像
逆に、以下のような投資スタンスの人は、らくたまとの相性があまり良くない可能性があります。
- いつでも自由に解約できる「完全な流動性」を最優先したい人
- 数日〜数週間単位の超短期売買で利益を狙うトレーダー気質の人
- 元本割れリスクを一切取りたくない、元本保証前提の安全志向すぎる人
不動産クラウドファンディングという仕組み上、どうしても「運用期間中は原則として資金が拘束される」「元本保証ではない」という前提は避けられません。
預金や個人向け国債など、より保守的な商品でしか運用したくない場合は、らくたまのリスク・リターンのバランスが合わない可能性があります。

自分の投資スタイルと照らし合わせて、「どの資金を・どの期間だけ・どのくらいの割合で」らくたまに回すのかを具体的に決めておくと、サービスとの相性がぐっと良くなりますよ。無理に全力投資を狙うのではなく、ポートフォリオの一部として冷静に組み込むのが、結果的には一番失敗しにくい使い方だと思います。
他社と比較したらくたまの強みと選ばれる理由
らくたまは後発サービスでありながら、短期間で業界トップクラスの評価を獲得しています。その背景には、多くの不動産クラウドファンディングには見られない「制度設計の巧さ」「安全性の層の厚さ」「投資効率の高さ」が揃っている点が挙げられます。単なる利回りの高さだけでなく、投資家が実際に“使いやすい・選びやすい・安心できる”と感じる運用環境が整っていることが、らくたまが選ばれる最大の理由です。
業界平均を大きく上回る利回り帯と独自ルールの組み合わせが強い
多くの不動産クラウドファンディングの想定利回りは3〜5%が中心ですが、らくたまは5.5〜6.5%前後のファンドを安定して提供しています。ただし、評価されているのは利回り“だけ”ではありません。投資家保護と収益性向上を両立する独自ルールが、他社との差別化につながっています。
主な要素は次の通りです。
- 全期間配当保証
早期償還でも運用全期間の配当が保証され、実質利回りが大幅に上振れするケースが多い仕組みは、他社にはほとんどありません。 - 5日ルール+翌日償還
資金拘束が極端に短く、再投資サイクルが早いことで実質利回りが高まりやすく、複利運用に近い感覚で資金を回せます。
これらは、単に利回りを上げるのではなく、「投資家の実質リターンを最大化する仕組み」を重視した設計で、他社よりも一段深い価値を提供しています。
安全性の層が厚くリスク管理に強い
不動産クラウドファンディングにおいて安心感を左右するのは「どこまでリスクを抑え込めているか」です。らくたまはこの点で非常に優位性が高く、制度面・財務面の両方から多重に安全性を確保しています。
特に投資家の評価が高いポイントは次の3つです。
- 劣後出資割合40〜60%と高水準
多くのサービスが10〜30%である中、らくたまは平均40%前後。中には60%超のファンドもあり、元本保護力が段違いです。 - 償還リザーブ10億円と不動産含み益80億円
市場変動や売却遅延リスクに強く、償還遅延ゼロを実現するための財務的な“厚さ”が他社より際立っています。 - ファンド延長ゼロの方針と自社買戻し体制
運用期間が伸びてストレスになるケースが業界ではしばしば見られますが、らくたまは延長ゼロを掲げ、買戻しで対応する仕組みを整備しています。
安全性に関する取り組みは、単なるアピールではなく実績と体制が伴っており、高倍率でも投資家が離れない理由になっています。
情報開示量が多く投資判断がしやすい
ファンドページの情報量は他社と比較すると明確に多く、数字・根拠・収支の流れまでが丁寧に整理されています。特に、想定収支の内訳や出口戦略の明示は初心者だけでなく経験者からも評価が高い部分です。
- 収益モデルの説明が具体的で、曖昧な点が少ない
- 賃料収入、経費、売却戦略が数字ベースで把握できる
- 優先劣後割合や担保の考え方が明確
- 運用会社の財務情報も積極的に開示している
投資家に“判断材料を十分に渡す姿勢”があるため、不確実性を感じにくい点が支持につながっています。
サービス設計が投資家目線で最適化されている
利回りや安全性だけでなく、使い勝手の部分でもらくたまは優秀です。短期償還・資金効率・優待など、利用満足度を高める工夫が多く、長期利用しても飽きがこない設計になっています。
特に評価されるポイントは次の通りです。
- ハッピーパスポートによるベネフィットステーション使い放題
- ランク制度に応じたポイント付与
- 先着・抽選の使い分けで投資機会を確保
- ファンド組成の頻度が高く機会損失が少ない
優待やポイント制度をここまで充実させているサービスは非常に珍しく、「投資+生活メリット」を両立している点が選ばれる理由です。
成長スピードが速く将来性がある
サービス開始から短期間でファンド数を増加させ、元本割れゼロ・償還遅延ゼロを維持しながら規模を拡大できている点は、運営力の高さを示しています。
後発でありながら一定のシェアを獲得しつつある背景には、投資家の再投資率が高いことも影響していると考えられます。
- ファンド数の伸びが速い
- 安全性を損なわず組成件数を増やしている
- 財務基盤が安定しており継続成長が見込める
「伸びているサービス」に投資したい投資家にとっても魅力的な選択肢です。

このセクションのポイントを短くまとめると、らくたまは“利回り×安全性×情報量×資金効率”の4点で他社より抜きん出ている、という結論になります。特に安全性と制度設計の深さは業界でも頭一つ抜けていますよ
らくたま
株式会社日本保証
リスクを抑えつつ高いリターンを狙える案件が多く、供給数も充実

| 案件数 | - |
| 直近10件平均利回り | - |
| 直近10件直近最低利回り | - |
| 直近10件直近最高利回り | - |
| 直近10件募集割合平均 | - |
らくたまがおすすめの理由
らくたまがおすすめの理由は「投資家保護を意識した安全性の高い仕組み」と「短期案件を中心とした資金効率の良さ」です。
らくたまは2008年創業の不動産会社グループが運営しており、長年にわたる不動産投資や運営の実績を背景にサービスを提供しています。2024年にスタートした比較的新しい不動産クラウドファンディングですが、運営母体の信頼性に加え、投資家資産を守るための「投資家プロテクトルール」や、優先劣後出資方式を採用することで、投資家のリスクを抑える仕組みが整えられています。さらに、3〜12ヶ月程度の短期運用案件を数多く扱うため、資金が長期間拘束されにくく、効率的な資産運用を目指す投資家にとって魅力的な選択肢となります。
メリットとしては、まず「劣後出資割合が平均40%前後」と高水準で設定されている点が挙げられます。これにより、万が一運用が計画より下振れした場合でも、事業者側が先に損失を負担する仕組みとなり、投資家の元本リスクが軽減されます。また、運用案件は都心や横浜など需要が高いエリアが中心で、比較的安定した収益性が見込めます。さらに、らくたま独自の「5日ルール」により、入金から運用開始、払戻しまでのスケジュールが短縮されており、実質的な利回り向上につながる点も評価されています。加えて、50万円以上の運用で利用できる「らくたまハッピーパスポート」によって、福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を利用できるのも投資家にとっては魅力的です。
一方でデメリットとしては、まず「投資が抽選制」であるため、希望した金額をそのまま投資できるとは限らない点があります。人気のファンドでは競争倍率が高く、落選してしまうケースや、部分当選のみとなることも少なくありません。また、運用が開始すると途中で解約や売却ができないため、運用期間中に資金を急に引き出すことはできず、突発的な資金需要に対応しづらいというリスクも存在します。さらに、不動産クラウドファンディング全般に共通する点として、地震や災害、経済環境の変化などにより、元本割れの可能性が完全に排除されるわけではありません。
とはいえ、らくたまは「投資家保護を重視した仕組み」と「短期案件中心の効率的な運用設計」を兼ね備えたサービスとして、不動産投資初心者から経験者まで幅広く検討する価値があります。運営会社の信頼性や独自ルールによる安心感、利回りの安定性を求める方にとって、バランスの取れた不動産クラウドファンディングサービスといえるでしょう。
| 案件数 | - |
| 直近10件平均利回り | - |
| 直近10件直近最低利回り | - |
| 直近10件直近最高利回り | - |
| 直近10件募集割合平均 | - |
| 優先劣後方式 | ○ |
| 最低投資金額 | 10000円 |
| 募集方法 | 先着、抽選 |
| 組合契約 | 匿名組合型 |
| 物件の種類 | 戸建、商業施設、オフィス |
| 優遇サービスあり | ○ |
| 物件の開示情報 | 築年数、住所、面積 |
| 出金手数料 | 無料(GMOあおぞらネット銀行) |
| 運用レポートの共有あり | × |
| 運営会社設立年月 | 2008年 |
| 運営会社資本金 | 100,000,000円 |
| 上場 | ○ |