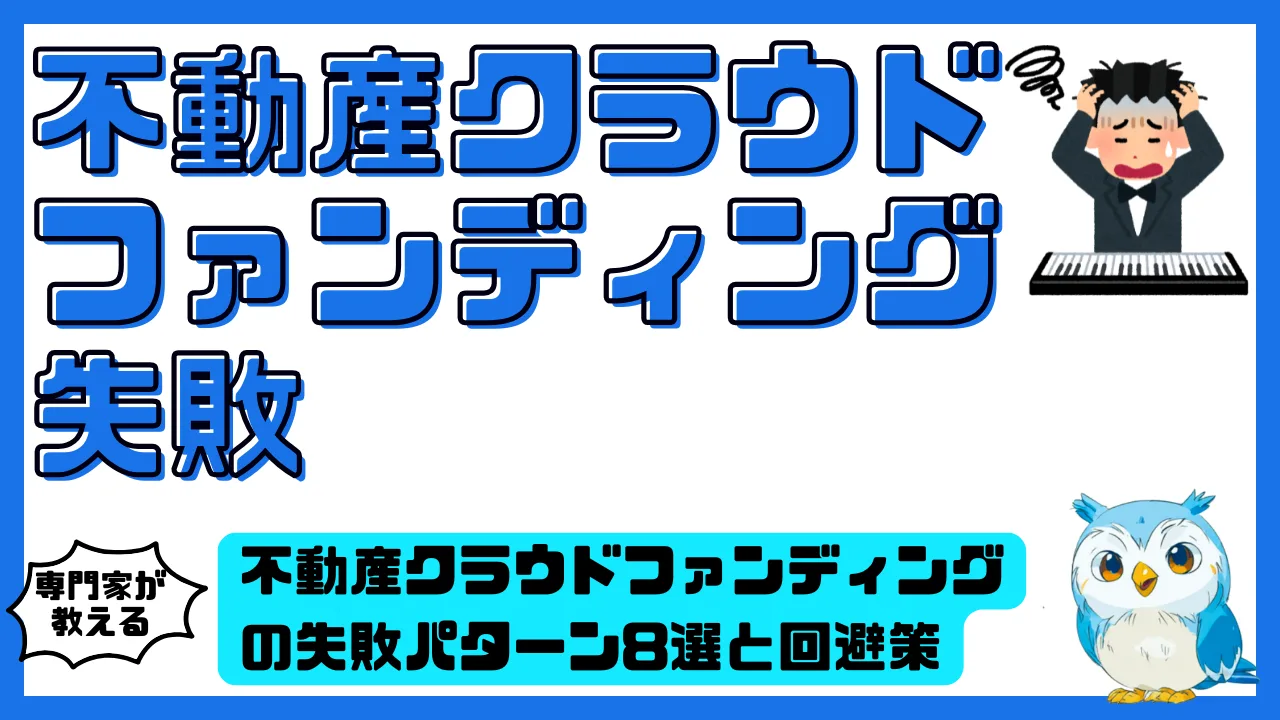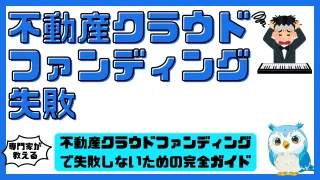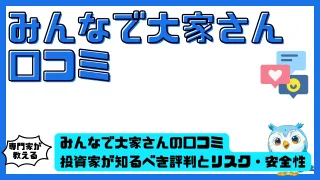本ページはプロモーションが含まれています。
目次
分配金が支払われないケース
不動産クラウドファンディングでは、投資家が最も期待するのが定期的な分配金です。しかし、ファンドの運用状況によっては、予定されていた分配金が支払われない場合があります。このリスクは見落とされがちですが、実際の投資成果に直結する重要なポイントです。
分配金が支払われない主な要因
- 入居率の低下
賃貸物件を対象としたファンドでは、空室が長引くことで家賃収入が大幅に減少します。特に人口減少エリアや供給過多の地域では入居率の低下が続きやすく、分配金の不払いにつながります。 - 観光需要の変動
ホテルや旅館を対象とした案件では、観光客の減少が直撃します。新型感染症や自然災害、国際情勢の影響で需要が一気に落ち込むと、稼働率が低下し分配金が途絶える可能性があります。 - 運営成績の悪化
不動産の維持管理コストや修繕費が予想以上に膨らむケースもあります。管理がずさんな運営会社では、費用増大が収益を圧迫し、分配金の支払いが困難になることがあります。
投資家が取れる回避策
- 過去の配当実績を確認する
事業者ごとに「これまで分配が遅延したかどうか」をチェックしましょう。信頼性の高い事業者は、配当実績を公開しています。 - 対象物件の収益源を把握する
入居需要が安定しているか、観光地の需要が持続的かを確認することが大切です。 - リスク分散を徹底する
一つの案件に集中せず、複数の物件や事業者に投資することで、不払いリスクを平準化できます。

分配金が支払われないケースは、投資家にとって大きな不満につながるリスクです。だからこそ、事業者の信頼性や物件の安定性を丁寧に調べておくことが重要なんです。投資の前に「本当に継続的に収益が見込めるか」を冷静に判断するようにしましょう
元本割れが発生するケース
不動産クラウドファンディングで最も注意すべきリスクのひとつが「元本割れ」です。これは、運用終了時に戻ってくる償還金が投資額を下回ることを指します。投資家にとって損失となるため、十分な理解と対策が欠かせません。
元本割れが起こる主な要因
- 不動産市況の下落
運用期間中に不動産市場全体が下落すると、売却価格が想定を下回り、投資額を割り込むリスクがあります。特に短期的な景気後退や金利上昇局面では価格調整が急激に進むこともあります。 - 経済危機や社会情勢の変化
リーマンショックやコロナ禍のような大規模な経済危機が発生すると、不動産需要が急減し、価値が大きく下がる可能性があります。外国人観光客依存のホテルや商業施設は影響を強く受けやすいです。 - 自然災害や環境リスク
地震や豪雨災害で建物の価値が毀損すると、修繕費用や売却損失につながります。特に日本は自然災害が多いため、立地や建物の耐震性の確認は欠かせません。 - 管理コストや修繕費の増加
老朽化や不測の修繕により運営費が膨らむと、収益性が悪化し、結果的に投資家に戻る元本が減少する場合があります。
元本割れを避けるための回避策
- 事業者の実績と公開情報を確認する
償還実績が豊富で、過去に元本割れの事例が少ない事業者を選ぶことが重要です。上場企業が運営するサービスは財務の透明性が高い傾向があります。 - リスク軽減制度を活用する
優先劣後出資方式(事業者が先に損失を負担する仕組み)やマスターリース契約(一定の賃料保証がある契約)を採用している案件は、元本割れリスクを軽減できます。 - 複数ファンドに分散投資する
1つの案件に集中せず、複数の地域や物件タイプに投資することで、特定案件の元本割れリスクを分散できます。 - 市況動向を把握する
金利や不動産価格の動向を把握し、過度に高リスクなタイミングでの投資を避けることも有効です。

元本割れは「投資である以上避けられないリスク」なんです。でも、事業者の信頼性や仕組みをよく調べて、分散投資を心がければリスクは大きく下げられますよ。安易に高利回りだけに目を奪われず、堅実に判断していきましょう
途中解約ができない問題
不動産クラウドファンディングの大きな特徴のひとつは、運用期間中に基本的に解約ができないことです。ファンドによって3か月程度の短期から2年以上の長期まで幅がありますが、一度投資を行うと、その期間は資金が拘束されるのが一般的です。
流動性リスクの現実
急な出費や資金需要が発生しても、途中で現金化できないために対応が難しくなる可能性があります。例えば、医療費や引っ越し費用など予期せぬ出費に直面した際、株式やREITのようにすぐ売却して現金化することはできません。資金計画を誤ると、生活に支障をきたすリスクがあります。
運用期間中の市場変化に対応できない
不動産市況が悪化したり、金利や経済情勢が変化した場合でも、満期まで資金を引き上げられないため、運用状況に不安を感じながらも待つしかありません。これは特に長期ファンドでリスクが大きく、心理的な負担になることもあります。
回避策と対応方法
- 余裕資金で投資する
短期間で必要になる可能性のあるお金を投資に回さないことが基本です。生活資金や緊急資金とは分け、余裕のある資金を使うようにしましょう。 - 運用期間の異なるファンドを組み合わせる
短期と中長期のファンドを分散して投資すれば、資金回収のタイミングを分けられ、急な出費にもある程度対応できます。 - 途中解約可能なサービスを選ぶ
例外的に「COZUCHI」のように途中解約(中途換金)が可能なサービスも存在します。手数料がかかる場合がありますが、資金流動性を優先したい投資家には有効な選択肢です。

途中解約ができない点は、不動産クラファン特有のリスクです。だからこそ「生活資金を投資に使わない」「短期と長期を分ける」「途中解約可能なサービスを知っておく」ことが大切なんですよ。リスクを理解して選べば安心して投資できます
事業者の倒産リスク
不動産クラウドファンディングにおける最大のリスクの一つが、事業者の倒産です。投資家は物件そのものに直接出資しているわけではなく、運営事業者を通じて出資しています。そのため、事業者が経営破綻すると、たとえ不動産自体に価値があっても資金が回収できないケースが多いのです。
倒産が発生する背景
事業者が倒産する要因には、以下のようなものがあります。
- 過剰な資金調達や拡大戦略の失敗
案件数を急拡大しすぎて資金繰りが悪化するケースがあります。 - 不動産市況の悪化による運用失敗
市場下落や需要減少で収益が減り、返済や分配に行き詰まる場合があります。 - 内部管理体制の不備
リスク管理不足やコンプライアンス違反によって行政処分を受け、そのまま経営悪化につながる事例もあります。
投資家に及ぶ影響
事業者が破綻すると、投資資金の大部分が失われる可能性があります。元本割れどころか、分配金が一切戻らないケースもあり、被害額は少額投資であっても無視できません。また、倒産処理は時間がかかるため、資金が長期間拘束されるリスクも考慮する必要があります。
リスク回避のための対策
投資前に以下の点を確認することが有効です。
- 財務基盤の強さをチェック
上場企業や大手不動産会社の子会社など、経営基盤が安定した事業者を選ぶと安心です。 - 過去の実績と透明性
償還実績や分配遅延の有無、決算情報の公開状況を確認しましょう。 - リスク軽減策の導入
「優先劣後方式」や「マスターリース契約」といった投資家保護の仕組みがあるかどうかを確認することも大切です。 - 複数事業者への分散投資
一社に依存せず、複数の事業者に分散して投資することで、万一の倒産リスクを軽減できます。

事業者の信頼性を見抜くことが、実は最も大事なんです。財務の健全性や実績を確認して、安心できる運営会社を選んでください。そうすれば、倒産リスクはかなり減らせますよ
人気案件に投資できない
不動産クラウドファンディングでは、案件そのもののリスクだけでなく「投資したい案件に応募すらできない」という問題があります。特に人気の高い案件は募集枠が小さいことも多く、投資家が殺到することで数分以内に募集終了となるケースも少なくありません。このような状況では、投資資金を用意していても機会を逃す可能性が高まります。
投資できない主な理由
- 先着方式の競争
募集開始直後に申込が集中し、数分で完売するケースが多発しています。平日昼間などに募集が始まると、仕事の都合で参加できない投資家は不利になりやすいです。 - 抽選方式の高倍率
一見公平に見える抽選方式ですが、人気案件では数十倍以上の倍率になることも珍しくありません。例えばCOZUCHIでは、数千%を超える応募倍率が発生した実例があります。 - 募集額の小規模さ
数千万円程度の小規模案件は特に競争が激しく、短時間で完売します。少額から投資できる魅力が裏目に出て、より多くの投資家が殺到する傾向があります。
回避策と工夫
- 事前の会員登録と入金を済ませる
募集開始時点でログインや資金準備が整っていなければ、わずかなタイムロスが致命的になります。募集カレンダーを確認し、前日までに入金を済ませておくことが必須です。 - 複数サービスを併用する
COZUCHI、CREAL、Jointoαなど複数の口座を開設しておけば、投資機会が広がります。特定サービスに集中すると、人気案件が完売するたびに投資できない事態が続く可能性があります。 - 抽選案件にも積極的に応募する
当選確率は低くても、応募しなければ可能性はゼロのままです。複数案件に同時応募することで、当選チャンスを増やせます。 - 中長期案件を狙う
短期案件は競争が激しい一方、中長期案件は応募期間が比較的長いことが多く、投資できる可能性が高まります。資金を拘束されるリスクはありますが、安定して投資を継続するための戦略となります。

人気案件はどうしても取り合いになりますが、事前準備と分散戦略を取れば投資機会は広がりますよ。焦らず、複数の選択肢を確保して挑むことが大切です
投資できるファンドが見つからない
不動産クラウドファンディングは、常に投資先が公開されているわけではありません。株式やREITのように「好きなときに購入できる投資商品」とは異なり、ファンドごとに募集開始日・終了日が明確に設定されており、案件数自体も限られています。そのため、せっかく資金を準備しても、募集タイミングと合わずに待機せざるを得ない状況が起こりがちです。
ファンドが見つからない主な要因
- 募集数の少なさ:各事業者が扱う案件数は限られており、数週間〜数カ月間、新規募集がないこともあります。
- 資金タイミングのミスマッチ:ボーナスや臨時収入など投資余力ができても、その時点で案件がなければ機会損失につながります。
- 地域や物件タイプの偏り:自分が投資したい条件(エリア、利回り、短期案件など)と一致する案件が出てこないケースも少なくありません。
回避策
- 複数の事業者に口座を開設する
特定の事業者だけに依存すると投資機会が極端に減ります。COZUCHI、CREAL、Jointoαなど実績のある事業者にあらかじめ口座を作っておくことで、案件を比較しながら選択できます。 - 募集スケジュールを事前に把握する
公式サイトやメールマガジンで発表されるスケジュールを確認し、投資資金を事前に入金しておくと機会損失を防ぎやすくなります。 - 分散戦略を採用する
「不動産クラファン × 株式・REIT」など、他の投資手法と組み合わせることで、案件がない期間でも資金を遊ばせるリスクを下げられます。 - 中長期型ファンドも検討する
短期案件だけに集中すると機会が限られます。中長期ファンドを取り入れることで、安定した運用と投資機会の確保を両立できます。

ファンド数が少ないのはサービスの仕組みによるものです。だからこそ複数口座の開設やスケジュール管理で「いつでも投資できる体制」を作っておくのが大切ですよ
確定申告を忘れてしまう
不動産クラウドファンディングで得た収益は、税法上「雑所得」や「不動産所得」に区分されるケースが多く、条件によって確定申告が必要になります。しかし、源泉徴収が行われるため「もう税金の手続きは終わった」と誤解してしまい、申告を怠る投資家が少なくありません。この油断が、後に追徴課税や延滞税につながる大きな落とし穴になります。
確定申告が必要になる代表的なケース
- 年間の雑所得が20万円を超える場合(給与所得者)
- 複数の収入源がある場合(副業・兼業含む)
- 医療費控除やふるさと納税などを利用している場合
- 年収2,000万円を超える会社員や、公的年金収入が400万円超の場合
特に、副業感覚でクラウドファンディングを利用している方は「雑所得20万円ルール」を見落としがちです。少額からの投資でも、他の所得と合算すると基準を超えて申告が必要になるケースが多いため注意が必要です。
確定申告を忘れた場合のリスク
- 無申告加算税や過少申告加算税の対象となる
- 延滞税の発生で余計な出費が増える
- 税務調査による指摘や信用低下につながる可能性
「忘れたから申告しない」では済まされず、余計なペナルティを負うことになります。特に数年分まとめて指摘されると大きな負担になるため、早めの対応が欠かせません。
回避策
- 毎年1月時点で、前年度の投資収益を集計しておく
- 各サービスから発行される「年間取引報告書」を必ず確認する
- 税理士や会計ソフトを活用し、申告作業を効率化する
- 還付申告の可能性も考慮し、必要なくても申告を検討する(源泉徴収税が戻る場合がある)
不動産クラウドファンディングは投資先ごとに課税区分が異なる場合があるため、事業者の説明資料を確認し、疑問があれば税務署や専門家に相談するのが安全です。

確定申告を忘れると余計な出費や手間が増えてしまいます。投資の利益を守るには、事前準備と知識が欠かせません。投資そのものだけでなく、税務対応まで含めて「一連の運用」と考えて動くことが大切ですよ
利回りだけで案件を選んでしまう
不動産クラウドファンディングでよくある失敗のひとつが、利回り数値だけを基準に投資先を選んでしまうことです。高利回りは一見すると魅力的ですが、裏を返せばリスクが高い案件である可能性が非常に高いと考えるべきです。
高利回り案件に潜むリスク
高い利回りが提示される背景には、以下のような要因があるケースが多くみられます。
- 需要が不安定なエリアや地方物件で空室リスクが高い
- ホテルやリゾート開発など、景気や社会情勢に大きく左右される用途
- 短期的な売却益を前提とした強気の事業計画で、計画倒れのリスクがある
- 事業者が投資家を集めるために過度に強調した利回り設計を行っている
数字だけでは見えないリスクが多く潜んでいるため、想定通りの収益を得られない可能性が高まります。
投資判断で見るべきポイント
利回りに目を奪われないためには、案件ごとに以下の観点を確認することが重要です。
- 物件の需要性:立地条件や入居需要、地域の人口動態を確認
- 事業者の実績:過去の分配実績や元本割れの有無をチェック
- リスク軽減策:優先劣後方式やマスターリース契約の有無
- 事業計画の妥当性:過度に楽観的な売却前提になっていないか
こうした複合的な視点を持つことで、利回りの高さだけに依存しない堅実な投資判断が可能になります。
回避策
- 想定利回りはあくまで「目安」と捉える
- 過去の実績を持つ事業者や透明性の高い企業を選ぶ
- 利回りだけでなく、物件の需要や立地、リスク軽減策を加味して総合的に判断する
- 一つの案件に集中せず、複数案件や複数事業者への分散投資を心がける

利回りの数字だけに惑わされると、見えないリスクを抱え込みやすくなります。利回りは判断材料のひとつにすぎない、と冷静に捉えることが大切ですよ