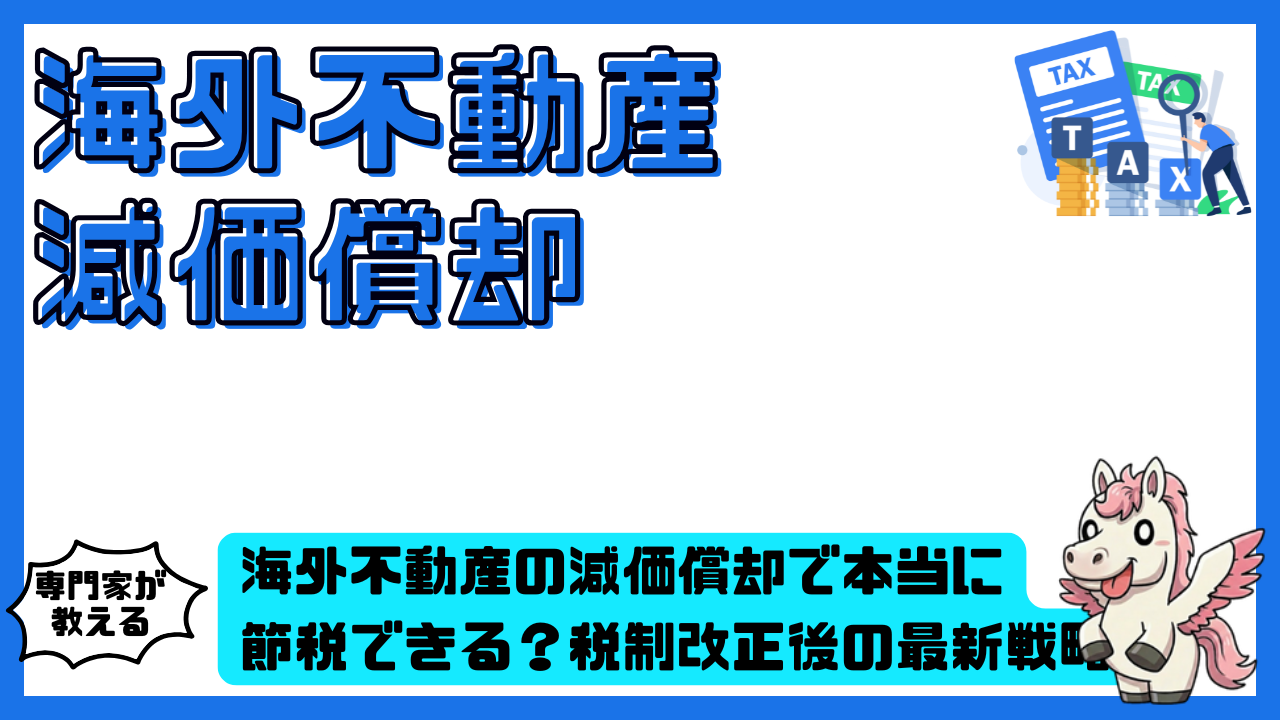本ページはプロモーションが含まれています。
目次
海外不動産の減価償却を調べる投資家の本音
海外不動産 減価償却と検索する投資家の多くは、単なる制度の説明ではなく「今でも本当に意味があるのか」という結論を求めています。2020年税制改正後に環境が変わったことは理解していても、それでもなお活用余地があるのではないかと考えているのが本音です。
特に、以下のような悩みや期待を抱えているケースが目立ちます。
- 税制改正後でも合法的に税負担を軽減できる方法は残っているのか
- 個人では難しいなら法人で活用できないか
- アメリカ不動産は本当にまだ有効なのか
- 節税なのか、それとも単なる課税の繰延なのかを見極めたい
- 出口まで含めたトータルの税インパクトを把握したい
単に減価償却の仕組みを知りたいのではなく、「自分の所得状況で意味があるのか」という実践的な判断材料を探しています。
節税は終わったのかという疑問
高所得層の投資家ほど、「海外不動産の減価償却はもう使えない」という情報に強い違和感を持っています。完全に封鎖されたのか、それとも条件付きで活用できるのか。その線引きを明確にしたいと考えています。
特に年収2,000万円超の経営者や医師、法人オーナー層は、累進課税の影響が大きいため、減価償却による所得圧縮効果のインパクトを過去に実感しています。そのため「本当にゼロになったのか」という確認が検索行動の動機になっています。
個人と法人の違いを整理したい
投資家が強く意識しているのは、個人スキームと法人スキームの違いです。
個人では損益通算が制限された一方で、法人はどうなのか。法人税率とのバランスはどうか。売却時の税率はどうなるのか。
この比較を整理できていないと、戦略設計ができないからです。
単に「法人なら可能です」という説明では足りません。
法人で行う場合、
- 実効税率との比較
- 売却益への課税
- 繰越欠損金の活用
- 退職金や設備投資との連動
こうした経営戦略と税務を組み合わせた設計が必要になります。投資家はそこまで踏み込んだ情報を求めています。
アメリカ不動産に関心が集中する理由
検索ユーザーの多くが具体例として想定しているのはアメリカ不動産です。理由は明確で、過去に減価償却スキームの中心だった市場だからです。
- 建物比率が高い
- 中古市場が発達している
- 法人活用との相性が良い
- ドル建て資産として分散効果がある
単なる節税商品ではなく、資産分散・インフレ対策・キャピタルゲインまで含めた総合投資として検討しているケースが増えています。
つまり、減価償却は「入口の魅力」であり、本質的には資産形成戦略の一部として見ています。
節税と繰延の違いを本気で知りたい
検索ユーザーの中でも経験値の高い投資家は、「節税」と「課税繰延」の違いを正確に理解したいと考えています。
減価償却で税金を減らしたように見えても、
- 将来の売却時に回収されるのではないか
- 税率差がなければ意味が薄いのではないか
- キャッシュフロー改善効果だけなのではないか
といった疑問を持っています。
短期的な税額減少ではなく、トータルの税負担とキャッシュフローを比較したいという思考です。これは一般的な節税記事では触れられない、より高度な視点です。
出口戦略まで見据えたい
海外不動産の減価償却を調べる投資家は、購入時点の税効果だけで判断しません。
- 5年超保有による譲渡税率の違い
- 未償却残高の扱い
- 為替影響を含めた実質利回り
- 法人で売却した場合の税率
取得から売却までのシナリオ設計ができるかどうかを重視しています。
入口だけを強調する情報には警戒感を持っているのが現実です。
リスクを事前に把握したい
税制改正を経験した投資家ほど、「また制度が変わるのではないか」というリスクを強く意識しています。
- 将来の税制改正リスク
- 為替リスク
- 現地管理リスク
- 国際税務の複雑さ
単なる節税商品として飛びつくのではなく、制度変更耐性のある投資かどうかを見極めようとしています。
そのため、減価償却の可否だけでなく、制度変動に強い設計かどうかを知りたいというのが本音です。
投資家が本当に知りたいこと
最終的に、検索ユーザーが求めているのは次の一点に集約されます。
「今の自分の所得・法人状況・保有資産構成で、海外不動産の減価償却は戦略として有効なのか」
制度説明ではなく、戦略判断材料です。
そして、その判断は税務単体ではなく、資産形成・法人経営・出口設計まで含めた総合設計の中で決まります。
減価償却はゴールではありません。
資産戦略の一部としてどう使うかが、本当のテーマなのです。

海外不動産の減価償却は魔法の節税ではありませんが、制度の本質を理解し法人設計や出口戦略まで組み込めば、今でも有効な武器になります。大切なのは入口の税額ではなく、取得から売却までのトータル設計ですよ
海外不動産の減価償却とは?仕組みと基本ルール
海外不動産の減価償却とは、海外に所在する賃貸用不動産の「建物部分」の取得価額を、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ経費計上していく会計・税務上の制度です。
不動産投資では、家賃収入から必要経費を差し引いた不動産所得に対して所得税や法人税が課税されます。減価償却費は、実際のキャッシュアウトを伴わない経費でありながら帳簿上の費用として計上できるため、課税所得を圧縮できる点が最大の特徴です。
ただし、海外不動産であっても日本の税法に基づいて減価償却を計算するため、国内不動産と同様の基本ルールを正確に理解することが重要です。
減価償却の対象は建物のみ
海外不動産の減価償却でまず押さえるべきポイントは、償却できるのは建物部分のみという点です。
- 建物本体
- 建物附属設備(給排水設備、電気設備など)
- 一定の構築物
一方で、土地は価値が減少しない資産とされるため減価償却はできません。
そのため、海外不動産を購入した場合は、売買契約書や鑑定評価などをもとに「土地と建物の按分」を明確にする必要があります。特にアメリカ不動産のように建物割合が高い市場では、建物比率が高いほど減価償却可能額が大きくなるため、投資設計に直結します。
取得価額の考え方
減価償却の基礎となる取得価額は、単純な物件価格だけではありません。一般的には次の要素で構成されます。
- 物件の購入代金
- 仲介手数料
- 登記費用
- 取得に直接要した付随費用
海外不動産の場合、現地での弁護士費用やエスクロー費用なども取得価額に含まれるケースがあります。税務処理の前提として、どこまでを資産計上するかの整理が必要です。
償却方法の違い 定額法と定率法
減価償却の計算方法には主に定額法と定率法があります。
- 定額法
毎年同じ金額を均等に償却する方法 - 定率法
未償却残高に一定の償却率を乗じて計算する方法
個人の不動産所得では原則として定額法が適用されます。法人の場合は資産区分により選択や届出が必要です。
投資家にとって重要なのは、どの方法を使うかで初年度の経費計上額が変わり、キャッシュフローや税負担のタイミングが変化する点です。
法定耐用年数の基本
減価償却は、法定耐用年数に基づいて計算されます。耐用年数は建物の構造ごとに定められています。
- 木造住宅 約22年
- 鉄骨造 約34年
- 鉄筋コンクリート造 約47年
海外不動産であっても、日本の耐用年数表に基づいて計算します。現地の税法ではなく、日本の税法が基準になる点は見落とされがちです。
中古資産の簡便法による耐用年数短縮
海外不動産投資で大きな論点となるのが、中古資産の耐用年数の取り扱いです。
中古建物については、一定の条件のもとで「簡便法」により耐用年数を短縮できます。代表的な計算方法は次のとおりです。
- 法定耐用年数を経過している場合
法定耐用年数 × 20% - 一部経過している場合
(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
例えば、木造22年の建物で築30年の場合、22年 × 20%=4年となり、4年で償却可能になります。
この短期償却により、初期数年間で多額の減価償却費を計上できることが、かつて海外中古不動産が節税商品と呼ばれた理由の一つです。
不動産所得との関係
減価償却費は不動産所得の計算上、必要経費として差し引かれます。
不動産所得 = 家賃収入 − 必要経費(管理費・修繕費・減価償却費など)
減価償却費は実際の支出を伴わないため、キャッシュフローが黒字でも帳簿上は赤字になるケースがあります。この赤字がどこまで他の所得と通算できるかが、海外不動産投資の税務戦略の核心です。
ただし、2020年税制改正以降は、国外中古建物の減価償却費相当額について個人の損益通算に制限が設けられています。制度の詳細は別途整理が必要ですが、仕組みを理解せずに投資判断を行うのは極めて危険です。
節税と課税繰延の違い
減価償却による税効果は、厳密には「税金の圧縮」なのか「課税の繰延」なのかを区別する必要があります。
減価償却により当期の所得は減少しますが、その分、将来売却時の譲渡所得計算に影響します。未償却残高との関係を理解せずに節税と断定するのは誤解を招きます。
海外不動産の減価償却は、単年度の税額だけでなく、取得から保有、売却までを通じたトータル設計が前提となる制度です。

海外不動産の減価償却は、建物だけを日本の税法で年数按分して経費化する仕組みです。短期で多額の償却ができる中古物件は魅力的に見えますが、本当の勝負は取得から売却までの一体設計にあります。目先の税額だけで判断せず、出口まで逆算して戦略を組み立てることが大切です
2020年税制改正で何が変わったのか
2020年の税制改正は、海外不動産を活用した減価償却スキームの「核心部分」を直接制限する内容でした。ポイントは、海外中古建物に対して簡便法を用いて算出した減価償却費による損失を、個人が他の所得と通算できなくなったことです。
改正の正式名称は「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」の創設です。適用は令和3年分(2021年分)以後の所得税からとなっています。
国外中古建物の損益通算特例の創設
改正の中核は次の考え方です。
個人が国外中古建物を取得し、簡便法により短縮耐用年数を算出して多額の減価償却費を計上した場合、その減価償却費に相当する部分の損失は「なかったもの」とみなされます。
ここで重要なのは、「減価償却費相当額」が対象である点です。つまり、海外不動産の赤字のうち、簡便法で算出した減価償却費に対応する部分が損益通算の対象外とされました。
その結果、次の通算ができなくなりました。
- 給与所得との損益通算
- 事業所得との損益通算
- 国内不動産所得との内部通算
従来のように、高額給与と海外不動産の減価償却赤字をぶつけて総合課税の課税所得を圧縮するスキームは、個人レベルでは実質的に封鎖されたといえます。
なぜ改正が行われたのか
背景には、海外中古不動産、とりわけアメリカ不動産を用いた短期大量償却スキームの急増があります。
築古物件に簡便法を適用すると、耐用年数が4年など極端に短くなるケースがありました。これにより、多額の減価償却費を短期間で計上し、最高税率帯の給与所得と通算することで、大幅な税負担軽減が可能でした。
しかし、会計検査院が「国外中古資産に日本の簡便法を機械的に適用することの合理性」に疑義を示し、税制上の歪みが問題視されました。その結果、総合課税側での過度な税率差活用を抑制する方向で制度が設計し直されたのです。
改正前と改正後の本質的な違い
改正前は、次のような構造が成立していました。
- 短期償却で大きな赤字を作る
- 最高55%近い総合課税から圧縮
- 5年超保有後に約20%の長期譲渡課税で出口
この「総合課税の高税率」と「分離課税の低税率」のギャップを活用することが節税の本質でした。
改正後は、このうち「総合課税側での圧縮」が制限されました。つまり、入り口でのインパクトが削がれた形です。
ただし重要なのは、制度が全面禁止になったわけではない点です。
- 修繕費や管理費など実際の支出は従来通り経費算入可能
- 売却時の取得費計算における未償却残高調整は維持
- 法人は特例の直接対象外
したがって、「即座に完全終了」という単純な話ではありません。総合課税側の節税を抑制し、分離課税側や法人スキームへのシフトを促す構造に変わったと理解するほうが実態に近いです。
個人投資家に与えた影響
個人投資家にとって最大の影響は、給与所得との損益通算が実質的に使えなくなったことです。
高所得者ほどメリットが大きかった仕組みであったため、影響は主に次の層に集中しました。
- 医師や経営者など高税率帯の給与所得者
- 海外中古物件で4年償却を前提に資金計画を組んでいた層
- 総合課税圧縮を主目的としていた投資家
一方で、純粋なインカム投資や長期保有を前提とする投資家にとっては、投資の本質部分は大きく変わっていません。
制度変更の本質は「封鎖」ではなく「再設計」
2020年改正は、海外不動産投資そのものを否定したわけではありません。
- 総合課税での過度な圧縮を制限
- 分離課税での調整余地は残す
- 法人スキームは継続可能
という構造に再設計した改正です。
したがって、「もう海外不動産では何もできない」という理解は誤りです。重要なのは、どの課税区分で、どの主体で、どのタイミングに税効果を発現させるかを再構築することにあります。
制度変更を表面的に捉えるのではなく、課税構造全体を俯瞰して戦略を再設計できるかどうかが、改正後の勝敗を分けています。

2020年改正は“海外不動産はダメ”という話ではなく、“総合課税での過度な圧縮はダメ”に変わっただけです。個人でやるのか法人でやるのか、入口と出口をどう設計するのかまで考えれば、まだ戦略は十分に組めますよ
税制改正前に海外不動産が節税商品だった理由
2020年税制改正前、海外不動産は単なる資産分散商品ではなく「高所得者向けの強力な税務戦略ツール」として機能していました。とくにアメリカの中古不動産を活用したスキームは、所得税の累進構造と減価償却制度の特性を組み合わせることで、極めて高い節税効果を生み出していたのです。
ここでは、なぜ海外不動産が節税商品として成立していたのか、その本質的な理由を整理します。
建物比率が高く減価償却額を最大化できた
海外、とりわけアメリカの中古住宅は、土地よりも建物の評価割合が高いケースが多いのが特徴です。日本では「土地8:建物2」といわれることが一般的ですが、米国では「土地2:建物8」となる事例も珍しくありません。
減価償却の対象は建物部分のみです。つまり、建物比率が高いほど、購入価格のうち経費化できる金額が大きくなります。
1億円の物件で建物割合が8,000万円であれば、その大部分を減価償却の対象にできます。これが海外不動産、とくに米国物件が節税商品として注目された第一の理由です。
簡便法による短期償却で一気に赤字を作れた
中古資産には「簡便法」という耐用年数の特例計算があります。法定耐用年数を超過している物件であれば、法定耐用年数の20%が耐用年数になります。
たとえば木造住宅(法定耐用年数22年)で築30年の物件であれば、
- 22年 × 20% = 4年
となり、4年で全額を償却できました。
仮に建物価格8,000万円なら、年間2,000万円を経費計上できます。実際のキャッシュアウトは発生しないにもかかわらず、帳簿上は大きな赤字を作れる構造でした。
この「短期大量償却」が、海外中古不動産スキームの核心です。
給与所得との損益通算が可能だった
税制改正前は、不動産所得の赤字を給与所得など他の所得と損益通算することが可能でした。
高所得者ほど所得税率は高くなります。
- 所得税:最大45%
- 住民税:10%
- 合計:最大55%
仮に給与所得2,000万円の人が、不動産所得で2,000万円の赤字を作れば、課税所得をゼロに近づけられます。単純計算でも、
- 2,000万円 × 50%前後 = 約1,000万円の税負担圧縮
というインパクトがありました。
減価償却による帳簿上の赤字が、そのまま高税率部分を削る効果を持っていたため、累進課税構造と極めて相性が良かったのです。
長期譲渡税率との税率ギャップを活用できた
もう一つの重要なポイントは「出口戦略」です。
個人が不動産を5年超保有して売却した場合、譲渡所得税は分離課税で約20%になります。
一方、減価償却で圧縮できるのは総合課税部分で最大55%です。
つまり、
- 減価償却で圧縮する税率 = 最大55%
- 売却時の税率 = 約20%
この税率差を利用した構造が成立していました。
保有期間中に高税率で節税し、売却時には低税率で課税される。結果として税負担の「時間差」と「税率差」を同時に活用できたのです。
この構造があったからこそ、単なる「納税の繰延べ」ではなく、実質的な税率差益を取りにいくスキームとして機能していました。
高所得者に集中した合理的スキームだった
このスキームは、誰にでも有効だったわけではありません。
特に効果が大きかったのは、
- 給与所得が高い経営者
- 医師や士業などの高額所得者
- 累進課税の上位税率に位置する層
でした。
所得が低い層では税率差が小さいため、スキームの魅力は限定的です。一方、税率40%超の層では極めて合理的な戦略になっていました。
この「高所得者に偏った強い効果」が、最終的に税制改正へとつながる背景となります。
税制改正前の海外不動産は、
- 建物比率の高さ
- 簡便法による短期償却
- 給与所得との損益通算
- 長期譲渡20%課税との税率差
という4つの要素が組み合わさることで、強力な節税商品として成立していました。
しかし、その効果が大きすぎたために、制度は見直されました。重要なのは「なぜ機能していたのか」という構造を理解することです。そこを理解すれば、改正後の戦略設計にも応用が利きます。

税制改正前の海外不動産は、減価償却で高税率部分を削り、売却時は低税率で課税するという“税率差ビジネス”でした。仕組みを理解すれば、改正後も使える発想が見えてきますよ
現行制度でも活用できる3つの戦略
2020年税制改正により、個人が国外中古建物の簡便法による減価償却費を使って給与所得などと損益通算するスキームは封じられました。しかし、制度が厳格化された現在でも、設計次第で税務上の合理的な活用余地は残されています。
重要なのは「単年度の節税」ではなく、「取得から保有、売却までを通したトータル戦略」で考えることです。ここでは、現行制度下でも実行可能な3つの戦略を整理します。
海外不動産同士の所得内通算を戦略的に使う
税制改正後も、国外不動産同士であれば不動産所得内での通算は可能です。制限されたのは「簡便法による減価償却相当額を他所得と通算すること」であり、すべての損失が無効になったわけではありません。
具体的には、以下のような活用が考えられます。
- 既に黒字化している海外物件と、取得初期で償却負担が重い海外物件を組み合わせる
- 国やエリアを分散しつつ、同一年内での損益バランスを調整する
- コストセグリゲーションなどを活用し、減価償却の発生時期をコントロールする
たとえば、アメリカ不動産のように建物比率が高い市場では、初期数年で償却負担が大きくなります。一方で、安定稼働している物件があれば、その黒字と内部通算することで、不動産所得全体としての課税所得を圧縮できます。
これは「他所得との損益通算」とは異なりますが、不動産ポートフォリオ全体で見ると、税負担の平準化という意味で実務上の価値は高いです。単体物件ではなく、複数物件を前提とした設計がカギになります。
法人スキームで簡便法を継続活用する
税制改正の直接的な対象は個人であり、法人は現時点では簡便法による耐用年数計算および減価償却の損金算入が可能です。
法人活用のポイントは以下の通りです。
- 中古資産の耐用年数を簡便法で短縮できる
- 事業利益と通算できる
- 青色欠損金の繰越控除が可能
ただし、ここで誤解してはいけないのは「法人=節税」ではないという点です。法人での減価償却は、多くの場合「課税の繰延」です。売却時には法人税が課税され、個人のような長期譲渡税率の優遇はありません。
そのため、法人スキームを機能させるには、以下のような出口設計が不可欠です。
- 売却益計上時期を退職金支給や大型投資と重ねる
- 業績が落ち込んだ期に売却して通算する
- 欠損金繰越と譲渡益を相殺する
法人であれば、事業との組み合わせによって税率コントロールが可能になります。単なる不動産保有法人ではなく、事業法人の一部として組み込む設計ができるかどうかが、成否を分けます。
売却時に未償却残高を活用して譲渡所得を最適化する
現行制度で最も見落とされがちなのが、売却時の取得費計算です。
国外中古建物の損益通算特例により「なかったもの」とされた減価償却相当額は、譲渡所得計算上の減価償却累計額から控除される扱いとなります。その結果、未償却残高が増加し、取得費が大きくなります。
つまり、賃貸期間中に通算できなかった損失は、売却時に取り戻す構造になっています。
この構造を理解した上で重要なのは、保有期間の設計です。
- 取得から売却年の1月1日時点で5年超かどうかで短期・長期が判定される
- 長期譲渡になれば税率は約20%
- 短期譲渡の場合は約39%
単純に「5年経てばよい」わけではなく、1月1日基準での判定が重要です。売却時期を数か月ずらすだけで税率が大きく変わるケースもあります。
したがって、海外不動産は購入時点で出口シナリオを描く必要があります。
- 何年目に売却するか
- 為替水準はどうか
- 他の所得状況はどうか
- 長期譲渡判定を確実にクリアできるか
これらを総合的に設計することで、現行制度下でも十分な税務最適化が可能です。
まとめ
2020年税制改正によって、海外不動産の減価償却を使った「単年度での大幅な所得圧縮」は封じられました。しかし、制度を正しく理解すれば、戦略的な活用余地は残されています。
- 海外不動産同士の内部通算
- 法人スキームの活用
- 売却時の未償却残高調整と長期譲渡設計
重要なのは、節税を目的にするのではなく、キャッシュフロー・為替・市場成長・税務を一体で設計することです。海外不動産は税商品ではなく、あくまで投資商品です。その前提に立った上で税務を活用する視点が、今後の勝敗を分けます。

海外不動産の減価償却はもう使えないと誤解されがちですが、制度の本質は“封鎖”ではなく“再設計”です。単年の節税ではなく、取得から出口までのシナリオを組めば、今でも十分に戦える戦略になりますよ
法人活用での減価償却メリットと注意点
2020年税制改正により、個人による国外中古建物の簡便法償却は実質的に封じられました。一方で、法人は「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」の直接的な対象外であり、現在も簡便法による耐用年数計算と損金算入が可能です。
この違いこそが、海外不動産を法人で保有する最大の論点です。ただし、法人化すれば無条件で節税になるわけではありません。メリットと同時に、構造的なリスクと出口課税まで見据えた設計が必要です。
法人で活用する主なメリット
法人活用の強みは、減価償却そのものよりも「課税コントロール力」にあります。
- 簡便法による中古建物の短期償却が引き続き可能
- 本業利益との損益通算が可能
- 法人実効税率が概ね23%〜30%台で安定
- 青色欠損金の繰越控除が可能
- 売却益の計上時期を経営判断でコントロール可能
個人の場合は最高55%近い累進課税が問題になりますが、法人は比例的な税率構造です。そのため、高所得者ほど法人の方が税率面で安定的です。
例えば、法人で2,000万円の減価償却費を損金算入し、実効税率30%と仮定すれば、600万円相当の法人税負担を繰り延べできます。この「税金の前倒し回避」は、キャッシュフロー経営において極めて重要です。
節税ではなく課税繰延という本質
法人活用で最も誤解されやすい点は、「節税」と「課税繰延」は別物だということです。
法人は売却時にも法人税が課税されます。個人のように5年超保有で20%の長期譲渡税率になる仕組みはありません。減価償却で圧縮した分は、売却時に益金として跳ね返る構造です。
つまり、
- 減価償却で利益を圧縮
- その分だけ売却益が増加
- 売却時に法人税課税
となるため、単純な永久節税ではありません。
本質は「税率差」ではなく「時間差」です。
税金を将来に回すことで、その間の運用効率を高められるかどうかが勝負になります。
売却戦略と法人スキームの設計
法人活用の真価は、出口設計と組み合わせたときに発揮されます。
- 退職金支給タイミングと売却益を連動
- 大型設備投資の年に売却益をぶつける
- 業績悪化年度に売却して相殺
- 繰越欠損金と相殺
法人の青色欠損金は最長10年繰越可能です。売却タイミングを意図的に調整できる点は、個人投資との大きな違いです。
海外不動産は流動性の高い市場を選ぶことで、売却タイミングのコントロールがしやすくなります。特に中古市場が成熟しているエリアは、法人戦略との相性が良いと言えます。
法人活用の注意点とリスク
一方で、法人化には次のリスクがあります。
- 法人維持コスト(税理士費用・申告コスト)
- 国際税務対応の複雑性
- 為替差損益の影響
- 移転価格・過少資本税制などの論点
- 将来の税制改正リスク
また、法人で利益が出た場合、最終的に個人へ配当すれば二重課税が発生します。法人税と配当課税を合算すると、実効税負担は決して低くありません。
法人で保有する場合は、「会社に資産を積み上げる戦略」なのか、「最終的に個人に戻す戦略」なのかを明確にする必要があります。
法人化が向いている投資家像
法人活用は万能ではありません。向いているのは次のようなケースです。
- すでに法人で安定利益がある
- 本業利益と損益通算したい
- 退職金設計まで含めた資産戦略を持っている
- 長期的に法人内で資産を増やす方針
単に「個人で使えなくなったから法人にする」という発想では不十分です。
取得から保有、売却、そして資金の最終帰属まで一体設計することが、法人活用の絶対条件です。

法人活用は魔法の節税ではありませんが、課税をコントロールできる強力な経営ツールです。減価償却だけを見るのではなく、売却時期や退職金設計まで含めて考えることで、初めて戦略になりますよ
アメリカ不動産投資と減価償却の相性
アメリカ不動産が減価償却と相性が良いと言われてきた背景には、日本国内不動産とは異なる市場構造と資産評価の考え方があります。税制改正により個人の損益通算スキームは制限されましたが、それでもなおアメリカ不動産が議論の中心にあるのは、単なる節税商品ではなく「投資資産」としての合理性があるからです。
まず大きな特徴は、建物割合の高さです。日本では土地の評価割合が高く、建物部分は比較的低く算定される傾向があります。一方でアメリカは土地が広大で供給余地も大きく、物件価格に占める建物比率が高くなりやすい市場構造です。
建物割合が高いということは、減価償却対象額が大きくなることを意味します。減価償却は建物部分のみが対象であるため、同じ価格の物件でも建物比率が高いほど税務上のインパクトは大きくなります。この構造が、かつて海外不動産を活用した節税スキームの中核となっていました。
次に、中古市場が主流である点です。アメリカでは年間取引件数の大半が中古物件であり、築年数が経過していても市場価値が維持されやすい傾向があります。築30年、40年といった物件でも流動性が高く、売却が難しくなるケースは限定的です。
この中古市場の厚みは、減価償却戦略と極めて相性が良い特徴です。なぜなら、中古資産は簡便法による耐用年数短縮が可能であり、短期間で償却を進められる一方、出口では市場価格が一定水準で維持されやすいからです。
さらに、コストセグリゲーションの活用可能性も無視できません。これは建物を一括償却するのではなく、設備や内装、構築物などを細分化し、それぞれの耐用年数で償却する手法です。結果として、より短期間で償却費を計上できる場合があります。
個人では2020年税制改正により給与所得との損益通算は制限されましたが、法人であれば簡便法や設備区分を活用した償却設計は引き続き可能です。ただし重要なのは、これは「節税」ではなく「課税繰延」である点です。償却により当期の利益を圧縮しても、売却時には法人税が課税されます。したがって、取得から出口までを一体で設計することが不可欠です。
アメリカ不動産は出口戦略の設計自由度も高い市場です。流動性が高いため、売却タイミングを調整しやすく、法人であれば以下のような調整も可能です。
- 退職金支給年度に売却して損益通算する
- 大型設備投資年度に譲渡益をぶつける
- 繰越欠損金がある年度に出口を設定する
このように、法人の事業計画と連動させやすい点も、アメリカ不動産と減価償却の相性が良い理由です。
加えて、投資対象としてのファンダメンタルズも無視できません。人口増加、経済規模、ドル建て資産としての通貨分散効果、インフレ耐性など、税務以外の合理性が存在します。減価償却だけを目的にすると制度変更リスクに弱くなりますが、投資収益そのものが成立する市場であれば、税効果はあくまで付随メリットとして位置付けられます。
重要なのは次の3点です。
- 減価償却はキャッシュを生まない会計処理である
- 個人では総合課税側の圧縮効果は制限されている
- 法人では繰延戦略として設計すべきである
アメリカ不動産は、建物割合の高さ、中古市場の厚み、流動性の高さ、法人活用との親和性という点で、減価償却設計と構造的に相性が良い市場です。ただし、単体での節税商品として考えるのではなく、取得・保有・売却までのトータルシミュレーションを前提に活用する必要があります。
税制は今後も変更される可能性があります。だからこそ、短期的な節税テクニックではなく、資産配分・法人戦略・為替リスクまで含めた総合設計が投資家には求められます。

アメリカ不動産は減価償却と相性が良い市場ですが、本質は節税ではなく戦略設計です。建物割合、中古市場、法人活用、出口タイミングまで一体で考えられる人だけが、本当の意味でメリットを最大化できます
海外不動産減価償却で失敗しないためのチェックポイント
海外不動産の減価償却は、制度を正しく理解しなければ「思ったほど節税にならない」「出口で想定外の税負担が発生する」といった事態に陥ります。特に2020年税制改正以降は、個人・法人で扱いが大きく異なるため、事前の設計がすべてを左右します。
ここでは、投資家が実務レベルで確認すべき重要ポイントを整理します。
節税と課税繰延の違いを正確に理解しているか
減価償却による税効果は「税金がなくなる」のではなく、「税金の支払い時期が後ろにずれる」ケースが多いです。とくに法人スキームでは、減価償却によって当期利益を圧縮しても、売却時には未償却残高や譲渡益に対して法人税が課税されます。
本当に節税なのか、それとも単なる課税繰延なのかを、以下の視点で確認することが重要です。
- 減価償却による当期税率と売却時税率の差
- 保有期間中のキャッシュフロー改善効果
- 退職金支給や設備投資など他の損金との相殺可能性
単年度の税額だけで判断すると、出口で想定外の税負担が発生します。必ず取得から売却までの通算税負担でシミュレーションすることが必要です。
個人と法人の適用ルールを混同していないか
2020年税制改正により、個人が国外中古建物を簡便法で償却して生じた損失は、給与所得などとの損益通算が制限されています。一方、法人は原則として簡便法による減価償却を引き続き活用可能です。
しかし法人であっても、次の点を見落とすと効果が限定されます。
- 実効税率を踏まえた税効果の試算
- 法人内に十分な課税所得があるか
- 将来の売却益への課税インパクト
- 繰越欠損金との調整可能性
「法人にすれば大丈夫」という単純な判断は危険です。法人活用は高度な出口設計とセットで検討すべき戦略です。
建物割合と評価の妥当性を検証しているか
減価償却の対象は建物部分のみです。海外不動産では、土地と建物の評価割合が日本と異なるケースが多く、建物割合が高いことが投資メリットとされてきました。
しかし、税務上の建物割合が合理的でなければ否認リスクがあります。特に注意すべき点は以下です。
- 売買契約書上の内訳が適正か
- 現地鑑定評価やコストセグリゲーションの根拠
- 日本の税務基準で説明可能か
将来の税務調査で説明できるロジックがあるかどうかが重要です。形式だけでなく実質的な妥当性を確認しておく必要があります。
短期譲渡と長期譲渡の判定を正確に理解しているか
個人の場合、譲渡所得は保有期間によって税率が大きく異なります。5年超かどうかの判定は「取得日から5年経過」ではなく、「売却年の1月1日時点で5年超保有しているか」で判断されます。
この判定を誤ると、想定より高い税率で課税される可能性があります。
- 売却タイミングの最適化
- 為替状況との調整
- 譲渡益と未償却残高のバランス
税率差だけでなく、為替益や市場価格も含めて総合判断することが重要です。
為替リスクを税効果と切り離していないか
海外不動産はドル建てや現地通貨建てで運用されます。減価償却で税効果が出ていても、為替変動によって円換算の収益が大きく変動します。
チェックすべき視点は次の通りです。
- 購入時為替レートと売却時レートの差
- 円換算ベースでの実質利回り
- 為替差損益と税務処理の関係
税引後キャッシュフローと為替変動を統合して評価しなければ、本当の投資成果は見えません。
現地管理体制と出口戦略が具体化されているか
税制面だけに注目すると、本質的な投資リスクを見落とします。現地管理体制が不十分であれば、空室や修繕費増大によって想定利回りは崩れます。
確認すべきポイントは以下です。
- 現地プロパティマネジメントの実績
- 修繕履歴と今後の資本的支出予測
- 流動性と売却市場の厚み
- 買い手層の構造
減価償却はあくまで会計上の処理です。実際の資産価値と市場流動性が伴って初めて戦略として成立します。
国際税務に強い専門家と連携しているか
海外不動産投資は、日本の所得税・法人税だけでなく、現地税制や租税条約も関係します。源泉税、現地譲渡税、二重課税調整など、複雑な論点が絡みます。
次のような体制が整っているかが重要です。
- 国際税務に精通した税理士
- 現地法務・会計専門家との連携
- 出口まで見据えた税務シミュレーション
単なる物件紹介ベースの提案ではなく、税務・財務・市場を統合した設計ができているかが成否を分けます。
海外不動産の減価償却は、制度の穴を突く短期節税スキームではなく、取得から出口まで一体設計する中長期戦略です。税制改正後の環境では、安易な期待は禁物ですが、適切に設計すれば依然として有効な資産戦略になり得ます。

海外不動産の減価償却は魔法の節税ではありませんが、仕組みを正しく理解し、法人活用や出口設計まで含めて戦略的に組み立てれば、資産全体の税効率を高める有力な選択肢になります。単年度の税金ではなく、人生トータルのキャッシュフローで考えることが成功の鍵です