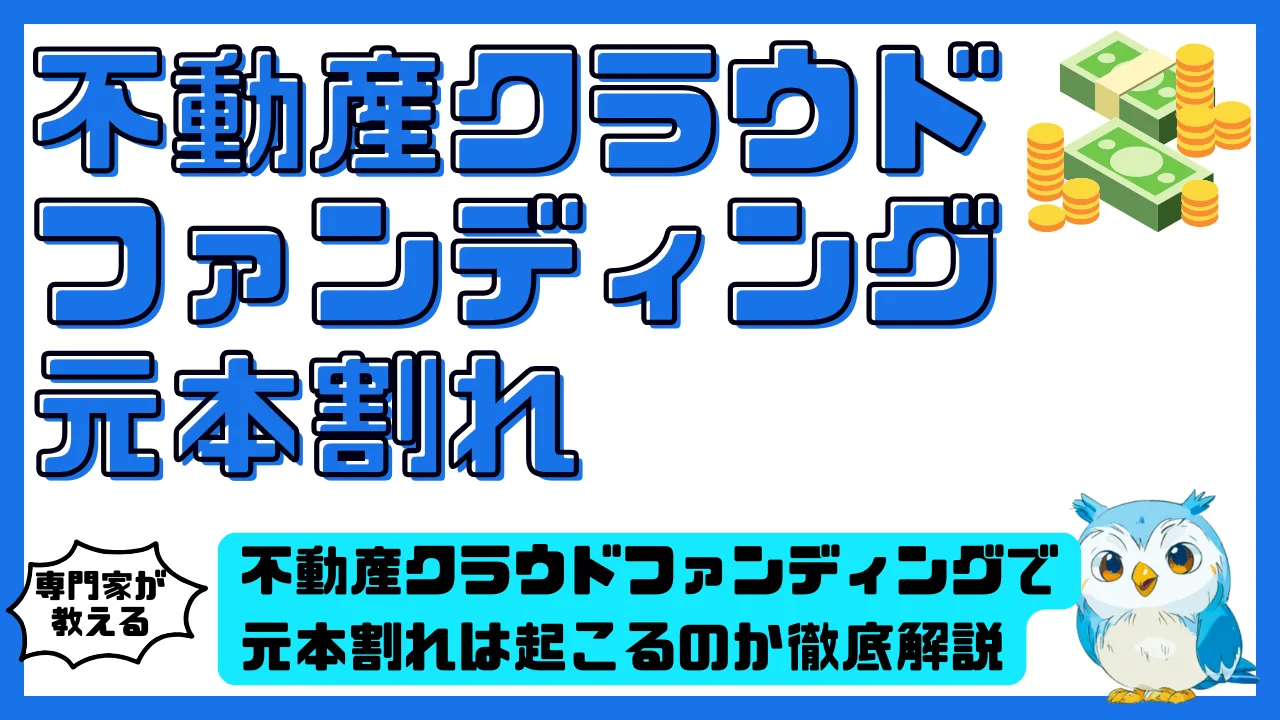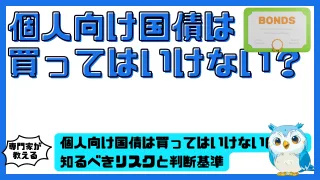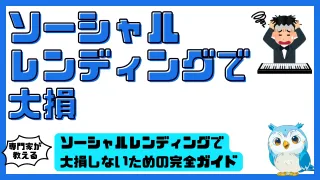本ページはプロモーションが含まれています。
目次
不動産クラウドファンディングの基本と仕組み
少額から始められる新しい不動産投資
不動産クラウドファンディングは、従来の不動産投資のように数百万円単位の資金を必要とせず、1口数万円から始められる投資手法です。インターネット上のプラットフォームを通じて投資家が資金を出し合い、運営事業者がその資金で不動産を取得・運用する仕組みになっています。個人投資家がアクセスしにくかった大型物件や収益性の高いプロジェクトにも、小口で参加できる点が大きな特徴です。
投資の流れと仕組み
投資の流れはシンプルです。投資家はオンライン上で会員登録を行い、案件ごとに設定された条件(利回り・運用期間・劣後出資割合など)を確認して出資を決定します。募集が成立すると運営事業者が物件を購入し、賃貸経営や開発、リノベーションを行ったうえで収益を確保します。運用期間終了後には物件の売却や賃料収入によって得られた利益から分配が行われ、元本償還が実施されます。
収益の源泉
不動産クラウドファンディングにおける収益は、大きく分けて「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」に分類されます。
- インカムゲインは物件を賃貸することで得られる家賃収入から生まれる利益です。比較的安定性があり、運用期間中に定期的な分配を受けられるのが特徴です。
- キャピタルゲインは物件を売却した際の価格差益から得られる利益です。不動産市場の動向によって大きく変動するため、利回りが高い一方でリスクも伴います。
多くのファンドでは、インカムゲインとキャピタルゲインを組み合わせた「ハイブリッド型」を採用しており、収益の安定性とリターンの最大化を狙っています。
インターネット投資ならではの利便性
すべての手続きがオンラインで完結する点も重要です。申し込みから契約、分配金の受け取りまで、すべてウェブ上で管理できるため、従来の不動産投資のように煩雑な契約や管理業務を担う必要がありません。また、案件情報も公開されているため、投資家は自分の投資方針に合った案件を選択できます。

不動産クラウドファンディングは「少額から不動産投資に参加できる新しい仕組み」で、収益は賃料収入と売却益の2本柱で成り立っています。インターネット完結型で投資のハードルが下がっているのは魅力ですが、利回りや案件条件は事業者によって異なるため、きちんと仕組みを理解してから参加することが大切ですよ
元本割れとは何を意味するのか
元本割れの基本的な定義
元本割れとは、投資で最初に出資した金額(元本)が、最終的に回収される金額を下回る状態を指します。不動産クラウドファンディングにおいては、運用終了時に受け取る償還金と、運用期間中に分配された配当金を合計しても、出資額より少なくなる場合がこれにあたります。つまり、投資家が当初投入した資金の一部が失われる可能性を意味します。
元本保証がない金融商品の共通リスク
不動産クラウドファンディングは銀行預金や国債と異なり、元本が保証されている商品ではありません。投資対象の不動産価格が下落したり、想定していた賃料収入が得られなかったりすると、分配原資が不足し、最終的に出資額を下回るリスクが生じます。これは株式や投資信託など、多くの金融商品にも共通する「投資の宿命」といえるものです。
どのような場面で起きるのか
元本割れは次のようなケースで発生する可能性があります。
- 不動産価格が下落し、売却金額が当初の購入価格を下回った場合
- 入居率低下や賃料滞納によって予定通りの収益が得られない場合
- 運営事業者が経営難や倒産に陥り、分配金や償還金を支払えなくなる場合
このように、元本割れは単なる「価格の変動」だけでなく、賃料収益の不足や事業者の信頼性にも影響される複合的なリスクです。
元本割れを正しく理解する意義
元本割れは「投資した資金がゼロになる」ことを意味するわけではありません。大半のケースでは、一部の資金が毀損することを指し、最悪の場合に全額失われる可能性があるという幅を持っています。この違いを理解しておくことで、投資家は過度な期待を避け、適切なリスク許容度で投資判断を行うことができます。

元本割れという言葉は不安を感じさせますが、その本質は「投資元本が減少する可能性がある」という事実を表しています。ゼロリスクの商品ではないことを理解し、分散や事業者の選定といった工夫でリスクを抑える姿勢が大切ですよ
不動産クラウドファンディングで元本割れが起きる主な原因
不動産クラウドファンディングは少額から始められる点で魅力がありますが、元本保証はなく、リスク要因を理解していないと損失を被る可能性があります。主な原因は以下の通りです。
不動産価格の下落や売却損失
ファンドの多くは運用終了時に不動産を売却して収益を確定します。その際、購入時よりも不動産価格が下落していると売却損が発生し、出資金を下回る償還になることがあります。
価格下落の要因としては、景気後退や金利上昇、地域需要の低下、さらには地震や台風などの自然災害による資産価値の毀損が挙げられます。キャピタルゲイン型ファンドでは特に価格変動の影響を受けやすく注意が必要です。
賃料収入の減少や滞納
インカムゲイン型やハイブリッド型ファンドでは、賃料収入が分配金の原資となります。入居率の低下、賃料相場の下落、借主の滞納などにより収益が想定より減少すると、分配金が十分に得られず元本割れに直結します。
特にオフィスや商業施設などでは景気の影響を受けやすく、賃料減少リスクが高まる傾向があります。
運営事業者の経営悪化や倒産
どれほど物件が健全に運用されていても、事業者自体が資金繰り悪化や不祥事で倒産すると、投資家の出資金が返還されない可能性があります。法律上、出資金は分別管理される仕組みがありますが、運用体制が不十分な事業者では資金流用や返還不能に陥るケースも考えられます。
直近でも一部事業者の破産によって投資家が損失を被る可能性が報じられており、事業者リスクは無視できません。
外部環境の急変
リーマンショックやコロナ禍のような世界的金融危機、政策変更、災害など予期せぬ事態は不動産価格や賃料需要を急激に変動させます。こうした外部要因は投資家がコントロールできないリスクであり、複合的に作用して元本割れを招く場合があります。

元本割れの原因は一つではなく、不動産価格・収益性・事業者の健全性・外部環境といった複数要因が絡み合って起こるんです。投資家としては「なぜ損失が出るのか」を理解し、対策を取ることでリスクを最小化できるようにしておきましょう
実際に元本割れが発生した事例と業界動向
元本割れが実際に起きた事例
2025年8月時点において、不動産クラウドファンディング業界で注目されたのが「DAIMLAR FUND」を運営していたダイムラー・コーポレーションの破産事例です。負債総額は約3.3億円に達し、出資していた投資家は約300人とされています。このケースでは、返還されない資金が生じる可能性が極めて高く、事実上の元本割れとして業界初の大規模事案になる見込みです。これまで多くの不動産クラウドファンディング事業者が「元本割れゼロ」を実績として強調してきましたが、事業者の経営破綻によるリスクが現実化した点は大きな警鐘といえます。
過去を振り返ると、リーマンショックのような世界的な金融危機や、大規模自然災害の影響で不動産価値が急落した局面において、事実上の元本割れに近い状況が起こった事例も確認されています。ただし、クラウドファンディングという仕組み自体が新しいこともあり、公に大規模な元本割れ事例が報告されたケースは少なく、2025年の破産事案は特に象徴的といえます。
業界全体の動向と投資家保護の流れ
一方で、業界全体では投資家保護に向けた規制や制度強化が進んでいます。不動産クラウドファンディング事業者は「不動産特定共同事業法」のもとで運営され、国土交通大臣や都道府県知事の許可・登録を得ることが義務付けられています。近年は分別管理の徹底や、優先劣後出資制度の導入が広がり、損失が一定の範囲内であれば事業者側が先に負担する仕組みが定着してきました。
さらに、金融庁や国交省による監督強化、外部監査体制の導入、投資家への情報開示義務の厳格化などにより、透明性は年々高まっています。また、大手不動産会社や上場企業が参入することで、経営基盤が安定した事業者による案件も増加しており、投資家にとって信頼性の選択肢は拡大している状況です。
ただし、利回りの高さを強調する中小規模事業者では、資本力不足や運営体制の脆弱さからリスクが依然として残ります。投資家は「高利回り=高リスク」であることを前提に、事業者の信頼性とリスクヘッジの仕組みを見極めることが不可欠です。

実際に元本割れは珍しいけれど、事業者の倒産や外部ショックが起きれば避けられないケースもあるんだよ。だからこそ「過去の実績に元本割れがない」だけで安心せず、規模・資本力・制度設計をしっかり見て判断することが大切なんだ
元本割れ以外に注意すべきリスク
不動産クラウドファンディングは少額から始められる点で魅力的ですが、元本割れ以外にも投資家が把握しておくべきリスクがあります。ここでは代表的なリスクを整理します。
途中解約ができない資金拘束リスク
不動産クラウドファンディングは、原則として運用期間中に途中解約ができません。クーリングオフ期間を過ぎれば資金は拘束され、急な資金需要に対応できない点がデメリットです。数カ月から数年にわたり資金がロックされるため、当面使わない余裕資金で投資することが重要です。
投資機会の制約
案件ごとに募集枠や期間が設定されており、希望するタイミングで必ず投資できるとは限りません。特に人気案件は抽選制や先着制で即時に募集が終了するケースも多く、狙った案件に参加できないことがあります。タイミング次第で投資計画が狂う可能性もあるため、複数のプラットフォームに口座を用意しておくなど工夫が必要です。
運営事業者リスク
運営会社自体の信頼性も大きなリスク要因です。分別管理が義務化されているとはいえ、事業者が倒産した場合、投資資金が返還されない可能性があります。また、財務基盤の弱い事業者では資金繰りが悪化し、配当の遅延や情報開示の不透明さにつながることもあります。許認可や実績、資本金、過去の案件運用履歴を確認することが欠かせません。
流動性の低さ
株式やREITのように市場で売買できる仕組みがないため、運用期間中に現金化できません。急に相場や経済情勢が変化しても途中でポジションを解消できず、リスクを抱えたまま運用を続ける必要があります。
情報開示の偏り
クラウドファンディングはインターネット上で手軽に投資できる一方、情報開示が事業者の提供資料に依存します。現物不動産のように自ら調査するのは難しく、投資家側が得られる情報は限られるため、案件のリスクを十分に判断できない場合があります。

元本割れだけではなく、資金拘束や事業者リスクも見落とせないポイントです。投資家の立場では「使う予定のない余裕資金で投資すること」「信頼性の高い事業者を選ぶこと」「複数の案件やサービスに分散すること」が現実的な対策になりますよ
元本割れリスクを回避するための実践的な方法
不動産クラウドファンディングで元本割れを防ぐためには、リスクを最小限に抑える仕組みを理解し、投資家自身が主体的に判断することが重要です。以下に具体的な対策を紹介します。
優先劣後システムを活用する
優先劣後システムは、投資家の元本を守るために設計された仕組みです。事業者が自ら劣後出資を行い、損失が発生した場合はその範囲内で事業者が先に負担します。劣後出資比率が高いファンドほど投資家の安全性は高まります。目安としては劣後比率10~30%程度のファンドを選ぶとリスクが軽減されやすいです。
事業者の信頼性を徹底チェックする
元本割れのリスクを抑えるには、事業者選びが最も重要です。不動産特定共同事業法の許可・登録の有無だけでなく、以下の点も確認してください。
- 財務基盤の安定性(資本金、自己資本比率など)
- 過去の償還実績や元本割れの有無
- 配当金の支払い遅延やトラブル事例の有無
- 運営会社が上場企業や大手グループに属しているか
透明性が高く、過去の実績を公開している事業者を選ぶことが信頼性の確保につながります。
分散投資を徹底する
単一案件や特定のエリアに資金を集中させると、市況変動や災害リスクの影響を強く受けます。リスク分散のためには、複数のファンド・エリア・運営会社に投資を分けることが有効です。また、不動産クラウドファンディングだけでなく、REITや株式、債券など他資産と組み合わせることでポートフォリオ全体の安定性を高められます。
利回りの高さに惑わされない
高利回り案件は魅力的に見えますが、その分リスクが高い場合が多いです。相場を大きく上回る利回りを提示するファンドは、入居率や売却益の見通しが不安定な可能性があります。安定的なリターンを重視するなら、過去実績がしっかりした中利回り案件を選ぶのが堅実です。
契約条件とリスク開示を確認する
契約書や募集要項に記載されたリスク説明を確認し、途中解約不可や資金拘束期間の長さを理解したうえで投資判断を行いましょう。事業者によるリスク開示の内容が不十分であれば、慎重な判断が必要です。

投資はリターンだけでなくリスク管理がカギになります。優先劣後システムや分散投資を組み合わせることで、元本割れの可能性を大きく下げることができますよ。信頼できる事業者を見極め、余裕資金で取り組むのが基本だと覚えておきましょう
投資家が確認すべきチェックポイント
不動産クラウドファンディングは少額から始められる手軽さが魅力ですが、投資先を誤ると元本割れのリスクを抱えることになります。投資家が事前に確認しておくべきポイントを整理しました。
利回り水準の妥当性
表面利回りが極端に高い案件は、裏にリスクが隠れている場合があります。特に「年利10%超」のような水準は、不動産市場の平均水準から乖離していることが多いため注意が必要です。リスクとリターンは表裏一体であり、安易に高利回りだけで判断しないことが重要です。
運営事業者の健全性
事業者の財務状況や過去のファンド運用実績を調べることは必須です。特に確認すべき点は以下です。
- 金融庁・国土交通省の許認可の有無
- 償還実績や元本割れの発生有無
- 分配金の遅延やトラブルの有無
- 資本金や親会社の有無による経営基盤の安定度
上場企業や大手不動産会社グループの運営は、比較的信頼性が高い傾向があります。
優先劣後出資の割合
投資家保護の観点から導入されている優先劣後構造は、必ず確認すべき仕組みです。劣後出資割合が高ければ高いほど、投資家の元本は一定範囲守られる可能性が高まります。10〜30%程度が一般的ですが、案件ごとに差があるため必ず確認しましょう。
投資対象物件の内容
投資先の物件がどのような種類かも重要です。立地、築年数、用途(住宅・商業施設・オフィス)などによって安定性が異なります。賃貸需要が高いエリアか、再開発の予定がある地域かといった点もチェックしましょう。
投資期間と資金拘束
不動産クラウドファンディングは原則として途中解約ができないため、投資期間中は資金が拘束されます。短期(6カ月程度)であれば流動性リスクは小さくなりますが、長期案件では余裕資金での参加が前提となります。資金計画と照らし合わせて判断しましょう。
情報開示の透明性
募集ページや事業者サイトでの情報開示が丁寧かどうかもチェックが必要です。物件の住所が非公開、収益シミュレーションの根拠が不明確といった場合は注意が必要です。投資家に対して積極的に説明責任を果たしているかどうかが信頼性の指標になります。

投資の判断で大切なのは「利回りだけで決めないこと」です。事業者の健全性、優先劣後の割合、投資対象の中身までしっかり確認して、数字の裏側に潜むリスクを見極める習慣を持ちましょう。それが元本割れを避ける第一歩になりますよ
元本割れリスクを理解した上での投資戦略
不動産クラウドファンディングは「少額から始められる」「手軽に投資できる」という魅力がある一方で、元本割れのリスクを完全に避けることはできません。大切なのは、リスクを前提として投資戦略を組み立てることです。ここでは、投資家が実践すべき具体的な考え方を整理します。
余裕資金で取り組む姿勢
不動産クラウドファンディングは原則として途中解約できないため、急な資金需要に対応しづらい特徴があります。そのため、生活資金や短期的に必要となる資金ではなく、余裕資金を充てることが基本です。投資資金を流動性の高い資産と組み合わせることで、資金計画に柔軟性を持たせることができます。
長期視点でのポートフォリオ構築
短期的な市況変動や突発的な事象によって元本割れリスクが高まる可能性はあります。しかし、不動産市場は長期的に見れば回復や上昇の局面を持つことが多いです。投資を数カ月から数年単位で考え、長期的に安定収益を狙う視点が重要です。
他資産との組み合わせで安定性を確保
不動産クラウドファンディングに資産を集中させるのではなく、株式・債券・REITなど他の金融商品と組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスクを抑えることが可能です。特に株式市場との相関性が低い部分を活かし、景気変動リスクを分散する戦略は効果的です。
リスクをゼロにしない姿勢でリターンを狙う
「安全だから投資する」という考えではなく、「リスクを理解した上でリターンを取りに行く」というスタンスが欠かせません。元本割れが起こる可能性を前提に、そのリスクをどこまで許容できるかを投資前に明確にしておくことが重要です。利回りの高さに目を奪われず、事業者の信頼性や案件の透明性を優先的に確認することが求められます。

投資というのはリスクとリターンのバランスを取る作業なんです。元本割れを怖がりすぎても何も始まりませんし、安易に飛び込んでも失敗します。余裕資金で、長期視点を持ち、資産全体でリスクを分散する──この姿勢を守ることで、不動産クラウドファンディングも十分活用できる投資手段になりますよ