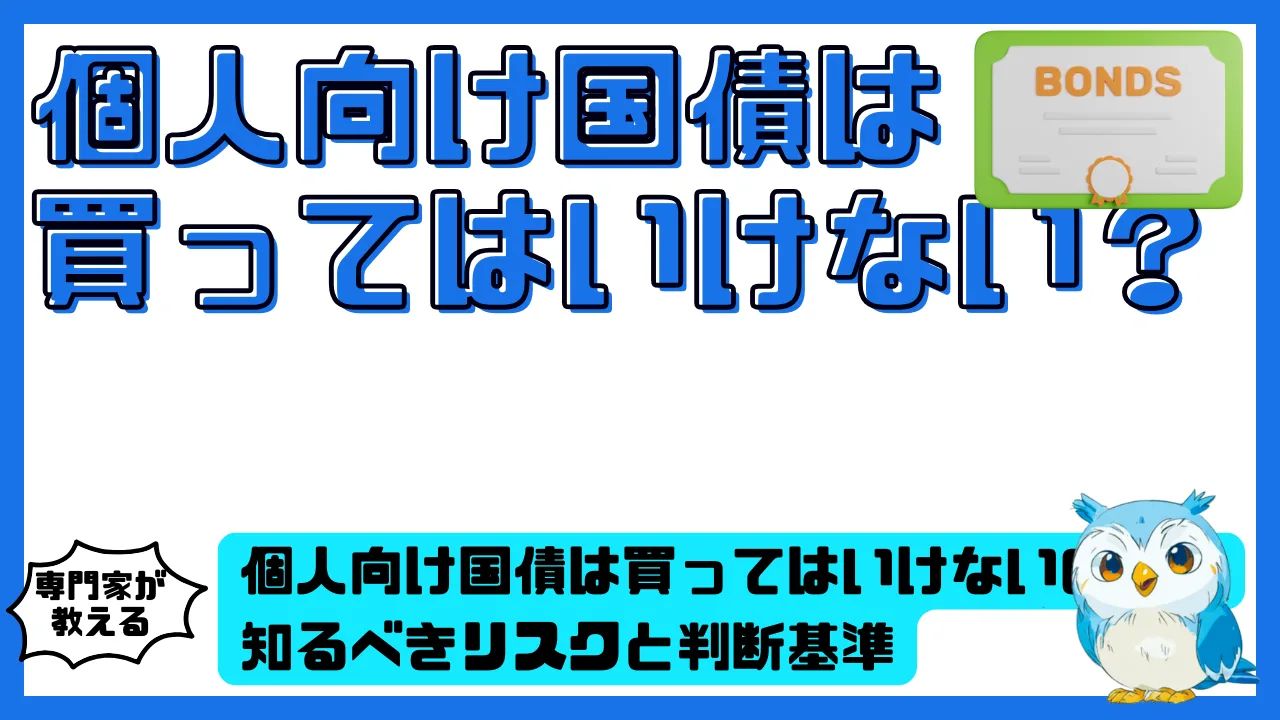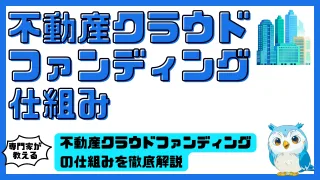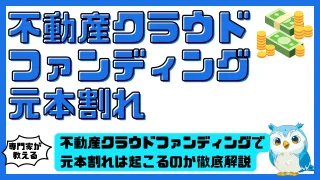本ページはプロモーションが含まれています。
目次
個人向け国債が「買ってはいけない」と言われる主な理由
利回りの低さ
個人向け国債は元本保証がある代わりに利回りが非常に低いのが特徴です。株式や投資信託のように数%〜数十%のリターンを期待できる資産と比べると、年0.1〜1%程度の水準にとどまるケースが多く、資産を増やす目的には物足りないと感じやすいです。特にインフレ局面では利息の伸びが物価上昇に追いつかず、実質的な資産価値が目減りするリスクがあります。
インフレに弱い構造
インフレが進むと、同じ額面の利息を受け取っても購買力は低下します。例えば物価が3%上昇しても利息が1%しか増えなければ、実質的には資産が減っているのと同じです。特に固定金利型の国債では、契約時の利率が満期まで変わらないため、インフレ時には資産防衛の役割を果たしにくくなります。
流動性の制限
個人向け国債は発行から1年間は中途換金ができないというルールがあります。急に資金が必要になっても解約できないため、柔軟性に欠ける点が投資家にとって不便に感じられます。緊急資金としては不向きであり、計画的に余裕資金を充てる必要があります。

個人向け国債は「安全性重視」には役立ちますが、資産形成や流動性確保の観点では弱点が目立ちます。買ってはいけないと言われる背景は、リターンの低さと柔軟性の乏しさにあるのです
低金利時代に指摘されてきた問題点
最低金利0.05%が長期化した影響
個人向け国債には「最低金利0.05%保証」が設けられていますが、日本銀行が長期にわたりゼロ金利・マイナス金利政策を続けた結果、この最低水準が実際の利回りとして適用される期間が極めて長く続きました。額面1万円あたり年間利息は5円、税引後は4円程度に過ぎず、投資家からは「実質的に利息がつかない」と批判を受けました。特に、他の資産クラスと比較した場合のリターンの物足りなさが際立っていたのです。
定期預金との差別化の難しさ
低金利時代においては、銀行の定期預金もほぼゼロ金利で推移していたため、国債と定期預金の金利差は事実上存在しませんでした。元本保証や流動性の観点からは、定期預金の方が解約しやすく使い勝手が良いため、わざわざ国債を選ぶインセンティブが弱かったのです。結果として、個人向け国債は「安全だがメリットが薄い商品」とみなされがちでした。
「資金を寝かせているだけ」という批判
株式や投資信託など、他の資産クラスが高いリターンを生んでいた時期と重なったため、個人向け国債を保有することは「お金を眠らせているのと同じ」というネガティブな評価を受けました。特にインフレ率がじわじわと上昇していた局面では、名目の利息を受け取っても実質購買力が下がる構造となり、投資妙味に欠けるとの見方が広がりました。投資家の間では、資産を増やす目的より「仕方なく置く場所」として扱われていたケースも少なくありません。

つまり、低金利時代の個人向け国債は「安全ではあるが実質的な利回りは限りなくゼロ」という扱いだったのです。資金を守るには良いけれど、増やす目的では期待外れになりやすかった、という点を理解しておく必要がありますよ
中途換金にかかるペナルティの仕組み
中途換金調整額とは
個人向け国債は1年経過後であれば途中解約(中途換金)が可能ですが、その際に必ず差し引かれるのが「中途換金調整額」です。これは直近2回分の税引後利息に相当する金額で、実質的に早期解約のペナルティとして機能します。投資家にとっては「利息を2回分返す」イメージであり、元本は守られるものの利息収入の一部を失うことになります。
計算方法と具体例
受け取り金額は次の式で算出されます。
額面金額 + 経過利子 − 中途換金調整額
- 経過利子は前回の利払い日から換金日までの日割り利息で、非課税で支払われます。
- 中途換金調整額は直近2回分の利息を合算した金額で、これが差し引かれます。
例えば年1%の変動10年国債を100万円分購入していた場合、半年ごとの利払いは約5,000円(税引前)です。仮に1年半後に換金すると、直近の2回分、約1万円分が調整額として差し引かれ、元本100万円と経過利子だけが戻る計算になります。
資金計画への影響
元本が必ず100%で戻る点は大きな安心材料ですが、満期を待たずに換金すれば利息が減るため「予定より利益が少なくなる」という落とし穴があります。特に教育資金や住宅資金など、数年以内に使う予定がある資金を投じてしまうと、必要なタイミングで思ったほどの利息が得られない可能性があります。
流動性とのトレードオフ
株式や投資信託のように市場で価格変動にさらされることはなく、額面100%で買い取ってもらえる点は他の債券にはないメリットです。しかし、ペナルティがある分、柔軟性に欠ける仕組みであることは否めません。短期的な流動性を重視する投資家には不向きで、当面使う予定のない余裕資金を充てるのが基本戦略となります。

中途換金は元本割れこそしませんが、利息を削られる仕組みになっています。だからこそ「余裕資金で満期まで保有する」前提で考えるのが大切ですよ
日本の財政リスクと信用問題
国債残高の拡大と将来不安
日本の国債残高はGDPの2倍を超える規模に膨らんでおり、主要先進国の中でも突出しています。2023年末時点で1,000兆円を超える水準に達し、財政健全化の道筋が見えにくい状況です。現状は低金利環境に支えられて利払い負担が抑えられていますが、金利がさらに上昇すれば国債費が急増し、財政運営に深刻な影響を与える可能性があります。
格付け会社による評価の低さ
日本国債の信用格付けは、米国や欧州主要国と比較すると低めに位置づけられています。ムーディーズでは「A1」、S\&Pでは「A+」とされており、投資適格ではあるものの、国の信用度が必ずしも盤石とはいえないことを示しています。格付けの低下は海外投資家の国債離れを招き、調達コストの上昇につながるリスクも考えられます。
国内投資家依存の構造
日本の国債はその大半を国内の金融機関や年金基金が保有しており、海外依存度は低いとされています。このため急激な資金流出リスクは限定的ですが、裏を返せば国内金融システムが国家財政に強く依存しているという構造的な脆さを抱えています。少子高齢化による貯蓄率の低下が進めば、国債の安定消化に支障が出る可能性も否定できません。
投資家が注視すべきポイント
個人向け国債は「日本政府の信用力」を前提とした商品です。したがって、国の財政状況や格付けの動向は投資判断に直結します。現状ではデフォルトリスクは極めて低いとされているものの、長期的には財政健全化の遅れや金利環境の変化がリスク要因になり得ます。投資家は「安全資産」としての一面に安心しすぎず、国家財政の持続可能性を冷静に見極める必要があります。

日本国債は今すぐ危ういものではありませんが、将来の金利上昇や財政運営の停滞がリスクを増幅させる可能性があります。投資家としては「絶対安全」と思い込まず、国の財政基盤や国際的な信用評価を常に意識しながら活用していくことが大切ですよ
インフレ局面での資産価値の目減り
インフレが及ぼす影響
インフレとは、物価が継続的に上昇する現象を指します。例えばインフレ率が年3%なら、今年100円で買えた商品が翌年には103円必要になるということです。つまり、保有する現金や固定利率の債券の実質的な購買力は減少します。個人向け国債も例外ではなく、利率が物価上昇率を下回ると「資産を守っているはずが、実際には価値が減っていた」という状況になり得ます。
実質リターンの低下
現在の個人向け国債(固定3年・5年、変動10年)は、元本保証や最低金利0.05%といった安全性が特徴です。しかし日本の直近のインフレ率は3%前後で推移しており、国債利回りが1%前後にとどまる局面では実質的なリターンはマイナスになります。例えば100万円を5年間国債に預けて利息を受け取っても、インフレによって生活コストが増加すれば、手元に残る購買力は減少している可能性があります。
長期投資に不向きな理由
個人向け国債は生活防衛資金の置き場としては有効ですが、インフレ局面での資産形成には不向きです。特に老後資金や長期的な教育資金を積み立てる目的では、インフレに負けない成長力を持つ投資対象と組み合わせる必要があります。株式や投資信託、インフレに連動する商品を活用しないと、実質資産が目減りしていくリスクを抱えることになります。
インフレ対応型商品の存在
個人向け国債と比較対象として挙げられるのが「物価連動国債」です。これはインフレ率に応じて元本や利息が調整される仕組みを持ち、物価上昇下でも実質的な価値を維持しやすい特徴があります。ただし、流動性や販売チャネルが限られるため、個人投資家が活用するには証券会社選びや投資計画が必要になります。

インフレが進むと、利率の低い国債では実質的にお金が目減りしてしまいます。安全性は確かに高いですが、長期的に資産を守るにはインフレに強い資産と組み合わせることが大事ですよ
「買ってはいけない」と感じやすい投資家の特徴
個人向け国債は安全性が高い金融商品ですが、その性質ゆえにメリットを感じにくい投資家も存在します。こうした人たちは、期待と実際のギャップが大きいため「買ってはいけない」と感じやすい傾向があります。
短期で現金化する可能性が高い人
個人向け国債は、発行から1年間は原則として換金できません。まとまった資金が急に必要になる可能性がある人にとって、この「1年縛り」は大きな不便さとなります。さらに、中途換金が可能になった後も、直前2回分の利息が差し引かれるため、短期運用を前提とする人にとっては効率的とは言えません。
高リターンを強く求める人
株式や不動産投資のように、高いリスクを取ってでも大きなリターンを得たい人にとって、年1%前後の利回りは物足りなく感じられます。とくにインフレ局面では実質リターンがマイナスになる可能性があり、リスク許容度の高い投資家からすれば「資金効率が悪い」と判断されやすい商品です。
日本の財政に強い不安を抱く人
日本は先進国の中でも債務残高が突出して大きく、格付けも高くありません。国家の信用に疑問を感じる人にとっては、元本保証という仕組み自体に安心感を持てないことがあります。このような投資家は、より格付けの高い米国債や欧州国債などに資金を振り向ける傾向があります。
インフレ耐性を重視する人
インフレ率が利回りを上回ると、資産の実質的な価値は減少します。インフレヘッジを重視する投資家にとって、固定金利型の国債は魅力が乏しく、物価連動国債や株式など他の資産の方が適していると考えやすいです。
手数料や運用効率を最重視する人
個人向け国債は手数料無料で購入できますが、リターンが小さいため送金手数料や管理の手間すら無駄に感じる人もいます。少額投資を効率的に増やしたい人にとっては、積立投資型の投資信託や新NISAの活用の方が合理的に映ることがあります。

要するに、短期流動性を重視する人や高いリターンを狙う人、そして日本の財政やインフレに不安を持つ人は、個人向け国債に魅力を感じにくいということです。投資は「自分のお金の性格」と合うかどうかが重要ですから、無理に選ぶ必要はありませんよ
逆に個人向け国債が適しているケース
個人向け国債は「買ってはいけない」と言われがちな金融商品ですが、条件次第ではむしろ最適な選択肢となる場面があります。リスクを過度に取らず、安全性を重視した運用を求める投資家にとって、国債の持つ特徴は強力な武器になります。ここでは具体的なケースを整理します。
ペイオフ上限を超える資金を安全に置きたい場合
銀行預金はペイオフ制度により1金融機関につき1,000万円までしか保証されません。これを超える資金を保有している場合、破綻リスクを考えると個人向け国債に振り分ける方が合理的です。国が直接償還を保証しているため、銀行よりも安全性が高いといえます。
投資初心者が元本保証を最優先したい場合
投資に慣れていない人にとって、株式や投資信託の価格変動は心理的な負担になります。個人向け国債は1万円から購入可能で元本保証があるため、初めて投資を試みる人が「まずは安全に体験したい」と考える際に適しています。手数料が不要な点もハードルを下げる要因です。
長期で安定した利息収入を得たい場合
個人向け国債は半年ごとに利息が支払われる仕組みです。年金の補填や生活費の一部を定期的にカバーする目的で活用すれば、安定したインカムゲインを確保できます。特に変動10年型は金利上昇局面で利息も増えるため、定期預金より柔軟性があります。
大口資金を効率的に運用したい場合
購入上限がなく、数千万円規模の資金を一度に安全資産として預けられるのも特徴です。退職金や相続資金など、大きな金額を安全に保有したいときには有力な選択肢となります。
資金を分散させたい場合
資産運用は株式や投資信託などのリスク資産だけに偏ると不安定になります。個人向け国債はリターンこそ低いものの、ポートフォリオ全体のリスクを抑える「安定装置」として機能します。株式市場の下落局面でも動じない資産を一部組み入れることで、精神的にも安心感を得やすくなります。

つまり、個人向け国債は「低リスクで資産を守りたい」「大きな資金を安全に置きたい」という場面でこそ真価を発揮するんです。株式や投資信託のように大きなリターンは望めませんが、資産運用の土台を固める安全資産としては非常に優秀だと覚えておいてください
投資判断のまとめと代替選択肢
個人向け国債は「買ってはいけない」と言われることがありますが、その評価は投資家ごとの目的や状況によって大きく変わります。低金利下では魅力が薄い一方、金利上昇局面や安全資産の確保が必要な局面では一定の役割を果たします。したがって、万能な答えではなく、資産全体の中でどのように位置づけるかを冷静に考えることが重要です。
個人向け国債を検討する際の視点
- 安全性重視:元本保証と政府の償還保証により、定期預金以上の安全資産として活用可能
- 利回りの限界:株式や投資信託に比べると成長余地は小さく、インフレ局面では実質的な価値が目減りするリスクがある
- 流動性制約:購入から1年間は換金不可、中途換金でも利息が差し引かれるため資金計画が不可欠
代替となる選択肢
新NISA・iDeCo
非課税メリットが大きく、長期的な資産形成を目的とする場合は最優先で検討すべき制度です。株式や投資信託を活用すれば、国債以上のリターンを狙えます。
定期預金
短期で資金を使う可能性がある場合や、換金の柔軟性を優先したい場合に適しています。金利は低めですが、解約手続きの手軽さが魅力です。
米国債・海外国債
信用格付けの高い国の国債は利回り水準が高く、分散投資先として有効です。ただし、為替リスクが伴うため円安・円高局面の影響を慎重に見極める必要があります。
投資信託・インデックスファンド
分散投資によりインフレ耐性と成長性を確保できる手段です。特に世界株インデックスファンドは、長期的なリターンを目指すうえで個人向け国債の弱点を補います。
判断基準の整理
- 生活防衛資金や余剰資金の保全 → 個人向け国債が有効
- 長期の資産形成・インフレ対策 → 新NISAや投資信託を優先
- 短期的な流動性確保 → 定期預金や普通預金が便利
- 高利回りと分散投資 → 海外債券やインデックスファンドを組み合わせる

個人向け国債は、リスクを抑えて余裕資金を守るには役立ちますが、資産形成を狙うならNISAや投資信託などと組み合わせて考えることが大切です。目的を明確にして、それぞれの特徴をうまく使い分けてくださいね