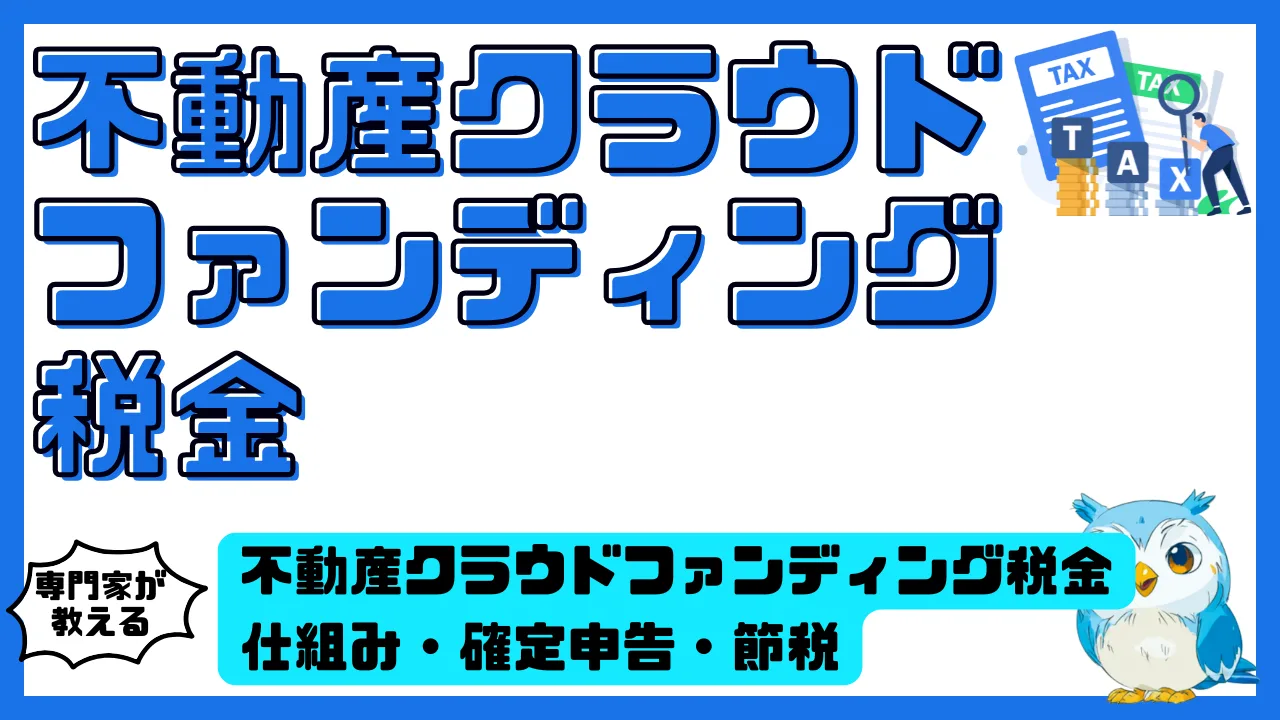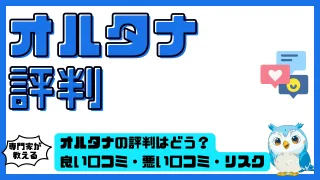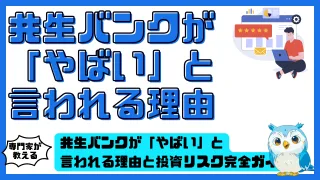本ページはプロモーションが含まれています。
目次
不動産クラウドファンディングで税金が発生する仕組み
不動産クラウドファンディングでは、投資額そのものに課税されるわけではありません。課税対象となるのは、投資から得られる分配金です。仕組みを理解しておくことで、確定申告や節税対応を誤らずに済みます。
分配金に対する源泉徴収
分配金を受け取る際には、所得税20%と復興特別所得税0.42%を合わせた 20.42% が自動的に源泉徴収されます。たとえば、5万円の分配金を受け取る場合には、約1万210円が差し引かれ、実際に手元に入るのは約3万9,790円となります。
雑所得としての扱い
不動産クラウドファンディングの多くは匿名組合契約型であり、不動産そのものの所有権を持ちません。そのため、分配金は不動産所得ではなく 雑所得 として扱われます。雑所得は給与所得などと合算され、総合課税の対象となります。つまり、他の所得と合わせた課税所得に応じて最終的な税率が決まります。
課税の流れのイメージ
- 投資額そのものには課税されない
- 運用期間終了後に分配金が支払われる
- 分配金から20.42%が源泉徴収される
- 年間の所得合計に応じて、確定申告が必要なケースでは税額が再計算される
このように、不動産クラウドファンディングでの税金は「投資収益に対して発生する仕組み」であり、仕入れや物件の取得とは異なる扱いになります。

不動産クラウドファンディングの税金は、投資額ではなく分配金に対して発生します。源泉徴収で一旦20.42%差し引かれますが、最終的には雑所得として他の収入と合算されるため、確定申告を行うことで還付を受けられる場合や追加で納税が必要な場合があります。仕組みを理解しておくことで、税金面での損失を避けられるのです
雑所得として扱われる理由と特徴
不動産を直接所有しない仕組み
不動産クラウドファンディングの多くは「匿名組合契約型」という仕組みを採用しています。この契約形態では、投資家は不動産を直接所有せず、事業者に資金を出資して運用益の分配を受け取る立場になります。所有権を持たないため、不動産所得ではなく「雑所得」として分類されます。これは株式や不動産の賃貸収入と異なり、事業そのものに参加しているわけではなく、利益配分を受け取るだけという性質が強いためです。
雑所得の税務上の特徴
雑所得は給与所得や不動産所得とは異なり、明確な必要経費の範囲が限定的である点が特徴です。支払った投資額そのものは経費にできず、原則として分配金にかかる税金がそのまま課されます。また、クラウドファンディングの分配金は事業所得のような青色申告控除や減価償却の適用もなく、税制上の優遇は受けにくいというデメリットがあります。
他の雑所得との通算可能性
雑所得は分類上「総合課税」に含まれるため、同じ雑所得区分で発生した損益を通算できます。例えば、FX取引や仮想通貨取引で損失が出ている場合、不動産クラウドファンディングの利益と合算することで課税対象額を減らし、結果として納税額を軽減できるケースがあります。ただし、事業所得や不動産所得とは損益通算できないため、現物不動産投資のような大規模な節税効果は期待できません。
所得の扱い方における注意点
雑所得は給与など他の所得と合算して課税所得を算出するため、総合課税のルールに従って税率が決まります。その結果、所得の多い方ほど税率が高くなる累進課税の影響を受けやすく、源泉徴収で引かれた20.42%よりも高い税率で課税される場合もあります。一方で、所得水準が低い方であれば、確定申告を行うことで源泉徴収された税金の一部が還付される可能性もあります。

雑所得として扱われるのは、不動産を所有せず分配金を受け取る仕組みだからです。節税の自由度は低いものの、FXや仮想通貨などと損益通算できる柔軟性がある点は押さえておきましょう。税率は所得全体で決まるため、自分の収入状況に合わせて確定申告を行うことが重要ですよ
確定申告が必要となるケース
不動産クラウドファンディングの分配金は、受け取り時に20.42%(所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されています。そのため「自動的に税金を払っているから確定申告は不要」と考える方も多いですが、実際には以下のケースでは確定申告が必要になります。申告を怠ると追徴課税のリスクがあるため、条件を正しく理解することが大切です。
雑所得が年間20万円を超える場合
不動産クラウドファンディングで得た分配金は「雑所得」に区分されます。年間の雑所得が合計で20万円を超えると、確定申告の義務が生じます。
対象となるのはクラウドファンディングの分配金だけでなく、以下のような収入も含まれます。
- FXや仮想通貨取引による利益
- 原稿料・印税・講演料
- 副業やネットショップでの売上
- 個人年金保険の年金受給額 など
複数の収入を合算した結果、20万円を超えた場合は必ず申告しましょう。なお、公的年金は雑所得に分類されますが「確定申告不要制度」が適用されるため合算対象外です。
年収2,000万円超の会社員や個人事業主
給与所得者であっても、年収が2,000万円を超える場合は必ず確定申告が必要です。また、個人事業主やフリーランスなど、もともと申告義務がある方も例外なく申告を行う必要があります。雑所得の金額が少なくても申告を省略することはできません。
控除を受ける場合
医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などの控除を受けるために確定申告を行うケースもあります。この場合、不動産クラウドファンディングの分配金も所得に加えて申告する必要があります。申告をすることで源泉徴収された税金の一部が還付される可能性もあるため、節税の観点からも見逃せません。
還付を受けられる可能性がある場合
課税所得が695万円未満の方は、本来の所得税率が20%以下になるため、源泉徴収で過剰に納税しているケースがあります。確定申告を行えば差額が還付される可能性があるため、雑所得が少額でも申告を検討する価値があります。

確定申告が必要になる条件は、雑所得の金額やもともとの収入状況、控除の有無によって変わります。自分がどのケースに当てはまるかを早めに確認しておくことが大切です。忘れがちな副収入や控除の適用条件も見落とさないようにしてくださいね
還付を受けられるケースと税率の仕組み
不動産クラウドファンディングで受け取る分配金は、支払い時点で20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されています。これは一律の税率で引かれるため、実際の所得税率がこれより低い方は確定申告によって払い過ぎた分の税金を取り戻せる可能性があります。
還付を受けられる主なケース
- 課税所得が695万円未満の人
所得税の税率は5%~20%の範囲に収まります。源泉徴収20.42%との差があるため、申告によって還付される可能性があります。
例:課税所得が300万円の場合、本来の税率は10%。源泉徴収との差額分が戻る可能性があります。 - 控除が多く課税所得が少ない人
基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などを適用することで課税所得が減少すると、税率がさらに下がり還付の可能性が高まります。 - 他の雑所得で損失がある人
FXや仮想通貨など同じ雑所得の赤字と通算できるため、分配金から差し引かれた税金の一部が還付される可能性があります。
還付を受けられない・追加納税が必要なケース
- 課税所得が695万円を超える人
所得税率は23%以上になるため、源泉徴収20.42%では不足します。確定申告で追加納税が必要になります。 - 確定申告をしない場合
源泉徴収された税額が確定税額として扱われ、還付を受けられません。還付を受けたい場合は必ず申告が必要です。
所得税の速算表(主な区分)
- 195万円以下:5%
- 195万円超~330万円以下:10%
- 330万円超~695万円以下:20%
- 695万円超~900万円以下:23%
- 900万円超~1,800万円以下:33%
- 1,800万円超~4,000万円以下:40%
- 4,000万円超:45%
源泉徴収率20.42%と比較し、これより低い区分の人は還付の可能性があります。

還付は「自分の本来の税率と源泉徴収率の差」で生まれるんです。課税所得が低い人や控除が多い人は払い過ぎになりやすいので、必ず申告して確認しましょう。逆に高所得層は追加納税になるので、見込みを立てておくのが大切ですよ
任意組合型と匿名組合型の違いと税務上の扱い
不動産クラウドファンディングには大きく分けて「匿名組合型」と「任意組合型」があります。両者は契約形態が異なるだけでなく、投資家にとっての税務上の取り扱いにも大きな違いがあります。
匿名組合型の特徴と税務上の扱い
匿名組合型は、不動産クラウドファンディングで最も一般的な契約形態です。投資家は事業者に出資し、その事業から得られる利益を分配金として受け取りますが、不動産そのものの所有権は持ちません。
税務上は以下のように扱われます。
- 分配金は「雑所得」として総合課税の対象
- 源泉徴収20.42%があらかじめ差し引かれる
- 他の雑所得(FXや仮想通貨など)と損益通算は可能
- 減価償却や相続税対策などの節税効果は基本的に期待できない
つまり、匿名組合型は投資家にとって税務処理がシンプルである一方、節税効果はなく、あくまで配当収益を得る仕組みと考えるのが適切です。
任意組合型の特徴と税務上の扱い
任意組合型は、投資家が組合契約を通じて不動産の持分を直接保有する仕組みです。投資家は出資者であると同時に不動産の共有者となり、事業の成果や損失に応じて所得を計上します。
税務上は以下のように扱われます。
- 所得区分は「不動産所得」に該当
- 他の不動産所得や給与所得などと損益通算が可能
- 減価償却を利用できるため節税効果が見込める
- 相続時には現物不動産同様に評価されるため、相続税対策として利用できる可能性あり
ただし、匿名組合型と違って「優先劣後方式」が適用されない場合が多く、損失が発生した際には投資家が直接負担するリスクも大きくなります。そのため、高度な税務メリットがある一方で、投資リスクも重くなる点を理解しておく必要があります。
選択のポイント
- 安定性重視・節税効果不要 → 匿名組合型が向いている
- 節税効果や相続税対策を重視 → 任意組合型が有力な選択肢
ただし任意組合型は案件数が少なく、法律上も「無限責任」を伴うことが多いため、専門家の助言を受けて慎重に判断することが重要です。

任意組合型は節税や相続対策でメリットがありますが、その分リスクも大きいです。匿名組合型はシンプルで安心感がありますが、節税効果はありません。投資家の目的とリスク許容度によって選び方を考えてくださいね
法人で投資した場合の税金の違い
不動産クラウドファンディングに個人として投資する場合、分配金は「雑所得」として課税され、最大45%の所得税率が適用される可能性があります。これに対し、法人を通じて投資する場合は「法人税」が課税され、仕組みや税率に大きな違いがあります。
法人税率の仕組み
法人の場合、課税所得に対して法人税が課されます。2025年現在の標準税率は以下の通りです。
- 年800万円以下の所得:15%(資本金1億円以下の中小法人)
- 年800万円超の所得:23.2%
- 地方法人税・住民税を含めると実効税率は約30%前後
一方、個人の所得税率は累進課税であり、課税所得が4,000万円を超えると45%に達します。高所得者にとっては、法人を活用した方が税率が低くなりやすいのが特徴です。
法人投資のメリット
- 税率の安定性:個人は所得が増えるほど税率も上がりますが、法人は上限が23.2%に抑えられます。
- 経費計上が可能:法人名義で発生した経費(通信費、事務所家賃、人件費など)を損金算入できるため、課税所得を抑えることができます。
- 資産管理会社の活用:不動産や株式など他の資産と合わせて法人で一元管理することで、節税や承継の面で有利になります。
- 利益の繰延べが可能:役員報酬や配当の調整によって、利益の分配時期をコントロールできます。
法人投資のデメリット・注意点
- 設立・維持コスト:法人設立費用や毎年の決算・申告費用、社会保険料の負担が発生します。
- 損益通算の制限:個人の雑所得はFXや仮想通貨などと通算できますが、法人は法人全体の利益と損益計算されるため仕組みが異なります。
- 配当課税の二重課税:法人の利益を個人に配当すると、法人税に加えて配当所得として課税されるため、全体で税負担が増える場合もあります。
- 事業性の要件:単なる節税目的のペーパーカンパニーは税務署から否認されるリスクがあります。実態を伴った法人運営が必要です。
法人投資が向いているケース
- 所得税率が高い高所得者
- 不動産や株式など複数の資産を保有している投資家
- 長期的に資産管理会社を活用したい人
- 後継者への資産承継や相続税対策を意識している人

法人経由の投資は税率が低く抑えられる一方で、設立や維持のコスト、二重課税の可能性といったデメリットもあるんです。高所得層や資産承継を意識している方には有効な手段ですが、節税だけを目的に安易に法人化するのは危険ですよ。必ず税理士と相談して、自分に合った投資スキームを選びましょうね
確定申告の流れと必要書類
不動産クラウドファンディングで得た分配金は、雑所得として扱われるため、一定条件を満たすと確定申告が必要になります。ここでは申告の基本的な流れと必要となる書類を整理します。
確定申告の流れ
- 収入額を確認する
運営会社から送付される「支払調書」などで分配金の金額を確認します。給与所得やその他の雑所得と合わせて申告が必要か判断します。 - 必要書類を揃える
分配金を証明する書類や源泉徴収票、控除に関する証明書などを用意します。複数の収入がある場合はすべてをまとめて確認できるようにしておきましょう。 - 申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを利用すると、入力内容に沿って自動で計算してくれるため便利です。会計ソフトを利用すれば副業収入が多い場合でも効率的に作成できます。 - 申告書を提出する
電子申告(e-Tax)なら税務署へ出向かずに提出可能です。書面で提出する場合は税務署の窓口または郵送で対応できます。 - 還付や納付の確認
還付金がある場合は申告後おおむね1か月程度で指定口座に振り込まれます。追加納税となる場合は期日までに納付します。
必要書類一覧
- 分配金の支払調書(不動産クラウドファンディング事業者が発行)
- 勤務先からの源泉徴収票
- マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
- 控除を受けるための証明書(生命保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金払込証明書など)
- 還付を受けるための銀行口座情報
- 医療費控除を利用する場合の領収書や明細書
- ふるさと納税をした場合の寄附金受領証明書
これらの書類を事前に整理しておくと、申告作業をスムーズに進められます。

確定申告は難しそうに感じるかもしれませんが、手順を押さえて必要書類を揃えてしまえば流れはシンプルです。特に支払調書や源泉徴収票といった基本書類を早めに確認しておくことが、スムーズに進めるコツですよ
不動産クラウドファンディングと税金対策の注意点
不動産クラウドファンディングは少額から投資できる魅力的な仕組みですが、税金対策を目的とする投資には注意が必要です。制度の特徴を正しく理解しないまま節税効果を期待すると、思わぬ誤算につながる恐れがあります。
節税目的の投資には不向き
不動産クラウドファンディングの多くは「匿名組合型」であり、投資家は不動産の所有権を持ちません。このため現物不動産のような減価償却による節税はできず、相続税の圧縮効果も期待できません。あくまで配当収益を狙う仕組みであり、節税効果を重視する方には適していません。
確定申告での還付を過度に期待しない
分配金は源泉徴収20.42%が自動で差し引かれます。確定申告を行えば課税所得の状況によっては還付を受けられることもありますが、すべての投資家に当てはまるわけではありません。特に課税所得が高い場合は、逆に追加納税になるケースもあるため注意が必要です。
他の所得との合算リスク
雑所得として扱われるため、給与や副業収入と合算して総合課税の対象となります。課税所得の区分が上がると税率も上昇するため、想定以上に納税額が膨らむ可能性があります。税負担を軽減するどころか、収益の手取りが減ることもあり得ます。
長期的な視点での運用が重要
短期的な節税メリットを狙うよりも、安定した利回りを得ながら資産を積み上げていくことが本質的な活用方法です。税制上の仕組みを理解した上で、生活に支障のない範囲で長期的に続ける投資として設計することが大切です。

不動産クラウドファンディングは節税商品ではなく、収益を得るための投資手段なんです。税金面では「過度に得をしよう」と考えるより、「仕組みを理解して損をしない」意識が重要ですよ